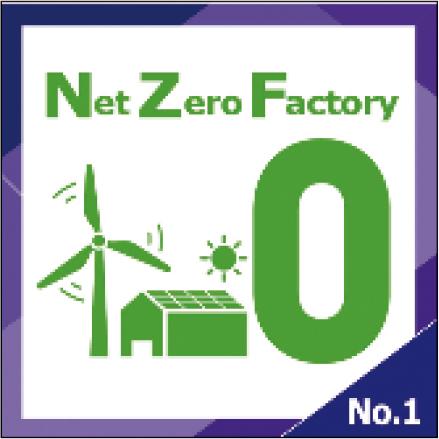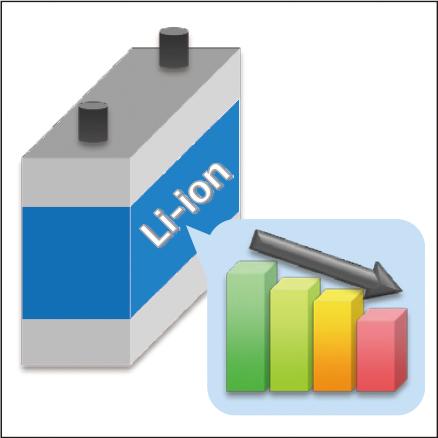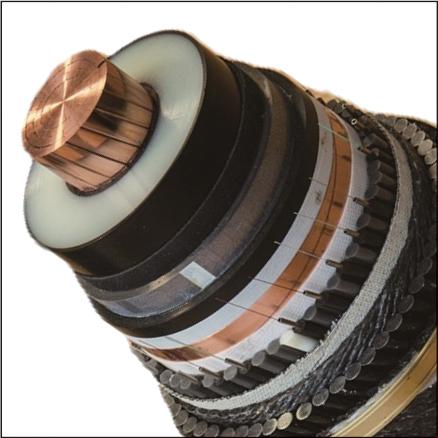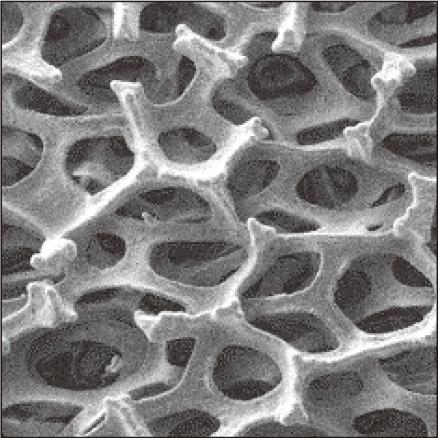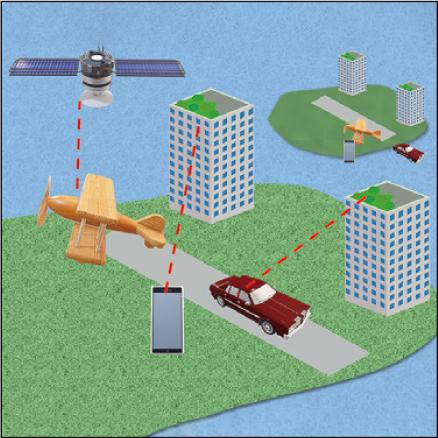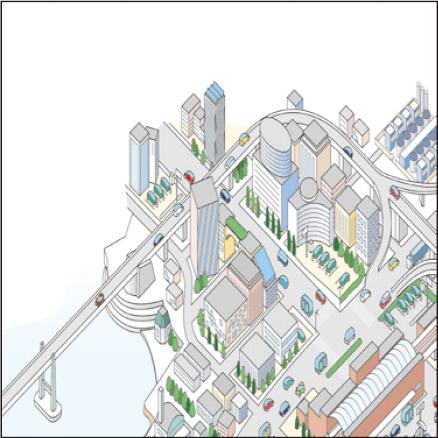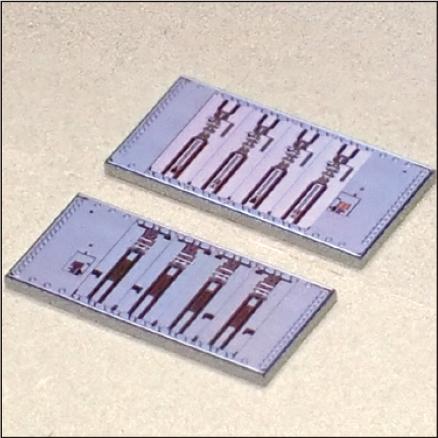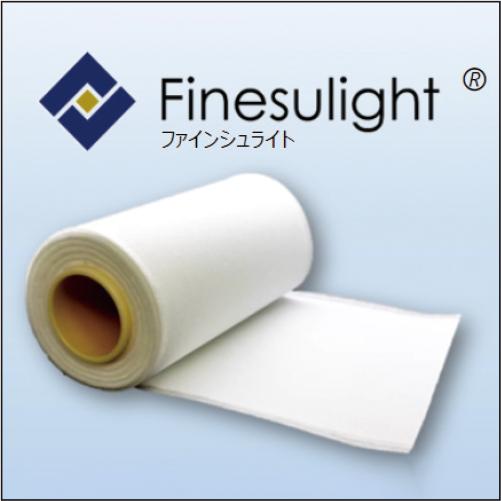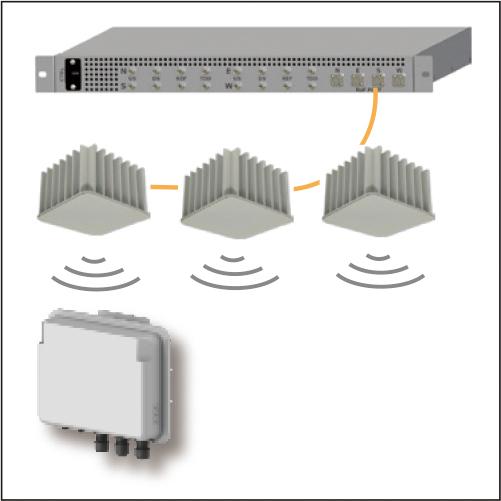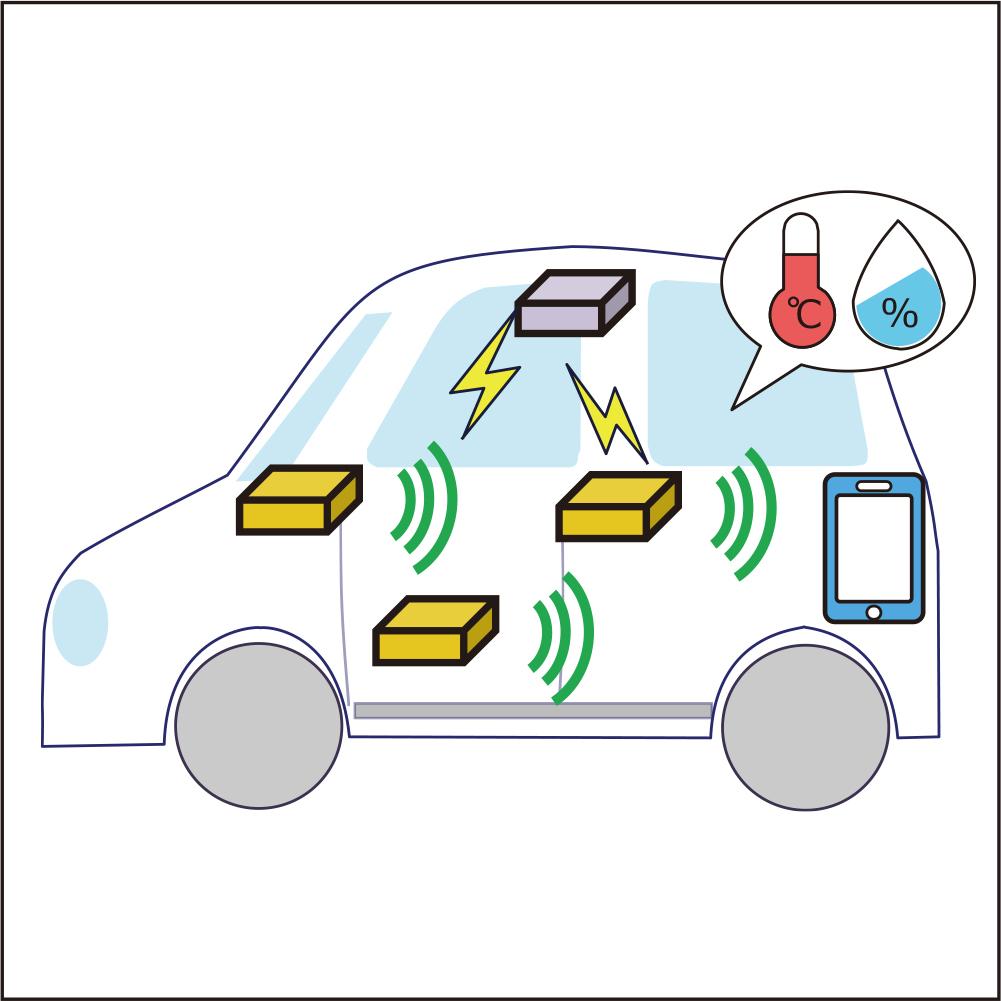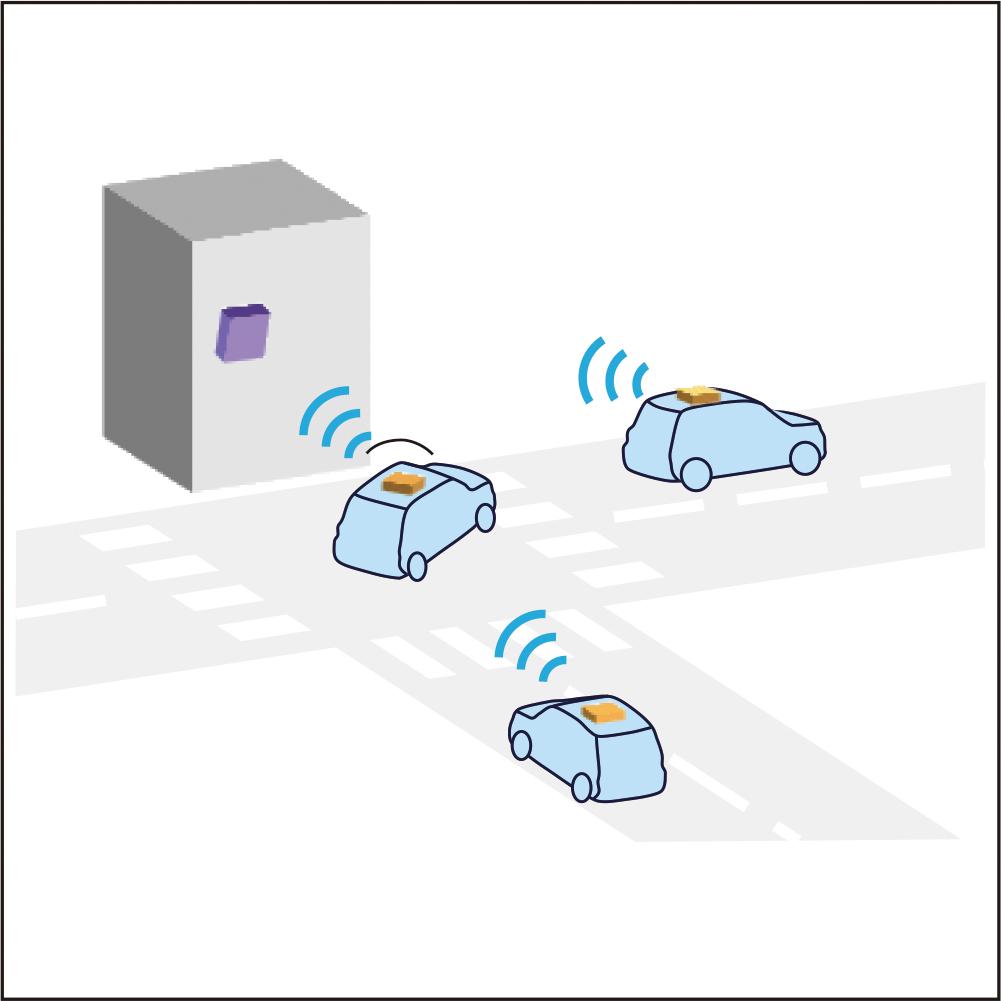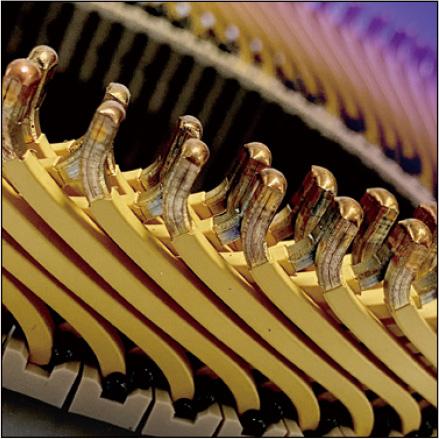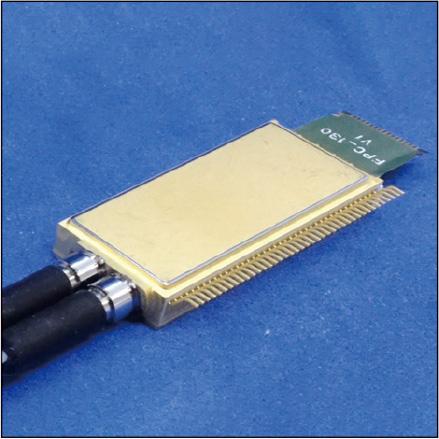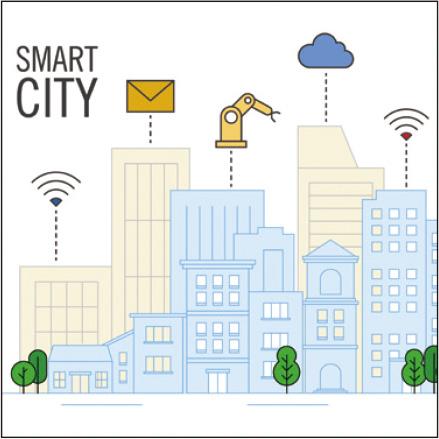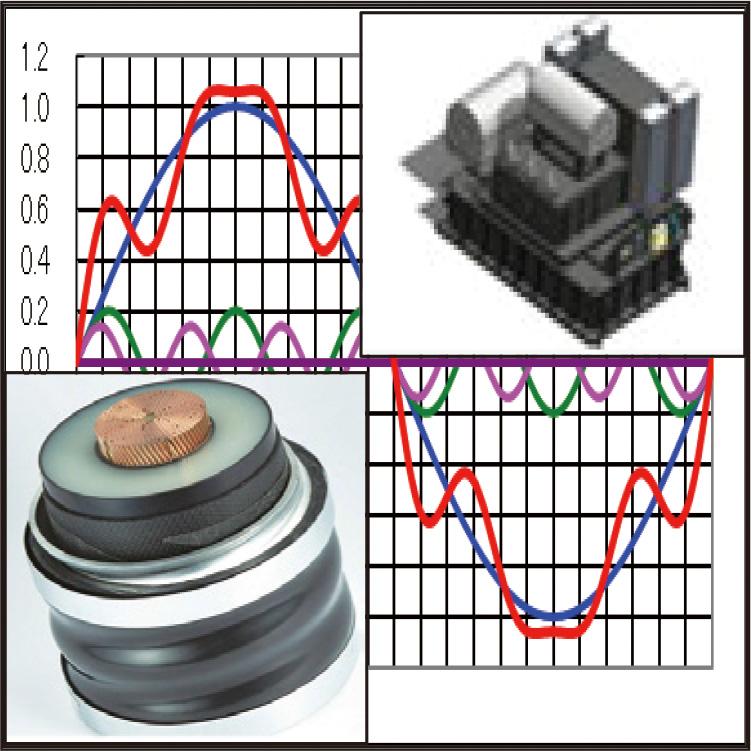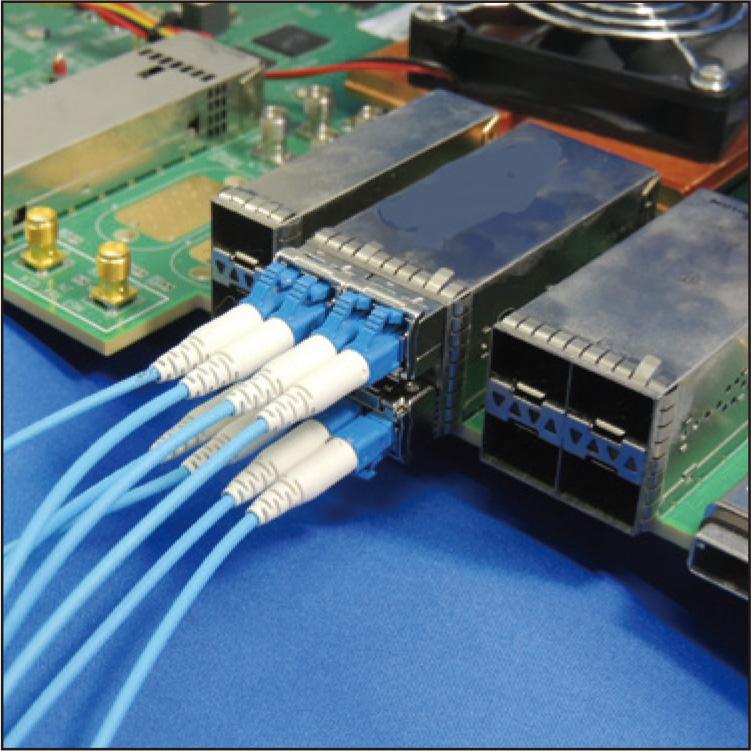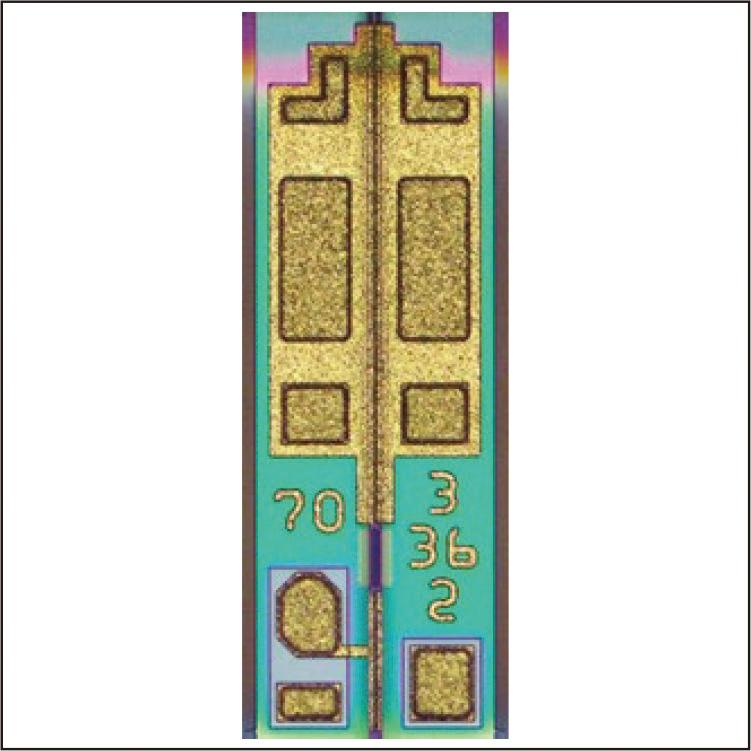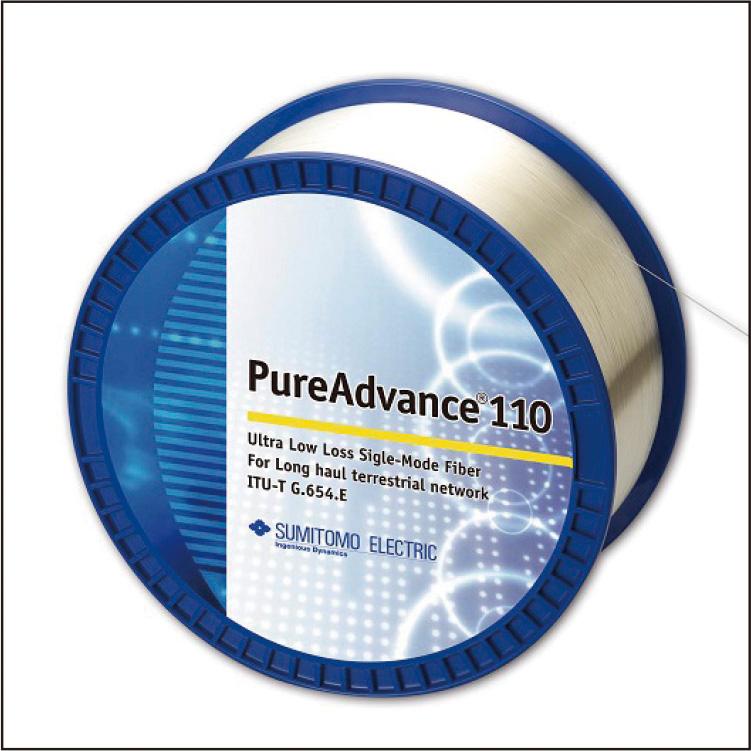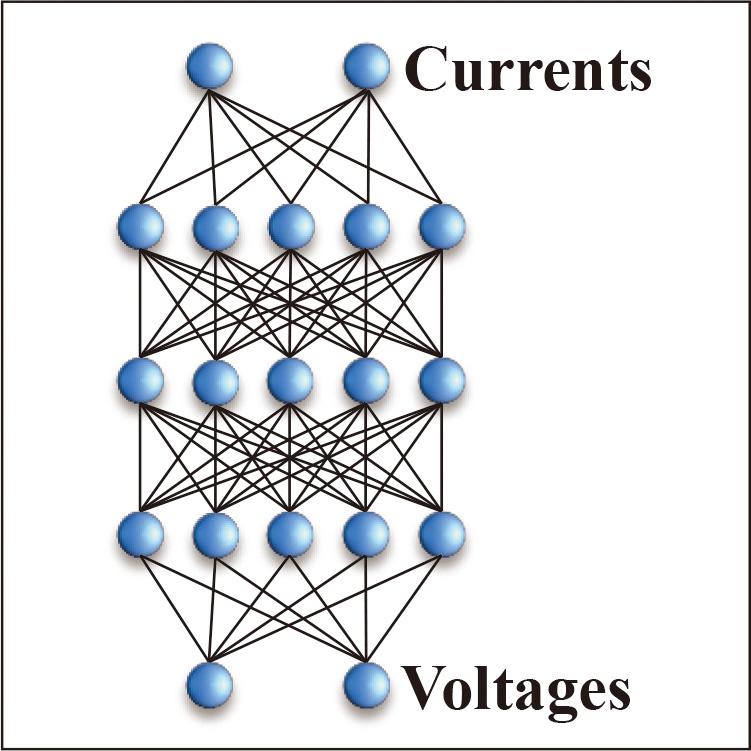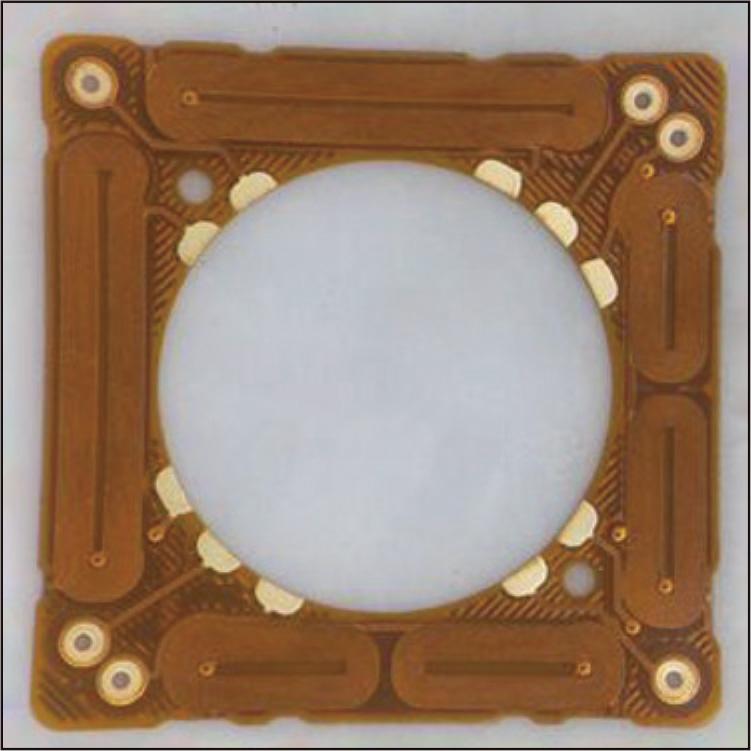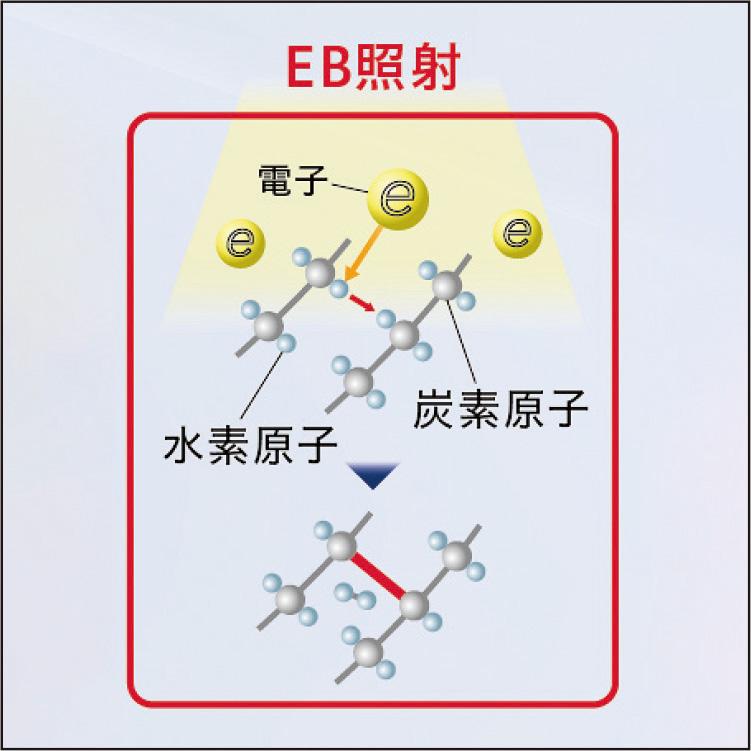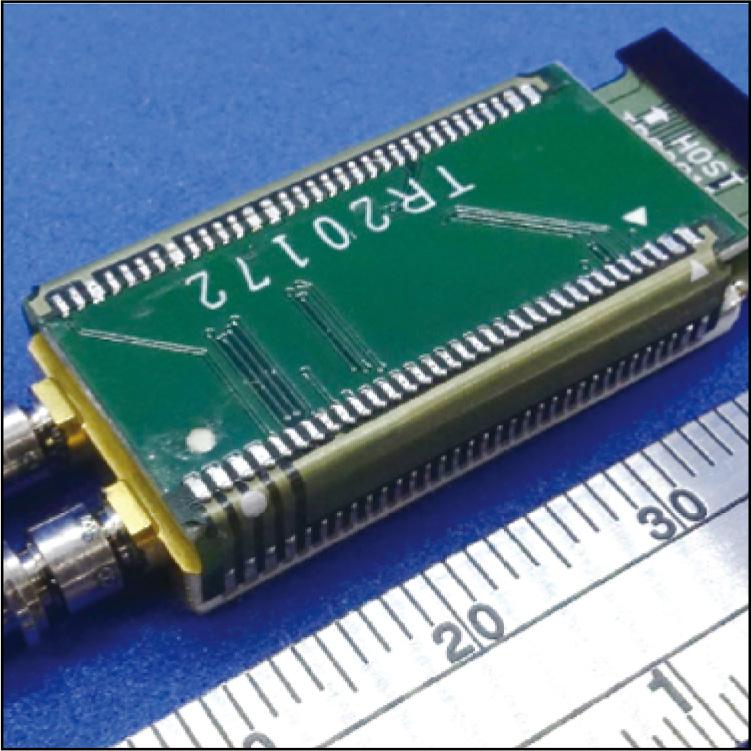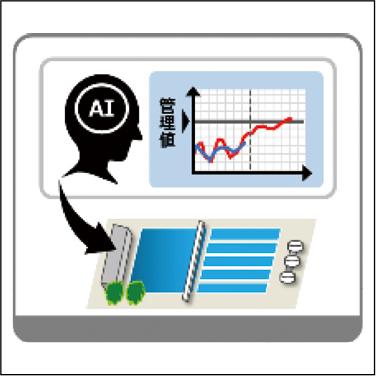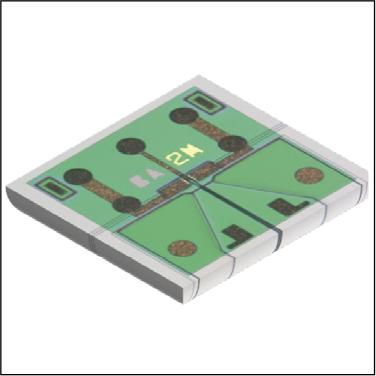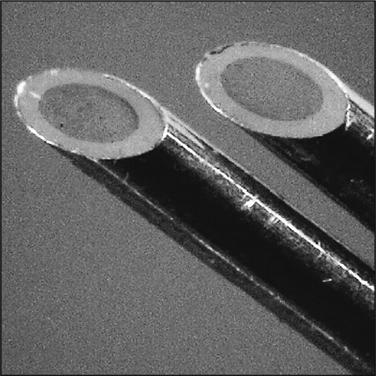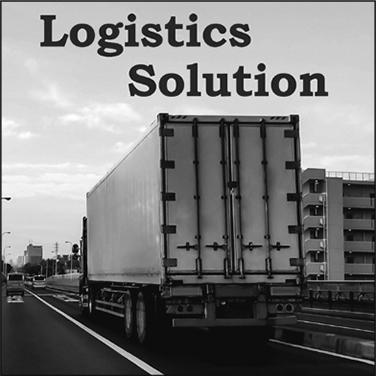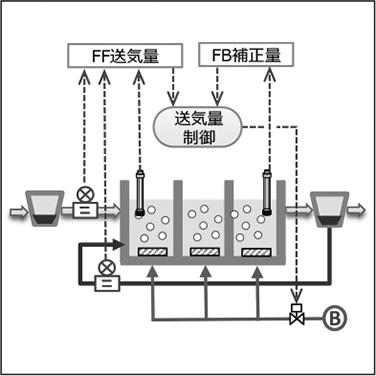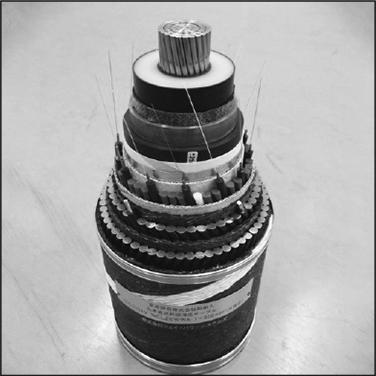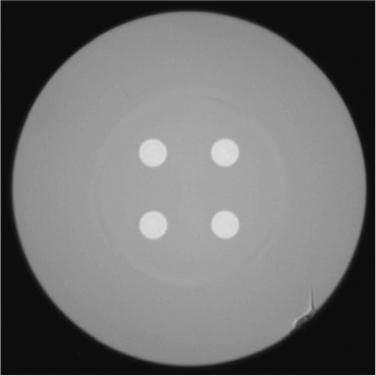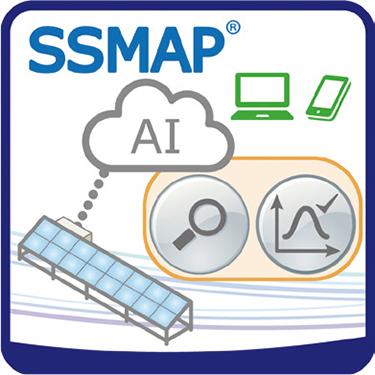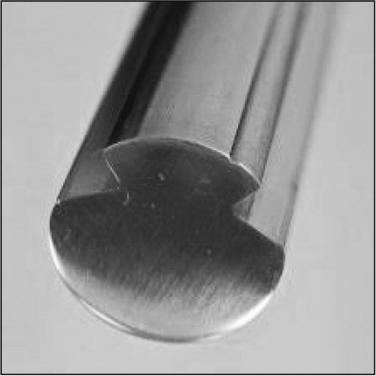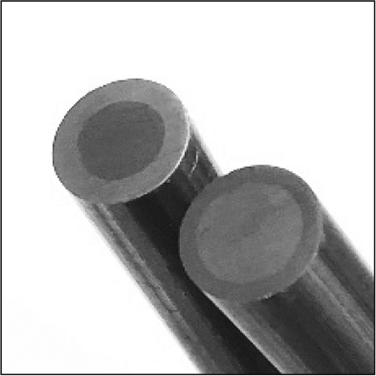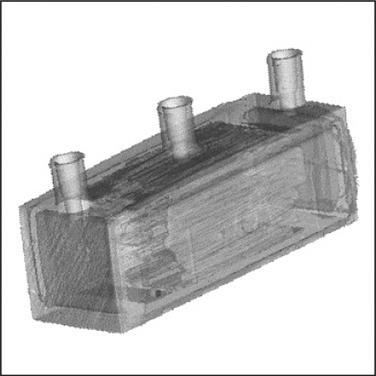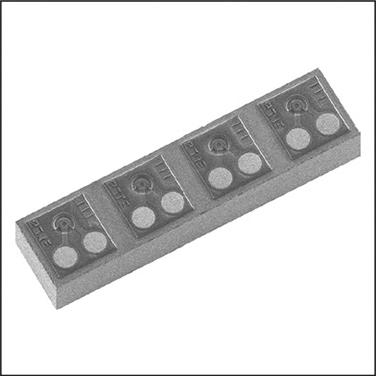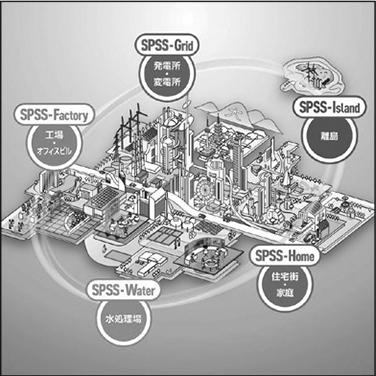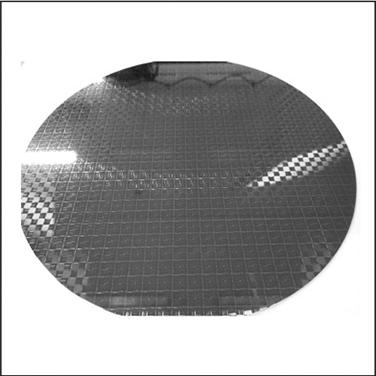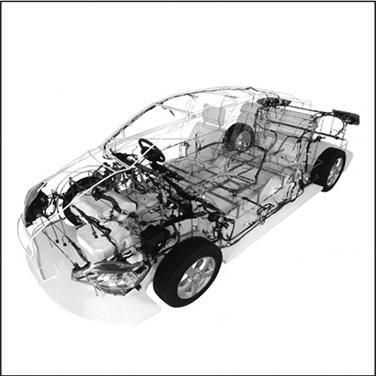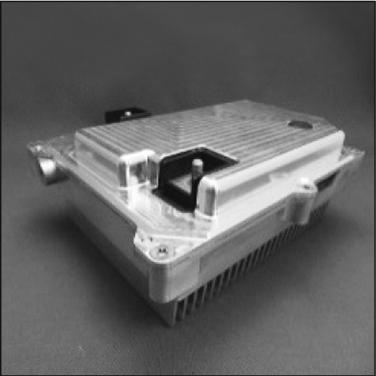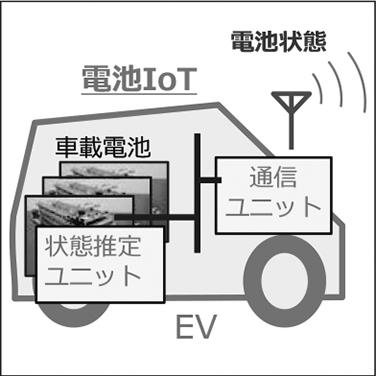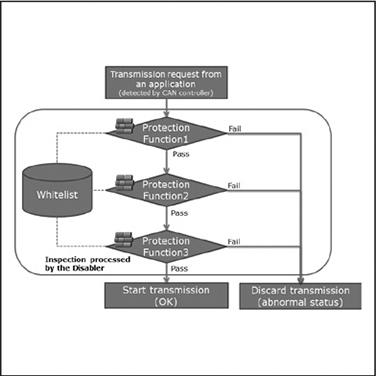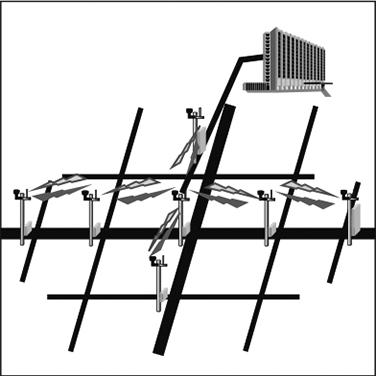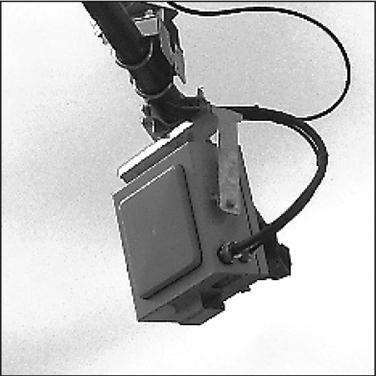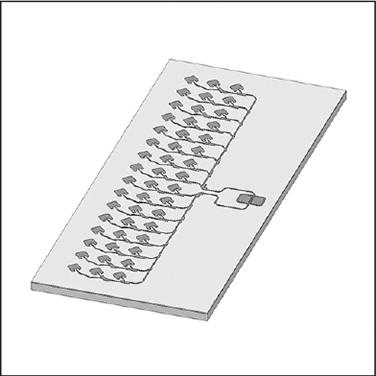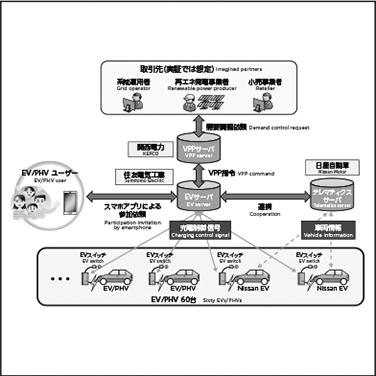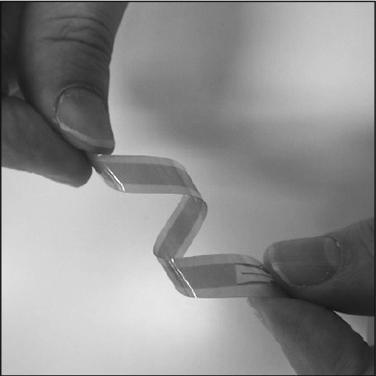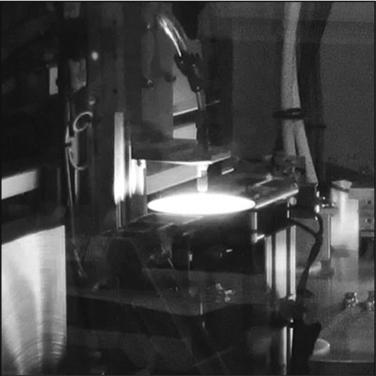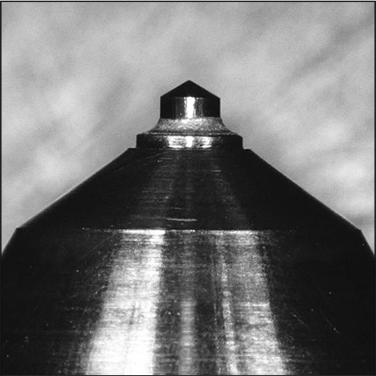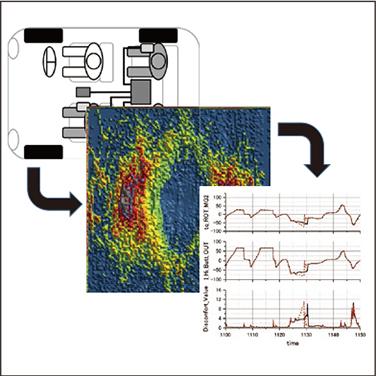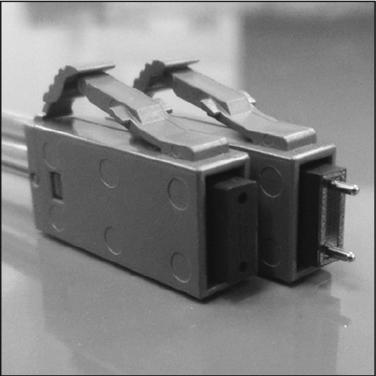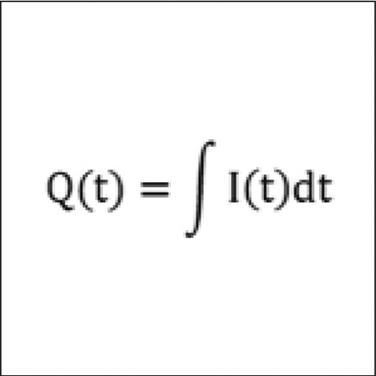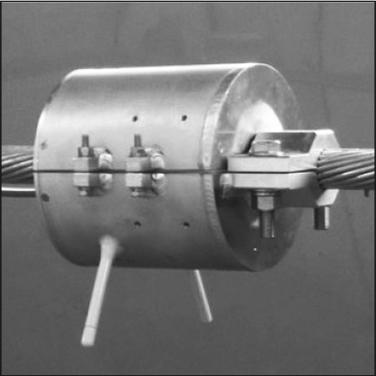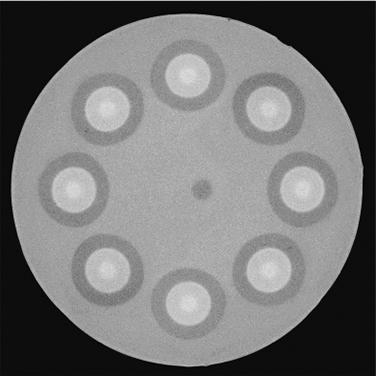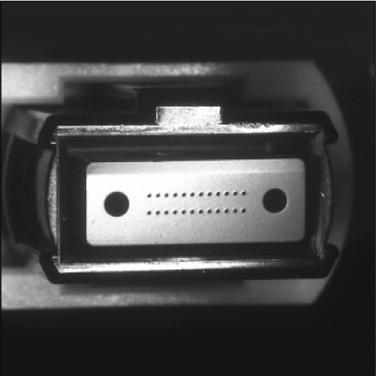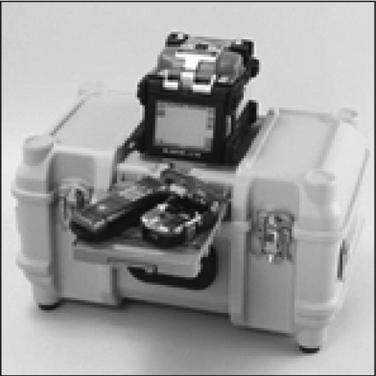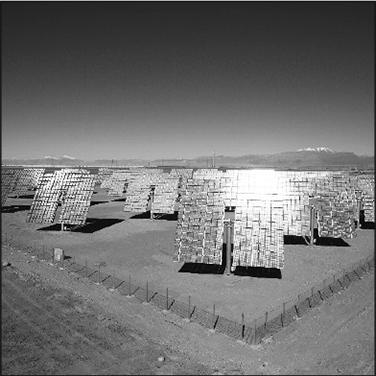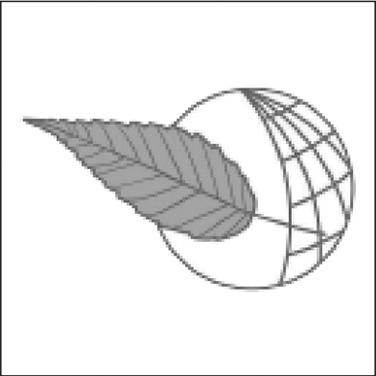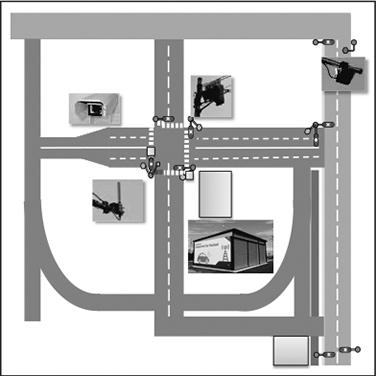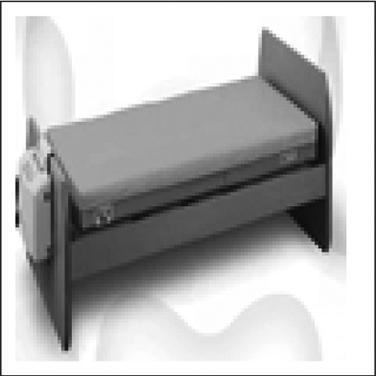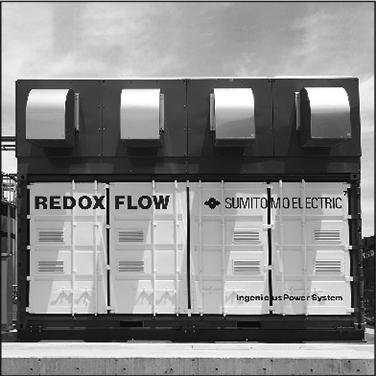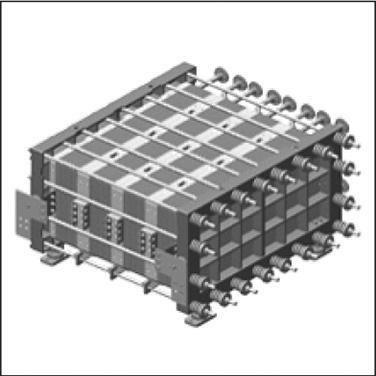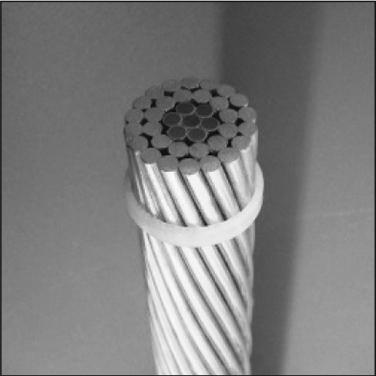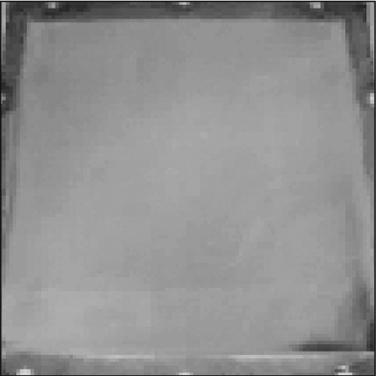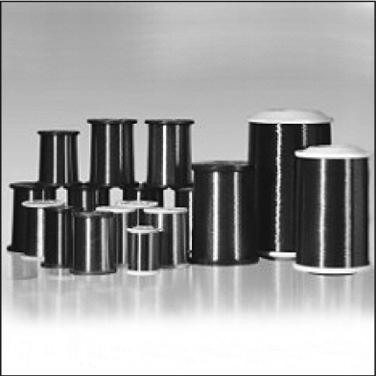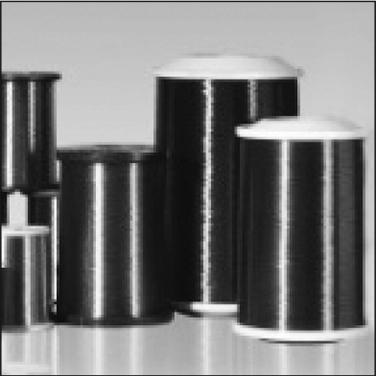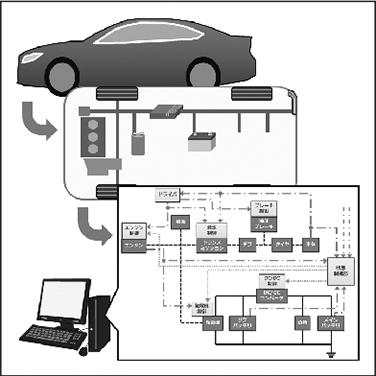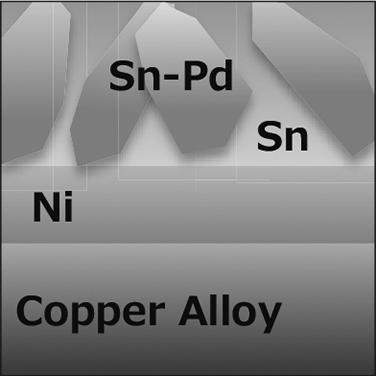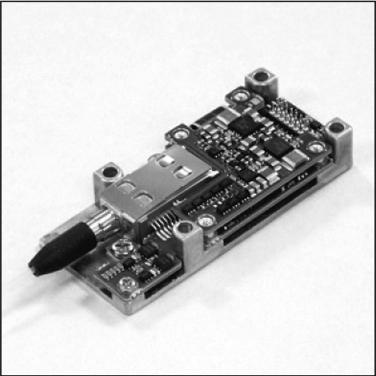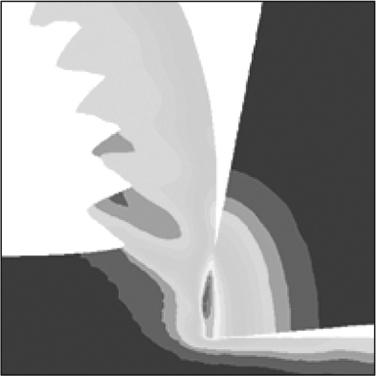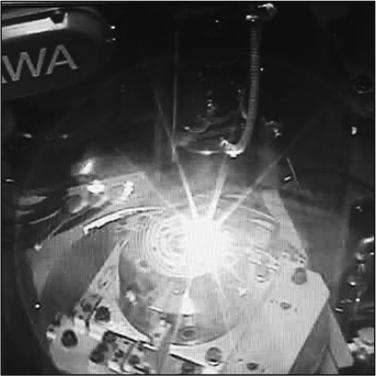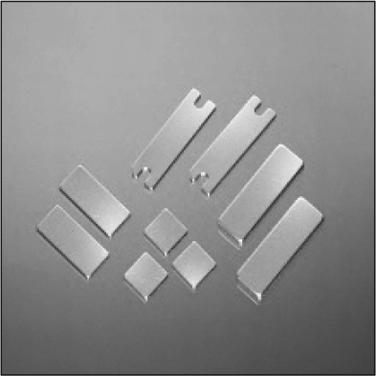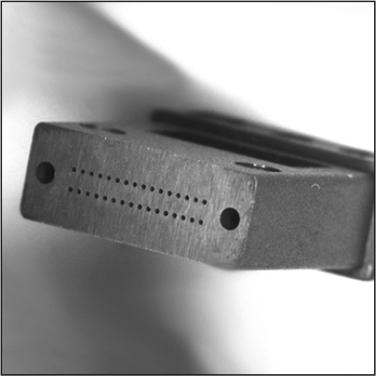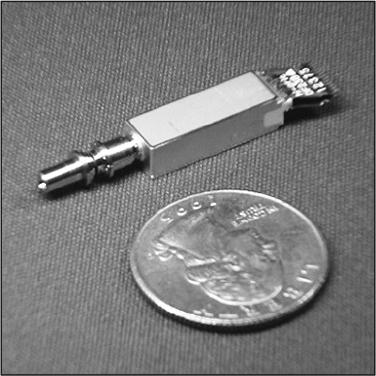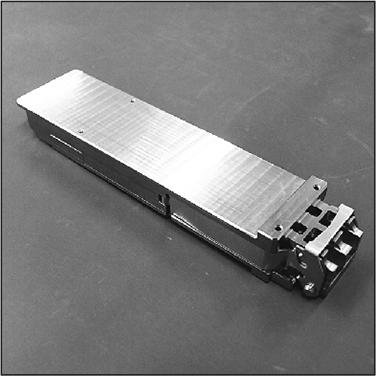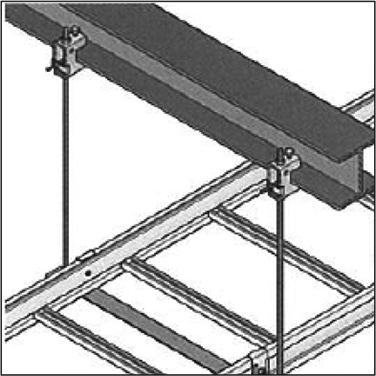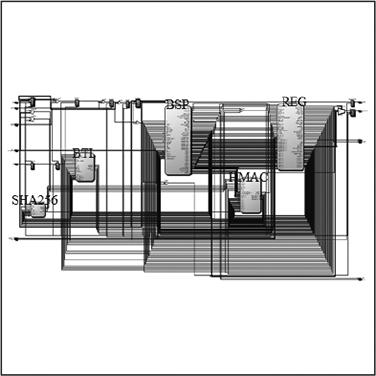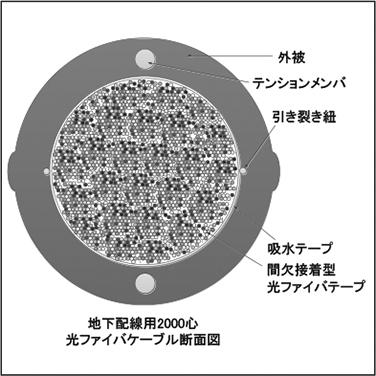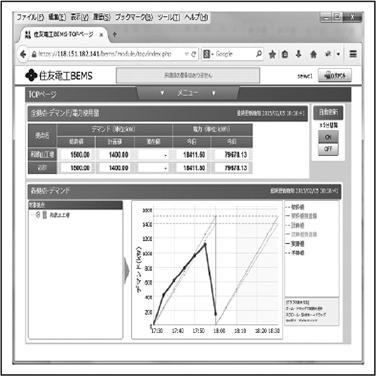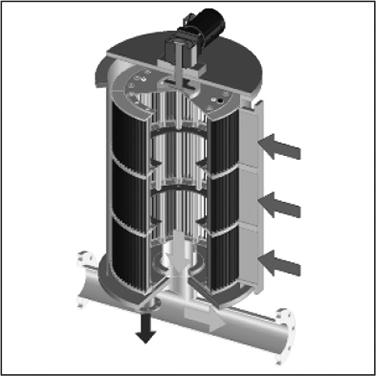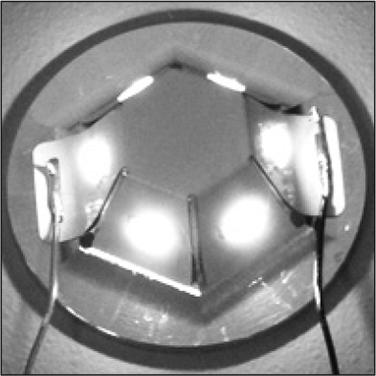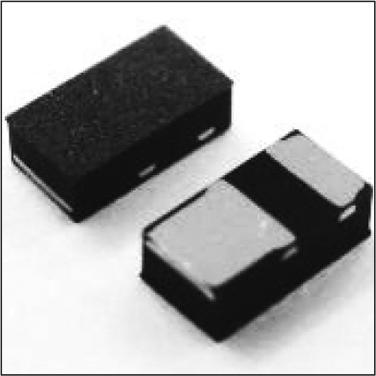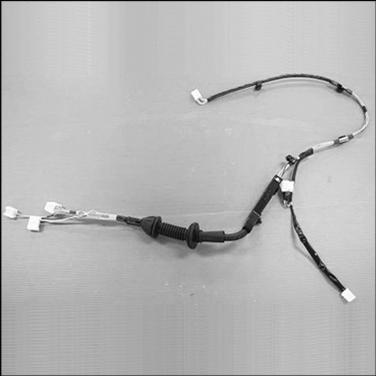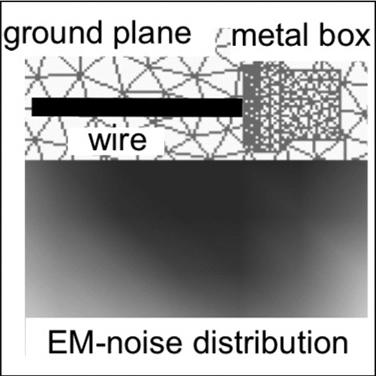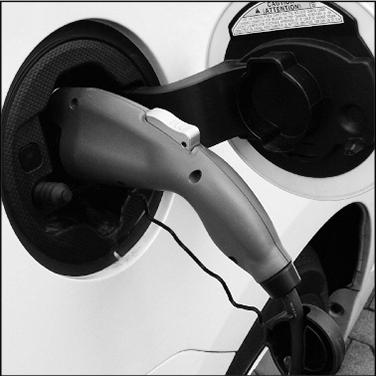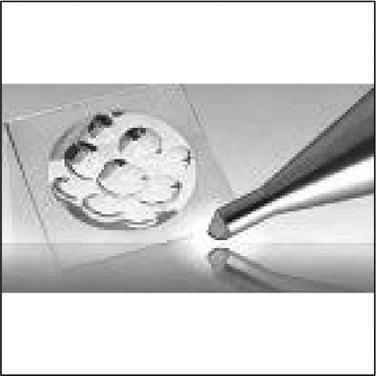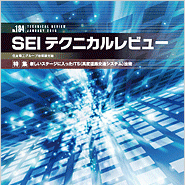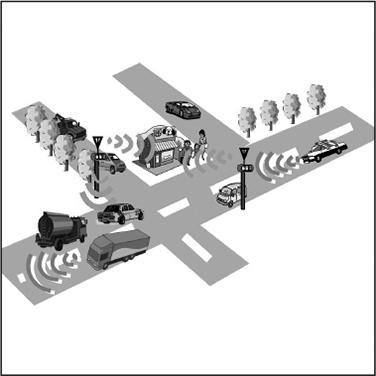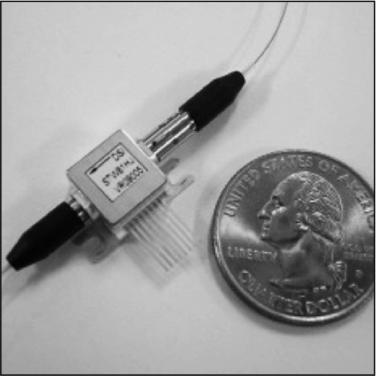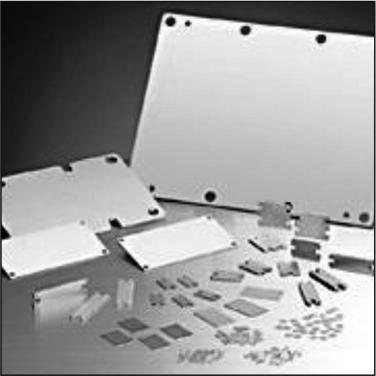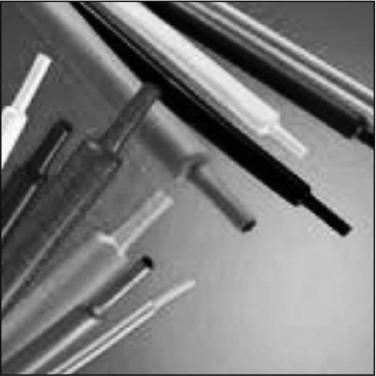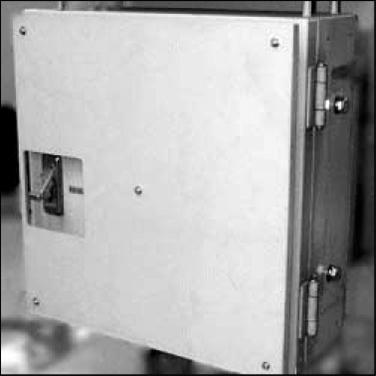すべて
すべて
近年の地球温暖化に起因すると考えられる異常気象の増加を機に、脱炭素化への取り組みが活発になってきている。日本政府は2020年に「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、経済と環境の好循環を目指す産業政策をまとめた実行計画「グリーン成長戦略」を公表した。2021年に策定された第6次エネルギー基本計画では、日本のエネルギー政策の基本方針を示し、安全性を大前提とした上で、エネルギーの安定供給、環境への適合、経済効率性の同時達成を目指していた。この時点では人口減少や省エネルギーの進展により、電力需要量は減少すると見込まれていた。しかし、その後、電力を多く消費するデータセンターや半導体工場の新増設に伴い、一転して電力需要の増加が見込まれるようになった。
2.1 MB
地球温暖化対策および再生可能エネルギー導入の拡大に伴い、電力系統の安定化と長期運用可能なエネルギー貯蔵システムへのニーズが高まっている。本論文では、電力品質の安定化に効果的な電力貯蔵技術として注目されるレドックスフロー電池の性能向上と最新の開発状況と設計について報告する。特に、セルスタックの出力向上やエネルギー密度の向上に焦点を当て、多様な運用要求に対応可能な蓄電システムの実現を目指した。さらに、30年にわたる長期運用に耐える高い信頼性を確保し、ライフサイクルコストの低減に寄与する技術開発も行った。本開発の成果により、再生可能エネルギーの効果的な蓄電と長期的な安定運用の実現に貢献していきたい。
2.5 MB
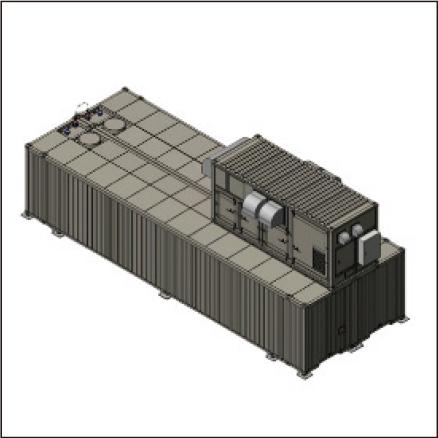
2.5 MB
脱炭素社会の実現に向け、世界では2050年までのカーボンニュートラルを目指し2030年までに温室効果ガス排出量を半減、日本では2050年に実質排出量ゼロ、2030年までに46%削減(2013年度比)を掲げている。再生可能エネルギーの普及が欠かせない一方で、このような変動性を有する電源の有効活用には大型の電力貯蔵装置が必要不可欠となる。特に、季節や昼夜による電力需給の差を吸収できる長時間エネルギー貯蔵(LDES:Long Duration Energy Storage)のニーズが高まっている。当社製レドックスフロー電(RF電池)は、安全性に優れ、充放電サイクルによる寿命低下が極めて小さく、大容量かつ長時間のエネルギー貯蔵が可能な定置用蓄電池である。日本をはじめ、世界各国でRF電池の導入が進んでおり、再生可能エネルギーの有効利用や地産地消型エネルギーシステムの構築、電力レジリエンス強化に大きく貢献している。本稿では、RF電池が、よりクリーンで安定したエネルギー社会の実現にどのように貢献しているか、具体的な事例を紹介する。
3.2 MB

3.2 MB
データセンターの新増設等に伴う電力需要の増加、世界情勢の影響による化石燃料調達リスクの高まり、2050年のカーボンニュートラルの実現等により、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーへの投資と活用の重要性が増している。他方で、再生可能エネルギーは天候の影響で出力が変動するため、その大量導入により電力系統が不安定化するという課題を伴う。この課題への対策の一つが調整力の確保であり、調整力を捻出できる蓄電池の活用が注目されている。日新電機㈱は、蓄電池から受変電設備までのシステムを一括導入するソリューションを提供している。昨今、蓄電池の活用についてさまざまなニーズが登場していることを踏まえ、本稿では、日新電機㈱のソリューションに、住友電気工業㈱のエネルギーマネジメントシステムであるsEMSA(Sumitomo Energy Management System Architecture)を組み合わせた蓄電池活用ソリューションを紹介する。
2.2 MB
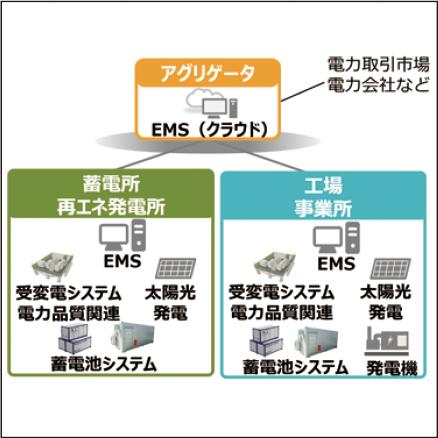
2.2 MB
カーボンニュートラルの実現に向けて再生可能エネルギーの普及が拡大しており、発電機設備と組合せてエネルギーの安定供給に寄与する定置用蓄電池システム(Battery Energy Storage Systems : BESS)のニーズが高まっている。BESSの蓄電池の大部分はリチウムイオン電池(LiB)であるが、BESSの導入が先行している海外だけではなく、最近では国内でもLiBの異常による火災事故が増加しており、海外および国内で安全基準が規定された。国内ではJIS C4441:2021規格がそれに該当するが、この規格に準拠するためには、要求事項の一つであるBESSの異常発生時(LiB等の熱暴走異常時など)に発生するガスや火災を検知し、外部へ警報を発するシステムを備えることが必要である。日新電機㈱は、BESSのコンポーネントとして、LiB異常時に発生するガスを検知するセンサを開発した。本機の特徴とフィールド事例について紹介する。
2.9 MB

2.9 MB
近年の環境志向の高まりを受け、欧州を中心に再生エネルギー導入が進み、直流ケーブルの需要が増加している。当社では、架橋工程を省略することで製造時の省エネ化を達成でき、乾燥工程も不要となりリードタイムを短縮できることから、従来DC-XLPEより環境に優しい直流用非架橋材料の開発に取り組んだ。これまでの研究により、各種機械特性、および電気特性は従来DC-XLPEと同等の性能を有し、直流寿命も十分な直流用非架橋材料の開発に成功した。モデルケーブルを作製し、ケーブルにおける基礎特性も問題無いことが確認できた。更に、架橋剤分解残渣が存在しないため、ケーブル作製直後から厚み方向で体積抵抗率が安定しており、架橋剤分解残渣量によって体積抵抗率が変動し得る従来DC-XLPEよりも品質が安定するメリットがある。今後、更なるケーブル試作、評価を進め、従来DC-XLPEと同様の高信頼性のケーブルを開発する。
1.2 MB

1.2 MB
近年のグローバルなカーボンニュートラル化の潮流に伴い、大規模な再生可能エネルギーの開発が進むとともに、その電力を需要地に届けるための長距離送電網の構築が急速に進められている。我が国においても、北日本から首都圏に直流海底送電を行うなど、長期・大規模な送電網構築のマスタープランが示されている。この潮流を見越し、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)では2015年度から直流海底送電に関する技術開発が継続して行われ当社も参画してきた。国内での直流海底送電計画が具体化した現在、これまでの開発の経緯と意義を振り返るとともに、今後の実プロジェクト適用や将来に向けた開発の展望について考察する。
3.8 MB

3.8 MB
近年、世界各国で温室効果ガス削減の取り組みが強化され、洋上風力発電の導入が進んでいる。風車で発電した電気を送電する海底ケーブルの製造性、コスト、施工性の課題を解決すべく、これまで当社は、遮水層を省略した構造の海底ケーブルの開発を進めてきた。ケーブル絶縁体に水分が浸入すると、水トリー劣化が起こるため、遮水層省略には耐水トリー(TR)絶縁体の使用が必須だが、その適切な評価法もなかった。前回、ヒートサイクルにより絶縁体に生じる過飽和水分量に着目した浸水課電試験を検討した。今回、同試験と各種試験の結果を比較し、同試験では現実的な期間で水トリー劣化が生じ、実線路30年の長期TR性評価が可能なことを確認した。加えて、TR絶縁体開発にも同試験を用いて30年TR性を評価し、将来の高電圧化に対応可能な高いTR性と低い誘電正接を持つ材料を見出している。引き続きケーブルの開発を進めており、洋上風力発電の拡大に貢献できると考える。
1.7 MB

1.7 MB
カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの主力電源化の取り組みが進められている。しかし、架空送電線において送電容量不足により再生可能エネルギーが接続できないという課題がある。この課題解決のために2022年より既存設備を最大限活用するN-1電制の適用が開始されている。N-1電制とは、送電線の事故などによって送電できなくなった電流が、他の健全回線へ流れることで過負荷となった場合に、一部電源の出力を抑制し過負荷を解消するものである。そこで、リアルタイムで電流を計測できる当社製送電線センサを活用したセンサ伝送型OLRシステムを開発・実用化したので紹介する。
2.4 MB

2.4 MB
新興国においては、未だ配電網が脆弱な地域が数多く存在し、安定した電力供給が課題となっている。そこで、そうした地域においても送電線が存在するエリアが少なくないことに着目し、送電線から電源供給用に大容量化した電源用計器用変圧器(Power Voltage Transformer(PVT))を用いて直接低圧電力を供給可能なマイクロ変電所を有効な対策として開発を進めてきた。2025年6月、PVTを用いたマイクロ変電所をインドに導入し、実証試験を開始したので紹介する。なお、本活動は、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の国際実証事業(JPNP 93050)として実施したものである。
3 MB
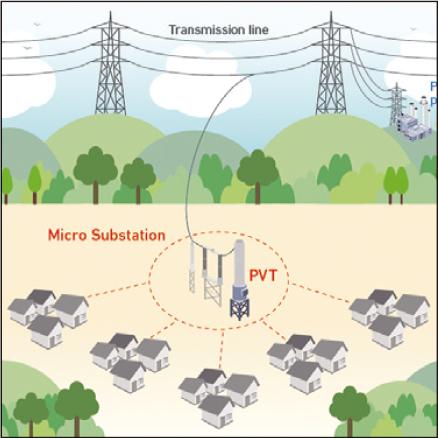
3 MB
1~2.5µmの波長域で動作する近赤外センサ(SWIRセンサ)は農業、医療、工業から宇宙までの様々な分野での応用が期待されている。当社はこれまで受光層にInGaAs/GaAsSb量子井戸構造を採用することで2.5µmまで動作する低暗電流の近赤外センサを開発してきた。量子井戸構造に関する理論計算からInGaAsをInAsとGaAsからなるデジタルアロイに置き換えた(InAs)(GaAs)/GaAsSb量子井戸構造を用いることにより量子効率が向上することが示唆された。本報告では、実際にデジタルアロイ型量子井戸構造を受光層に持つセンサを試作した結果およびバリア層を追加することによって暗電流の一層の低減に成功したことについて述べる。
1.7 MB
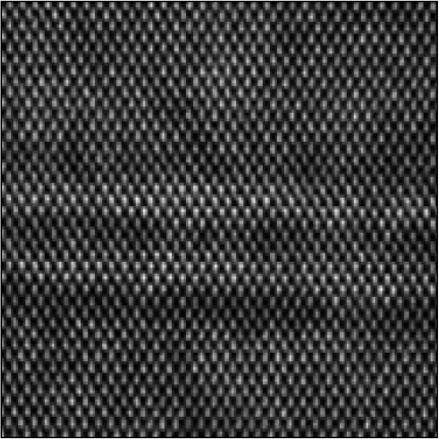
1.7 MB
基地局無線通信用の高周波デバイスなどで、取り扱う情報量が増大し、発熱が課題となり、より高放熱性デバイス構造が望まれている。高熱伝導率のダイヤモンドをヒートシンクとすることはその有効な解決策として取り組まれてきているが、従来の接着方法では数µmのデバイスからヒートシンクまでの熱抵抗が無視できなくなっている。より効率的な放熱方法として、GaN半導体デバイスとダイヤモンドヒートシンクを接着剤・はんだ材料なしで直接接合した、GaN-on-多結晶ダイヤモンド構造を、2インチサイズの大口径で作製することに成功し、GaN-HEMTのデバイスの試作とその高放熱特性を確認した。
3.9 MB
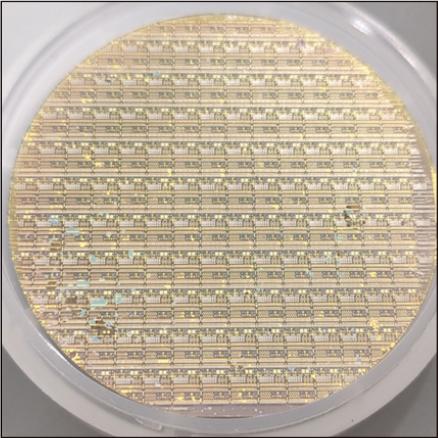
3.9 MB
本稿では、産業ロボット、医療・介護、車載などの分野で応用が期待され、物理的な微小検知ができる製品として開発している細径圧電センサワイヤについて報告する。本開発品は、従来の画像認識や静電容量式センサでは検知が困難な、微小変位や接触力の検出ニーズに注目し、加えて柔軟で複雑な変形への追従性を備えたワイヤ状センサである。当社の金属・樹脂複合線を製造するワイヤ製造技術を活用することで、縫製糸程度の細線を実現し、設備などの構造体や衣服、機械部品への組込みを可能とした。また、高い信号出力と高速応答性を示すことも特徴である。現在、触覚センシングや構造健全性モニタリングへの有効性を見出しており、今後の社会ニーズである高密度センサネットワークやスマートマテリアル技術への展開が期待される。
4.9 MB
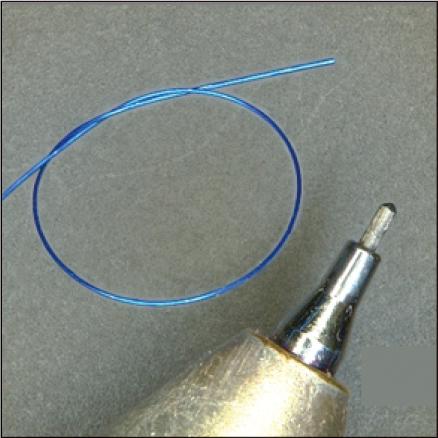
4.9 MB
近年の電子機器の高機能化に伴い、薄膜配線の膜厚と均一性の精密な制御が重要となっている。特に無電解銅めっきは絶縁基板上の成膜に必須であるが、銅の析出に関わる反応の複雑さから、製造条件の最適化は経験知に頼ることもある。本研究では、無電解銅めっき反応における銅の析出挙動を定量的かつ空間的に可視化するため、放射光を用いたその場測定技術を開発した。X線吸収微細構造(XAFS)により、液中のCu2+イオンが金属銅に還元される銅価数変化をリアルタイムに解析することを可能とした。また、X線イメージング手法により、銅膜厚の面内分布を測定して析出の面内分布の可視化を可能にし、さらに、気泡吸着が局所的な析出阻害の原因であると明らかにした。本技術により、無電解銅めっきの析出挙動の理解が進むことで将来的には無電解めっきプロセスに関する生産技術の発展が期待される。
1.9 MB
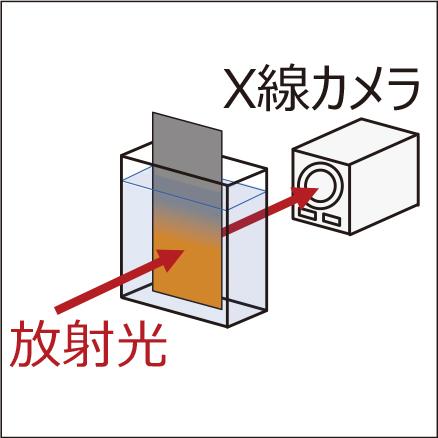
1.9 MB
脱炭素社会の実現に向けて、出力不安定な再生可能エネルギーを普及するには、蓄電池とデマンドレスポンスによる調整力の活用が必要である。一般家庭においては、蓄電システムを活用することで、太陽光発電の余剰電力を蓄えて夜間・朝方に利用でき、また、災害等で長時間停電した場合でも住宅への電力供給が可能となる。当社は蓄電システムの普及促進に向け、施工性が良い住宅用蓄電システムPOWER DEPO(パワーデポ)シリーズを2012年より販売している。この度、従来製品で市場の評価が高い、ハイスペック・一体型コンセプトを継承しつつ、課題であった配送、設置面積を改善するPOWER DEPO Rを開発した。
0.7 MB
近年クラウドコンピューティングや動画配信、生成AI等の進展により、大規模データセンタ(DC)の建設が進んでいる。DC 棟間を結ぶ光ケーブルは、主に地下ダクト内に敷設され、高圧空気と共にケーブルを押し込む敷設方法に対応したマイクロダクト光ケーブルが普及しつつある。既存の地下ダクトの寸法は固定されているため、ケーブルの細径化の需要が高まっている。今回、従来の200μm光ファイバより細径の190μm光ファイバを開発し、更にそれを使用した間欠リボンおよび従来ケーブル径から20%以上細径化した864心マイクロダクト光ケーブルを開発し販売を開始した。
1.1 MB
超硬合金製高精度極薄カッター(以下、超硬刃)は高硬度で優れた耐摩耗や耐食性を持ち、焼成前のセラミック材料、フィルム、箔、繊維などの精密切断に使用される。㈱アライドマテリアルでは超硬合金の素材製作から刃付け・刃先加工までの一貫生産体制を構築、顧客要望に応じ最小厚み0.05mmまでの極薄切断刃を製造している。また切断対象物に適した仕様設計(刃先角度、刃先先端形状等)や切断評価も可能で、切れ味や耐久性など、用途に応じ最適な切断刃を提案、提供している。本稿ではこの、超硬刃についてその特長と切断性能を紹介する。
1.9 MB
近年、電動車両シフトや自動車機器の電動化加速に伴い、制御対象を電気信号で操作するバイワイヤ制御の採用が拡大している。しかし、バイワイヤ制御は車両電源(鉛バッテリ等)が異常をきたした場合に制御不能となる課題がある。住友電工グループの住友電装㈱は、車両電源異常時に複数のバイワイヤ制御を継続可能とする統合バックアップ電源を開発し、2023年発売のプリウスに採用され、順次展開されている。今回、GEN3の保有エネルギーを維持し、小型・軽量化を実現した統合バックアップ電源(GEN4)の量産を開始し、2025年発売されたトヨタ自動車㈱のアクアに採用頂いた。新製品は従来品に比べ体積約▲30%、重量約▲50%の低減を達成し、車両搭載性の向上と省資源化に貢献している。
1.1 MB
BEV/PHEV/HEVの生産台数の増加に伴い、モータ、ギア、インバータを一体化したeAxleの開発が活発化している。eAxleモータの電源配線はバスバーが主流であるが、耐振動性に優れ、設計の自由度も高まる電線にニーズがあると考え、油冷方式のeAxleモータの電源配線をターゲットに、配策しやすい柔軟な電線の開発に取り組んだ。柔軟な絶縁被覆材のベース材料として、冷媒兼潤滑油であるATFへの耐性と、耐熱性に優れるフッ素ゴムを選定した。しかし、柔軟性と背反する、耐摩耗性、絶縁被覆材同士の耐互着性の改善が課題であった。そこで、耐摩耗性は結晶成分の微分散で、耐互着性は架橋による分子の運動性のコントロールで課題を解決した。本検討により、ISO200℃定格適合、耐ATF性、柔軟性、を兼ね備えた電線を開発でき、上市した。
1.6 MB

1.6 MB
NTTが提唱した次世代情報通信基盤の構想であるIOWN(アイオン)構想は、IOWN Global Forum(IOWN GF)の活動を通じて、世界規模で異業種の企業が参画し、社会実装に向けて技術とユースケースが議論されており標準化団体への提言として展開されている。IOWN構想は、オールフォトニクス・ネットワーク(APN: All-Photonics Network)をベースとした低遅延(1/200)・大容量化(伝送容量125倍)・低消費電力(電力効率100倍)を特徴としている。特に従来の1/200という低遅延性は、データセンターの配置や金融システム高度化への貢献に加え、今まで不可能であった新たな映像サービスの創出が期待でき、当社ブロードネットワ-クス(BNS)事業部の映像機器部門では新たな市場開拓に向けた基盤技術と商品開発に取り組んでいる。今回その一環としてIOWN構想のAPNの特徴を活かした超低遅延メディアコンバータ(LLMC)を開発した。本稿ではその設計思想と、IOWN GFのAI支援エンターテインメントILM(AIC-Entertainment Interactive Live Music)ユースケースにおいて定義された目標性能に対し、低遅延性能を実現した結果を報告する。
2.1 MB

2.1 MB
本稿では、施工性に優れたデータセンター向け細径6912心Outdoor/Indoor兼用光ケーブル(以下、細径6912心O/Iケーブル)の構造、特性および施工性について述べる。本ケーブルは、従来の200µm光ファイバを用いた間欠12心ファイバテープに加え、AI DC等に用いられている16心パラレル伝送に適した間欠16心テープも開発し、細径6912心O/Iケーブルに適用した。そして、ケーブルの細径化を実現するために「X-treme Spacer Cable」と名付けた中心テンションメンバ型スペーサーケーブルを開発した。本構造は従来のスペーサー型の特長である曲げ方向性がなく、敷設作業性に優れた特長を活かしつつ、細径化を実現した構造である。さらに、高難燃低発煙のLow Smoke Zero Halogenの外被材料も開発し、北米の厳しい難燃規格であるULライザー規格にも合格した。当該ケーブルを使用することでDC光配線の大幅な施工時間短縮、施工コスト削減が見込まれる。
5.5 MB
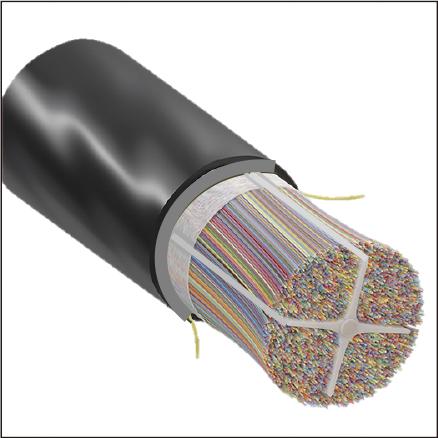
5.5 MB
電子線照射技術は、電線被覆の耐熱性やタイヤ用ゴムシートの流動性の改善などの多くの工業的プロセスで利用されている。 ㈱NHVコーポレーションはこれまでに、広範なエネルギー領域(100kV~5MV)の電子線照射装置(Electron Beam Processing System:EPS)を国内外の顧客に多数納入してきた。近年、持続可能な開発目標の達成に向けた取り組みにより、EPSに対して環境への配慮や作業者の安全確保、装置小型化の要求が高まっている。これらの要求に対応するため、我々は環境負荷の高い鉛材の使用量を大幅に削減し、保守作業の安全性を向上させた省スペースな新型のEPS(EB-XW)について報告する。
3.4 MB

3.4 MB
レーザ溶接は様々な産業で利用され、特に自動車産業では車体の軽量化や電動化といった需要の高まりを受けて利用が拡大している。レーザ溶接ではセンタービームとリングビームを組み合わせたデュアルビームを金属材料に照射することでスパッタ低減等の加工品質向上が図れることが知られている。その実現方法としてはデュアルビームを出力可能な発振器を導入するかビーム分岐DOE(回折型光学素子)を使う方法があるが、それぞれ導入コストが高い、デュアルビームの強度比を調整できないといった課題があった。そこで当社では既存のシングルビームシステムに後付けするだけでデュアルビーム化を実現でき、尚且つ任意の強度比に調整できるアジャストシェイパを開発した。本稿では製品の特長と実際のレーザ加工ヘッドに搭載した評価結果を紹介する。
1.7 MB

1.7 MB
当社では従来、不良品の検査を人による目視で実施していたが、人手が相応に必要なうえ、担当者によって検査基準にばらつきが生じやすかった。そこで外観検査AIシステムを開発し、不良品の検査の自動化を進めているが、同システムの教師データとして利用する不良品の画像がなかなか集まらず検出精度が上がらないことが課題であった。そこで、少量の不良品画像から多量の疑似的な不良品画像を生成できる画像生成AIを導入し、さらに、同システムが誤判定しやすい画像、すなわち、弱点を分析・特定する仕組みもあわせて開発することで、その弱点を克服する画像を生成し、弱点を集中的に訓練するループ(弱点トレーニング・ループ)を繰り返し回すことができるようにした。これにより、不良品画像が十分収集できていない状況でも、外観検査AIシステムの開発期間を大幅に短縮しつつ検出精度を向上することができたので報告する。
2.7 MB
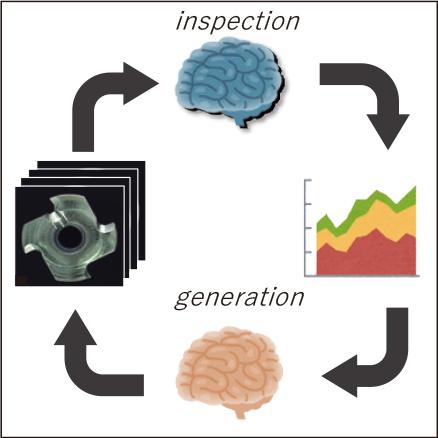
2.7 MB
当社では製品の外観検査を行うAIの開発・運用を進めている。そのようなAIを製造現場に導入するうえで、課題を二点挙げることができる。まずAIの開発に必要な画像データとその注釈(教師データ)の準備に多くの人手を要すること、次にAIの検査結果の根拠が可視化されず製造現場での信頼が得にくいことである。前者については、ChatGPTに も採用されたTransformerというAIに教師データを極力必要としない自己教師あり学習を応用し、後者については、AIの注視領域を明示する技術であるアテンションを応用して人の知見をAIに反映させる機能を開発したので報告する。アテンションを活用する方法として弊社独自のシグモイドアテンションを採用したことで、より明確にAIの判断根拠を可視化しつつ性能向上にも寄与することができたため、あわせて報告する
3.4 MB
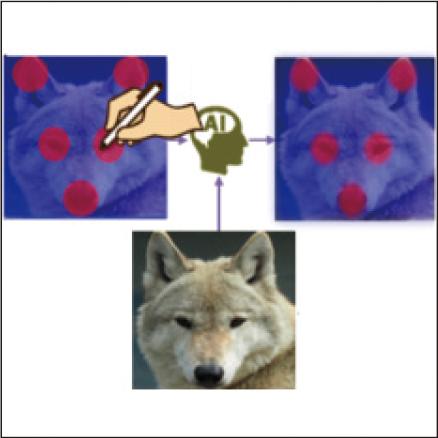
3.4 MB
AOC(Active Optical Cable)は端末に光電変換素子を搭載しマルチモードファイバにて光信号の長距離高速伝送(ex. 100m, 40Gbps)を実現する光ハーネスである。近年、医療/産機分野では高速信号伝送路中の電気ノイズ抑制を目的に、メタル線から光ファイバを用いたAOCへの置き換えが注目されている。しかしながら用途によっては電源供給等に依然としてメタル線が必要となるためメタル線と光ファイバを複合したAOC が必須である。また同分野では機器の小型化や可動部の増加に伴い、配線材に対して非常に高い機械信頼性の要求がされることが増えてきたが、光ファイバとメタル線の機械信頼性の差が問題となっていた。本報では、光ファイバと比較して機械信頼性の低いメタル線を、当社技術であるTCC(Thick Copper Covered)ワイヤーに専用の樹脂被覆を施しAOC に採用可能な機械信頼性の高いメタル線を開発したため、このUnbreakableActive Optical Cable(UB-AOC)について紹介する。
1.3 MB
近年、加熱用途におけるマイクロ波の利用が広がりを見せており、電子レンジの食品加熱をはじめとする民生用途に加え、産業用の食品加工や木材・樹脂等の乾燥、半導体装置のプラズマ生成等にもマイクロ波の活用が進んでいる。従来、マイクロ波加熱においては安価で高出力が得られる真空管素子のマグネトロンが主流であったが、近年では長寿命、高信頼性、低雑音といった特長を持つGaN HEMTが注目されている。更にGaN HEMTには位相・周波数・出力電力の制御性が高い利点があり、均一加熱や部分加熱といった新たな加熱機能の実現が可能になる。
0.9 MB
船舶用レーダは航行、衝突回避、気象監視に用いるレーダとして使用され、使用周波数はX 帯やS 帯である。近年では自動航行を目指した安全性重視の高まりにより、レーダ需要の拡大が見込まれている。また、マグネトロンなどの真空管素子から窒化ガリウム高電子移動度トランジスタ(GaN HEMT)といった固体素子への置き換えが進んでいる。その背景としてマグネトロンは寿命による交換のサイクルが1年から2年と短く、運用コスト上昇の一因となることが指摘されている。一方、固体素子は10年以上の長期信頼性を持つことでマグネトロンのように定期的な交換が不要となり、運用コストの削減が期待できる。また、パルス圧縮等の技術を用いることでマグネトロンと比べ、より小さい電力で同等以上のレーダ性能を実現可能となることから今後も需要の拡大が期待される。
0.6 MB
産業素材部門は、当社5セグメントの中でも唯一市場別でなく、素材という当社側の製品分類によって纏められた部門であり、従い、各事業分野における顧客や市場、アプリケーション、それに向けた研究開発の方向性には統一性が見出しづらい。一方で、産業素材各部門それぞれで、素材、材質に特徴を持たせ、それを当社の優位性として他社との差別化を図ろうとする点や、その開発に後述する計算科学、機械学習等を用い、科学的かつ効率的な研究開発アプローチには共通性も見ることができる。今回、産業素材特集発刊にあたり、素材にフォーカスを当てた各事業での開発の歴史と今後の方向性を簡単にご紹介する。
1.2 MB
切削加工では加工中の刃先を直接見ることができないため、加工条件の最適化には熟練作業者の勘や経験に頼ることが多かった。近年、工作機械に内蔵された各種センサから総合的に切削力などの加工状態を監視する技術が実用化されている。しかし、切削点から測定点が遠く、その感度や精度は十分ではない。そこで、当社では切削点に最も近いインサートやドリル、エンドミルを保持するホルダにひずみセンサを組み込みデータを無線で機外に転送することで、加工中の切削力が測定できるセンサ搭載切削工具、センシングツールSumi Forceを開発した。Sumi Forceは工作機械に簡単に取り付けられるため、顧客実機、実製造ラインでも切削力の測定が可能である。本稿では、Sumi Forceを活用して、顧客の加工を最適化するソリューションサービスと、切削力の変化から工具摩耗や工具の欠損などの異常を検知する技術の開発について報告する。
3.8 MB

3.8 MB
切削工具に対するニーズは年々変化しており、電動化が進む自動車産業ではアルミ合金製部品をより高能率で加工するため工具の軽量化が求められている。航空機産業では、エンジンの騒音低減や燃費向上のため、切削熱の発生が著しい難削材であるニッケル基合金やチタン合金の使用量が増えており、刃先をより効果的に冷却可能な内部給油式工具が求められている。当社ではこれら市場ニーズの変化に対応するため、Additive Manufacturing(AM)を活用した革新的な工具の開発を進めている。今回、AMによる複雑な内部構造の形成を活用し、肉抜きで軽量化しつつ刃先剛性を維持したアルミ加工用カッタ、および、内部流路の最適化で刃先全体を均一に冷却可能な難削材用カッタを実現した。
6.9 MB

6.9 MB
近年、自動車産業をはじめ各産業分野でGX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けた取り組みが進んでおり、切削加工工程でもCO2排出量の削減が要求されている。CO2排出量削減には工作機械の消費電力量低減が効果的であるため、工作機械の稼働時間を低減できる高能率加工に特化した工具への需要が高まっている。この要望に応えるため、当社ではアルミ加工用の「マルチドリルMDA型」、および鋼・鋳鉄加工用の「マルチドリルMDH型」を開発した。「マルチドリルMDA型」は高い加工精度を維持しながらアルミの高能率加工を可能とし、「マルチドリルMDH型」は鋼・鋳鉄加工時の負荷および消費電力を低減しつつ高能率加工を実現する。これらの工具により穴あけ加工での省電力化に貢献する。
9.5 MB

9.5 MB
自動車部品などで用いられる鋼の切削加工においては、環境負荷の低減や資源の効率的な活用を目的とした様々な取り組みが進められている。当社は連続加工から断続加工まで幅広い加工環境での安定加工を実現する工具として2016年に新CVDコーティング技術「Absotech」を適用した鋼旋削材種AC8000Pシリーズを発売し、順次製品ラインアップを拡大している。近年の鋼旋削加工では特に加工時間の短縮や切削液を使用しないドライ加工への要望が以前にも増して高まっている。当社はこれらのニーズに応えるべく、高能率加工やドライ加工で特に優れた性能を発揮する新材種「AC8115P」を開発した。これらの加工おいては工具刃先が高温になるため、工具の摩耗進展や塑性変形の抑制が課題となる。「AC8115P」は耐摩耗性と耐塑性変形性を大幅に向上させた材種で鋼旋削加工において加工コストおよび環境負荷の低減に貢献する。
8.2 MB

8.2 MB
チタン合金は軽量かつ高強度であり、耐食性にも優れることから、航空機産業で多用されているほか、生体親和性も高いことから、医療産業向けの用途も拡大している。近年、これらの産業は伸長が著しく、それに伴いチタン合金を加工する工具の需要は今後大幅に増加すると見られている。一方、チタン合金は工具との化学反応による凝着や、熱伝導率の低さによる加工時の摩耗で、工具の寿命が著しく低下する問題がある。そこで当社ではこのようなチタン合金の旋削加工において、安定長寿命を実現する新しい工具材種「AC9115T」および「AC9125T」を開発した。これらの新材種はチタン合金の旋削加工において当社従来材種と比較して2倍以上の長寿命を実現し、加工コストを大幅に低減させることが可能となった。
8.7 MB

8.7 MB
スミボロンCBN工具は、ダイヤモンドに次ぐ硬度と熱伝導率に加え、鉄系金属との反応性が低いcBN粒子を金属やセラミックの結合材で結合させた焼結体を用いた工具であり、高硬度で削りにくい焼入鋼加工や高精度加工が求められる鋳鉄・焼結合金加工の加工能率向上やコスト低減に貢献してきた。近年、自動車や建設機械等の重要な構成部品である鋳鉄・焼結合金部品の加工では部品の高精度化に伴う高い寸法精度と表面性状に加え、製造ラインの省人化に伴う安定長寿命と高能率化の需要が高まっている。今回これらの要求に応えるため、「BN7115」と「BN7125」を開発した。「BN7115」は耐チッピング性を改善した仕上げ加工用新材種であり、高い加工面品位が求められる場合においても安定加工を実現する。「BN7125」は耐欠損性を改善した汎用加工用新材種であり、工具負荷が大きい環境下でも安定長寿命を実現する。本稿ではBN7115とBN7125の特長と性能について述べる。
3.1 MB

3.1 MB
スミボロンCBN工具は、cBN粒子にセラミックス若しくは金属結合材を混合して焼き固めたCBN焼結体を用いた切削工具である。中でもコーテッドスミボロンは 、自動車部品などの素材である焼入鋼を加工する工具材料として適用範囲を拡大してきた。近年の製造現場では、部品加工の多様化に伴う変種変量生産体制や環境対応の重要性から設備の消費電力低減によるCO2排出量削減、価格競争に対応するために生産ラインの省人化を構築する傾向にあり、切削工具には高能率化と長寿命化の強い要求がある。様々な部品形状におけるこれらの要求に応えるため、当社はBNC2100シリーズと題した「BNC2105」「BNC2115」「BNC2125」「BNC2135」の4材種を新たに製品化した。
4.3 MB

4.3 MB
PC鋼材の緊張作業は、コンクリート構造物へ適切なプレストレス力を導入する作業であり、構造物の耐久性に影響を及ぼす重要な工程である。この緊張作業において、従来はPC鋼材の緊張機器を手動で操作し、アナログ式測定器を目視で読み取って記録するという作業が行われていた。そのため、作業に人手を要する、測定値において人の読み取り誤差が生じる、動作中の緊張機器に人が近づく必要があるといった課題があった。自動緊張管理システムは制御装置やデジタル式測定器を用いてこれらの作業を自動化する緊張機器であり、緊張作業の省人化、測定精度の向上、安全性の向上に寄与する。本稿では無線通信を採用することで通信ケーブルの配線を不要とした無線式自動緊張管理システムの概要ならびにその適用例と適用効果について報告する。
7.7 MB

7.7 MB
ゴム製品の補強材として用いられるスチールコードは、燃費、耐久性、操縦安定性、騒音対策等を高い水準で要求される自動車用タイヤにとって重要な部材である。従来の開発では、要求性能から適切なスチールコードを実証的に検討し、多くの評価を実施、必要に応じ修正するプロセスを繰り返していた。しかし、この手法では試作評価に膨大な手間、時間等のコストを要し、開発期間が長期化すること、廃却屑の発生等によりサステナブル社会の実現に向けた対応が困難であること、また、タイヤ性能はタイヤ設計因子の影響も受けることが課題となっていた。当社はスチールコード特性も反映できる性能予測技術を開発することで、これらの課題に対処した。結果、スチールコードを含むタイヤ設計における仕様検討、絞込み及び評価の技術的解釈を高い精度で効率よく実施可能となった。タイヤ性能向上、SDGsへの貢献を達成することにもつながり、顧客からも高く評価されている。
2.6 MB

2.6 MB
高強度鋼線(ばね用鋼線)を用いた、高い刈取能力を有し、安全な草刈り機用刈刃への適用検討を行った。当社製異形線を用いて刈刃を製作し、(国研)農研機構の圃場にて刈払機およびリモコン草刈り機による実証試験を行った。鋼線の断面形状を、単純な平角線から、鋭角な頂部を有する5角形断面とすることで、従来のチップソーに匹敵する刈取り性能が得られた。リモコン草刈り機では、ナイロンコードでは不可能な、直径10mmを超える灌木や、木化した植物を刈取ることができた。また、刈刃の取付け部を回転可能なフリー刃構造とすることで、鋼線刃の疲労破壊を抑制するとともに、キックバック(危険な反動現象)を起こさない刈刃が得られた。一方で、石跳ね試験では却って石の飛散が大きく、硬質物との衝撃試験では取付け部強度に課題が見られたので、対処方法を提案した。
9.8 MB

9.8 MB
カーボンニュートラルの実現にはCO2排出量の削減と同時にCO2吸収量を増大させることが必要となる。CO2吸収量を増大させる方法には、CO2を原料とするものづくりであるカーボンリサイクルがある。ここでは当社製造現場と親和性のある鉄とCO2から機能性素材である炭酸鉄(商標名:metacol)を生産する方法について報告する。炭酸鉄を自社製品に活用し、排出されたCO2を材料循環に取り入れて大気から隔離し続けることを目指す。原理検証、機能性評価、装置設計、工場実証、知財保護を経て、今後は顧客価値を検証する。CO2収支マイナスの達成と採算性を確認し、カーボンリサイクルを通じたカーボンニュートラルへの貢献を目標とする。
1.2 MB
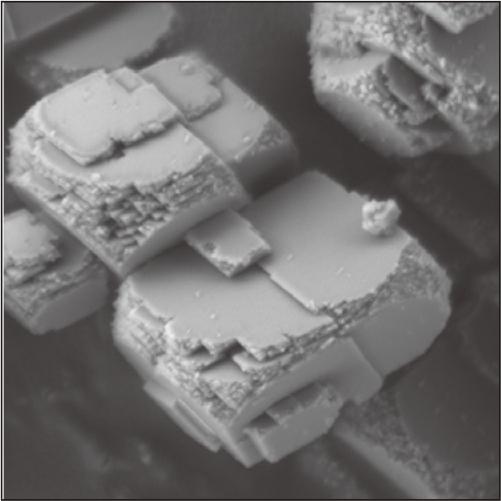
1.2 MB
サステナビリティ社会の実現に向け、圧粉磁心とそれを採用したアキシャルギャップモータ(AGM)を開発した。圧粉磁心の製造過程におけるCO2排出量は電磁鋼板に対し約1/4と試算され、更に、モータステータを粉砕して得られた粉末を圧粉磁心の原料として再利用する水平リサイクル技術を開発、リサイクル前後での磁気特性変化がほとんどないことを実証した。また、駆動モータを想定した75kW級では出力密度12.6 kW/kgのAGMを設計し、圧粉磁心とAGMが高出力密度化による部材使用量削減に有効であることを示すとともに、20kW級では製造時のCO2排出量が低いフェライト磁石を採用したAGMにて、Nd焼結磁石を採用したラジアルギャップモータと同体格・同出力・高効率を実証した。
4.5 MB

4.5 MB
粉末冶金法は粉末を金型で圧縮して成形体を作製し、焼結することで高強度化させる製法である。成形型構造の工夫によって完成品に近いニアネットシェイプでの成形が可能となる。サポートパーキング部品は、ガソリン車だけでなく、ハイブリッド車や電気自動車など多くの車種に搭載されており、駐車時に車輪の回転を止めるパーキングロックシステムに使用され、その形状は多種多様である。今回、粉末冶金法の形状自由度を活かしてサポートパーキング部品の開発に成功し、焼結市場拡大に貢献できた。具体的な開発事例である、粉末除去による密度バランス調整、異形2個押し成形、横溝(アンダーカット)2個押し成形、複数部品一体化を紹介する。さらに、部分的にレーザー焼入れを適用することで精度を確保しながら環境に配慮した開発も実現できた。
2.4 MB

2.4 MB
脱炭素を実現する有力候補の一つであるフュージョンエネルギーの研究活動が盛んになっている。核融合炉の構成機器のうち、2000℃を超える超高温に晒されるダイバータにはタングステンが使用されている。発電実証に向けた原型炉では長時間の運転が想定され、核融合炉に用いるタングステン(W)材料にはより高い機械的健全性が求められる。㈱アライドマテリアルでは大学などとの共同研究を通して種々の材料を試作評価し、カリウム(K)ドープWの有効性を見出してきた。これを実際にプラズマ対向機器に適用してくことを目標にプラズマ対向機器に適用可能な規模を有するKドープW厚板を開発した。本稿ではそれら材料の主な特性の評価結果について報告する。
3.3 MB
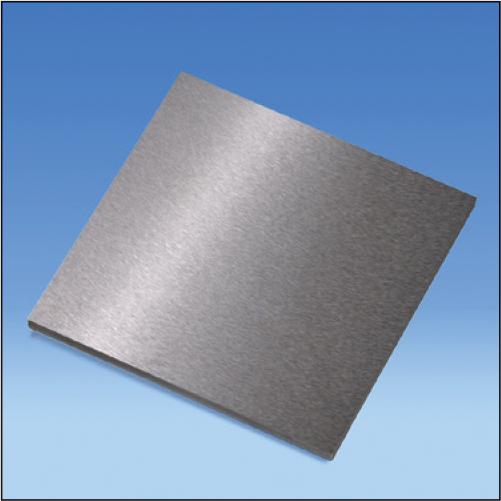
3.3 MB
近年、米国では歩行者の死亡事故が急増しているため、交通事故防止を目的とするシステムに使用する横断者検知センサの需要が高まっている。しかし、既存センサの多くは垂直方向の検知範囲角度が十分ではない。実際の交差点では、センサは高所に設置されるため、センサ直下付近が死角となる。そのため、設置地点と横断歩道が隣接する場合、横断歩道の一部や横断歩道の流入口に存在する歩行者を検知できない。この課題への対策のため、筆者らはレーダにカメラを組み合わせたフュージョンセンサを試作した。このフュージョンセンサは、カメラがセンサ直下の横断者を検知することでセンサ直下の死角を解消する。また、カメラ画像に対して物体認識AIを用いることで、レーダ単体では困難であった検知対象の種別の識別も可能となる。本稿では、試作したフュージョンセンサ構成の紹介と性能検証実験の結果を報告する。
7.7 MB

7.7 MB
電線ケーブル製品はその実使用環境を想定し、曲げをはじめとした様々な外力印加時の振る舞いを評価することが重要である。我々は、最新のX線CT装置を用いた外力を印加しながら観察を行う技術、および画像解析を始めとしたデータ解析技術、を活用し、ケーブル製品の外力に対する動的振る舞いの評価を推進している。本稿では前半で、最新のX線CT観察事例(曲げた状態での観察および、従来困難であった1メートル級の大きな試料の観察)を紹介し、後半では曲げ変形を受けたケーブル製品のX線CTデータに対する画像解析技術を紹介する。これらには当社独自の技術が詰まっており、ハード面・ソフト面の両方の技術に基づき、各種製品の外力下での動的振る舞いを明らかにすることで、よりよい設計や品質課題の解決に活かしている。
4.2 MB
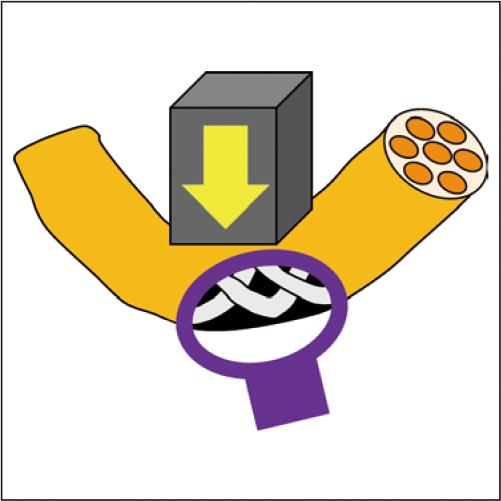
4.2 MB
地域新電力会社向けとして初めてのレドックスフロー電池設備を柏崎あい・あーるエナジー㈱(新潟県柏崎市)に納入した。再生可能エネルギーの導入拡大が進む中、今後導入が加速するとされている6時間以上の長時間容量蓄電池を直接電力系統に接続した蓄電所の導入事例である。
1.5 MB
磁石、セラミックスなどの焼成工程ではモリブデンの板・棒材により製造した焼成用敷板、高温炉のヒーター、リフレクタが数多く利用されている。焼成物の品質向上のために、焼成時のガス抜き性、敷板と焼成物の固着抑制などの観点からモリブデン製のメッシュ(網材)の需要が高まっている。このメッシュ材は直径0.5mm以下の線材により製作される。本報では、モリブデンメッシュとともに、実使用時に確認された“ほつれ”や“高温使用による破損”という問題に対し、改良を施した「折り返し付メッシュ」や「耐折損性向上メッシュ」を紹介する。
1.3 MB
長期間の使用が前提である光ファイバにおいて、ガラスファイバを保護する被覆層の長期信頼性は非常に重要である。この長期信頼性には内層被覆であるプライマリ層の硬化物性が密接に関係しており、製造条件を最適化するには任意の被覆硬化条件で硬化物性を予測することが望ましい。被覆には紫外線照射で硬化する紫外線硬化型樹脂が使用されている。その硬化反応は、多成分ゆえの機構の複雑さから物性予測が困難であった。今回、我々は光重合開始剤の反応のみに着目し、化学反応速度論に基づく光重合開始剤濃度の解析式を新たに導出した。更に、硬化後の光重合開始剤消費率に対する検量線を得ることにより、プライマリ層の被覆物性を予測することをも可能とした。
1.6 MB

1.6 MB
光通信トラフィックの急速な増加に対応するべく、光デバイスを高密度に集積して大容量化させる一方で、光デバイスの発熱による特性の劣化が問題となっており、高温環境下でも特性が劣化しにくい温度特性に優れた半導体レーザが求められている。我々は、量産性の高い有機金属気相成長法による独自の低温成長技術を展開し、光通信に適した1.3 µm帯GaAs基板上GaInAs/GaAsSb/GaInAsタイプⅡ活性層レーザを作製した。しきい値電流密度の特性温度は25℃~100℃において152 Kと、従来のInP基板上InGaAsP系レーザの60 Kを大きく上回る値が得られた。タイプⅡ活性層を用いることで高温環境下でも特性が劣化しにくい1.3 µm帯半導体レーザを実現可能であることを示した。
1.4 MB
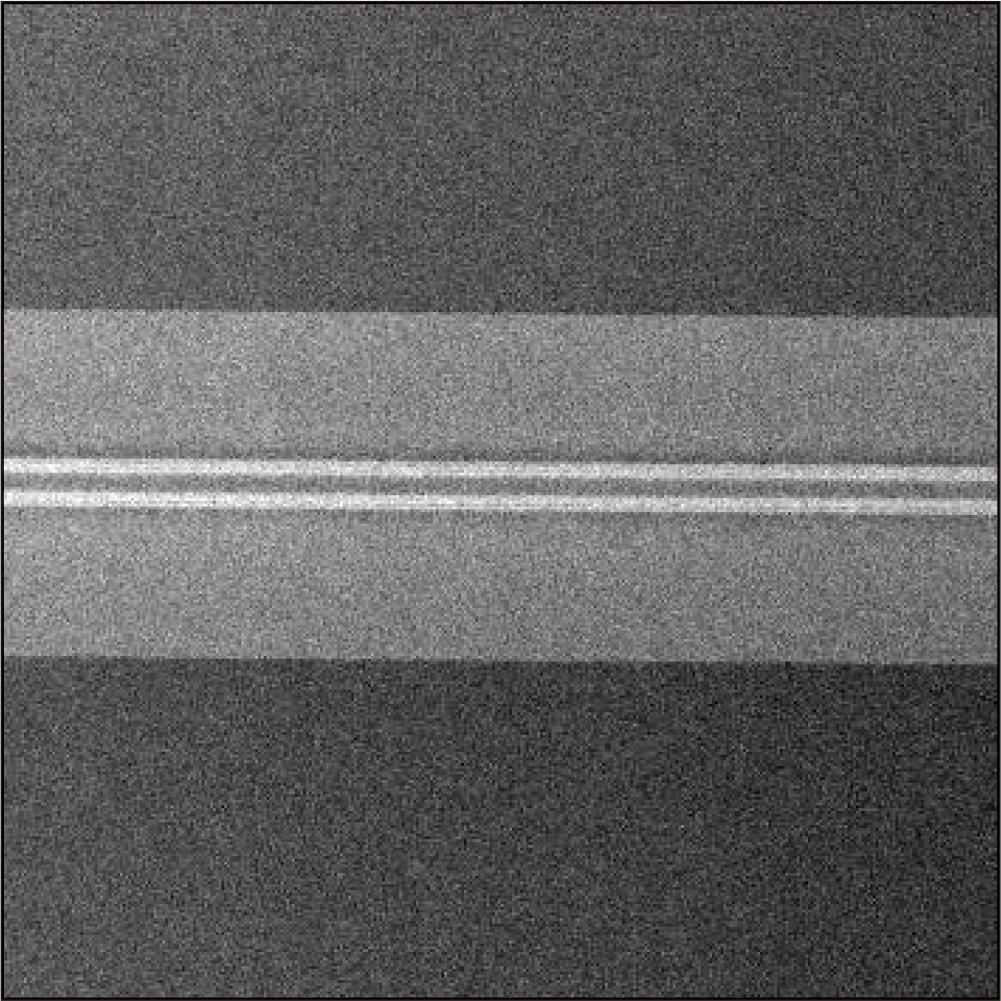
1.4 MB
生成AIやHPCの需要増加に伴ってデータセンタ内通信の高速化及び省電力化の重要性が高まり、Co-Packaged Optics(CPO)へ注目が集まっている。CPOの構成部品であるExternal Laser Sources(ELSs)には数百mWの高光出力と電力変換効率20%以上の低消費電力性が求められており、本稿ではCPO向けのELSsである1.3 µm帯高出力半導体レーザにワイドストライプ導波路の半導体光増幅器(SOA)を集積し、またそれぞれ素子を電気的に分離した素子構造を用いることで電力分配の最適化を可能とし素子温度45℃にて400 mWを超える光出力と25%の電力変換効率を実現したことを報告する。
1.7 MB
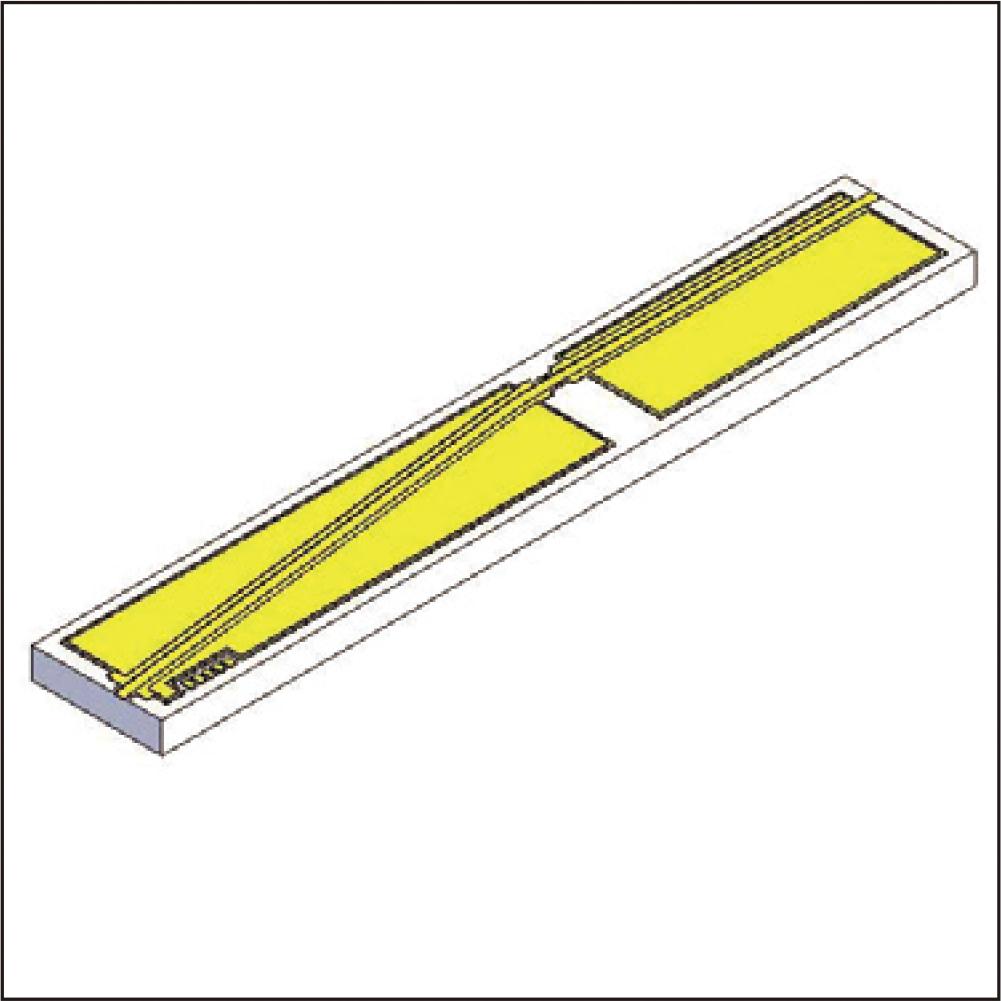
1.7 MB
5G無線アクセスネットワークにおけるモバイルフロントホールでは、通信トラフィックの増加に対応するため25Gbit/sの伝送速度が広く採用され、波長分割多重方式を駆使した光ファイバ利用効率の向上が期待されている。特に近年、アンテナ装置と中央拠点に集約された無線制御装置を繋ぐモジュール間で波長可変光トランシーバの需要が高まっている。今回我々は、モバイル・アクセス市場向けに低消費電力動作が可能な8波長可変電界吸収型変調器集積レーザを開発し、その諸特性を小型送信機ならびに25Gbit/s DWDMトランシーバ(SFP28)に搭載して評価したので、ここに報告する。
1.8 MB
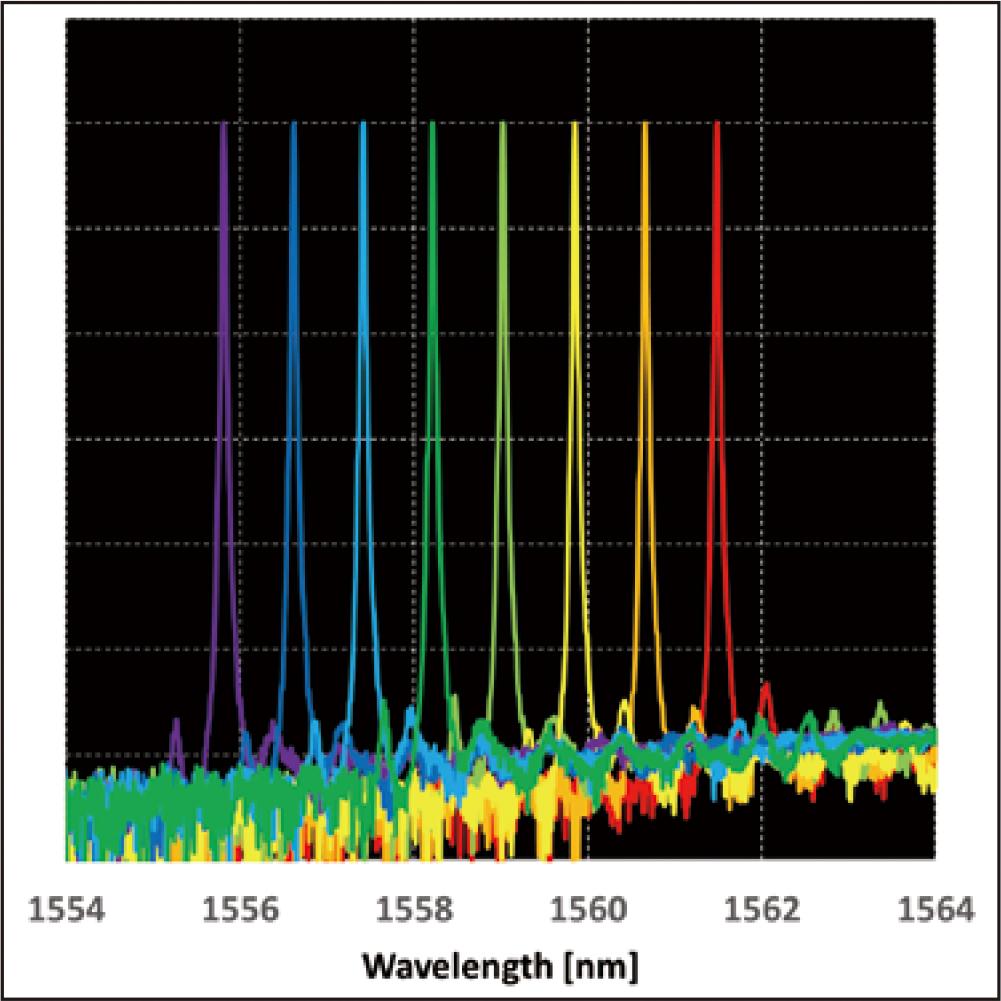
1.8 MB
HVDC技術と高分子絶縁技術が進歩するに従い、絶縁体中の電気伝導および空間電荷挙動の正確な評価の需要が増している。通常、これらの計測は、試料中の弱い電流を計る微小電流計測や、空間電荷挙動を計るパルス静電応力(PEA)法など、測定対象に応じて適切な手法が選択される。しかしながら、それは、これらの手法が特定の物理現象に特化しており、計測にしばしば特別な処理が必要であることの裏返しでもある。日本では、最近、電流が関わる現象を相補的かつ俯瞰的に理解しようと、「電流積分法」(Q-t法)の利用が増えている。Q-t法は、積分コンデンサを試料と直列に接続し、試料内を流れる弱い電流を積分して電荷量として計測する方法である。積分により得られる利点を誘電計測に活用するため、材料の選別・評価の他、絶縁体の状態診断、使用限界条件の把握など広い応用範囲を考えることができる。ここでは、Q-t法の特長とその応用例をいくつか紹介する。
1.7 MB
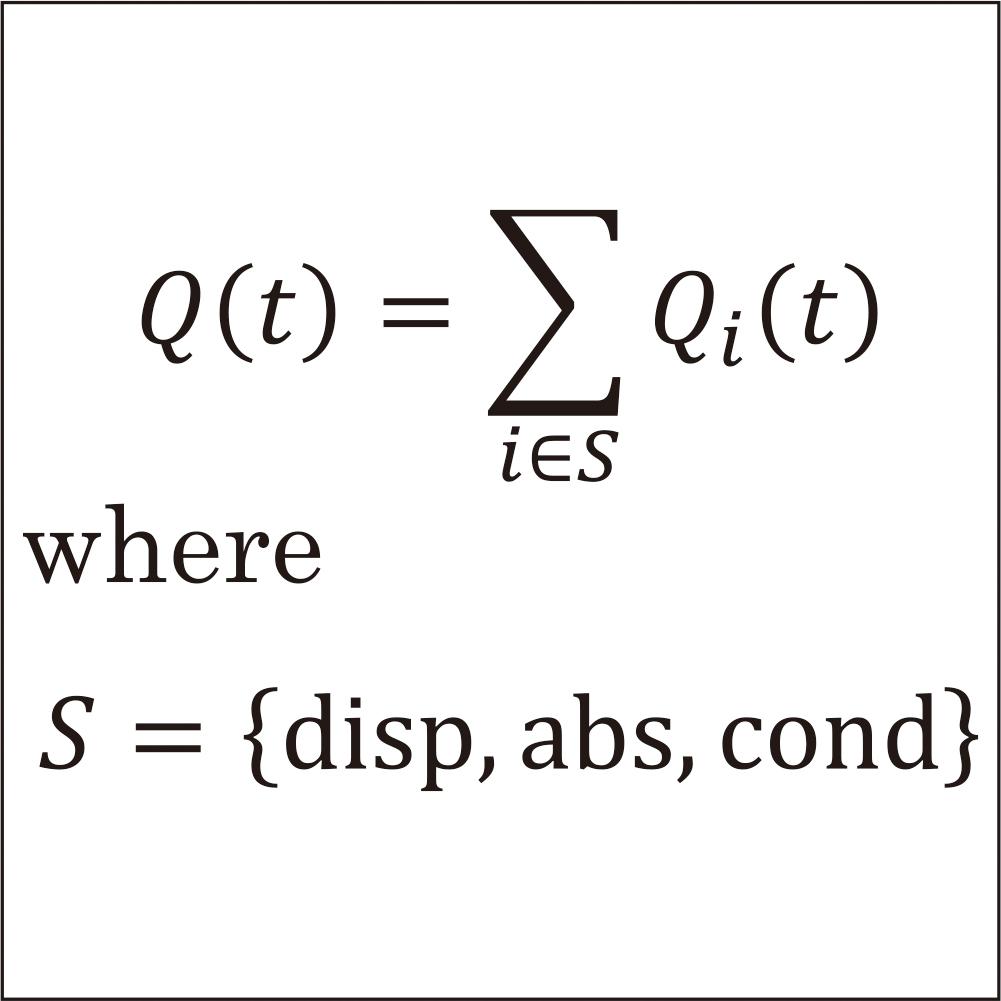
1.7 MB
近年、地球環境への負荷低減、資源の効率的な活用を目的とした様々な取組みがなされており、自動車等に用いられる鋳鉄部品加工の分野でも、軽量化が急速に進んでいる。軽量化に伴い、各構成部品はより薄肉、複雑形状化し、薄肉化した場合にも十分な強度を確保する必要性から、使用される被削材はより高強度・難削化し、工具寿命の低下が課題となる。また、加工現場では、コスト削減要求の高まりや、工作機械の性能向上を背景に、高速・高能率加工への要求が以前にも増して高まっている。そのような鋳鉄加工市場での課題を解決するため、鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド新材種「AC4125K」を開発した。「AC4125K」は鋳鉄の鋳肌・断続加工における圧倒的な安定・長寿命化を実現する。さらに使用済みコーナーの視認性に優れるため、工具の誤使用や誤廃棄の防止を可能とする。これにより鋳鉄の幅広い加工において、加工コストの低減を可能とした。
5.3 MB

5.3 MB
高い空間分解能を有する走査型透過電子顕微鏡(STEM)は、結晶材料の原子レベルの構造解析に不可欠のツールである。金属やセラミックスなど多結晶材料の場合、結晶粒子の界面が材料特性を左右することが多いが、粒子同士はランダムな方位で接合しており、STEMで解析可能な方位で接合している粒子ペアを効率よく抽出することは困難であった。この問題に対し、本研究では電子後方散乱回折法(EBSD)を活用した新しい結晶方位解析技術の開発に取り組んだ。超硬合金の一種である炭化タングステン(WC)とコバルト(Co)の焼結体試料を反射と透過の2種類のEBSD法で観察し、特に透過EBSDにより実用的なスループットでSTEM分析可能な粒子界面の抽出が可能であることを確認した。更にSTEM分析も実施し、WC粒子界面のステップ構造や析出するCo分布の偏りを捉えることに成功した。今回開発したSTEMとEBSD法を組み合わせた分析は、多結晶材料の特性改善を図るための界面構造解析に極めて有効な手法と言える。
4.1 MB
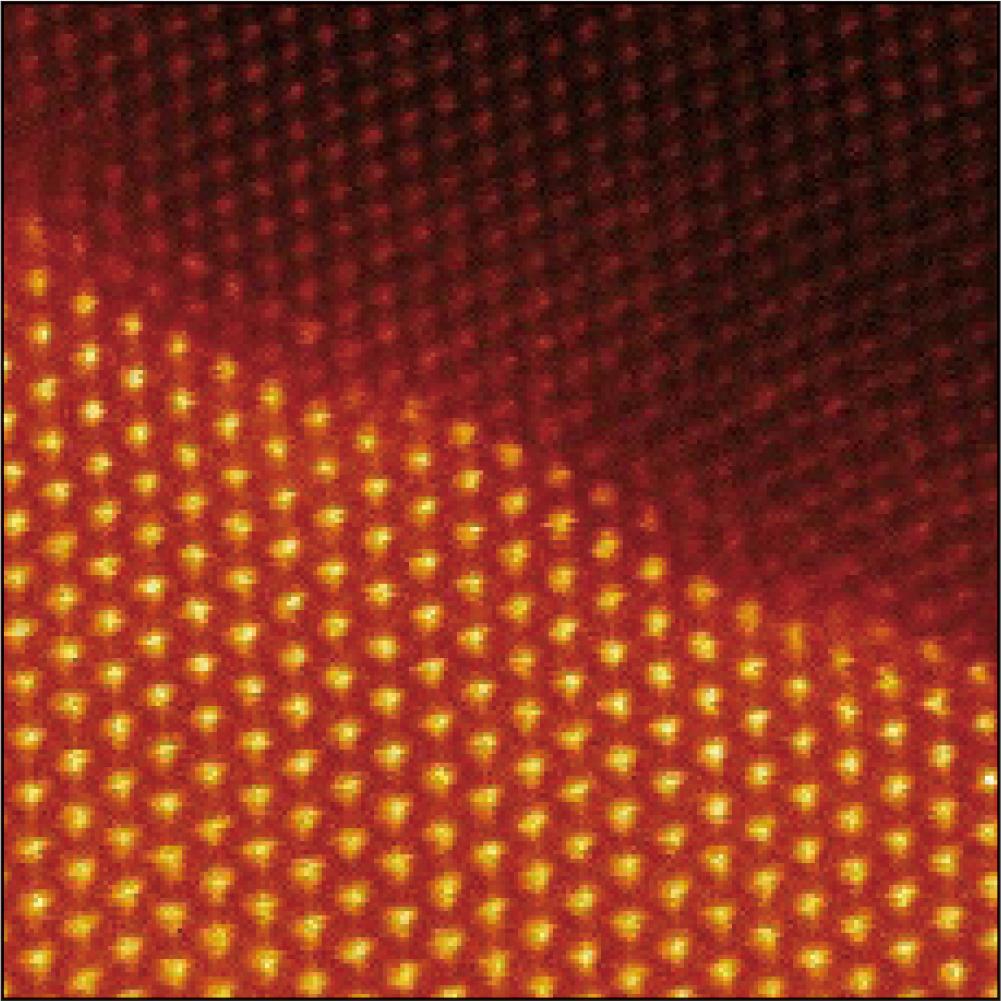
4.1 MB
近年、技術の発展に伴って、高性能なレーダの需要が高まっている。これまで、電子管や低出力・低周波の半導体素子を用いられていたものが、レーダの探知距離の拡大化や高精度化のため、高出力・高周波数に最適なGaN HEMTが採用されている。高出力を考慮されたレーダとしてアクティブ・平面フェーズドアレイがあり、個々の素子アンテナを格子状に配列し、電磁波として放射される電力は空間合成され、さらに励振位相を変化させてビーム走査を行う。そのため素子アンテナに内蔵されるGaN HEMTは配列される間隔を搬送周波数の1/2~2/3にする必要があり、X帯であれば、最大でも19mm間隔で配置される。つまり、パッケージ幅をより小さくする必要がある。
0.7 MB
モバイル通信市場では、4Gから5Gへと高速、大容量、低遅延、多数端末接続など、様々なコンテンツサービスの創出につながるモバイル通信サービスの導入が進んでいる。このサービスを様々な場所で使えるよう、高層ビルや屋内施設、地下街などの携帯電話がつながりにくい場所では、通信キャリアのネットワークと接続した基地局を設置し、その基地局から屋内無線装置に信号を送る屋内基地局設備を導入し、サービスの展開を図っている。この屋内基地局設備の無線装置への配線では、給電線と光コードを一体化した光複合給電ケーブルが使用されている。今回給電部と光部をケーブル状態で分離可能なセパレート構造の平形光複合給電ケーブルを開発し、販売を開始した。
1 MB
タングステンカーバイド粉を主原料とする超硬合金は高硬度で摩耗に強く、切削工具として用いた場合に加工コストや時間を削減できることから、自動車や航空機、電子機器などの幅広い分野で活用されている。より小さい部品に多機能、高機能が求められる昨今、高精度な工具が必要であり、シャープな形状を実現できる微粒WC粉を原料とした超硬合金の需要が高まっている。
0.9 MB
当社の自動車事業は、ワイヤーハーネスを中核として長期的な成長を遂げてきた。一方で近年、自動車業界には100年に一度と言われる“CASE”の変革の波が押し寄せている。この変革は単にクルマに「コネクティッド」、「自動化」、「シェアリング/サービス」、「電動化」といった要素を導入するにとどまらず、クルマの社会的な位置付けをも変えてしまう可能性を秘めており、将来的に自動車の産業構造が大きく変わっていくことが予見される。
1.4 MB
自動車業界は100年に一度と言われる変革期を迎え、とりわけ地球温暖化の一因であるCO2排出ガス削減に向けて電気自動車(EV)の世界的な普及が進みつつある。一方、再生可能エネルギーの普及に伴う電力系統の受給バランスの乱れに対応する電力調整力も必要になると考えられている。これまで住友電工グループは、モビリティサービス関連製品としてEVの快適な走行を支援するTraffic Vision Green、エネルギーサービス関連製品として分散電源の最適な運用計画を立案するsEMSAなどの提供を通じて社会に貢献してきた。今後、モビリティとエネルギーをつなぐシステムを一括して提供することで、EV稼働状況を考慮した有効かつ経済的なエネルギーマネジメントシステム(EMS)の提供が可能と考えている。本稿では、住友電工グループのモビリティとエネルギーを融合させたEMSに対する過去実績及び将来に向けた取り組みについて報告する。
2.1 MB

2.1 MB
各国でのCO2排出抑制に向けた燃費・排ガス規制の政策により、今後も電動車(HEV、PHEV、BEV等)は増加し、特にBEVの普及が加速すると予測される。当社は電動化車両向けの電池パック内接続部品(電池配線モジュール、高圧ジャンクションボックス、ワイヤーハーネス等)の開発・量産を行っており、今後増加するBEVの進化に応じた開発を推進している。電池パック内接続部品は、電池パックの性能向上に大きく影響し、小型・省スペース化、大電流化の対応、安全性の向上が求められている。本稿では、接続部品の内、電池配線モジュール、高圧ジャンクションボックスの製品概要、要素技術の特徴について紹介する。
3.1 MB
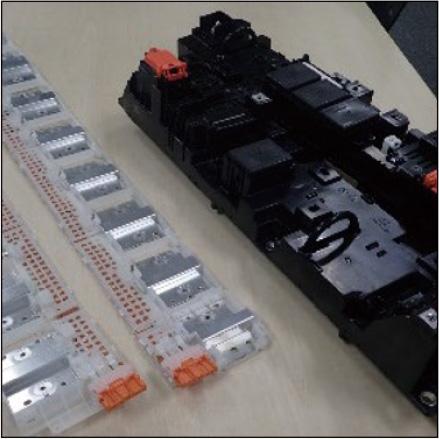
3.1 MB
自動車産業はCASEにおける技術革新により、自動車の知能化が進み、車載システムの開発期間は増加の傾向にある。その一方で、製品を早く市場に投入することで競争力の向上が求められている。㈱オートネットワーク技術研究所では、最適なアーキテクチャを短期間に導出するため、アーキテクチャ検証にデジタル技術を活用する取り組みを行っている。本稿では、ゾーンECUの搭載数、バリエーション数を設計パラメータとしたときのアーキテクチャ検証フローへの数理最適化の適用を行い、さらに導出した結果から設計パラメータの最適条件の予測を行う応答曲面法を組み合わせることで、従来と比較して検証時間を短縮することができたので、その取組みについて紹介する。
1.6 MB
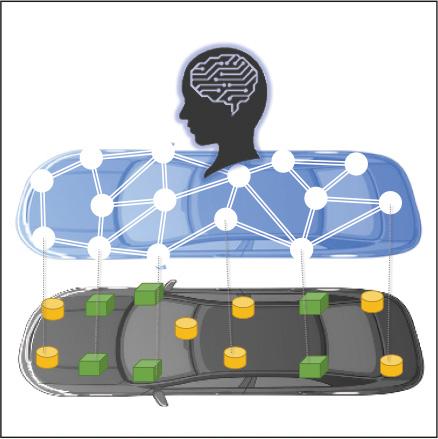
1.6 MB
近年、自動車の電子制御システムにもイーサネットの搭載が進んでおり、自動車の電子制御システムに適したサービス指向プロトコルとしてSOME/IP(Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP)プロトコルが採用されてきている。SOME/IPプロトコルではサービスを探索するためのプロトコルであるSOME/IP-SD(Service Discovery)プロトコルを実行した後、サービスを受信することが可能となる。しかしながらその一方で、SOME/IP-SDプロトコルの保護が十分でなくセキュリティリスクがあることが課題となっている。このため、本稿ではSOME/IP-SDプロトコルに対する保護を実施するための拡張プロトコルについて提案する。さらに、提案プロトコルを評価し、他のプロトコルよりも優位であることを示す。
1.1 MB
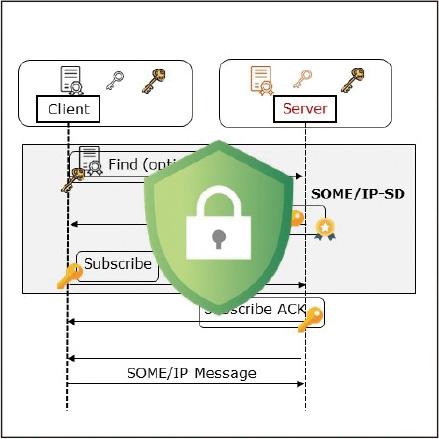
1.1 MB
近年、車両のCASE進化による車載ネットワークの高速化ニーズが高まり、次世代通信として車載イーサネットが注目されている。本通信用部品は、標準化団体Open Allianceが定める厳しい通信規格に適合する必要があるため、100Mイーサ適合検討をおこなった。まず、既存のCAN用部品による特性評価においては、電線、コネクタ共に伝送特性、クロストーク特性共に適合しなかった。そのため、新規電線、コネクタを開発すると共に、高速通信部品開発に必要な端末加工技術開発、CAE解析技術開発、通信特性評価技術開発を実施した結果、通信規格に適合することができた。当社は高速通信部品をワイヤハーネスの重要部品と考えており、今後も開発を推進する。
4 MB
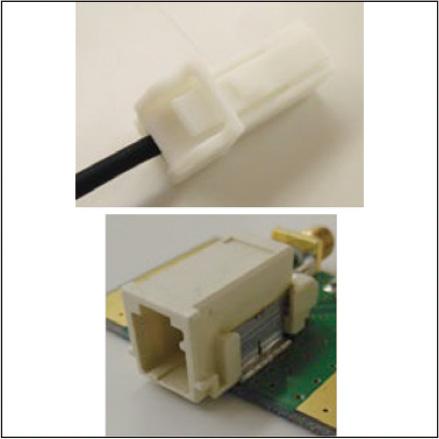
4 MB
CASEの実現に向け車両に搭載される機器の性能が向上する中、特に自動運転に関してはLiDAR等の大容量情報処理を必要とする機器の増加に伴い、車内データ通信に高速化が要求されている。この大容量データ通信の実現に向け住友電工電子ワイヤー㈱では、新規に設定される通信規格の逐次把握を行い、これに準拠する情報伝送サブハーネスの開発・製造を進めてきた。またサブハーネス加工においては、複数存在するデファクトスタンダードコネクタを効率的に生産できる自動加工設備の開発も行ってきた。本稿では、車載機器及び関連の通信規格の技術動向と機器間を接続する高速通信用サブハーネスの主要特性を占める 電線及び端末加工技術の開発・評価について概説する。
2.4 MB

2.4 MB
自動運転の実現に向けて、高速・大容量や低遅延といった特徴を持つ5Gの活用が期待されている。センシング情報など大量のデータ通信を行うためには、5Gにおいて数百MHzの帯域幅を確保できるミリ波帯の利用が望ましい。ミリ波帯での5Gアンテナは、送受信する電波の方向を制御するビームフォーミングに対応するため、複数のパッチアンテナ素子からなるアレーアンテナを用いる。しかしながら、このアレーアンテナを自動車のルーフ上に搭載する場合、放射特性が乱れてしまうという課題がある。本稿では、Electromagnetic Band Gap(EBG:電磁バンドギャップ)、Artificial Magnetic Conductor(AMC:人工磁気導体)といったメタマテリアル技術の応用によりこれらの課題を解決した、5Gミリ波通信に適したアンテナについて報告する。
3 MB
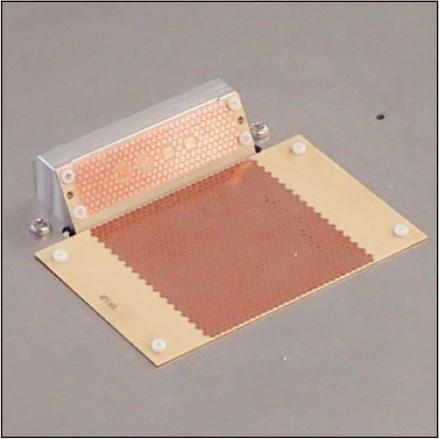
3 MB
自動車は自動運転化等のCASEに伴い、高機能化による搭載機器及び回路数の増加が進んでいるが、車室空間は快適性向上に向けて拡大ニーズがあるため、ワイヤーハーネス※2を省スペースで配索できる形態の変革が求められている。一方で従来のワイヤーハーネス製造はその複雑な作業故に自動化が難しく、現在も世界の各拠点で、多くの人員を雇用して製造を行っている。そのため、各製造拠点からの長距離輸送に伴うコスト、CO2排出という問題を解決できる形態を研究開発する必要があった。我々は自動車の商品力向上に向けた室内空間の拡大、且つ労働集約型から脱却し、地産地消※3を実現できる自動化に向けたワイヤーハーネスを開発し、大手自動車メーカーでの採用を実現した。本稿ではワイヤーハーネスの新規形態となるe-STEALTH W/Hに関する構造と技術を紹介する。
2.3 MB

2.3 MB
自動車の電動化の進展に伴い、モーターや減速機などに用いられる歯車や軸受といった転がり滑り環境下で使用される部品の耐久性向上や摩擦損失低減が重要になってくると考えられる。日本アイ・ティ・エフ㈱では用途に応じて様々なタイプのDLCをコーティングおり、その中でも水素フリーDLCは潤滑油中での摩擦低減効果が高いことが確認されている。この研究では、水素フリーDLCを歯車に適用した際の耐久性の変化や転がり滑り環境下における水素フリーDLCの摩擦低減効果の調査を行った。その結果、水素フリーDLCを歯車にコーティングすることで歯車の耐久性が向上することが確認された。また、『低粘度』、『高回転』、『高い滑り率』の環境下ほど、水素フリーDLCの摩擦低減効果が高いことが確認された。
1.7 MB

1.7 MB
車載コネクタ用端子は小型化が進み、端子用銅合金は薄肉、高強度化している。端子は主に曲げ加工によって成形され、銅合金の高強度化によって曲げ割れが起きやすくなっている。従来は経験に基づいたトライアンドエラーにより対策されていたが、近年の短い開発期間に対応するためCAEによる曲げ割れの予測技術が求められている。過去に曲げ割れの予測技術としては金属の結晶性を反映した特殊な弾塑性解析が報告されているが、実際の端子用銅合金への適用は困難であった。そこで、我々は曲げ割れの発生メカニズムから板厚方向のせん断に対する変形抵抗が曲げ割れ発生に大きく影響すると考え、薄板材の板厚方向のせん断試験方法を開発した。その測定結果を用いることで一般的な弾塑性解析で曲げ割れをシミュレーションで予測することが可能となったので紹介する。
2 MB
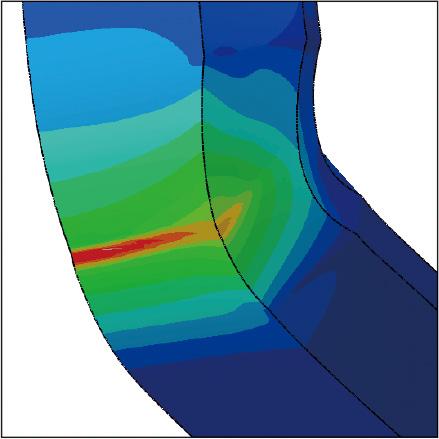
2 MB
近年、本格的な5Gのサービス利用が開始するなど、通信機器で使用する周波数の高周波化が進んでいる。通信の高周波化に伴い、従来問題とならなかった通信ケーブルからの不要電磁波放射がEMC問題に繋がる懸念があるため、筆者らは、車内通信などの配線として一般的に使用されているツイストペアケーブル(UTPケーブル)に着目して評価を行い、特定の周波数帯で不要電磁波放射が発生することを確認した。UTPケーブルからの放射は、漏洩ケーブルとの構造の類似性から、漏洩ケーブルと同一のメカニズムで説明でき、放射帯域は漏洩ケーブルの定式で記述できる。本稿では、UTPケーブルからの放射特性を紹介した後に、放射のメカニズムについて詳細を解説する。また、放射帯域の定式を基に、UTPケーブルを選定する際の指針を提案する。
2.8 MB

2.8 MB
データセンタの光配線では光ケーブルの細径多心化が求められており、光ファイバの細径化はその有力な手段の一つである。光ファイバを細径化することに伴う主要課題の一つは、ケーブル状態のマイクロベンド損失(MB損失)の増大である。光ファイバ構造を決定する際、この損失への影響を考慮しつつ複数のパラメータを調整する必要がある。我々は、Cocchiniが被覆外径250µmの標準的光ファイバを前提に提案した手法を応用し、被覆外径165µm以下の細径光ファイバ用にMB損失を予測可能な解析式を新たに導出した。これにより、任意の光ファイバ構造でMB損失を予測することが可能となった。
1.2 MB
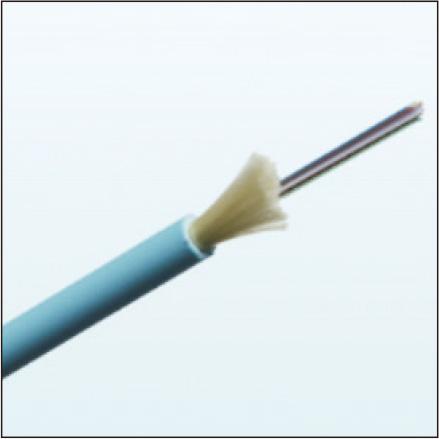
1.2 MB
本論文ではナノ構造Si-Ge熱電材料を用いたサーモパイル赤外線センサの特性について報告する。サーモパイル赤外線センサは電力消費なく動作できる特長がある。一方で、低感度であることが短所であった。私達はこの感度を向上するため、低い熱伝導率と高いゼーベック係数が期待できるナノ構造Si-Ge熱電材料の開発に取り組んだ。ナノ構造Si-Ge熱電材料は、従来のSi-Ge結晶と比較して、1/8倍の低い熱伝導率(0.8W/(m·K))と2.8倍のゼーベック係数(330µV/K)を示し、それを用いることで、サーモパイル赤外線センサの高感度化が期待できる。実際に、本材料を応用したサーモパイル赤外線センサは雰囲気圧力1×10-1Pa以下にて1200V/Wを示し、高感化を実現した。
1.4 MB
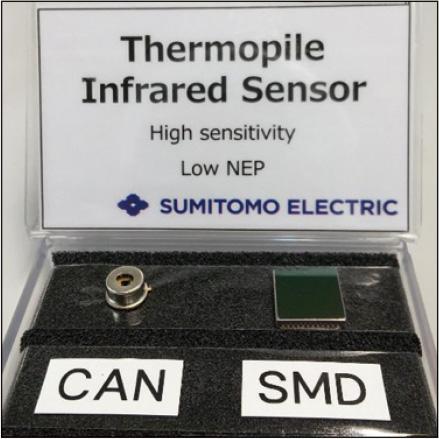
1.4 MB
カーボンニュートラル、CO2排出削減といった国際的な環境規制強化の動向に対し、年々発熱密度の増大が進む電子製品や車載電動化製品において熱マネジメントが重視されている。これまで主流であった空冷や水冷といった冷却機構だけでなく、ヒートポンプやベーパーチャンバー、蓄熱システムなど放熱能力に優れた冷却機構の利用拡大が期待される。これらのシステムの能力を決めるカギとなる放熱デバイスとして熱交換器や蓄熱器があるが、その性能向上に寄与する素材として高熱伝導率と高空隙率、微細孔径を両立させた多孔質金属材料を開発した。本材料は、冷却に必要なエネルギーの低減を実現し、CO2排出削減に貢献できると考えている。
2.3 MB

2.3 MB
USB3.0電源で3Wの低消費電力で動作するダイヤモンドNVセンターを用いたコンパクトでポータブルな量子センサモジュールを開発した。NVセンサは、住友電気工業㈱の独自の超高圧合成技術により製作された高品質な汎用のダイヤモンドを用い、㈱NHVコーポレーションにて電子線照射の処理を行うことで高感度のものを製作した。また、ダイヤ基板をコーナーキューブにすることにより、光電流を直方体の形状に比べて2.1倍に高めることに成功した。加えて、λ/4オープンスタブとλ/4変成器を用いたマイクロ波共振器によりNVセンターを強力に磁気駆動させ、マイクロ波の電力を20dB低減した。これら光学系とマイクロ波系の効率向上により、5×10×20mmの小さなセンサヘッドで磁界と温度を計測できるコンパクトでポータブルな量子センサモジュールを実現した。本稿では、ダイヤモンドセンサの社会実装に資するべく、これらの技術成果を報告する。
3.1 MB
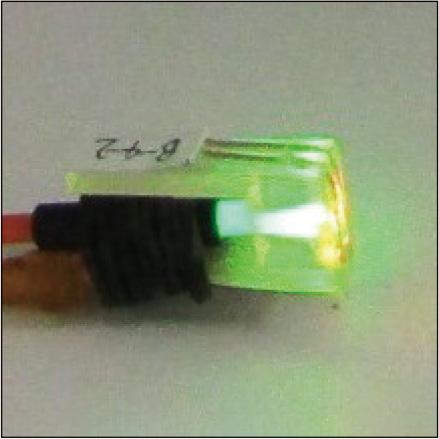
3.1 MB
我々の暮らしを支えている電線製品は省資源化やCO2排出削減の観点で軽量化が求められている。特に自動車用の細径の電線では高強度かつ高導電率の導体材料として銅合金が重要度を高めている。銅合金では純銅へ微量に添加した元素を原子レベルで緻密に形態制御することにより高機能を発揮させており、製品の特性を最適化する際に最先端の解析技術を活用することが不可欠である。本報告では、電線の強度と導電率をバランスよく両立できる材料設計指針獲得に繋がる原子レベルの新規解析技術として、3D-AP、TEM、XAFSを適用することで、ナノスケールの析出物の形態からミリスケールでの析出と固溶の割合の評価が可能であることを示す。
2 MB

2 MB
半導体薄膜の積層構造、めっき、樹脂の表面処理など、多くの製品において表面近傍における元素のプロファイルが製品特性に影響し、様々な事情からそれらを非破壊で評価したい需要は多い。我々は過去にX線光電子分光(XPS)のデータから非破壊で深さプロファイルを推定するMSM(Maximum Smoothness Method)という独自の解析手法を開発したが、このたびそのMSM解析をエネルギー分散型X線分光法(EDX)分析データに適用できるよう拡張した。EDX分析は分析の専門家でなくとも比較的簡便に実施でき、10 nm~1 µm程度の3桁にわたる厚みレンジに対応可能なため幅広い用途に展開できる。さらにEDX分析では試料の面内方向におけるマッピング分析が容易に実行できることから、MSM解析と組み合わせることで試料の3次元元素分布を非破壊で評価することが可能となる。本論文ではEDX分析を用いた非破壊深さプロファイル評価および非破壊3次元元素マッピング評価の事例を紹介する。
2.5 MB
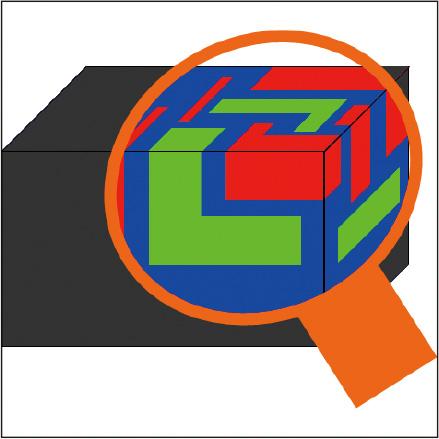
2.5 MB
車載電子機器のアーキテクチャにおいてこれまで単一のECU で実装されていた各機能は、拡張性・汎用性が求められる次世代アーキテクチャでは制御を集積した頭脳(セントラルECU)とセンサや負荷を駆動する手足(ゾーンECU)へ分割実装される傾向がある。
1.1 MB
交通信号制御は、交差点の方向別の交通状況に応じて、青信号の長さの割り当て等の信号制御パラメータを適切に決定することで、安全性の向上、渋滞の改善、CO2排出量の削減等に寄与している。従来は交通状況の把握に車両感知器が用いられてきたが、その設置及び維持に要するコストが課題とされている。
0.6 MB
近年クラウドコンピューティングや動画配信、5G対応等の進展により、通信トラフィックが急増したことで、大規模データセンタ(以下、DC)の建設が進んでいる。DC間を結ぶ光ケーブルは主にダクト内に布設され、高圧空気と共に押し込む布設方法に対応したマイクロダクト光ケーブルが用いられる場合がある。また、DC屋内には難燃特性が求められるため、DC屋外に使用される非難燃特性の光ケーブルとの接続点が必要であった。当社は、DC 屋内外を兼用で接続点無く一続きに布設できる288心の難燃マイクロダクト光ケーブルを開発し、販売を開始した。
1 MB
当社の延伸ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製多孔質体「ポアフロン」は広範な産業分野で利用されている。その中で例えば半導体関連用途では、高集積化の進展によるプロセス薬液の高清浄度化が求められており、分離膜においては微細孔径化のニーズが高まっている。これまでに当社は超微細孔径PTFE 膜「ポアフロンナノ」を独自に開発してきた。今回は更にこの中空糸膜をオールフッ素樹脂製ハウジングに搭載した「ポアフロンナノモジュール」を開発したので、その特徴(仕様と応用)について報告する。
1.1 MB
自動車、電子部品、医療をはじめとした産業で使用される小径かつ精密な小物部品の切削加工では、ばり・びびり・加工面不良を抑制し、加工の高品位化を実現できる工具へのニーズが高まっている。当社ではこれらニーズに応えるべく、優れた切れ味により高い加工品位を実現する小型旋盤用G級3次元チップブレーカ「SL型ブレーカ」を開発した。その特長、性能を紹介する。
3.4 MB
EVや太陽光発電(PV)の急速な普及に伴い、SiCパワーデバイス市場は年々拡大しており、数年以内に生産枚数を2~5倍に引き上げるといった設備投資も拡大している。また、SiCウェハのサイズは現在6インチ(150mm)が主流であるが、8インチ(200mm)の開発及び製品化に向けた動きも見られ、SiC パワーデバイスをより安価に製造するための技術開発が活発に行われている。
0.6 MB
半導体レーザは既存のレーザ光源と比べ小型・高効率・長寿命など優れた性能を有し、ヘルスケア、センシング、板金加工など多くの分野で社会実装が進んでいる。また、カーボンニュートラルの観点からも注目度が高く、最近ではレーザ核融合でも検討されている。上記を背景に今後も半導体レーザ市場は成長が期待されており、更なる高出力化、ビーム品質向上などが求められている。性能向上にはレーザダイオード(Laser Diode、以下LD)技術だけでなく、LD が発振時に発する熱を効率的に逃がし、熱による歪みが出ないようにするための放熱基板も非常に重要となっている。本報では、高放熱かつ低熱膨張などの特長を持ち、高出力な半導体レーザの放熱基板に適した銅とダイヤモンドの複合材について紹介する。
1.3 MB
近年増加を続ける下りアクセスネットワークトラフィックの65~70%を映像配信トラフィックが占めている。放送サービスのチャンネルあたりの最大所要帯域は、映像の高画質化と映像圧縮技術の高度化が標準化とセットで進んだ結果、20年間あたり、圧縮前が約40倍、圧縮後が国内RF放送において約5倍、IPTVにおいては約20倍のペースで増加してきた。一方、今後の市場の成長は、8K化に加え、360° 3D映像やAI、デジタルツイン技術と組み合わせたXR(クロスリアリティ)映像サービスが牽引することが期待されている。この機に、映像通信技術の動向と当社の取り組みを振り返ると共に、クラウドコンピューティングと家庭や職場を結ぶ全光および無線ネットワークに求められる各種Key Indexの内、特に、没入感ある双方向性の3D, XR映像配信サービスの実現に欠かせないMotion-to-Photon遅延と呼ばれる性能に着目し、他の要件への影響について考察する。
2.5 MB

2.5 MB
情報通信システムは、私たちの社会を支える重要なインフラである。特に電波を用いた無線通信技術は、直近の30年あまりで著しい進歩を遂げ、地上通信では高速データ通信や低遅延を実現する第五世代(5G)サービスが2020年より開始された。一方で、その通信ネットワークは、海洋、宇宙にまで広がり始めている。当社は、この通信インフラを支える伝送デバイス(光通信向けデバイス、無線通信向けデバイス)の開発・製品化を通じて、社会に貢献してきた。無線通信基地局向けキーデバイスであるGaN HEMTは、当社が世界で初めて量産・製品化に成功し、現在では世界トップシェアカンパニーとしての地位を確立した。本論文では、GaNに代表される化合物半導体デバイスとその応用の黎明期から現在のGaN HEMT増幅器、そして将来技術として不連続な性能向上を目指した新規の結晶成長技術やデバイス技術について論述する。
3.5 MB
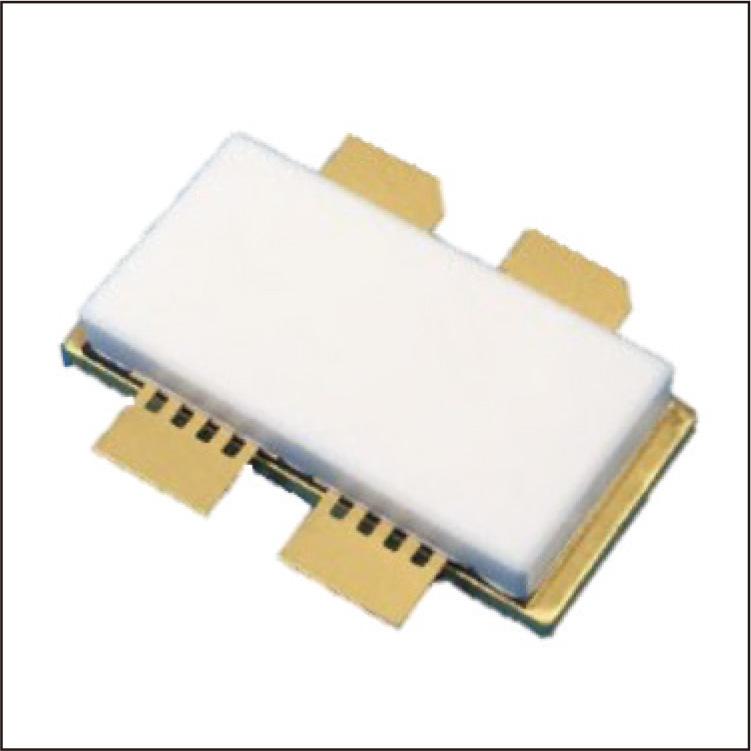
3.5 MB
気候変動は世界的な社会課題であり、その対策としてCO2排出量削減が求められている。主な排出源の1つである自動車交通のCO2排出量を削減するためには車両自体の排出量削減の取り組みと共に、交差点の交通信号制御の改良による渋滞削減等、車両が無駄なエネルギーを消費せずに走行できる環境を整備する取り組みも重要である。CO2排出量削減対策として交通信号制御の改良を推進していくためには、その効果の定量的な検証が必要であるが、交差点を通過する車両のCO2排出量の定量化については広く認められた手法は存在しない。そこで、交通信号制御の改良の効果検証に広く利用されることを目指し、交通信号で制御された交差点を通過する車両のCO2排出量を車種等を考慮して算出するモデルを作成した。
0.8 MB
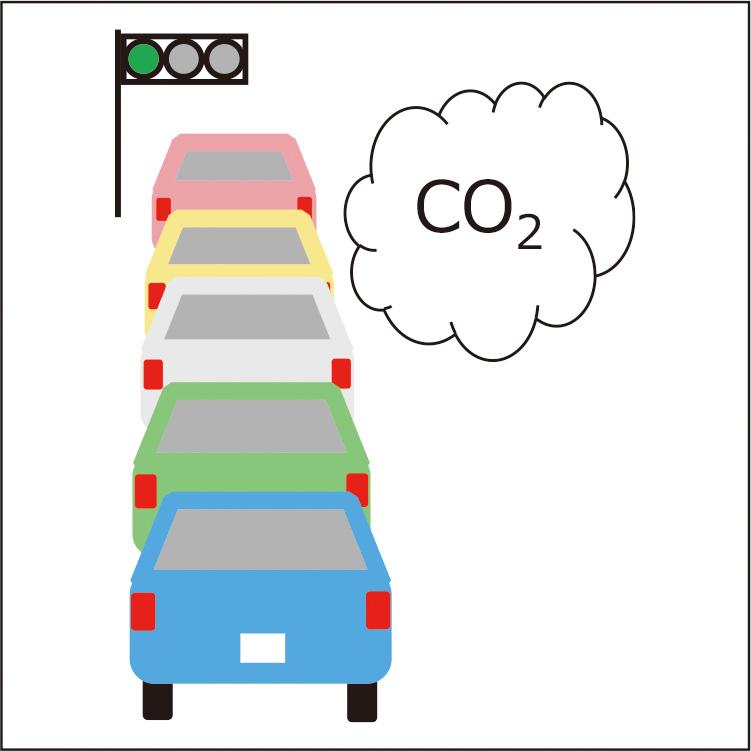
0.8 MB
交通の安全と効率向上のため、世界各国で歩行者検知センサの需要が高まっている。交差点において歩行者検知センサで十分な検知精度を得るためには、適切な設置先を確保することが課題となる。しかしながら、センサを設置するために新しいポールを設置するには大きなコストを必要とするため「既存のポールを活用できること」が、歩行者検知センサを世界に広めるために重要となる。一方で、遠方と近傍の歩行者検知を両立させることは、センサの視野角が不足するために難しく、多くのセンサはその直下の歩行者を検知できないために設置場所が制限される。この課題への対策のため、筆者らは僅かなコストアップで広いアンテナ視野角を持つレーダセンサを開発し、設置場所の自由度を向上した。本稿では、開発した新しい技術と、それを用いて広い検知エリアを実現した検知結果を紹介する。
3.2 MB
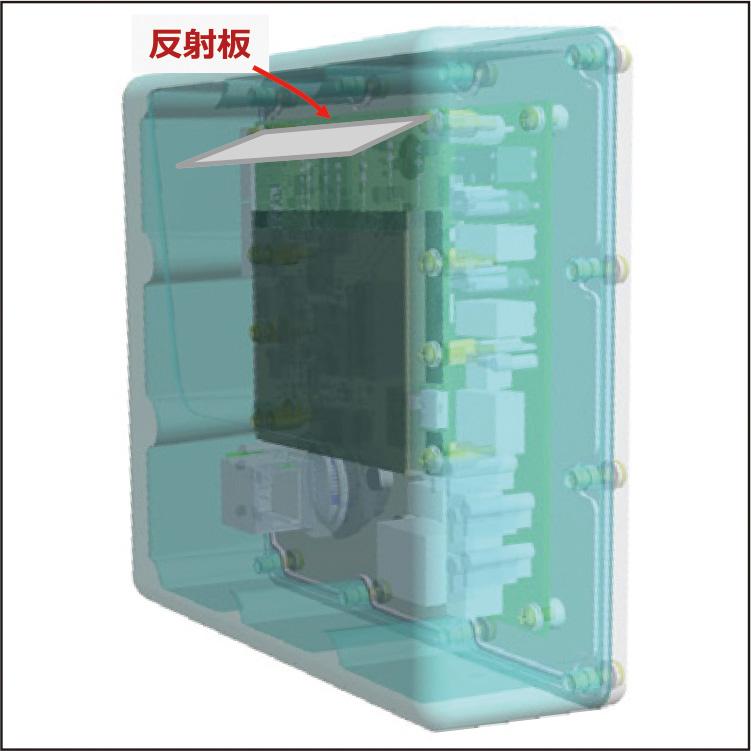
3.2 MB
情報通信量が増大の一途を辿る中、データセンタでは、多チャネル化により通信量の急増に対応してきた。一方、現状のシステムでは、1チャネルにつき1つの半導体レーザを使用するため、消費電力の増大や、部品点数の増加による高コスト化が問題となっている。高光出力の単体レーザ素子から多チャネルに光を分岐する構成が提案されており、その要求を満たす高出力かつ単一モードの通信用レーザが求められている。しかし、既存の通信用レーザで、単一モードかつ高出力を得ることは、原理的な限界を迎えつつある。我々は、単一モードと高出力動作を両立する次世代の半導体レーザとして、1.3 µm帯のInP系フォトニック結晶レーザを検討している。ドライエッチングと再成長技術を用いて作製したInP材料系PCSELにおいて、室温連続駆動において200 mWを超える単一モード発振を実証した。さらに、短パルス駆動においては、4.6 Wの高出力を達成し、通信だけでなくセンシング用途にも応用可能である結果を見出した。
2.5 MB
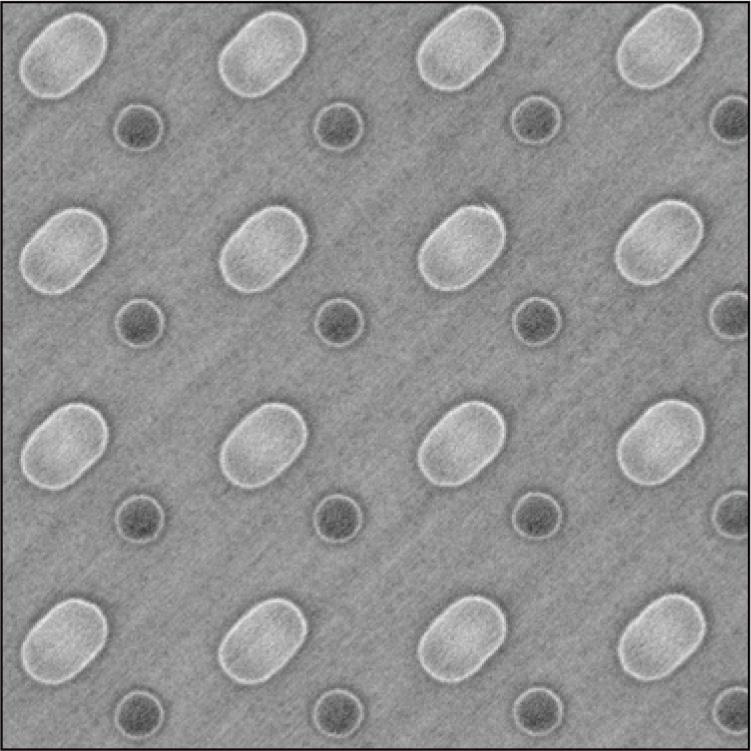
2.5 MB
当社はフッ素樹脂ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の延伸加工による多孔質化技術を世界に先駆けて開発し、2000年代初頭には、中空糸膜状の水処理膜モジュールを上市し、PTFEの耐薬品性、高強度を強みに国内外の様々な地域で、上下水処理用途や産業排水処理用途に納入してきた。一方で、近年増加している海水淡水化やかん水中のレアアース回収といった塩成分の分離ニーズの増加に対して、PTFEの有する疎水性を活かし、かつ海水中の塩成分や水資源中のレアアースといった溶質を分離できる膜蒸留法に着目し、膜蒸留法に必要である耐水圧と気体透過性を両立したPTFE中空糸膜を開発したので報告する。
2.3 MB

2.3 MB
近年、世界各国で温室効果ガスの削減に対する取り組みが行われており、洋上風力発電に注目が集まっている。発電した電力を送電する海底ケーブルは、風車の大型化と出力増加の影響による高電圧化、大容量化に伴い大型化が進んでおり、製造性、コスト、施工性等が課題となっている。当社はこれらの課題を解決するため、遮水構造の無い海底ケーブルの開発を進めてきた。海底ケーブルの運転寿命は未解明な点が多く、特に浸水状態ではケーブル絶縁体中で水トリーと呼ばれる劣化が進行するため、ケーブル寿命を推定することは難しい。当社は非遮水構造のケーブル寿命を評価するため、ケーブル絶縁体中の過飽和水分量の継時変化を解析することで、現実的な試験期間で実線路30年の長期運用を模擬可能な長期水トリー試験法を検討した。今後、検討した試験法を用いて実線路での長期運用や更なる高圧化に対応可能な耐水トリー性を有するケーブルの開発を進める。
1.8 MB

1.8 MB
化合物半導体は高機能デバイス実現に有用な材料的特長を有している。デバイス性能への影響が大きい半導体表面あるいは界面の状態を高精度で分析するため、本研究では放射光分析の一種であるX線光電子分光法(XPS)を活用した。まず無線通信用のGaN系高電子移動度トランジスタでは、O2アッシャ処理の影響について調べた。この目的のためXPS励起エネルギーを600 eVまで下げ、分析深さを約2 nmに限定。フォトルミネセンス分析も併用し、不適切な処理条件では表面からのN抜けと酸化物の増加、及び、GaN結晶中の欠陥残留をもたらすことを見出した。また、光通信の受光素子に用いられるInP系フォトダイオードでは、絶縁膜に被覆されたInPの表面電位シフトを7940 eV励起の硬X線光電子分光で評価し、受光感度劣化をもたらす界面リーク電流を低減できる製膜条件の探索に成功した。放射光分析のタイムリーな活用は、製品開発期間の短縮に非常に有効と言える。
1.7 MB

1.7 MB
近年、脱炭素社会の実現に向け電動車両へのシフト、並びに自動車機器の電動化が進んでいる。機器の電動化は制御対象を電気信号で制御するバイワイヤ制御の採用が拡大している。しかし、バイワイヤ制御は鉛バッテリなどの車両電源が異常となった場合に、制御ができなくなる課題がある。住友電工グループの住友電装㈱、㈱オートネットワーク技術研究所は、車両電源異常時にも複数のバイワイヤ制御を継続するための統合バックアップ電源を開発した。本製品は、2023年に発売されたトヨタ自動車㈱のプリウスに採用頂いた。
0.8 MB
近年クラウドコンピューティングや動画配信、5G 対応等の進展により、通信トラフィックは急増し、大規模データセンタ(以下、DC)の建設が進んでいる。DC 間を結ぶ光ファイバケーブルは主に屋外ダクト内に配線されるため、限られたダクトスペースに光ファイバを高密度に詰め込む技術が重要となる。当社は2017年に当時、世界最高心数である6912心光ファイバケーブルを開発、商用化し、さらに配線ソリューションも開発することで、DC 全体での配線高密度化および施工性向上に貢献してきた。本稿では国内向けダクトサイズに適合した超多心高密度光ファイバケーブルとして、200μm 心線適用の3168心型、250μm 心線適用の2016心型を開発し、販売を開始した。
0.7 MB
近年船舶・気象用増幅器としてマグネトロンに代わり半導体デバイスが高出力化したことで固体化が進んでいる。固体化のメリットとして長寿命が挙げられ、定期的に交換が必要であったマグネトロンに対し、半導体は交換不要であり維持費削減が可能となる。またマグネトロンレーダは周波数変動が大きく小さな物標を観測することが困難であったが、固体化レーダはその周波数安定性からこれまで観測が困難であった物標も観測できるようになり探知性能が向上するメリットが挙げられる。しかしながら固体化レーダがマグネトロンレーダと同等の探知距離を実現するには半導体デバイスを複数並べる必要があり、合成数を減らすにはさらなる高出力化が求められている。今回我々は業界最高出力であるS 帯(3GHz)800W GaN HEMTを開発したので報告する。
1.9 MB
カーボンニュートラルの実現に向けた再生可能エネルギーやEV の急速な普及に伴い、次世代パワー半導体の需要が拡大している。特にSiCはSiに比べて高耐圧、省電力化を実現する新素材として一部で使用され始めているが、広く普及するには製造コスト面で課題がある。SiC ウェハ及びデバイスの製造工程では高能率にウェハ厚みを加工できる研削加工が用いられているが、硬脆材料であるSiCの加工において①工具の消費量が高い②加工抵抗が高いことが課題として挙げられており、耐摩耗性を有し低抵抗で加工できる工具の開発が望まれている。そこで㈱アライドマテリアルでは独自に開発した超微細組織の高精度分散制御技術を用いることで、工具寿命と加工抵抗を両立したビトリファイドボンドホイールを開発し、2022年度からナノメイト マスパワーの商品名で発売を開始した。
0.7 MB
1990年台初頭のインターネットの普及以降、人々はほぼ時間遅れなしに世界中の情報を入手することが可能となり、データ伝送容量は年々増加している。送られる情報は、初期は音声や文字であったが、その後、写真や動画が加わり、近年は例えば自動運転に必要なデータや人工知能(AI)、メタバースといった人々の生活を変える技術に活用されつつある。また、通信の主体も人からモノへと広がり、大量のデータが常時飛び交っている。
1.9 MB
高機能モバイル端末の普及や、提供されるサービスの多様化に伴う通信トラフィックの増加に対応するため、5Gへの移行が進みつつある。5Gのモバイルフロントホールには25Gbpsの光トランシーバが用いられており、伝送容量拡大のため、波長分割多重方式が広く用いられている。当社は、これまでに開発したCAN型光受信デバイスと、C-Band用端面入射型導波路アバランシェフォトダイオード (Avalanche Photodiode : APD) を組み合わせて、25Gbps DWDMトランシーバ (SFP28) に搭載可能な光受信デバイスの開発を行ったので、その結果を報告する。
3.1 MB

3.1 MB
IoT技術を用いた様々なアプリケーションの進展により通信量が増大し、2030年にはデータレートが10 Tb/sを超えると予想されている。一方、光通信を支えてきた単一材料光デバイスにおいては10 Tb/s級のデータ伝送に向けた広帯域化と低消費電力化の両立に限界が見え始めており、技術的なブレークスルーが求められている。高速・高効率動作に優れたIII-V族化合物半導体と素子の小型化による高密度集積が可能なシリコン(Si)フォトニクスのそれぞれの利点を組み合わせた異種材料集積光デバイスは、その有望なアプローチの一つとして期待されている。本稿では異種材料集積を利用した波長可変レーザについて報告する。
7.7 MB
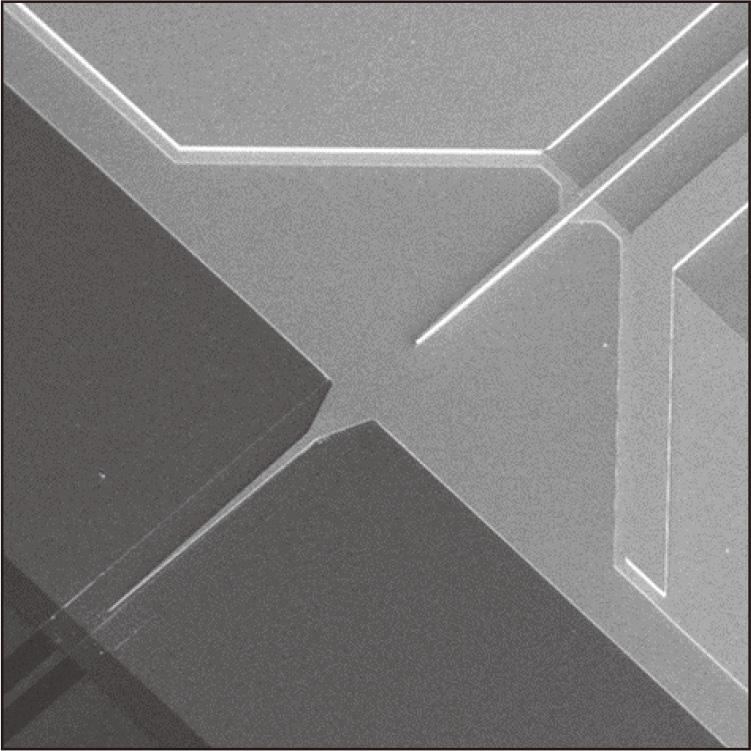
7.7 MB
データセンタ内の消費電力増加に対し、電気と光機能を一体集積することで消費電力を削減可能なCo-Packaged Optics(CPO)スイッチが注目を集めている。CPOスイッチには、低背・高密度・低損失・高信頼性な光接続部品が新たに必要とされる。そのため、90°に小径曲げ加工を施した光ファイバと、2次元配列の精密孔あきガラスプレートを組み合わせた、90°曲げ2次元光ファイバアレイ(2D-FBGE(FlexBeamGuidE))を開発した。2D-FBGEは、高さ5.5mmの低背性、24心/mmの高密度性、0.5dB以下の低挿入損失、20dB以上の高い偏波保持特性を示し、CPO向け光接続部品に必要な性能を有していることを確認した。
2.6 MB
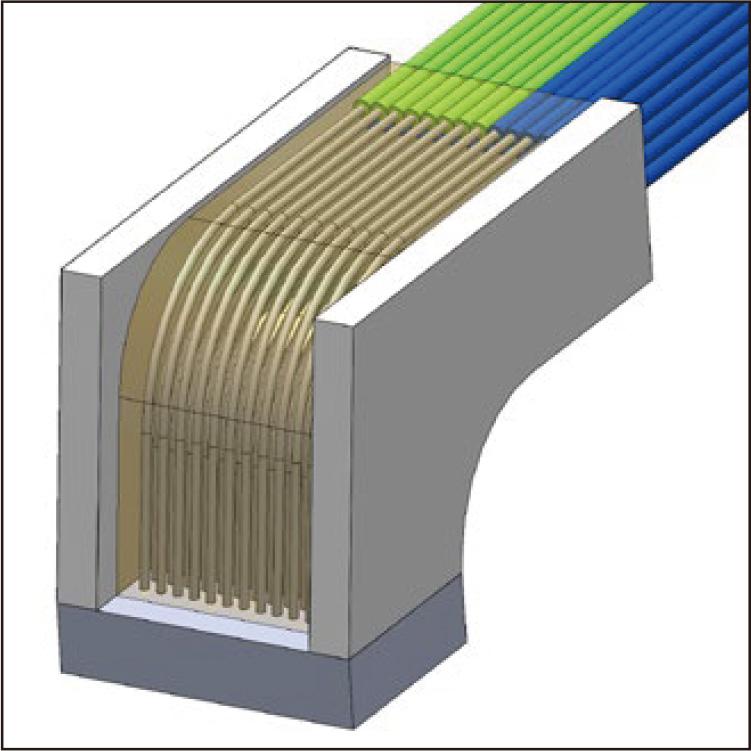
2.6 MB
データセンタなど光ファイバネットワークの拡張が世界的に進められる中、光ケーブルの柔軟かつ効率的な布設を可能とするテープ心線型マイクロダクト光ケーブルが開発され、実用化され始めている。この度、ケーブルの実装心数を96心から864心まで幅広く開発すると共に、施工時間の削減を目的として屋内外兼用の難燃外被構造も開発したので本稿にて報告する。開発したケーブル構造としては、間欠12心テープ心線を用いて一括融着接続性と自身の柔軟性を活かした高密度収納を両立させ、細径かつ軽量なケーブル構造を実現できた。また、空気圧送特性を向上させるために、低摩擦外被を採用した。これらの新開発マイクロダクト光ケーブルは、顧客のネットワーク配線方式を考慮した様々な布設環境に適用でき、従来と比較し効率的で柔軟なネットワークの構築が実現できる。
1.6 MB
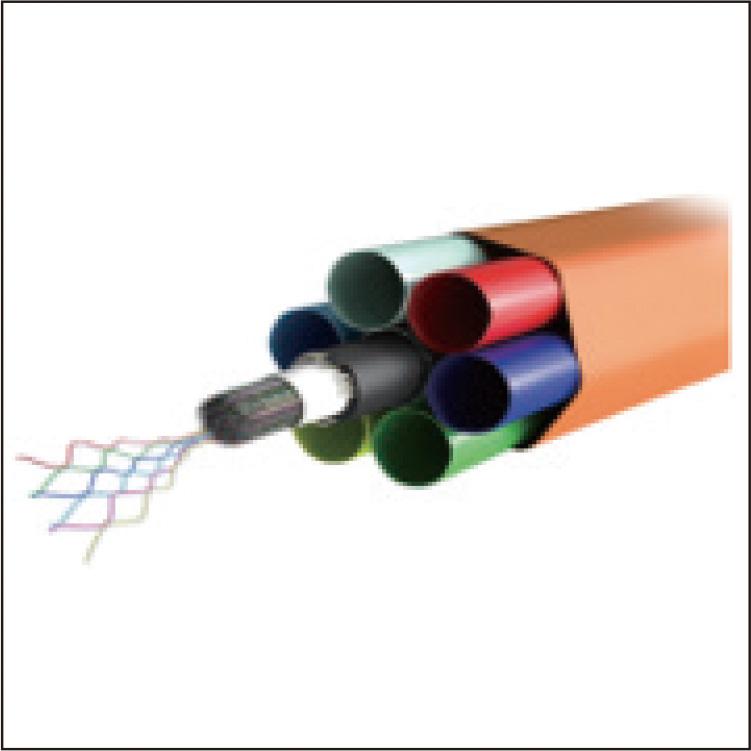
1.6 MB
大規模データセンタの施工時間削減を目的として、超多心ケーブルの端末に予め工場で多心コネクタを取り付けた成端ケーブルを開発、販売開始した。ケーブル構造としては、細径200µm光ファイバを用いた間欠12心光ファイバテープ心線とスロット構造から構成される細径3456心光ファイバケーブルを用いた。ケーブル先端に24心MPOコネクタを取り付け、牽引保護管で保護する構造としたが、保護管に関しては牽引特性、機械強度等を加味した構造の選定を行った。開発したケーブルを用いて、実布設を模擬した牽引実験を行い、従来の非成端ケーブルと同等のダクト収納心数を達成できることを確認。本ケーブルを用いることで、従来時間を要していた多心融着作業をコネクタ接続により、接続時間を削減することができ、従来ケーブル対比で約40%のケーブル施工時間削減が見込まれる。
2.3 MB
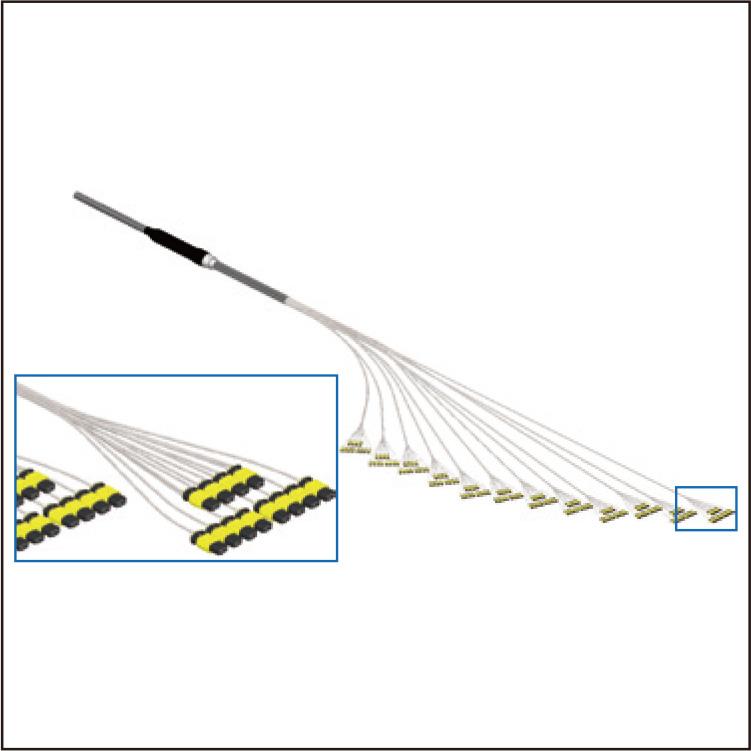
2.3 MB
マルチコア光ファイバ(MCF)を用いた光通信においてはコア間のクロストーク(XT)を抑えることが信号品質を維持するために重要である。本研究では、マルチチャネルOTDRを用いることでボビン巻き状態のMCFのファイバ長手方向での曲げ半径変化によるXTの変化を測定できることを明らかにした。また、MCFを用いた双方向伝送時に考慮が必要となる後方散乱XTを、マルチチャネルOTDRを用いて測定する手法を開発し、後方散乱XTのファイバ長依存性の理論予測を検証し、ファンアウトの後方散乱XTへの影響も明らかにした。本研究成果により、マルチチャネルOTDRによるXTの長手依存測定の有用性を示すとともに、MCFにおける対向伝搬の優位性を示した。
2.2 MB
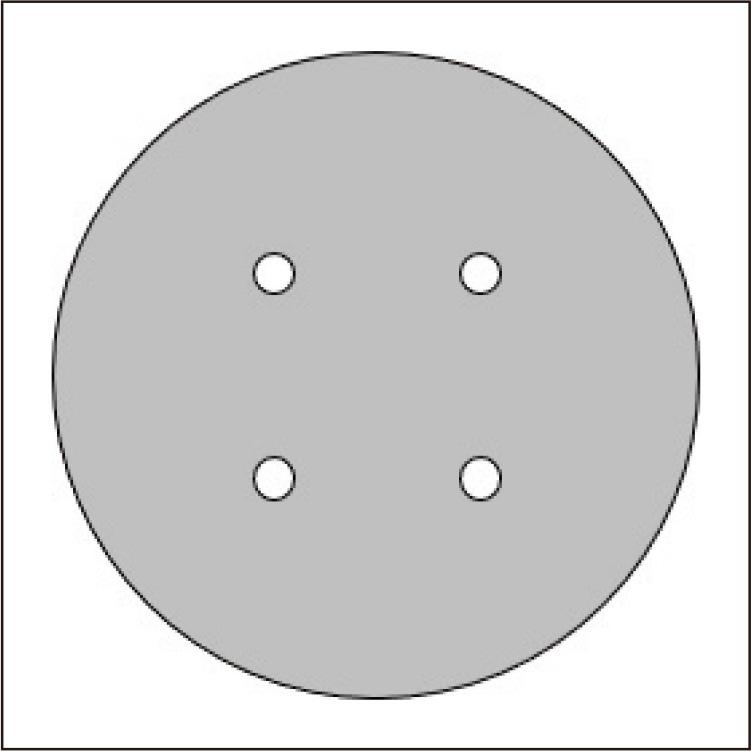
2.2 MB
光通信ケーブルの低温環境における伝送ロス増大は長年の課題であるが、そのメカニズムはいまだ未知の部分が多い。我々はメカニズム解明に向けた最大の障害のひとつであった、光ケーブル実試料の低温環境における形状評価技術を開発し、分析・データ解析・CAEの三位一体の体制でこの課題に取り組んでいる。具体的には、既存の一般的なX線CT装置に対する簡便な後付け機構で低温観察を実施する独自技術、および不明瞭なCT像から正確にファイバ1本1本の形状を抽出し3次元的に定量化する独自技術を開発した。特に後者の技術は光ケーブルのみならず幅広いケーブル製品に適用可能で、ビックデータを活用したケーブル製品設計のDX推進に多方面で貢献している。本論文では多心光ケーブルの低温環境での形状評価を例に、実測とCAEの両面からケーブル評価を実施する取り組みを紹介する。
3.7 MB
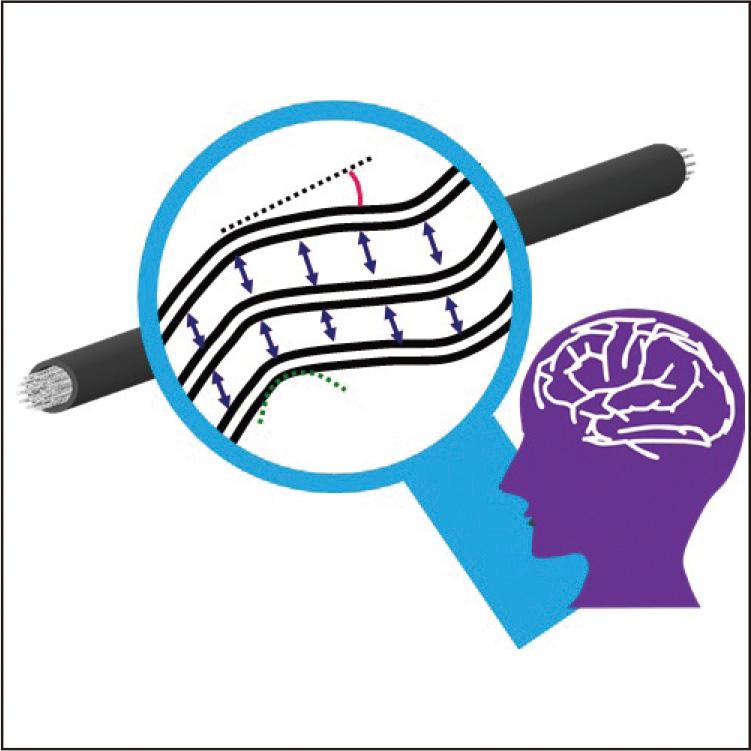
3.7 MB
高い電力効率を持つ増幅器は、発生する熱が少なく軽微な放熱機能で動作が可能となるため、通信装置の小型化、軽量化、低コスト化に対して有効である。特にMassive Multiple Input Multiple Output(MIMO)では、多数の増幅器を使用するため、より高効率な増幅器が必要とされており、窒化ガリウム高電子移動度トランジスタ(GaN HEMT)による増幅器の普及が携帯電話基地局用途で進んでいる。一方変調波効率の向上を目的とした増幅器技術として負荷変調が注目されており、中でも、アウトフェージング増幅器は、従来のドハティ増幅器よりも、変調波効率が高効率に実現できることが知られている。今回、当社GaN HEMTを用いアウトフェージング増幅器の設計試作評価を行った。その結果、増幅器の高効率化により従来のドハティ増幅器の構成と比較し1増幅器あたり1.1W消費電力を削減でき64送信のMassive MIMO基地局で70.4Wの消費電力を削減でき基地局の小型化に貢献できることを確認できた。
1.6 MB
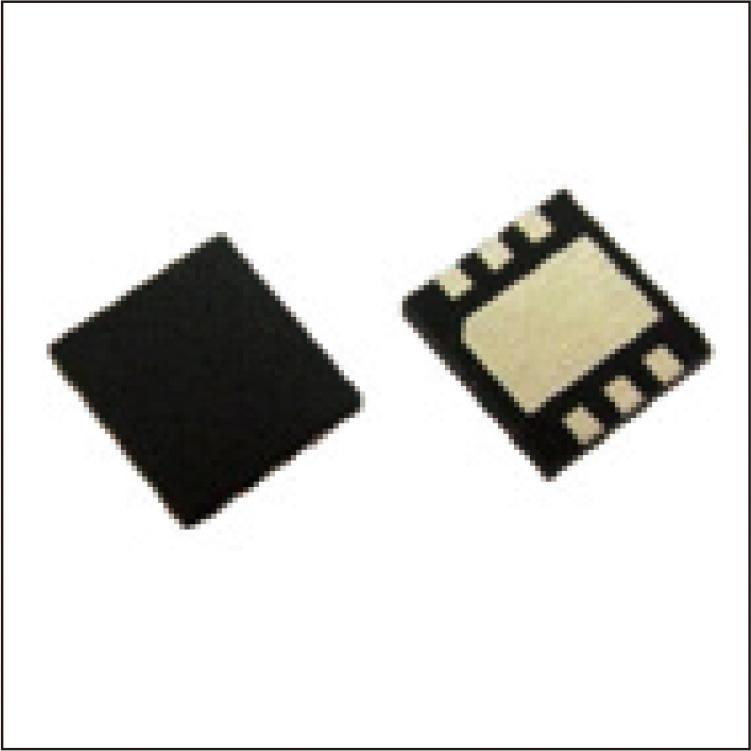
1.6 MB
GaN HEMTを用いた衛星搭載用高出力・高効率内部整合型増幅器パワーアンプを開発した。今日の無線通信技技術は、インターネット、携帯電話のコミュニケーションに加えて、電子マネー決済にも利用されており、日常生活に欠かせないものとなっている。世界的な情報網の拡大と、自然災害の影響を受けにくい衛星通信の必要性が高まっている。 今回開発したパワーアンプは、衛星通信の主力周波数であるC帯(f=3.7~4.2GHz)において、CW動作条件下で出力電力100W、電力付加効率60%を達成した。開発に使用したGaN HEMTは長期信頼性の実績があり、性能および信頼性の両面において、業界トップクラスの製品である。
3.1 MB
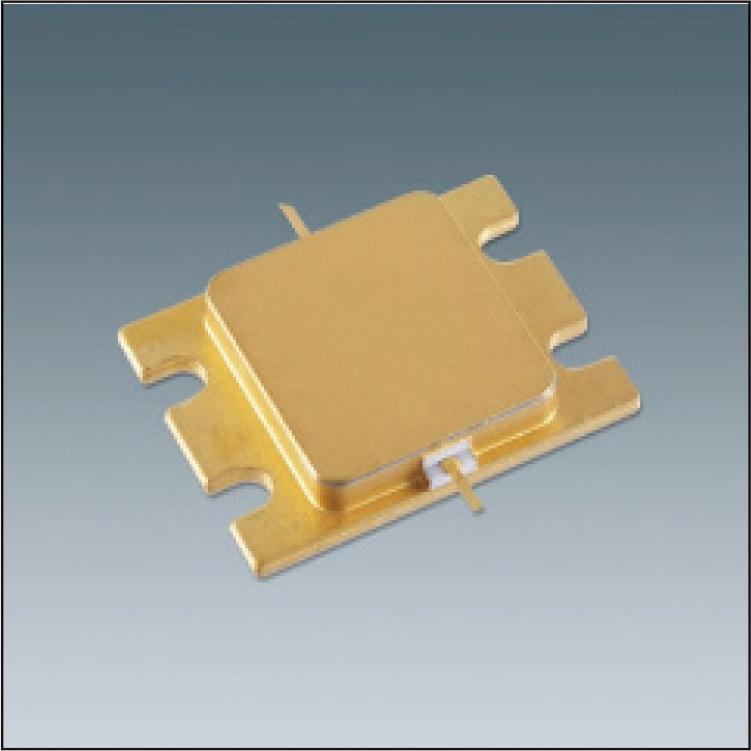
3.1 MB
近年AIによるヒト・モノ・コトなどの映像解析が幅広い分野で進んでいる。同時に、より広範囲に、より高精細に見たいニーズから、4Kや8Kなど、カメラ映像の高解像度化が進んでいる。それに伴い、映像データの伝送量や保存コスト、AI分析の処理負荷の増大が課題となっている。今回、データ量を大幅に削減でき、且つ圧縮伝送後のAI処理負荷を低減できるAI応用映像処理技術(AVP: AI-based Video Processing)を試作した。その有効性を検証するために行った工場実証実験では、従来圧縮技術と比較して平均ビットレートを92.2%削減できたと同時に、クラウド側AI処理負荷の低減により限られた計算リソースでより高解像度映像の解析ができ業務改善に繋がった。
4.9 MB

4.9 MB
㈱日新システムズは、“誰でも簡単に地域とつながることができる”をコンセプトに、在宅高齢者向け支援システム「L1m-net」を開発し、高齢者の在宅支援ソリューション展開を進めている。「L1m-net」の実証を進める中で、在宅支援に加えて孤立・孤独からコミュニケーションを生む仕組みとして、被災地、障がい者支援施設、高齢者向け賃貸住宅などの分野への展開も可能であることが分かってきた。 近年増加している局地的な豪雨による水害・土砂災害の発生により被災した地域では、長年住んでいた家を失い仮設住宅に移った高齢者が孤立し、孤独死につながる課題が生じている。本稿では、この課題に対応すべく、「L1m-net」を活用した被災地での導入事例について報告する。
2.7 MB

2.7 MB
複雑な組合せ最適化問題を高速に解く技術として量子コンピューティングが注目されている。当社では物流事業者に向けた業務支援ツールの一つである配送計画システムを20年前から販売しており、継続的に研究開発を行っている。配送計画システムは輸配送コストが少なく効率的な配送経路を計算する機能を有するが、この機能の実現には複雑な最適化計算が不可欠である。我々は、この最適化計算に量子コンピューティングを適用することを目指し、この実現に必要となる定式化と実装・性能評価を行っているが、実用化に向けては解の精度の検証が不可欠である。本論文では、イジングマシンと古典コンピュータを用いた結果を比較評価することで定式化の妥当性が確認できたため、その成果を報告する。
1.6 MB
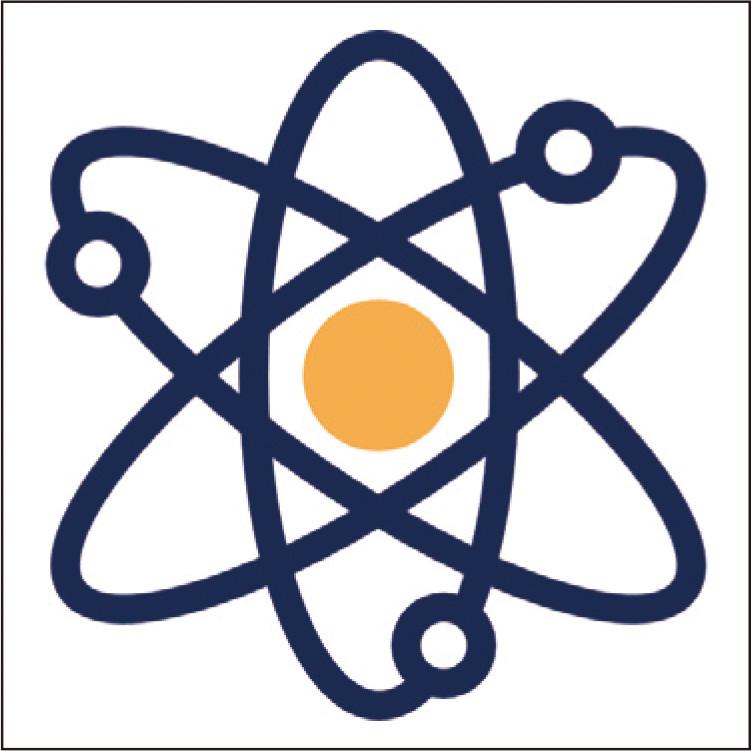
1.6 MB
近年、省エネルギー化への注目度に更なる高まりが見られる中、電力制御に使用されるパワーデバイスの高効率化の重要性がますます高まっている。現在、パワーデバイスにはシリコン(Si)が主に用いられているが、より高効率な炭化ケイ素(SiC)の実用化が始まっている。当社では、低抵抗化に有利なV溝型のゲート構造を採用した金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)を搭載したパワーモジュールの開発を進めてきた。今回、市場に流通するシリコン搭載モジュールと形状互換であり、シリコン搭載モジュールよりも低オン抵抗で高速スイッチングが可能な1,200V-400A定格のパワーモジュールを開発した。本報告では、このモジュールの特徴や電気的特性を紹介するとともに、量産化に向けた信頼性試験の結果も報告する。
1.4 MB
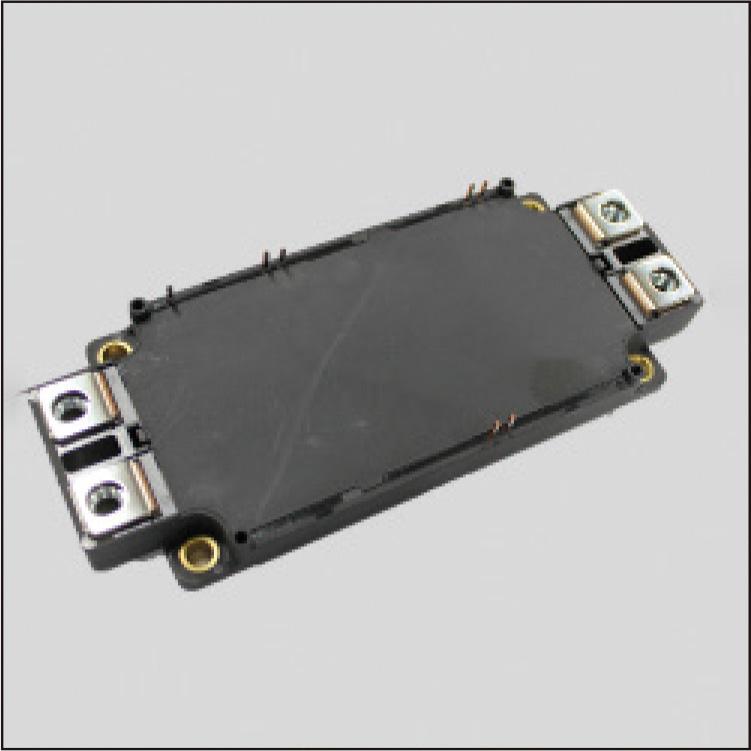
1.4 MB
当社は、レーザービームプリンター(LBP)の重要部品であるポリイミド定着ローラを1993年から製造している。近年では、高速印刷に適用可能な高熱伝導定着ローラを開発しており、強靱なポリイミド樹脂と熱伝導性の高いカーボンナノファイバーとを複合化した複合材料を使用している。カーボンナノファイバーは熱伝導性に優れた材料である一方で、ナノマテリアルにカテゴライズされており、規制等のリスクが高まっている。今回は、このカーボンナノファイバーを代替できる材料として、同じく炭素系のフィラーである黒鉛フィラーについて適用検討を行い、新しい高熱伝導定着ローラを開発したので、その詳細について報告する。
2.6 MB

2.6 MB
カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの主力電源化の取り組みが進められている。しかし、再生可能エネルギーの増加に伴って電力系統が混雑し、新規電源の接続が困難になるという課題が生じている。この課題に対して、系統の混雑に対応するために従来の運用方法を見直す日本版コネクト&マネージの検討、新たな運用技術で送電容量の拡大を図るダイナミックレーティングの導入検討が行われている。これらを実現する上で、送電線の状態と鉄塔周辺の環境をリアルタイムに監視する装置が必要であり、将来再生可能エネルギーが大量導入されていく中で、このようなシステムが重要な役割を担うことになると考えられる。当社は、再生可能エネルギーの大量導入に向けた架空送電線監視システムの開発を行っており、本稿では、開発したシステムと装置の特徴について紹介する。
1.5 MB

1.5 MB
固体酸化物形燃料電池(SOFC)用の集電体として、富山住友電工㈱の製品である三次元網目構造を有した多孔質金属体「セルメット」の適用を目指している。中でも開発中のNiCoセルメットは、高温酸化雰囲気で導電性酸化物を形成することから空気極集電体への適用が可能であり、更に多孔体としての高いガス拡散性を発揮することから、インターコネクタに形成されるガスの流路となる溝加工をなくしても高出力が得られることを報告している。今回、そのメカニズム解明の一環として、セルメット適用による直流抵抗への影響について検討した。セルメットは柔軟性のある金属体であるため、セルの反りにも追従して変形することで、接触性が向上することを明らかにし、更にNiCoの酸化膨張によりスタック内部から圧力をかけることができ、良好な接触性が維持可能であるとの結果を得たのでその内容を記載する。
2.4 MB
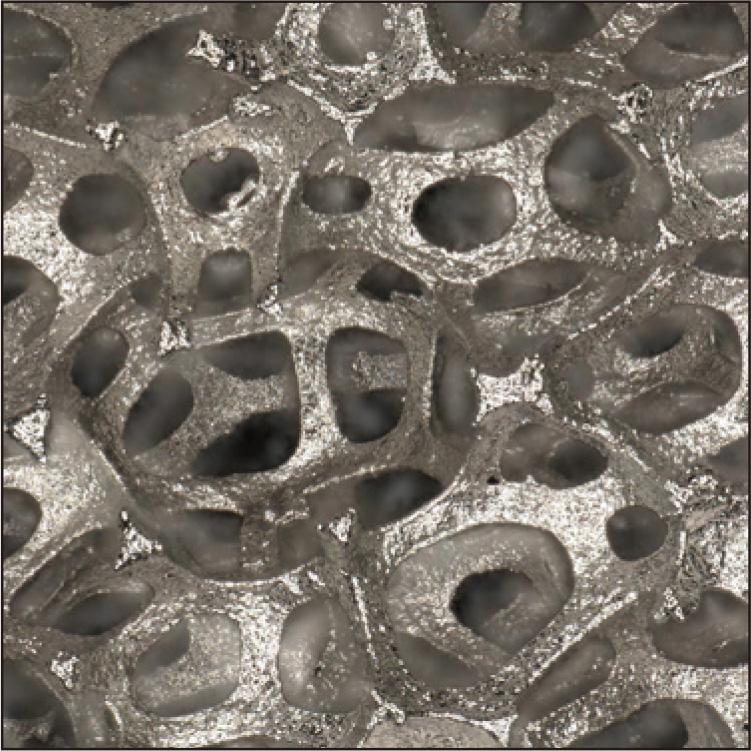
2.4 MB
カーボンニュートラル、省資源化への要求の高まりから、自動車のエンジン、クラッチ等の主要な駆動部品に用いられるばね製品も小型・軽量化が求められており、特に要求特性とされる疲労強度に関連してばね材料の高強度化が必要となっている。従来、高疲労強度化≒高強度化(高引張強さ)という方針で材料開発が進められてきたが、あらゆる金属材料の中でも最も高い疲労強度を求められるばね材料では頭打ちになってきており、材料の使用環境などを考慮した新たなアプローチが必要となりつつある。本稿では、成分設計から製造条件確立まで新規に実施した、高強度オイルテンパー線新鋼種の性能と、その特性向上メカニズムについて報告する。
1.9 MB

1.9 MB
昨今、脱炭素社会の実現に向けた効率的なエネルギー利用の観点から、太陽光発電の余剰電力を蓄えて夜間に利用できる家庭用蓄電システムへの関心が高まっている。太陽光発電と蓄電池を組み合わせたシステムは災害等で長時間停電した場合でも住宅への電力供給を維持できるなど、住宅のレジリエンス確保にも効果的である。当社は蓄電システムの普及促進のために小型軽量で施工性が良い住宅用リチウムイオン蓄電システム、POWER DEPO シリーズを2015年より販売している。この度、電力の自給自足を促進するべく、蓄電容量を従来製品の4倍とし、太陽光パネルで発電した直流電力を家庭用の交流電力に変換する太陽光発電用パワーコンディショナーを内蔵するハイブリッド蓄電システム「POWER DEPO H」を開発した。
1.1 MB
自動車の足廻りに配策される多芯複合ケーブルの曲げ形状、屈曲負荷を精度良く算定する解析技術を開発した。多芯複合ケーブルは、複数本の電線(コア線)を束ねて一体化したもので、ホイール内に配置される電動パーキングブレーキ、車輪速センサー等と車体側の電子制御ユニットを繋ぎ、給電と信号伝送を担う。自動車の電動化、先進運転支援システム(ADAS)の技術開発が進展し、需要が拡大している。ケーブルの訴求点は、走行時にホイールの上下動に伴う繰り返し屈曲を受けても導体が断線しない耐屈曲性である。従来、CADで実車配策形状を決め、ケーブル設計を行っていたが、屈曲負荷の算定精度が低く、ケーブル設計決めのために試作/評価での合わせ込みが必要で、開発期間が長引く原因となっていた。今回開発した解析技術により、ケーブル両端を所定の位置・角度で固定した際の曲げ形状、屈曲負荷を精度良く算定でき、開発を効率化できた。
1.9 MB

1.9 MB
慶應義塾大学の石榑教授が発明されたポリマー光導波路の製法の一つであるモスキート法は、市販のマイクロディスペンサーと多軸シリンジ走査ロボットを用いたコアパターンを3次元的に形成可能な技術である 。本作製方法を用いることでマルチコアファイバ(MCF)の導入に不可欠なファンイン・ファンアウト(FIFO)デバイスの実現などが期待できる。一方で、先行研究は主にマルチモードの導波路の検討であり、シングルモード化にはいくつかの課題を有している。特に、クラッド中のニードル走査によるモノマー流動のため、コア形状が円形から悪化する傾向があり、光ファイバとの接続損失を増加させる要因となっている。本論文では、モスキート法によるシングルモード導波路の作製およびシングルモード光ファイバとの接続損失を低減するために、モスキート法を用いて円形コアを形成する方法を理論的および実験的に検討した内容について紹介する。
8.3 MB
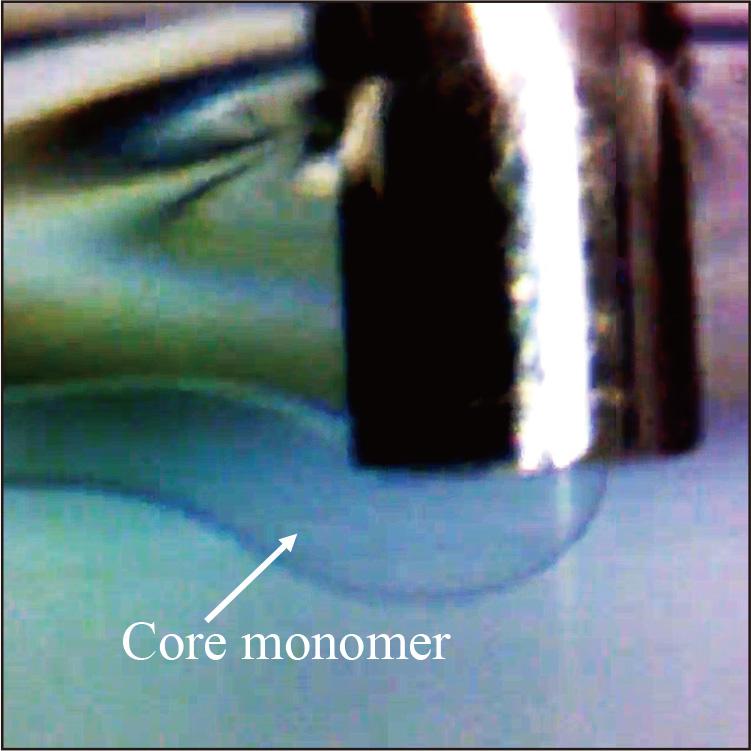
8.3 MB
現代の必須無線通信手段のひとつとして衛星通信が挙げられる。その小型地球局に搭載される電力増幅器には、消費電力やコスト削減などの理由から、高出力化・高効率化・小型化・低歪み化の要求が高まっている。当社は、これらの要求に最適な窒化ガリウム(以下、GaN)の高電子移動度トランジスタ(以下、HEMT)テクノロジーを新規に開発し、衛星通信の地球局向けKu帯48W GaN MMIC 電力増幅器を開発した。小信号利得は32.5dB、最大出力電力は46.9dBm(49W)、電力付加効率は32.8%、3次相互変調歪は-25.6dBcと、業界トップクラスの性能を達成した。
1.1 MB
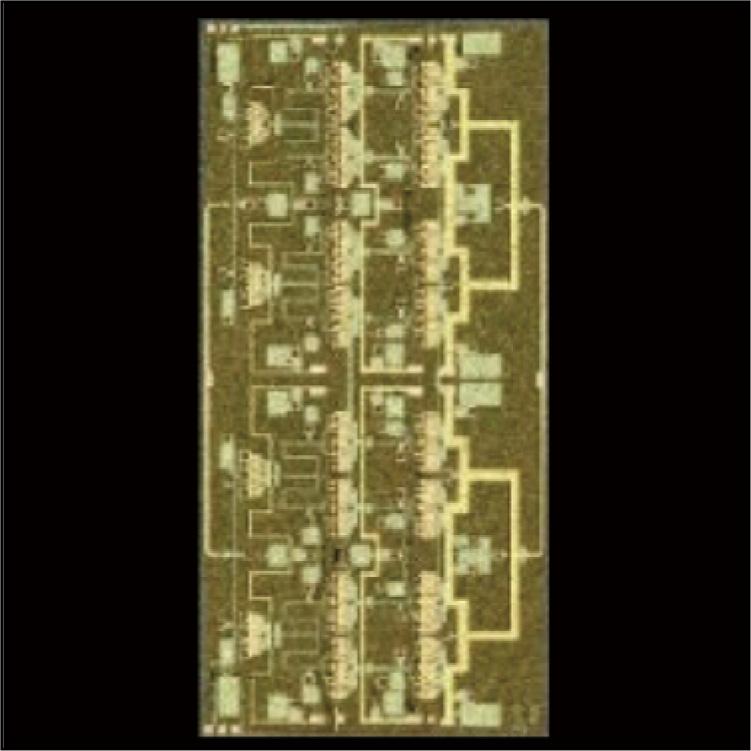
1.1 MB
より環境負荷の低い化学プロセスの構築に向け、日進月歩の触媒開発が続いている。セルメットは三次元網目構造を有する気孔率90%以上の金属多孔体であり、担体として用いることで低い圧力損失と高い変形性を有する触媒への応用が期待される。また、セルメット担体は通電加熱によって触媒を直接加熱できる利点もある。本報告ではRu微粒子を担持したCeO2粉をNiセルメットにコートした触媒が市販の球状Ru触媒に匹敵する優れたプロパン水蒸気改質性能を示し、実用的なポテンシャルを有していることを明らかにした。さらに500℃に通電加熱したNiCrセルメットが良好な長期耐久性を有していることを抵抗変化量の経時変化から予測し、エネルギー消費量が少ない小型の反応器を構築できることを提案した。
2.9 MB
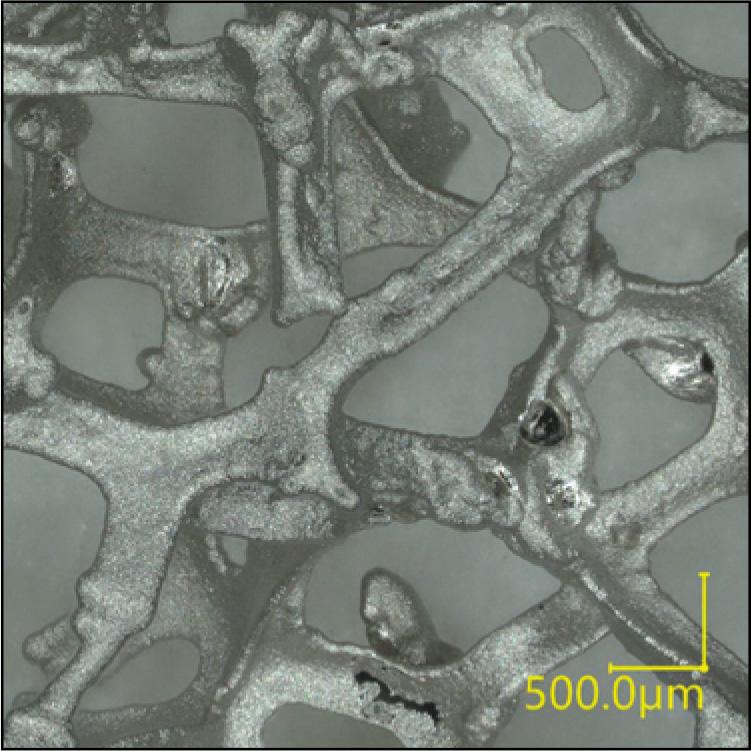
2.9 MB
電子部品の配線やコネクタの接圧保持用のばね線には、その使用中において接触圧力の維持や繰返し屈曲に耐えるために高強度化が求められる。しかし、汎用的に使用される銅合金線は高強度化に伴い導電性が低下する課題が生じる。本背景を踏まえ、我々は伸線・熱処理技術を活用し、外周にステンレス鋼、中心側に銅を備えた強度と導電性を両立する複合線を開発した。開発材は、銅合金の中で最高強度を有するベリリウム銅に対して、更に高い強度と導電率を有すると共に、曲げや捻りに対しても強いことを実証した。本報では本開発材料の各種特性並びに、接圧保持用導電ばね、繰り返し屈曲負荷される電線用途での耐へたり性評価、耐屈曲評価を行った結果について詳述する。
1.5 MB

1.5 MB
近年、航空機、石油ガス、医療、自動車産業等において、その機器や部品には耐熱性や耐食性に優れるNi(ニッケル)基、Co(コバルト)基、Ti(チタン)合金等の材料が多く使用され、その使用量は今後大幅に増加すると見られている。一方、これらの材料を切削加工する場合、被削材自体の高温強度が高いことや工具の刃先に溶着しやすいことなどから、工具の寿命が著しく低下する問題がある。そこで当社ではこのような難削材の転削加工において、安定長寿命かつ高能率加工を実現する新しい工具材種「ACS2500」および「ACS3000」を開発した。このACSシリーズは難削材転削加工において当社従来材種と比較して2倍以上の長寿命または高能率加工を実現し、加工コストを大幅に低減させることが可能となった。
2.1 MB

2.1 MB
近年、製造業において、製品開発やプロセス条件の最適化といったモノづくりの要素技術として、シミュレーション技術―CAEーはなくてはならないツールとなっている。CAEは物理法則に裏付けされたモノづくり、製品の機能発現を導き、さらには目に見えない現象である電磁波、熱、応力などを可視化することで設計者や生産技術者の想像力をかき立て新製品開発、新プロセスの改善へと結びつけている。また、新製品拡販のための説明やプロセスの変更申請において、実測結果に加えてCAE解析結果を求められるケースも増加している。このような状況下、有用で正確なCAE解析結果を導出するためには、現実と合致する高度なCAE技術と、その解析を高速に処理する計算機サーバーが必要である。今回、計算機サーバーにおいて計算の効率化と機能の高性能化を進めることで、これまで対応できなかったCAE解析を可能とした。その内容を各解析分野で紹介する。
2.4 MB
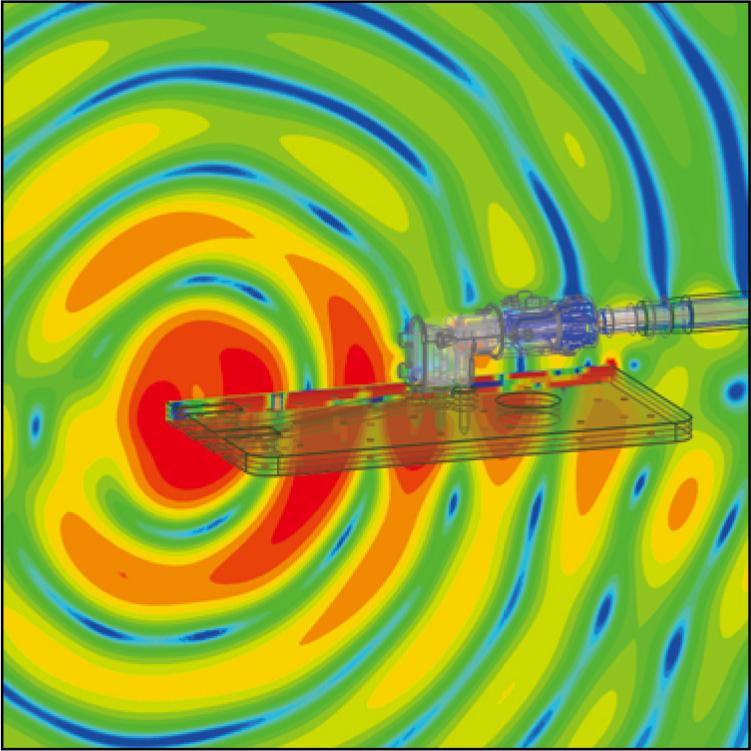
2.4 MB
第5世代移動通信システム(以下、5G)を活用し、工場や都市内のあらゆる情報を、高速かつ低遅延でクラウドに伝送し、AIによる情報分析などにより、生産性や安全性を向上させる産業用ソリューション市場が急速に立ち上がろうとしている。当社では、モバイルキャリアが展開するパブリック5Gと、企業や自治体が限定されたエリア内で5G ネットワークを構築するローカル5Gの両者で利用可能な産業用5G端末を開発した。本5G端末はエッジ処理機能を有し、ユーザが必要とするアプリケーションの実装が容易なことを特徴としている。本5G 端末でのエッジ処理とクラウドサーバーでのクラウド処理を組み合わせることで、ユーザ要件に合わせた最適なソリューションの実現が可能となる。
310 KB
住電通信エンジニアリング㈱は約20年に亘り、ヘルパーの活動実績に基づく対価を計算して請求先に請求するための介護システム(請求システム)“ケアタイム”を通じて介護事業者の業務に携わってきた。今回、管理者とヘルパーの業務の効率化を図り、更に、両者の相互情報伝達をオンタイム化して心のつながりを密にし、質の高いサービスを利用者に提供する介護事業者の想いを実現するシステムとして、介護システムとデータ連携可能なWEB システムを開発し、介護事業者にサブスクリプションサービスとして提供を開始した。
293 KB
とう道(通信ケーブル布設用トンネル)において蛍光灯からLED照明への置き換えが進んでおり、当社は2013年より保護等級IP67(耐塵・防浸)性能を持つ防浸型LED照明をリリースし販売してきた。しかし外形寸法の制約から狭小部への適用が限定的であった。今回、従来品の優れた部分は継承しつつ狭小部への適用が可能な小型で取り付けやすい製品にするとともに、バッテリの自動点検機能搭載による保守の作業性向上と漏えい電流の特性を改善した。
0.8 MB
現在、電力ケーブルは、架橋ポリエチレン(XLPE)を絶縁体に用いた、XLPE ケーブルが主流製品となっている。XLPEは架橋しているため、耐熱性に優れるものの、加熱しても流動性を示さず、マテリアルリサイクルが難しいというデメリットを有している。また、ケーブル加工時には、網目構造に結合させる架橋反応と、その反応に伴う副生成ガスを脱気するための乾燥工程が必要で、製造長が長いほど、リードタイムが長くなる場合がある。このような状況から、環境にやさしく、生産性の向上に貢献できる、非架橋絶縁電力ケーブルの開発を進めた。
1.5 MB
産業界における人手不足解消や、生産性向上のため産業用ロボット市場は急速に拡大し、精密軸受け(リニアガイド・ボールねじ)需要が高まっている。特に転動面の加工は高い生産性が求められることから総形研削加工が採用されており、その輪郭精度は総形砥石を成形・目立てするダイヤモンドロータリードレッサ(RD)が担っている。研削砥石は更なる高能率化のため、従来の一般砥石から高速研削が可能な硬質ホイールに置き換わり、これに伴って高い耐摩耗性を有する総形RDの開発が望まれてきた。この度、軸受け業界の要望に対し、独自のめっき技術を用いて、ビトCBNなどの硬質ホイール用の新しいRDを開発。発売を開始した。
1 MB
フライス工具は外周、端面もしくは側面に工具切れ刃を備えた切削工具であり、これが回転運動することで、様々な部品の加工が行われる。現在ではその切れ刃となるインサートを交換する工具が一般的に広く使用されており、様々な加工に用いられている。近年の工作機械の性能向上により、自動車や航空機、造船、産業機械、金型などの分野では、生産性向上のため、高能率加工に特化した工具への要求が強まっている。また、脱炭素社会の実現に向けたCO2排出量削減活動の一環として、機械加工の省エネルギー化も注目されている。今回開発した「SEC- スミデュアルミルDMSW型」はこれまで以上の高能率加工を可能にすることで、生産性の向上や省エネに貢献する。
1.4 MB
地球温暖化抑制に向けた脱炭素社会への取り組みは、世界的に大きな流れとなっている。国内においても、一昨年10月の「2050年カーボンニュートラル宣言」に基づく「グリーン成長戦略」にて、再生可能エネルギーや水素エネルギーなどに総力を挙げて取り組む方針が打ち出され、脱炭素イノベーションを日本の産業界の競争力強化につなげるねらいで、「グリーンイノベーション基金」も創設された。 とりわけ大きな期待がかけられている洋上風力発電は、官民協議会の「洋上風力産業ビジョン」にて2040年までに30~45GWとの意欲的な目標が示されている。一方、再生可能エネルギー資源の偏在の問題や、洋上風力発電においては台風等過酷な気象条件への対応などの課題がある。
1.3 MB
脱炭素社会の実現に向け、欧米先進諸国や日本では化石燃料を中心としたエネルギー構成から太陽光発電などの再生可能エネルギーを主力とした構成に組み換えが行われようとしている。しかし再生可能エネルギーは天候の影響で出力が変動するため安定した電力を供給することが難しいという課題がある。この課題解決の一つとして、再生可能エネルギーの出力変動を平準化するために需要家側に中小規模太陽光発電装置や蓄電池などの分散型電源を導入する取り組みが進められている。将来再生可能エネルギーが大量導入されていく中で、エリア内に分散配置された電源を統合し、安定的にかつ効率よく運用するエネルギー管理システムが重要な役割を担うことになる。本稿では、分散配置された電源を有機的に結び付け統合的に制御する自律分散+階層型の次世代エネルギー管理システムについて論じる。まず、分散電源を統合管理することの技術的な課題について述べ、次にその解決に向けた先行技術動向を整理する。最後に当社エネルギー管理システム「s EMSA-μGrid」について、その特徴と適用領域について説明する。
2.7 MB

2.7 MB
再生可能エネルギーである太陽光発電の普及や電力の自由化などを背景に、種々の社会問題を解決するため、エネルギーの地産地消や蓄電池、EVによる蓄電などについて、IoTを活用した高度なエネルギーマネジメントの実現に注目が集まっている。㈱日新システムズ(以下、NSS)は、IoT技術を通じてエネルギー分野における課題を解決するため、主に一般需要家向けのビジネス展開に必要となるゲートウェイ装置および、クラウドシステムによるソフトウェアやサービスを提供している。 本稿では、沖縄県宮古島市における「島嶼型スマートコミュニティ実証事業」にて構築したエリアアグリゲーションシステム(以降SPSS-Hと記載)の技術内容について紹介する。
13.5 MB
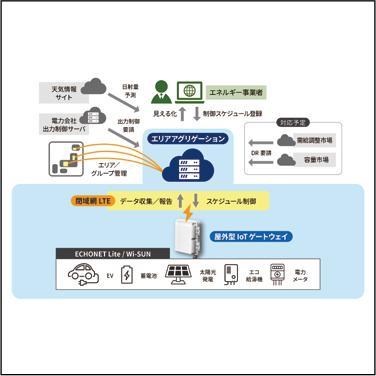
13.5 MB
高分子材料に電圧を印加した時に流れる微小電流は材料内で起こっている物理現象を反映しており、材料の誘電・絶縁現象を理解する上で非常に重要である。その解析手法として、我々は電流積分電荷法(Q(t) 法)を用い、電流を積分して電荷量として計測する手法を検討している。ここでは、矩形波電圧印加直後の瞬時充電電荷量(Q(0))と時間tm 後の電荷量(Q(tm))の比である電荷量比(Rc = Q(tm)/Q(0))を新たなパラメータとして導入し、交流および直流ケーブル用の架橋ポリエチレン(AC-XLPE およびDC-XLPE)を試料とし、数十時間の課電を行ってその空間電荷および伝導挙動について解析を行った結果を紹介する。
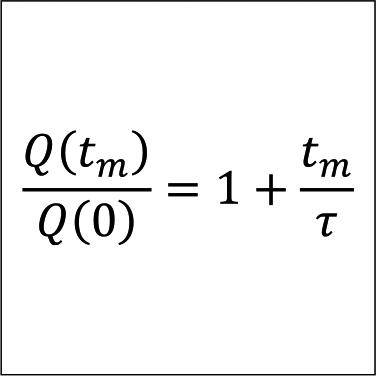
1.9 MB
温室効果ガスの削減が世界的に急務となり、洋上風力発電の導入が進んでいる。発電した電力を送電する海底ケーブルに関し、近年、風車の出力増加に伴う高電圧化(66kV級)や大容量化と、製造性、コスト、施工性を改善するために遮水層を省略するケーブル構造(非遮水海底ケーブル)が期待されている。遮水層の省略は、水トリーと呼ばれる絶縁体の劣化による事故リスクを高めるため、当社は耐水トリー性の絶縁体の検討を進め、2018年に制定された遮水層の省略可否を判定する規格(CIGRE TB722)を満たすことを確認できた。また、長期運用や将来の更なる風車の出力増加を見据え、66kV級を超える高電圧下でも使用できる高い耐水トリー性を有する絶縁体の検討にも取り組んでおり、今後の洋上風力発電の導入促進に貢献できるものと考える。
1.8 MB

1.8 MB
近年、再生エネルギーの導入拡大に伴い、直流送電線の建設や計画が増加している。直流ケーブルには、MI ケーブルやOF ケーブルといった油浸紙絶縁ケーブルが用いられてきたが、交流ケーブルと同様に環境面への配慮から、XLPEケーブルの採用が拡大している。当社は長年に亘って直流XLPE ケーブルの研究開発を行い、優れた特性の直流XLPE を実用化、電源開発㈱に納入した直流250kV XLPEケーブルが2012年に運転を開始した。これは直流XLPEケーブル線路としては世界最高電圧(当時)であり、かつ極性反転を行う線路への納入は世界初であった。その後、NEMO Link Limited社の直流400kV連系線(直流XLPEケーブルの世界最高電圧を更新)や北海道電力㈱の直流250kV連系線等を完工、現在も新たなプロジェクトに取り組んでいる。当社の直流XLPEケーブルは、常時導体許容温度が交流用と同じ90℃で、かつ極性反転が可能といった特長を有しており、今後の再生エネルギーの普及に伴い、ますます増えていくであろう直流送電線のさまざまなニーズに応えることができるものと考える。
3.3 MB

3.3 MB
現代社会において電力の安定供給の重要性は益々高まっているが、落雷等による送電線事故は皆無という状況に至っておらず、万一、送電線事故が発生した場合、迅速かつ効率的に事故発生箇所を特定して復旧対応を行う必要がある。特に、架空線と地中線が混在する送電線路においては、事故復旧の対応方法がそれぞれ異なることから、事故発生箇所が架空線か地中線かを判定することは、早期復旧する上で重要とされている。架空地線及び地中線に電流センサを設置して、その電流情報から架空線と地中線の事故を判定する「架空線/地中線事故判別システム」を開発し、電力会社に本格的に導入されたことから、その概要について報告する。
2.6 MB
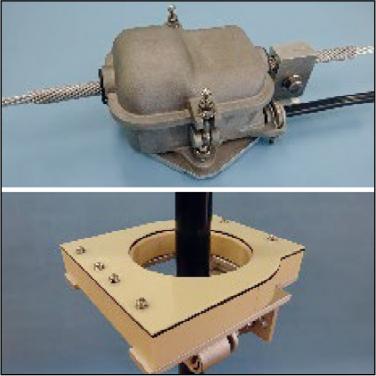
2.6 MB
地中送電線路の点検保守は、従来人手によって定期的に巡視等を行うTBMから、IoTやAIを活用したデジタルトランスフォーメーションを促進し、必要な時に効率的に保守を行う、より高度なCBM への転換を図るといったスマート保安の推進が要望されている。IoTを実現する課題として、地中送電設備の多くを占める管路布設ケーブル設備の保守情報を取得するための安価で安全かつ信頼性の高い通信方式の確保が困難であったことが挙げられる。本論文では、マンホール内から66kV の既設の電力ケーブル(XLPE)の金属遮蔽層を伝送路として利用して、保守に使用するセンサ情報やカメラ画像を収集する保守監視システムを東京電力パワーグリッド㈱と共同で開発を行ったので紹介する。

2.3 MB
本稿では、従来の200μm光ファイバを用いた間欠12心光ファイバテープ心線(以下、200μm間欠12心テープ心線)を実装したデータセンター向6912心ケーブルを細径・軽量化した細径高密度6912心光ファイバケーブル(以下、細径6912心ケーブル)の構造、特性および施工性について報告する。使用した200μm間欠12心テープ心線は、長手方向に間欠的にスリットが入った構造による柔軟性を持ち、さらに従来の250μm テープ心線や200μm 間欠テープ心線同士の一括融着接続性も持ち合わせている。今回はさらなる細径高密度化を実現するため、光ファイバの耐側圧性(以下、マイクロベンド耐性)向上およびスロット構造最適化、高強度シース材の適用等を行い、従来比約34%のケーブル断面積低減を実現した。本構造は細径化を実現しつつ、従来のスロット型の特長である曲げ方向性がなく、布設作業性に優れる構造とした。布設作業性に関して、従来の2インチダクトよりも細い1.5インチダクトに牽引しても通線の問題がなく、さらに押し込み、圧送工法も対応可能であることを確認した。本ケーブルを用いることで管路内での光ファイバ心線密度の向上と施工性の両立、さらには細径化、長尺化による材料使用量減による耐環境性の向上も見込まれる。
4.9 MB
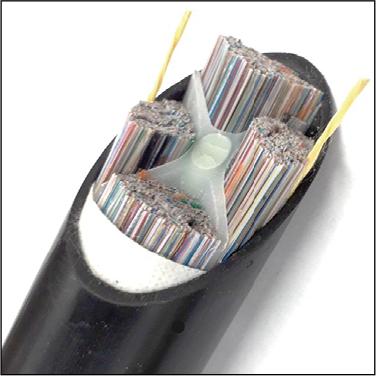
4.9 MB
コア間結合の強さが異なる3種のコア励起マルチコア・エルビウム添加光ファイバ増幅器を試作し、結合4コア光ファイバ増幅器で電力効率が24%と、コア励起方式が電力効率において優れていることを確認した。クロストークは非結合マルチコア光ファイバ伝送において重要なパラメータであり、非結合4コア光ファイバ増幅器において-43 dBと最高水準の結果を得た。結合マルチコア光ファイバ伝送において重要なパラメータであるモード依存損失は、非結合マルチコア光ファイバ増幅器や弱結合マルチコア光ファイバ増幅器のコア依存利得に対応し、弱結合7コア光ファイバ増幅器で0.52 dBと最高水準の結果を得た。
1.6 MB
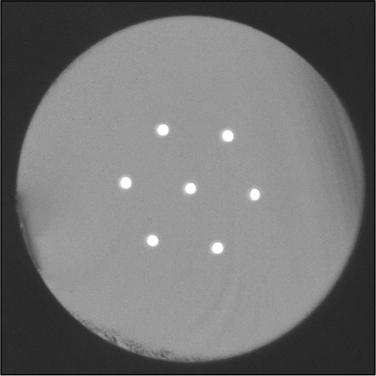
1.6 MB
近年、航空機、石油ガス、医療、自動車産業等において、その機器や部品に耐熱性や耐食性に優れるNi(ニッケル)基、Co(コバルト)基、Ti(チタン)合金等の材料が多く使用され、その使用量が今後大幅に増加することが見込まれている。当社は、これら難削材の連続加工から断続加工まで幅広い加工領域で安定長寿命を実現する工具材種として、新PVD コーティングを適用したAC5015S/AC5025S を発売している。一方、難削材の切削加工においてはさらなる加工能率の向上が求められており、当社ではAC5000S シリーズに新たに高能率加工用材種「AC5005S」を追加した。AC5005S は難削材旋削加工において、高い耐摩耗性・耐塑性変形性と耐欠損性を両立させた材種であり、AC5015S/AC5025Sと併せて幅広い難削材加工における加工コストの低減を実現する。
2.5 MB

2.5 MB
製品の開発や品質向上には構成する材料の構造、組成等の分析が不可欠である。中でも、例えば半導体基板、めっき、樹脂の表面処理など、製品表面の状態、具体的には表面近傍の化学種の深さ分布(プロファイル)が製品特性に影響するものが多く存在する。未知試料の表面近傍における化学種ごとの深さプロファイルを非破壊で評価したいという、従来の分析手法では実現困難であったニーズに応えるため、X 線光電子分光(XPS)分析データに対する新たなデータ解析技術「MSM」を新たに開発した。当社は情報深さの異なる3種類のXPS装置を利用することができ、それぞれMSM解析と組み合わせることで、深さレンジの異なるプロファイル評価が可能である。本論文では実際に3種類のXPS装置による分析データに対してMSM解析を適用することで、多様な製品に対して非破壊での化学種深さプロファイル評価が可能であることを示す。
2.8 MB

2.8 MB
近年、脱炭素社会の実現に向け電気自動車へのシフトを目的として各自動車部品の電動化が進んでいる。しかし、電動化は制御対象を電気信号で制御するバイワイヤ制御の採用が拡大するが、バイワイヤ制御は鉛バッテリなどの車両電源が異常となった場合に、制御ができなくなる課題がある。住友電工グループの住友電装㈱、㈱オートネットワーク技術研究所は、車両電源異常時にも複数のバイワイヤ制御を継続するための統合バックアップ電源を開発した。
0.5 MB
近年、高性能PC、自動運転システムの普及、またスマートフォンなどによる高画質動画データの通信など、データの処理能力向上が進んでいる。そのため、これらに用いられるプリント回路基板(PCB)には、これまで以上に高い耐熱性、耐久性が求められている。耐熱性、耐久性の向上にあたり、耐熱・放熱フィラーの改良・含有率の増大、基板の超多層化、基板の板厚増大が進んでいるが、これらは基板の穴開け加工にとっては難削化の方向となる。具体的にはドリル摩耗量の増大、それに伴う穴位置精度の劣化を引き起こし、加工穴精度、加工穴内壁品位悪化による基板信頼性の低下に繋がる。そのため、難削化するプリント回路基板の穴開け加工に対して、高精度・高品位を達成する新しいドリル材質の開発が望まれてきた。この度、市場の要望に対して新材質AF905を開発し、発売を開始した。
1 MB
陸上幹線ネットワークにおける大容量伝送を支えるため、ITU-T G.654.E勧告に準拠する低損失・低非線形光ファイバPureAdvanceを開発し、供給を行っている。PureAdvanceは、陸上伝送路で実運用可能なケーブル化が可能、接続損失が低い、ラマン増幅を適用可能といった、実際に陸上伝送路として敷設する際に要求される実用的な性能を有する。また、PureAdvanceを用いた伝送システムは、従来の光ファイバを用いた伝送システムに比べて高い伝送性能を有することから、PureAdvanceは、幹線伝送網を始め、データセンタ間伝送や、海底システム陸揚局~データセンタ間伝送などの陸上伝送路に最適な光ファイバである。
1.1 MB
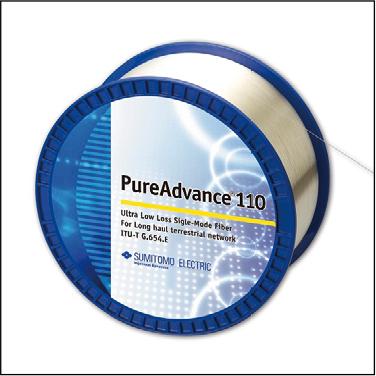
1.1 MB
脱炭素を実現できる有力候補の一つである核融合エネルギーの科学的および技術的実現性を実証することを目的としたITER※1計画が国際的プロジェクトとして進められている。ITERの構成機器のうち、2000℃を超える超高温に晒されるダイバータにはタングステンが使用される。ITERの安定した運転を可能とするために、高温加熱および冷却のサイクルを受けるタングステンには優れた耐熱衝撃性が要求されている。そこで我々は、高温加熱による再結晶粒の成長を抑制した耐熱衝撃タングステン材を開発した。この開発材からダイバータ小型試験体およびプロトタイプ用のモノブロックを作製し、核融合炉を模擬した熱負荷試験にて性能を評価した。その結果、過酷な条件下においても開発材は割れなかった。とくに、プロトタイプの評価結果はITER要求を大きく上回り、当社の開発材が世界に先駆けて“割れないタングステン”として評価された。
4.3 MB
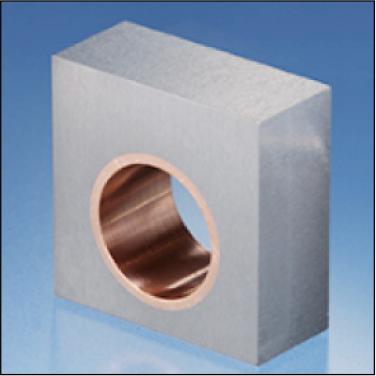
4.3 MB
プリント基板加工用CO2(炭酸ガス)レーザドリルマシンには、高速・高精度・高スループットの微小穴あけを実現するために高性能Fθレンズが用いられる。セレン化亜鉛(ZnSe)とゲルマニウム(Ge)はFθレンズのレンズ素材として優れているが、GeはZnSeに比べてCO2レーザに対する吸収率が高く、温度変化に伴う屈折率変化が大きい。そのため、穴加工の高密度化やレーザ高出力化によるFθレンズへの入力パワー増大に伴って、加工の不安定や品質低下を招きやすい。そこで、当社はZnSe素材から完成品までを一貫生産する光学部品メーカとしての強みを活かし、全ての構成レンズとDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コートカバーウィンドウにZnSeを用いた新しいFθレンズを開発した。ここでは、その技術概要を紹介する。
2.8 MB

2.8 MB
自動車部品等で用いられる鋼の切削加工においては、環境負荷の低減や資源の効率的な活用を目的とした様々な取り組みが進められている。当社は連続加工から断続加工まで幅広い加工環境での安定加工を実現する工具として2016年に新CVDコーティング技術「Absotech Platinum」を適用した鋼旋削用材種AC8000Pシリーズを発売し、順次製品ラインナップを拡大している。他方、切削工具には加工工程の自動化・無人化のための安定長寿命に加えて、近年では加工条件の高能率化に耐えうる、さらなる性能向上が強く要求されている。当社はこのニーズに応えるべく、高能率加工で特に優れた性能を発揮する新材種「AC8020P」を開発した。「AC8020P」は従来トレードオフの関係にあった高能率加工における耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立させた材種で、AC8000Pシリーズの既存材種と併せて幅広い鋼旋削加工における加工コストの低減を実現する。
3.2 MB

3.2 MB
銅やアルミより軽量・高導電性の次期電線用素材としてカーボンナノチューブ(CNT)に着目している。CNT単繊維は銅を超える導電性を持ち、既知の材料で最も高い引張強度を持つと言われている。CNT電線実用化を目指し当社独自の手法を開発する中で、鉄触媒からの炭素成長時における引張応力付与の有効性を発見した。また、共同研究先の筑波大学において、高速気流中でセンチメートル級での単繊維の成長を発見、成長時の応力付与がCNT長尺化に寄与していることを示唆している。この原理を基にした成長方法で本長尺CNT単繊維を集合したメートル級の集合線を作成、従来のCNT集合線の数倍の強度を持ち、市販の炭素繊維の引張強度も超える結果が得られたので報告する。これにより炭素繊維用途を置き換えるだけでなく、これまでにない新用途にも展開できる。
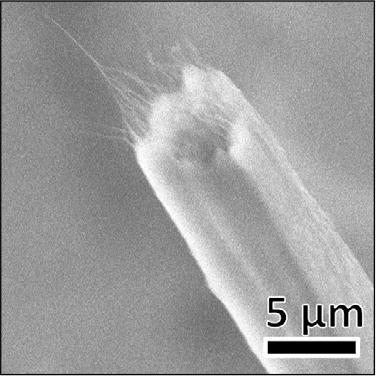
3.7 MB
マグネシウム合金は実用金属中最軽量であり、その一つである当社製AZ91板は、軽量性に加えて、高い強度・耐食性を示し、近年需要が高い薄型ノートPC筐体での実用化が進んでいる。一方で、情報機器業界では、IoTやAI等を活用するため、5Gの電子媒体への実装が進められているが、ハード面では電子機器の発熱が予想されており、これまで以上に電子機器の冷却が求められている。この対策として、材料面からは、材料の放熱性・熱伝導率の向上が挙げられる。今回開発したマグネシウム合金SMJ140の熱伝導率は120~140 W/(m・K)を示しており、この数値は、AZ91板の61 W/(m・K)に対して、2倍以上であり、汎用Al合金板材A5052に相当する。本論文では、軽量放熱板材として期待される高熱伝導性マグネシウム合金板材SMJ140を紹介する。
1.9 MB
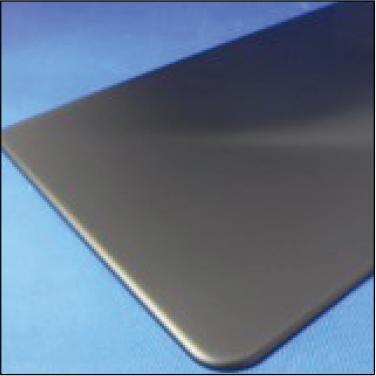
1.9 MB
2030年わが国は3人に1人が65歳以上の超高齢化社会を迎える。急速なデジタル化に伴い、あらゆるサービスが変化する社会環境において、IT(情報技術)リテラシーが低い高齢者の社会からの孤立、地域で高齢者見守りを行う支援者の高齢化・担い手不足が大きな社会課題となっている。それに加え長期化する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大において、直接対面できず見守り対象者が孤立する新たな課題も生まれている。人が人を支える福祉分野において、ITを活用した非接触で見守る仕組みのニーズは今後更に拡大すると期待される。本稿は、2019年度より富山県の社会福祉法人黒部市社会福祉協議会(以下、黒部市社協と記す)と共同で推進してきた実証実験を通じ、㈱日新システムズ(以下、NSSと記す)が“誰でも簡単に地域とつながることができる”をコンセプトに開発を行った在宅高齢者向けICT(情報通信技術)端末と、本端末を利用したサービスの内容について記載する。
2.2 MB

2.2 MB
電線用の銅線やアルミ線等では、熱処理の温度や時間等の製造条件が特性に大きな影響を与える。当社ではこのような製造条件最適化の強力なツールとして、高い透過能を持つ高強度な放射光X線を用いたその場測定技術を開発してきた。本技術は高効率な製造条件最適化への活用が期待されるが、限られた測定機会や、膨大なデータ処理の点で課題があり、実際の活用は限定的であった。そこで本報告では、当社が保有する住友電工ビームラインに複数の環境制御ステージを導入して測定までの時間を短縮すると共に、大量のデータを測定と並行して自動解析する新たなプログラムを作成することで、解析時間の短縮を実現した結果について述べる。これらの設備、プログラムを用いて銅及び銅合金の熱処理工程を模擬したその場測定を行い、温度変化に伴う軟化挙動の違いを短時間で解析できることを確認した。
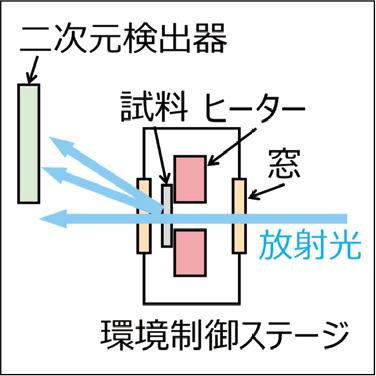
1.6 MB
自動車のヘッドランプやリアランプには従来ハロゲンランプが使用されてきたが、長寿命や省電力、最大光量までの点灯速度が速いという理由で、近年LED ランプが採用されるようになってきた。車載LEDランプの内部構造は、図1のように筐体内部にLEDランプやドライバモジュールが搭載されており、その配線には自動車用低圧電線が用いられている。LEDランプ内部に使用される電線には、長期間使用してもガラスが曇らない防曇特性が要求されるが、電線被覆は長期間経過するとアウトガスが発生してガラスを曇らせてしまう問題がある。したがって、LEDランプ内配線に使用される電線被覆には低アウトガス性が要求されている。今回、当社独自の配合技術で低アウトガス性を持つ絶縁材料を開発したので紹介する。
0.5 MB

0.5 MB
昨年1月以降の新型コロナヴィールスによる新型肺炎の蔓延により、100年前に流行したスペイン風邪との比較が何かと話題になった。スペイン風邪では、当時20億人だった世界人口の2%に相当する40百万人以上の人命が失われたという。名前はスペイン風邪だが、第一次世界大戦に参戦したアメリカ兵が米国から欧州に持ち込んだのが感染の淵源だったと言われている。史上初の世界大戦で、グローバルに兵士をはじめとする多くの人々が移動・接触したことで、感染があっという間に拡散したのであろう。第一次世界大戦での死者は軍民併せて15百万人と言われているので、スペイン風邪での犠牲者の方がはるかに多かったことになる。まさに世界中が大変な時代だった。
0.6 MB

0.6 MB
近年、航空機市場では長期的な需要増加が見込まれており、航空機部品製造の高能率化が求められている。航空機のエンジンや構造部品に使用される耐熱合金やチタン合金は難削材に分類され製造コストに占める加工費の割合が高いため、切削工具には高能率化と長寿命化が強く要求される。当社ではこれらのニーズを実現するため、耐熱合金およびチタン合金加工に特化した超硬工具材質を開発した。耐熱合金加工には高温下での圧縮歪量を75%低減した耐熱バインダー超硬合金を開発し、高速・高送り加工での塑性変形と摩耗を抑制し、高能率加工を可能とした。チタン合金加工には耐反応性に優れた新コーティングを開発し、工具への凝着を抑制することにより背分力を30%低減し、工具の長寿命化を実現した。
2.2 MB

2.2 MB
スミボロンCBN工具は、ダイヤモンドに次ぐ硬度及び熱伝導率に加えて鉄に対する低親和性を兼ね備えるcBN粒子を主成分とし、鉄系難削材料の仕上げ加工でコスト低減や加工能率向上に貢献してきた。一方、近年の自動車産業においてHEV、EV化の促進とともに、鉄系焼結合金加工では高い寸法精度とさらなる難削化への対応が、鋳鉄超高速加工では工具の安定長寿命化が要請されている。これらの切削加工における工具損傷解析に基づき、当社は新たな高cBN含有率材種「スミボロンBN7115」を開発した。BN7115は高純度cBN原料およびCo-Al-Cr-WC新結合材を適用することで、cBN粒子間結合力を飛躍的に向上させ、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立した。これにより、焼結合金加工における加工品位低下や鋳鉄加工における熱衝撃欠損を抑制し、工具の長寿命化に貢献できるものと期待される。
2.7 MB

2.7 MB
立方晶窒化ホウ素焼結体(CBN)は、ダイヤモンドに次ぐ硬度と鉄との親和性の低さを特長とするcBNを利用した工具材料であり、主に自動車産業での焼入鋼、鋳鉄や焼結合金の高速仕上げ加工で用いられる。航空機や金型産業などでも使用されているが、製品の軽量化、高出力化のため難削材の使用が増加する傾向にある。また加工精度の向上など高付加価値化が課題となっており、CBN工具に対する長寿命化や高精度化の要望が強くなっている。スミボロンバインダレスは、ナノ~サブミクロンサイズのcBN粒子が直接強固に結合した、従来CBN材種で用いる結合材を一切含まない焼結体である。従来CBN材種より硬度あるいは熱伝導率が高く、航空機、金型や医療産業などで用いられるコバルトクロム合金、チタン合金、ニッケル基耐熱合金等の難削材加工における高能率化、長寿命化を実現する。
2.1 MB
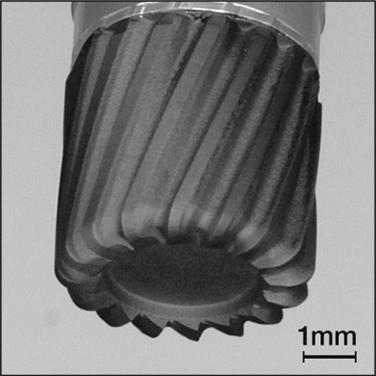
2.1 MB
近年、自動車関連の産業では、地球環境保護のため、自動車の燃費性能改善が求められており、部品の軽量化やHV、EV、FCV車の拡大に伴いアルミニウム合金などの非鉄金属材料の使用割合が増加している。これらの部品加工においては、生産性を向上させるため、加工時間の短縮を目的とした高能率加工や、非切削時間短縮のため、取り扱いが容易な工具、切りくず処理性に優れた工具が求められている。さらに、単位面積あたりの生産性向上を目的とした小型加工設備に対応できる軽量工具も、近年では求められている。これらに対応するため、当社はアルミニウム合金加工用高能率PCD※1カッタ アルネックスANX型を開発した。本報ではアルネックスANX型の特長について述べる。
2.1 MB
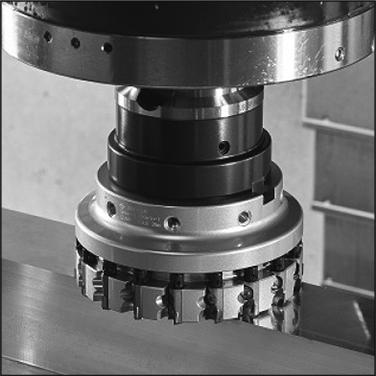
2.1 MB
移動体の電動化や家電・産業機器の高効率化が進み、モータ需要とその高性能化ニーズが高まっている。現在一般的に用いられているラジアルギャップモータに対し、アキシャルギャップモータは薄型で高トルクが得られるため、これらニーズを満たすものとして注目されている。当社ではこれまでに、圧粉磁心を搭載したアキシャルギャップモータが高トルク・高効率であることを実証し、今年度よりアキシャルコアの量産を開始した。アキシャルギャップモータの更なる普及拡大に貢献するため、より低損失な圧粉磁心や生産性に優れる一体ツバ付コア、モータ温度上昇抑制に貢献する薄膜絶縁塗装を開発したので報告する。
2.1 MB

2.1 MB
「SmART ストランド」(スマートストランド)は鋼材本体に作用する張力を測定するためのセンサを備えたPC鋼より線である。SmART ストランドは張力測定用センサとして光ファイバが内蔵されており、光ファイバを用いたひずみ計測技術を用いることによりその全長にわたる張力の分布を計測することが可能である。プレストレストコンクリートやグラウンドアンカーにおいては、構造物にプレストレスを与えるPC鋼材の張力を正確に管理、モニタリングできることが構造物の品質向上や維持管理において非常に重要である一方、従来技術では張力計測が可能な箇所が限定されており、ケーブル全体の長期的なモニタリングが困難であるという課題があった。SmART ストランドはPC鋼より線の全長における張力を把握し、施工完了後も計測可能な技術を提供する。本稿ではSmART ストランドを用いた張力計測技術ならびにSmART ストランドの構造、その適用例について報告する。
1.7 MB
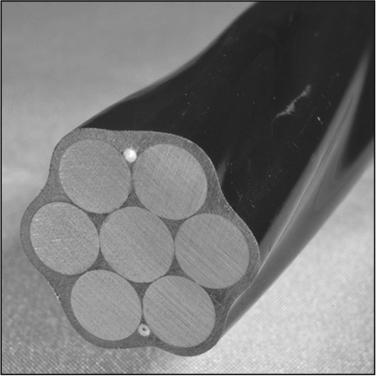
1.7 MB
カーボンニュートラル、CO2排出削減といった国際的な環境規制強化への変化が加速しており、電源機器や通信機器などの半導体デバイスにおける熱マネージメントが重視されている。軽量で電気伝導、熱伝導が良好なアルミニウム材料は、従来使用されている銅系材料に対する代替ソリューションとして期待されるが、150℃以上の温度域での強度低下するために適用範囲が限られている。当社では、急冷凝固法で得られる粉末アルミニウムを原料として採用することによって、250℃付近の高温まで強度が低下することを抑え、且つ、電気伝導および熱伝導を純アルミニウムに近い水準を維持した新たなアルミニウム材料を開発した。本アルミニウム材料は、導電部品、放熱部品などの軽量化ニーズに対して貢献できると考えている。
2 MB

2 MB
熱電材料を応用した赤外線センサであるサーモパイルは、非冷却、検出における消費電力フリーという特長がある。我々は、このサーモパイルの性能を向上させるため、赤外線検出部に用いられる熱電材料の開発に取り組んできた。感度の向上には、熱電材料の熱伝導率の低減、ゼーベック係数の向上が重要である。我々が開発したナノ構造Si-Ge熱電材料は、独自のナノ構造と共添加技術により、熱伝導率1Wm-1W-1、ゼーベック係数330µVK-1を有する。この新材料を用いてサーモパイルを作製し、赤外線の検出を実証するとともに、本サーモパイルと赤外線レーザを用いたガス検知システムにおいて、大気中のメタンの検出にも成功した。
1.3 MB
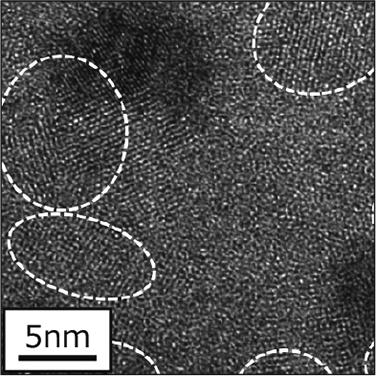
1.3 MB
米国の送電網では、1940年代から鋼管入り電力ケーブル(HPFF又はHPGF)が使われてきた。鋼管には絶縁油やガスが充填されており、老朽化に伴い、鋼管の腐食や漏油が問題化している。HPFF/HPGFケーブル※1は既に製造企業がいない上、都市部の線路では地中に水道・ガス管、通信ケーブルなどが混在することから、鋼管路の除去、新規布設が非常に困難であるため、既設の鋼管路をそのまま活用し、新たに設計されたケーブルシステムに置き換えないといけないという課題があった。本報では米国の既存送電網において、既設HPGFケーブルを撤去し、当社が米国・日本で特許を取得しているトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(CETケーブル)の開発・設計を行い、リプレースを完工した成果について報告する。
2.8 MB

2.8 MB
当社は、5G次世代通信、人工知能自動運転技術、データセンタ用大容量ストレージ等に不可欠な各種半導体の製造工程で使用される枚葉式成膜装置向けに半導体ウエハを加熱するヒータを供給している。半導体回路配線の微細化要求から均質な成膜分布のために、ウエハ面内温度分布の均一化の要求が日々厳しくなっている。これまでのヒータは、同心円状のゾーンに区分けして制御されていたが、均一化を妨げる様々な装置環境因子による周方向の微妙な温度分布ムラをカバーすることができず、均一化に対して限界を迎えていた。この限界を乗り越えるために、マルチゾーン化したヒータとそのヒータを高精度に制御するコントローラを開発したので、報告する。
2 MB

2 MB
近年クラウドコンピューティングや動画配信、5G対応等の進展により、通信トラフィックは急増している。一方、ダクト内スペースの物理的な制約もあり、光ファイバを高密度に収納した細径高密度光ファイバケーブルの需要が増している。欧州、北米等のFTTHでは、一度管路(マイクロダクト)を布設すれば、追加の道路工事等なく追い張り布設でき、経済的なネットワーク構築が可能となる空気圧送用光ケーブルが普及している。この空気圧送用に用いられる細径ダクトがマイクロダクトであり、近年の伝送容量増やFTTH等の進展でマイクロダクト光ケーブルの多心高密度化のニーズが高まっている。当社は従来の外径250μmの光ファイバよりも細径な200μm光ファイバを用いた間欠12心光ファイバテープ心線(以下、200μm間欠12心テープ)を実装した432心以下の空気圧送用光ファイバケーブルを開発し、販売を開始した。
0.7 MB

0.7 MB
太陽光発電の余剰電力の買取価格は低下が著しく、電気料金を下回っている。このため、太陽光により発電された余剰電力を売るよりも自家消費に利用することが検討されている。夜間の電気料金が安い時に電気を蓄電池に蓄え、昼間の電気料金が高い時に電気を使うことにより、電気料金を節約することができる。また、近年、風水害による大規模停電があり、家で使用できる非常用電源が必要とされている。これらの要求に応えることができる住宅用蓄電システムが注目されている。当社では2017年に住宅用蓄電システム「POWER DEPOIII」の販売を開始し、2020年に「POWER DEPO IV」を開発した。
0.6 MB

0.6 MB
近年、携帯電話基地局の小型・低消費電力化への要求の高まりに伴い、効率特性に優れたGaN HEMT増幅器の採用が進んでいる。今後サービスが本格化する5Gの市場においては、データ通信における容量・速度のさらなる向上が求められることから、増幅器の広帯域化に有利なGaN HEMTの存在感がこれまで以上に増していくことが予想される。本報告では、携帯電話基地局向けGaN HEMT増幅器の開発を目的として当社が取り組んでいる、GaN HEMTの電流源に関する評価・解析手法について述べる。従来のI-V測定に代わり、実際のRF動作に近い評価が可能である低周波ロードプル測定を新たに採用し、GaN HEMTの設計指針を探った。また、大信号モデルを用いて、増幅器の高効率化の手法として知られるF級および逆F級動作におけるゲート電圧クリッピングの影響を解析し、効率の制約要因について明らかにした。
1.1 MB

1.1 MB
SiCパワーデバイスはSiに代わる次世代デバイスとして市場拡大が進んでおり、大電流かつ高信頼性が要求される車載用などの用途においては、SiCエピタキシャル層の高品質化が特に重要である。SiC基板に含まれるBPD(Basal Plane Dislocation: 基底面転位)はバイポーラデバイスにおける順方向通電動作時に積層欠陥拡張を引き起こし、デバイス信頼性の致命的な劣化原因となるが、近年、再結合促進層と呼ばれる高窒素濃度のエピタキシャル層の導入による積層欠陥抑制技術が提案されている。本稿では、PL(Photoluminescence: フォトルミネッセンス)イメージング測定法による受光フィルターの検討を通して、再結合促進層中のBPD評価手法を新たに確立するとともに、BPDの極めて少ない再結合促進層を備えた6インチSiCエピタキシャル基板を新規開発した成果について報告する。加えてドリフト層のBPD品質、表面欠陥品質との両立も確認しており、開発したエピタキシャル基板は大面積素子における安定したデバイス特性を実現するものである。
1.3 MB

1.3 MB
1986年末に高温超電導体が発見されて以来、当社ではパワー応用を目指した高温超電導線材の高性能・長尺化に取り組み、特に、ビスマス系2223線材(Bi2223線材)開発では、開発初期より長尺化、高性能化で世界をリードしてきた。また、線材開発と並行して各種応用製品の開発にも取り組み、マグネット、電力ケーブルなどで実用レベルの応用機器が開発されるに至っている。電流リード応用においてはMRI用を始め、商業化された応用機器に組み込まれる例も増えてきた。本稿では、最近のBi2223線材の開発・製品化状況及び線材の周辺技術として今後の用途拡大に重要な接続技術、大電流導体化技術、並びにBi2223線材を用いた各種応用機器の開発・製品化状況を紹介する。
2.5 MB
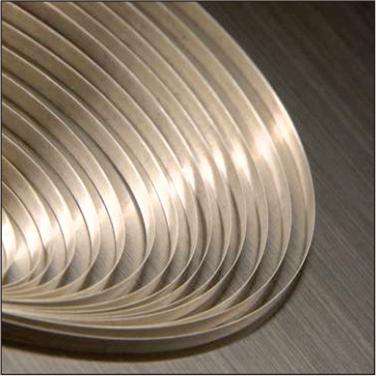
2.5 MB
材料の研究開発においては化学種の3次元的な分布の把握が多くの場合で重要であり、その情報を豊富に含む分析4次元ビッグデータの有効活用が今後重要な鍵となる。我々は「2段階多変量スペクトル分解法」という新しいデータ解析手法を開発し、4次元構造のデータを直感的に理解できる形で表現することに成功した。本手法は、2回の多変量スペクトル分解およびその間の「2値化」処理を行うことが特徴である。薄膜サンプルの飛行時間型二次イオン質量分析法によって得られたデータに本解析手法を適用し、複雑な3次元的微細構造を理解することができた。従来のデータ表現法と比べ、2段階多変量スペクトル分解法を用いることで4次元の分析データが明瞭に、かつ理解しやすくなることがわかった。
1.6 MB
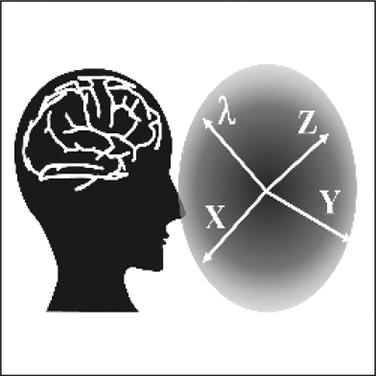
1.6 MB
粉末冶金製品に求められる高い寸法精度への要求に応えるべく、製造プロセスの設計支援として粉体シミュレーション技術の開発に取り組んできた。粉体シミュレーションは、粉体を構成している個々の粒子の運動を計算することにより、粉体の挙動をマクロに解釈するためのものである。本報告では原料粉末の粉砕工程、金属粉末の給粉工程に対して適用した事例を紹介する。粉砕効率はボールミルに投入されるボール同士の衝突エネルギーから予測できるが、衝突エネルギーを精度良く予測するには個々のボールについて複雑な衝突過程を伴う運動を正確に再現する必要があるため、スーパーコンピュータを利用することで膨大な数が投入されるボールの運動を解析できるようにした。今回、粉砕性の改善を目指して、粉砕条件を変更したときの衝突エネルギーの変化を予測する解析技術を開発した。また、給粉工程の課題である金型内の充填ばらつきが発生するメカニズムの解明を目指して、給粉過程の粉末挙動を可視化する解析技術も開発した。
1.9 MB
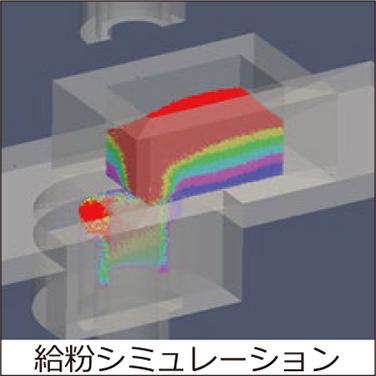
1.9 MB
近年、安全性・利便性向上を目的として、バイワイヤ技術の需要が拡大している。普及が進んでいるブレーキ、シフト等のバイワイヤ化は将来の自動運転車にも不可欠な技術であり、今後も市場が拡大していくとみられている。しかし、バイワイヤ技術は制御対象を電気信号で制御することから、鉛バッテリなどの車両電源が異常となった場合に、制御ができなくなる課題がある。住友電工グループの住友電装(株)、(株)オートネットワーク技術研究所は、車両電源異常時にもバイワイヤ制御を継続するためのX-バイワイヤ用バックアップ電源を開発した。本製品は、2020年に発売されたトヨタ自動車(株)のLEXUS UX300eに採用頂いた。
0.6 MB

0.6 MB
当社グループは、住友の銅事業に端を発する銅線の製造技術および、その応用製品としての電線・ケーブルを礎として、新技術・新製品の開発を継続的に行ってきた。電線・ケーブル技術は、主に「導体技術」と電線の被覆材料に必要な「絶縁技術」から構成されており、これらの技術発展と共に、当社製品の多様化の歴史を紐解くことができる。図1は、両技術をもとに生み出されてきた製品群の中から、本号で取り上げた技術およびその周辺技術の展開の歴史をまとめたものである。「導体技術」に関しては、1897年に当社の前身となる住友伸銅場が開設され、銅電線の製造を開始した。その後、この技術を元に、銅線にワニスの絶縁層を形成した巻線、銅電線と他の金属を層状に積層するクラッド法やめっき法などで複合化した電子部品及び自動車エンジン用導電材料、アルミ電線などが生まれてきた。また、めっき技術からは、金属多孔体が開発された。
0.8 MB

0.8 MB
空気バネは鉄道車両の乗り心地を向上させ、安全な高速走行を実現するには必須の部品である。都市人口の増加や環境問題への関心の高まりを背景に、自動車や航空機と比較して輸送効率が高くCO2排出量やエネルギー消費量を抑制できる鉄道に注目が集まっており、世界各国で鉄道網の整備が進められている。世界中に鉄道網が普及する中、路線や環境に応じて多種多様な空気バネ特性が要求されている。そのため、当社ではより迅速な設計を行うことで、より多様なニーズに応えた提案をするべく、革新的な設計手法としてシミュレーションによる設計技術を開発している。今回、空気バネの静的特性と動的特性をシミュレーションで精度良く予測する技術を開発した。
1.3 MB

1.3 MB
富山住友電工㈱の製品であるセルメットは、三次元網目構造を有した金属多孔体であり、高いガス拡散性と高い導電性を有している。固体酸化物形燃料電池(SOFC)の集電体には、ガスの均一拡散性や集電性が要求されるため、セルメットの適用により性能向上が期待できる。これまで量産品ニッケル(Ni)セルメットを空気極用集電体として適用検討してきたが、700~800℃もの高温域では、酸化による不導体化が起こるため、高い出力性能は得られていなかった。今回、新開発したニッケルコバルト(NiCo)セルメットは高温酸化雰囲気中で導電性酸化物を形成することから、空気極集電体に適用しても高い導電性を示す。本報告では、SOFC作動に要求される各種物性を評価し、更に空気極用集電体にNiCoセルメットを適用したSOFCの性能評価を行うことで、NiCoセルメットが高温域作動SOFCの空気極用集電体として有望であることを明らかにしたので、その内容を記載する。
1.8 MB
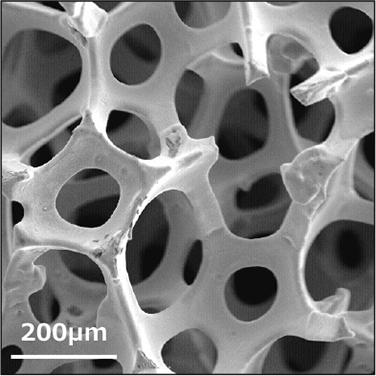
1.8 MB
PTFE(polytetrafluoroethylene)に代表されるフッ素樹脂は、固体中最小レベルの摩擦性、樹脂中最高レベルの耐熱性・耐薬品性・耐候性・電気特性を持つ優れたポリマーであるが、耐摩耗性が悪いこと、複合材料として用いる場合には基材と接着が難しいことが弱点である。特殊条件下で電子線照射を行うことでフッ素樹脂の架橋反応を促進させ、耐摩耗性を1,000倍近く向上、基材との接着も可能とした製品を開発した。今回、固体NMR(Nuclear Magnetic Resonance)にてその架橋状態を調査すると同時に、SPring-8の硬X線を活用して、基材との接着状態を解明したので、その内容を報告する。
1.9 MB

1.9 MB
従来品に対し、ろ過膜面積あたりの設置面積が小さく、かつ省エネ化した水処理用ポアフロン膜モジュール・ユニットを開発・上市した。成功のポイントは、ポアフロン中空糸膜が有する耐汚染性・耐閉塞性および高強度・耐屈曲性等の特長に加え、膜モジュール構造をカセット型とし、膜モジュールの膜有効長・充填率アップ、汚れ付着を防止する散気気泡の大径化を実現する新たな散気装置の開発である。日本下水道事業団他との都市下水処理での共同実証試験で、膜分離の普及ポイントと言われる電力使用量原単位目標の処理水1m3あたり0.4kWh以下を達成する試算結果を得、さらにその後、複数の現場での実証を経て商品化した。本稿では、開発実証の経緯、製品仕様、適用事例等について紹介する。
4 MB

4 MB
コンシューマエレクトロニクス市場において、4K・8K等の高精細ディスプレイや没入体験型ヘッドマウントディスプレイが登場してきている。この分野ではコネクタプラグの小型化及び広帯域・長距離伝送に対応したケーブルが必要とされるため、長距離伝送に優れた光ケーブルのニーズが高まっている。しかしながら、光ケーブルはメタルケーブルよりコネクタプラグのサイズが大きくなるという課題がある。今回当社は、汎用小型高速インタフェースであるUSB Type-Cコネクタに対応し、コネクタプラグがメタルケーブルと同等のアクティブ光ケーブルを開発した。本稿では、今回開発したケーブルの設計概要、伝送特性評価結果、信頼性評価結果について報告する。
1.3 MB

1.3 MB
自動車産業をはじめとする切削加工の現場では、工具寿命向上によるコスト低減、高能率加工による生産性向上、突発的なトラブル抑制による設備の自動化などが求められている。さらに、近年では加工設備集約などの取り組みが進み、1台の加工設備で様々な被削材を加工する現場が増えている。このようなニーズに応えるため、当社では鋼、鋳鉄問わず幅広い被削材のミリング加工で安定長寿命を実現する汎用材種「ACU2500」を開発した。さらに、鋼ミリング加工で高能率加工、安定長寿命を実現する専用材種「ACP2000/ACP3000」を、鋳鉄ミリング加工で高能率加工、安定長寿命を実現する専用材種「ACK2000/ACK3000」を開発した。これら5材種は幅広い被削材に対応するだけではなく、従来材種比1.5倍以上の安定長寿命または2倍以上の高能率加工を実現し、加工コストの大幅低減および生産性向上を可能にした。
4.9 MB

4.9 MB
自動車・産業機械に代表される製造業の鋼切削加工の分野では、地球環境への負荷低減および加工コストの低減を目的として、加工条件の高能率化が年々進んでいる。また、切削工具に用いられるサーメット材料は、鋼との親和性が低いことから高い加工面品質が得られる特長があり、特に仕上げ加工に多用されている。一方、高能率化による加工条件の過酷化に対応するため、サーメット工具に対する長寿命化と良好な加工面品質の両立が強く要求されている。そこで当社では、このような市場ニーズを背景として、長寿命かつ優れた加工面品質を実現する新たなサーメット工具材種「T2500Z」を開発し、製品化した。T2500Zは鋼旋削加工において、当社従来品比で2倍の寿命を達成しており、ユーザーの高能率化ニーズに応えることが可能となった。
2.5 MB
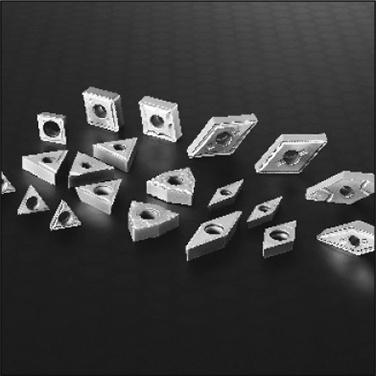
2.5 MB
熱電材料を用いた発電技術は、排熱から直接電力に変換することが可能であり、持続可能なエネルギー源となり得るため、低炭素社会に向けたエネルギー材料技術として期待されている。しかし、熱電変換効率に直結する熱電性能指数ZTの目標値が自動車排熱発電で4以上であり、現状、到達することは極めて困難であると見られている。我々はこの大きな課題を、ナノ構造の精密制御、および材料の電子構造の変調により打破すべく、研究開発を行っている。これまで我々は、Si-Ge熱電材料にナノ構造制御を適用し、従来比1/7倍となる低熱伝導率を実現し、材料性能を向上させてきた。今回、更に性能を向上させるべく、電子構造を有効に機能させる独自技術として、共添加法、即ち①Au添加による電子構造の制御に加え、②B添加によるフェルミ準位の制御を共に行う手法を提唱し、同型従来材料対比で世界最高となる材料性能指数ZT=1.38(従来0.9)を実証したので報告する。
1 MB
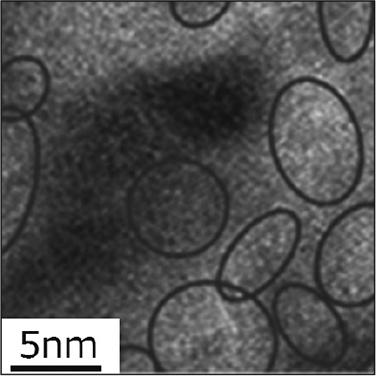
1 MB
量子カスケードレーザ(QCL)は、小型、高速、狭線幅等の優れた特長を持つことから中赤外ガスセンシング光源として期待されている。ガスセンシングへの実用化には、高感度センシングや複数ガス成分を一括で検知するために単一モード性やモードホップフリーな広帯域の波長可変幅がQCLに求められる。QCLの波長可変幅拡大には、動作温度を向上させることが有効である。そこで今回我々は独自の歪補償コアを設計し、さらに埋込ヘテロ(BH)構造を導入することで、高温で動作する分布帰還型(DFB)-QCLを開発した。その結果、パルス駆動において-40℃から200℃の範囲でモードホップのない単一モード発振が得られ、単一導波路のみで波長可変幅123 nmを実現することに成功した。今後、本QCLを光源に用いたガスセンシング手法の開発に取り組む。
1.6 MB
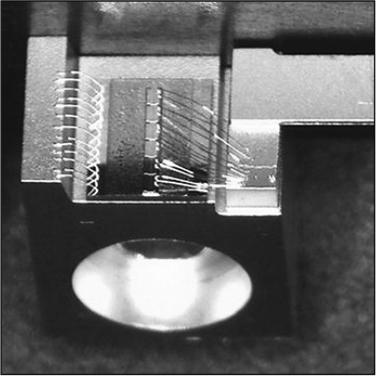
1.6 MB
近年クラウド・コンピューティングの普及に伴い、基盤となるデータセンターネットワークで通信されるデータ量が増大してきており、より超多芯で高密度なケーブルの需要が高まっている。当社は世界で初めて3456心以上のケーブルの製品化に成功し、多数の顧客へ納入している。一方、海外テレコム市場においても管路の制約等から光ファイバケーブルの多心高密度化が進んでおり、2000心相当の光ファイバケーブルのニーズが出てきている。海外テレコム用途では既存線路との接続性を重視する顧客も居り、現行超多心ケーブルで用いているMFD(Mode Field Diameterの略、光学的なコア径の意味)の中心値が8.6umの曲げ強化型シングルモードファイバ(ITU-T G.657.A1, G.652.D準拠)よりも汎用ファイバとして用いられているMFD9.2um中心のITU-T G.652.Dファイバの要望がある。さらにアジア等の屋外配線ではネズミ等の齧歯類対策のため、鋼テープ外装付光ファイバケーブルのニーズが高い。そこで今回は、MFD9.2umの汎用ファイバを用い、高密度性を実現するため、間欠8心リボン構造を採用した鼠
0.9 MB

0.9 MB
地球温暖化の進展に伴い、太陽光・風力を初めとする再生可能エネルギーの導入が推進され、電力系統安定化対策として大容量蓄電池の導入が重要になっている。レドックスフロー(RF)電池は、こうした蓄電池の1種であり、活物質※1を含む水溶液中のイオンの酸化還元(レドックス)反応※2によって充電および放電を行う蓄電池である。大容量化に適し、長寿命で安全性が高いことなどの優れた特長を有している。当社では、1985年からRF電池の開発に着手し、これまでに約30件の納入実績がある。世界的な動きとして、特に2010年頃から米国、欧州、中国等で開発が活発に進められるようになり、最近では、有機化合物を使う新規な電解液などの報告も多く見られる。本稿では、RF電池の開発経緯、大容量システムの実証状況、最近の開発動向を紹介する。
3.5 MB
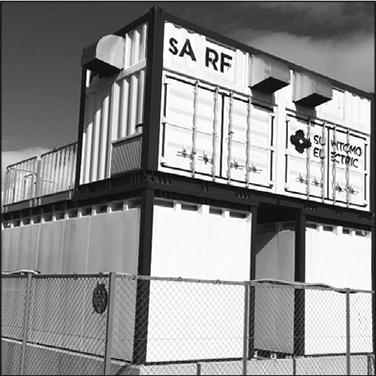
3.5 MB
本稿では、従来の外径250µmの光ファイバよりも細径な200µm光ファイバを用いた間欠12心光ファイバテープ心線(以下、200µm間欠12心テープ心線)を実装した432心以下の空気圧送用光ファイバケーブルの設計、製品ラインナップおよび施工上のメリットについて報告する。200µm間欠12心テープは柔軟性と一括融着接続性を両立するため、長手方向、幅方向に間欠的にスリットが入った構造を採用しており、スリット部と非スリット部の比率およびピッチを最適化することにより、両特性を満たすテープ心線を開発した。同テープ心線は200µm間欠テープ同士だけではなく、従来の250µmテープ心線との一括接続も可能である。尚、ケーブル構造は欧州等で主流のマイクロダクト用途に用いるため、細径、軽量かつ低摩擦な構造を採用した。今回は開発したケーブルの空気圧送特性を評価するため、ケーブル圧送試験を行ったので、その結果も報告する。
1.2 MB
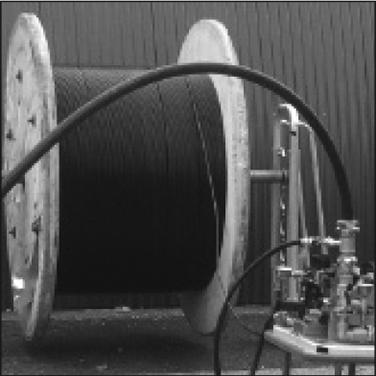
1.2 MB
GaN HEMTは高出力・高効率かつ広帯域という特長があり、近年は携帯電話基地局向けにシェアを伸ばしている。LDMOSと比べ、GaN HEMTは広帯域化により適しているため、市場要求であるマルチバンド対応高出力基地局への貢献が期待される。本報告では、当社のGaN HEMT技術を用いて開発した内部整合回路付きGaN HEMT、およびそれを用いた高出力・広帯域・非対称ドハティアンプの開発結果を報告する。180Wチップを2個搭載したトランジスタの内部回路は、広帯域特性を満たしつつ小型パッケージ内に実装できるよう、高誘電体基板を用いて構成した。このトランジスタを3個用い、LTEのB1、B3バンドで動作するように回路を工夫した非対称ドハティアンプを設計、試作し、1.8-2.2GHzの広帯域において、最大出力電力59.2dBm、8dBバックオフ時の効率50%以上を実現した。
2.3 MB

2.3 MB
電柱に架設される架空配電線として、銅導体に架橋ポリエチレンを被覆した絶縁電線が広く用いられているが、銅に比べ軽量で地金相場が低位安定しているアルミに導体を置換える動きがある。単純な置換えでは、銅とアルミの導電率の差があることから、同一の電流容量を確保するためには太径化が必要となるが、太径化に伴い電線に架かる風圧荷重が増大し、電柱など支持物の建替えも必要となる場合がある。当社では、電線の表面被覆に溝を設けることにより、銅導体品に比べて太径化しても風圧荷重が同等以下のアルミ導体低風圧絶縁電線を開発した。この低風圧電線は、都市部の風を想定した28m/sおよび沿岸部の台風を想定した40m/sの2つの風速に対し低風圧効果を有することに最大の特徴がある。当該品は、電気的特性や、コネクタなどの付属品との適合性・架線作業性も確認し、既に実線路で適用されている。
1 MB

1 MB
近年、航空機、石油ガス、医療、自動車産業等において、その機器や部品には耐熱性や耐食性に優れるNi(ニッケル)基、Co(コバルト)基、Ti(チタン)合金等の材料が多く使用され、その使用量は今後大幅に増加することが見込まれている。一方、これらの材料を切削加工する場合、被削材自体の高温強度が高いことや工具の刃先に溶着しやすいことなどから、工具の寿命が著しく低下する問題がある。そこで当社ではこのような難削材の旋削加工において、安定長寿命かつ高能率加工を実現する新しい工具材種「AC5015S」および「AC5025S」を開発した。このAC5000Sシリーズは難削材旋削加工において当社従来材種と比較して2倍以上の長寿命または高能率加工を実現し、加工コストを大幅に低減させることが可能となった。
1.3 MB
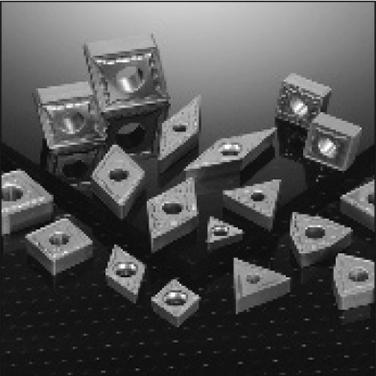
1.3 MB
高融点金属であるモリブデン(Mo)あるいはタングステン材料の使用環境が近年過酷になっており、さまざまな形状や寸法の材料における機械的特性の向上ならびに製品における寿命および信頼性の向上の要求がますます強くなっている。そこで我々は、Moに硬質粒子を添加することによって、熱間押出ダイスを含む塑性加工工具用に新しいMo合金である“MSB”を開発した。このMSBは従来のMo合金に比べ1000℃以下において優れた機械的特性を示した。さらに、MSBにチタン合金を添加することによって、より高温域で優れた機械的特性を示す合金“T-MSB”を開発した。 本研究で開発した“MSBシリーズ”を黄銅の熱間押出ダイスとして使用した結果、従来Mo合金ダイスの2.5倍以上の寿命を示した。
2.7 MB
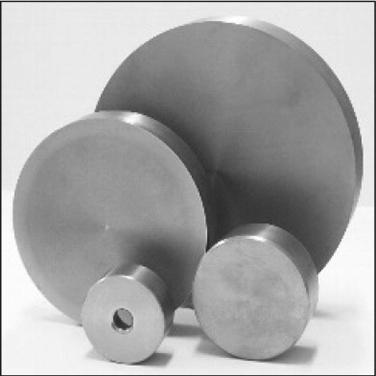
2.7 MB
化合物半導体デバイスの開発・製造では、その出来栄えや特性評価に原子レベルでの構造解析が求められる。この評価手法には走査透過電子顕微鏡(STEM)の活用が欠かせない。ところが、STEMの試料作製では集束イオンビーム(FIB)加工装置により試料厚を100 nm前後に薄くする必要があり、熟練の技術者が作業しても迅速に必要な試料数を作製できないという課題があった。これに対し我々はFIBの自動化機能を用いたスキルレス化、無人運転化による処理能力の向上を目指した。当社では多品種のデバイスを開発・製造しており、各デバイスの解析目的に応じた試料作製が必要だが、それぞれの試料作製工程で自動化条件を選定し、確立した自動化機能を組み合わせることで、迅速に多くの試料作製が可能な体制を構築した。これによりSTEMのスループットを向上し、迅速に試作と評価のサイクルを回すことで、開発加速、品質向上を進めている内容を報告する。
1.2 MB
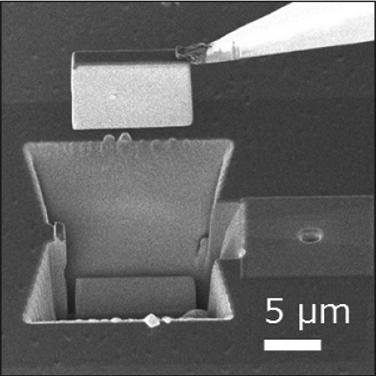
1.2 MB
2019年 7 月・SEI テクニカルレビュー・第 195 号 631. 概 要近年、燃費・排ガス規制、ZEV規制等の強化により電動化車両(EV、PHV、HEV)の普及が加速している。これら電動化車両は、モータ駆動用の電池パックを搭載しており、多数の電池モジュールを接続して高電圧、高容量を達成している。電池モジュールは、積層された複数の電池セルの電極間を電池配線モジュールのバスバーによって直列、並列に電気接続され、また各電池セルの電圧を監視するため、電池配線モジュールの電線を介して制御ユニットに接続される(図1)。住友電工グループの住友電装(株)、(株)オートネットワーク技術研究所は、電池モジュールの小型化を目的として、電池セル間接続をレーザ溶接に対応した電池配線モジュール(写真1)を開発した。本製品は、2019年に発売された日産自動車(株)のリーフe+に採用いただいた。
0.7 MB

0.7 MB
近年、自動車産業などでは地球環境保護のため、自動車の燃費性能改善が求められており、部品の軽量化やHV、EV、FCV車の拡大に伴いアルミニウム合金などの非鉄金属材料の使用割合が増加している。これらの部品加工においては生産性を向上させるため、加工時間の短縮を目的とした高能率加工や、非切削時間短縮のため、取り扱いが容易な工具、切りくず処理性に優れる工具が求められている。さらに、単位面積あたりの生産性向上を目的とした、小型加工設備に対応できる軽量工具も、近年では求められている。これらに対応するため、当社はアルミニウム合金加工用高能率PCD(多結晶焼結ダイヤモンド)カッタALNEX「ANX型」を開発した。ここではALNEX「ANX型」の特長について紹介する。
0.9 MB

0.9 MB
フライス工具は外周、端面もしくは側面に工具切れ刃を備えた切削工具であり、これが回転運動することで、様々な部品の加工が行われる。現在ではその切れ刃となるインサートを交換する工具が一般的に広く使用されており、平面削り加工、隅削り加工、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工等の様々な加工に用いられている。一方、機械加工の分野で部品に要求される寸法精度や加工品位は年々厳しさを増しており、工具に対しても高い加工面粗さや壁面精度の性能が求められている。また、軽量化を目的とした剛性の低い薄肉部品や固定が困難な複雑形状の部品が増加しており、鋭い切れ味を持つ工具の需要が高まっている。今回開発した「SEC-ウェーブミル WEZ型」(以下WEZ型、写真1)は広範な加工用途に使用可能で加工品位と切れ味に優れ、高い加工精度と切れ味を持ち、加工面粗さや壁面精度の向上、および生産性の向上に貢献する。
1.3 MB

1.3 MB
近年、クルマ及びクルマを取り巻く環境が急激に変化し出している。これまでの「走る」「曲がる」「止まる」に「つながる」が加わることで、クルマの価値の変化、すなわち単なる移動手段から移動+社会端末へと発展し、付加価値がユーザー個人から社会全体の価値へ広がってくる可能性が出てきている。2030年代のクルマ社会に向け、新たな産業を生み出す社会端末となることで、経営資源としての価値が見いだされる可能性もある。そこで従来のクルマとしての機能価値に加え、新たな社会ニーズに対応するための基盤技術の構築が必要となってくる。本稿では当社が有する社会インフラ技術と車載技術を融合させ、コネクティッドカー社会に向けた新たな基盤技術として開発を推進している次世代の車載電子プラットフォーム(以下、電子PF)について概説する。
2.9 MB

2.9 MB
近年、自動運転に代表されるように自動車の制御プログラムは複雑化が進み、同時に環境規制の強化を背景にした電動化の進展によりパワートレインも多様化している。こういった中でも開発期間は短縮され、サプライヤに対しては車両目線での提案が求められている。当社では機械系と電源系を連携した車両シミュレーション技術や、乗り心地と電費のトレードオフを検証する技術を開発してきた。さらに、車両目線でのシステム設計・提案力を強化するため、車両全体を模擬したシミュレーション技術開発を進めており、今回はEV自動充電システムを題材にして実車と連動した仮想環境(バーチャル車両)を構築したので紹介する。
1.6 MB

1.6 MB
近年、自動車には自動運転を含む高度運転支援システムの普及が進み、それに伴う通信量増大により、車載ネットワークに高速な車載Ethernetが導入されつつある。安全性確保の観点から、車載ネットワーク製品は熱やノイズ等厳しい条件下での通信信頼性が要求されるため、EMC性能が重要な指標の一つとなっている。しかし、これまでの試作によるEMC対策には、EMC性能を確保するために、多くの開発期間や、開発コストが費やされてきた。そこで、コネクタ、ワイヤーハーネス、ECU等から構成される車載Ethernet通信システムの物理層モデルを構築し、各条件下における通信システムのEMC性能を効率的に検証するシミュレーション技術を開発した。
3.2 MB
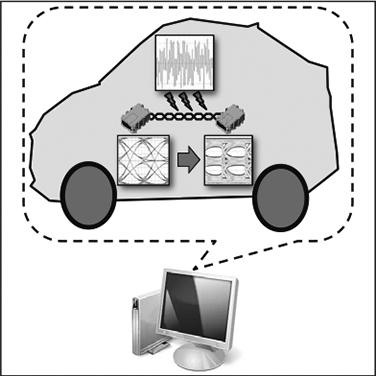
3.2 MB
この約四半世紀、CO2排出量増加による地球温暖化問題に対応するため、自動車業界ではHEV(ハイブリッド自動車)などの開発が活発に行われている。更に近年では内燃機関を使用しないEV(電気自動車)の開発が加速している。電気自動車は主に高圧バッテリ、インバータ、モータからなる電気駆動系で走行し、走行時にCO2を排出しないため環境問題の解決に大きく貢献できる。当社はこれまで電気駆動系に使用される高圧ハーネスや高圧コネクタを開発・製造しており、多数のHEVなどに採用されている。本稿では、EVにも適用可能なHEV用開発品として、高圧バッテリとインバータを接続するアルミ電線に適用したパイプハーネス、インバータとモータを接続するパワーケーブルとダイレクトコネクタを紹介する。
2.2 MB

2.2 MB
近年、環境への配慮、省エネ志向、原油高騰化などからハイブリッド自動車、電気自動車など自動車の電動化が急速に進んでいる。このような電動化した自動車をさらに普及させていくためには、電動化するためのシステムの小型・軽量化が必要である。一方、ガソリン車並みの走行性能、加速性能を実現するため、システムの高電圧化も必要である。そこで、バッテリ電圧を昇圧するためのコンバータ(昇圧コンバータ)の採用事例が増えている。当社では昇圧コンバータの基幹部品の1つであるリアクトルに新しい磁性材料および新しい放熱構造を適用し、従来と比較して同等性能で10%の小型・軽量化を達成した。
1.5 MB

1.5 MB
当社はこれまで電動化車両(HEV※1、PHV※2、EV※3等)向けの高圧関連製品を開発・量産してきたが、今後、中国を中心としたEV市場が急速に拡大していくと予測されており、EV向け製品開発を推進している。EVに搭載されるバッテリーパックは、航続距離確保のための大容量化、搭載セル数の増加が進んでいることから、パック内部品に対してより一層の省スペース化が求められている。またバッテリーパックの安全性についても、EV普及に伴いより高い安全性が必要となる。本稿では高圧バッテリーに搭載される電池配線モジュールに関して、EVバッテリー対応に向けた当社の取り組みを紹介する。
1.1 MB

1.1 MB
タブリードは、外装をアルミパウチフィルムとするパウチ型リチウムイオン電池(LIB)に使用される電池セル内部から電気を取り出すためのリード線である。パウチ型LIBは軽量で放熱性が高い特長があり、当社は世界に先駆けてパソコンや携帯電話等の小型電子機器用のパウチ型LIBに使用可能なタブリードを1990年代後半に上市し、高い信頼性を特長に多数の電池メーカーで採用実績がある。近年、電気自動車、ハイブリッド車の性能向上のため、大型化しても軽量にできるパウチ型LIBを搭載するニーズが高まっており、車載用に許容電流を高め、長期信頼性を向上させたタブリードを開発した。
1.5 MB

1.5 MB
自動車の電動化が進む中、電力制御に使われるパワーデバイスの電力変換効率はますます重要性が増している。現在の主流はシリコン(Si)を用いたパワーデバイスであるが、より高効率なシリコンカーバイド(SiC)の実用化が進んでいる。我々は、その中でも高効率化に有利なゲートを溝(トレンチ)型とした金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)を開発してきた。トレンチ構造は低オン抵抗化が可能な独自のV溝型構造を採用し、電界が集中しやすいトレンチ底部には電界緩和領域を導入することで高耐圧を実現してきた。今回、車載用途に必要とされる大電流を満たすため定格電圧1200 V、定格電流200 AのV溝型SiCトレンチMOSFET(VMOSFET)を開発したので報告する。VMOSFETは特性オン抵抗3.4 mΩ cm2、耐圧1660 Vと低オン抵抗と高耐圧を両立した。加えて、電界緩和領域により寄生容量を低減することで高速スイッチングも実現した。
1.6 MB
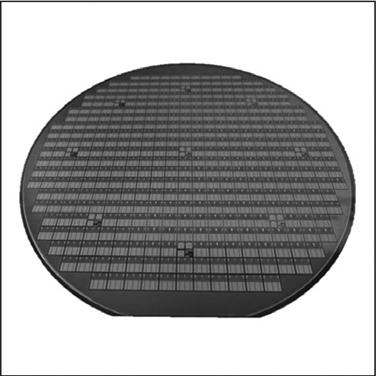
1.6 MB
我が国では、1950年代のモータリゼーションの急速な進展に伴って深刻化した交通事故増大や渋滞問題に対して、官民一体となって対策に取り組み成果を挙げてきた。この中で当社は、東京都に導入された広域交通制御システムの開発を始め、その後の国内における信号制御の発展に主導的役割を果たしてきた。また、培った技術をベースに新興国の交通課題に対処するため、JICAプロジェクトによりカンボジア・プノンペンの交通管制システムの導入等を進めている。さらなる安全性向上に向けては、路車協調型の安全運転支援システムに関する取り組みを行っているところであり、センサや無線通信装置の開発・製品化を行ってきた。今後、コネクティッド・自動運転時代の新たなニーズに対応すべく、AI・シミュレーション技術を活用した次世代交通システムの研究開発にも取り組んでいる。本稿では、住友電工の交通システムに対する過去実績及び将来に向けた取り組みを報告する。
0.9 MB
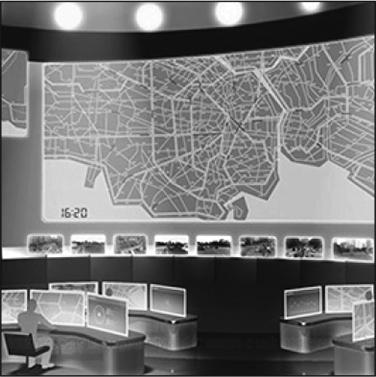
0.9 MB
2015年に報告されたジープチェロキーに対するサイバー攻撃では、遠隔からなりすましメッセージを車載ネットワークに注入することで車両が不正制御された。コネクティッド・自動運転時代に向けて、車載ネットワークでのセキュリティ対策は重要な課題である。車両においてサイバー攻撃に対する具体的な対策を講じるためには、時々刻々と変化する攻撃をいち早く検知する必要がある。本稿では、車載ネットワークに混入されたなりすましメッセージを、セントラルゲートウェイにおいて検知するための侵入検知システムについて提案するとともに、車載ネットワークのトラフィックデータを用いて評価した検知性能について報告する。
2.7 MB

2.7 MB
マグネシウム合金開発部では、世界で初めて高強度で耐食性の優れたAZ91合金の板材開発に成功、電子機器の筐体で製品化を推進しているが、より軽量化ニーズが高く、大きな市場が期待できる輸送機器へも展開すべく検討を開始した。しかしながら、輸送機器分野では、AZ91合金では対応できない新たな要求特性も明らかになり、それに対応すべく新合金の開発に取り組んでいる。本報告では、輸送機器分野で、マグネシウム合金を適用することにより大きな軽量効果が期待されるパワートレイン用ダイカスト部品をターゲットに、既存の耐熱マグネシウム合金の課題であった鋳造性やリサイクル性を克服する合金開発を富山大学と共同で取り組み、これらの課題をほぼ克服した新合金を開発したので紹介する。
1.9 MB

1.9 MB
近年、自動車メーカー各社は、環境に配慮する低燃費車を開発し市場に投入している。燃費対策として少気筒化やロックアップ※1範囲の拡大が図られることがあるが、特に3気筒CVT※2搭載車においては、ロックアップ開始時にサスペンション共振の影響で、車体振動が悪化する。この振動の改善が図れる防振製品を提案するには、従来のエンジン懸架系に加え、駆動系、サスペンション系を含む解析評価技術が必要となるため、筆者らは車両全体を評価対象としたフルビークル解析技術を構築した。また、この解析技術を用いて、ストラットマウント※3の液封化によるロックアップ時振動の低減を検討し、実車評価においても、その効果を確認した。この取り組みを通して構築したフルビークル解析技術は、今後の弊社における製品開発の基盤技術の一つになると考えている。
3.9 MB
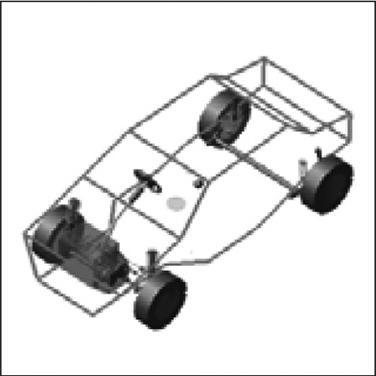
3.9 MB
現在、自動車分野は大きな変革期を迎えている。この構造変革は「CASE」(Connected、Autonomous、Shared、Electric)と呼ばれ、EV化や自動運転をはじめとした車両のエレクトロニクス化、デジタル化が急速に進みつつある。これに対し当社では、磁場配向による吸音ポリウレタンフォームの高熱伝導率化技術(MIF)を開発し、こうした車載エレクトロニクス製品の熱対策と騒音対策を両立できる防音製品の量産化を成功させた。最近では、車載小型製品以外にも、EV駆動用モータ等の大型製品向けの放熱、静粛性ニーズが高まっている。今回、MIFの伝熱構造に着目し、放熱性を従来の2.5倍(通常ウレタンの最大100倍)まで向上させた。これを応用し、モーターケースを覆うことで防音効果に加え、空冷性能をより高める防音冷却デバイスとしての可能性を見出した。
1.9 MB

1.9 MB
自動車用タイヤの補強材として用いられるスチールコードにおいて、ゴムとの接着性能及び長期耐久性は極めて重要な性能である。特に昨今当たり前となった低燃費化のみならず、EV化や自動運転時代を迎えつつある自動車の進化において、その重要性は益々増している。当社はこの長期耐久性の指標として湿熱環境下の耐久性(=耐湿熱性)に着目し、通常のスチールコードが持つブラスめっきに第3元素としてコバルト(Co)を添加した3元合金めっきを開発し、世界に先駆け量産技術を確立した。また、この開発の中で、めっき製造技術確立の他、従来ブラックボックスとなっていためっきとゴムの接着、及び接着層の劣化メカニズム解明も実現し、接着性能改善の効果を定量的かつスピーディーに確認することが可能となった。この革新的なめっき技術により、タイヤの長期耐久性は従来品と比較して大幅に向上することが確認されており、カスタマーから大きな期待が寄せられている。
2 MB

2 MB
航空機や自動車産業分野における機器・部品などには、耐熱性や耐食性に優れるNi(ニッケル)基、Co(コバルト)基、Ti(チタン)合金などの難削材が多く用いられるため、それらを加工する工具の需要は年々増加している。難削材の切削加工には、工具の刃先に被削材が溶着しやすいといった特徴があり、突発的に工具の刃先が欠損する等の問題が発生する。また、一般鋼の切削加工と比較しても工具寿命が著しく短いため、安定かつ長寿命な切削工具のニーズが高まっている。今 回 開 発 し た AC5015S/AC5025S は 新 開 発 の PVDコーティングと専用超硬母材を適用したことで耐摩耗性と耐欠損性が向上しており、長寿命化による工具交換頻度の低減と工具使用量の低減が可能となり、加工コストの削減に貢献する。
0.8 MB

0.8 MB
目視検査では、定量的な評価基準だけでなく、「異常なきこと」のような検査員に依存した判断基準もある。このような人の主観的な判断に依存した目視検査をアルゴリズム化することは困難な課題である。Sense Learningは、このような人に依存した判断を大量の良品データから学習して不良検知を行うために当社が開発したAI(Deep Learning)技術である。 Sense Learningでは、良品のみの画像を使ってautoencoder型のネットワークを使用し、良品に含まれる特徴に特化した画像の圧縮・復元方法をAIに学習させる。この学習済みAIに不良画像を入力すると、良品に見られない=不良特徴に対する圧縮・復元方法をAIは学習していないため、不良部位の特徴の復元を失敗する。その結果、入力画像と復元画像との間に一致しない違和感が発生する。この違和感を不良として特定することで不良の判定を行う。
1.6 MB
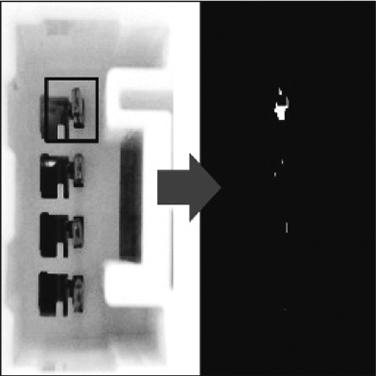
1.6 MB
自動運転システムが全ての運転タスクを実施するレベル3以上の自動運転を安全かつ円滑に実現するためには、車線レベルの準動的交通情報が必要である。車線レベルの準動的交通情報の生成には、車両が収集、送信するプローブ情報の利用が期待されているが、現状ではプローブ情報の車両位置精度が走行車線の特定には不足している、収集されるプローブ情報はまだ少ないといった課題がある。そこで、これらの課題を克服して車線レベルの準動的交通情報を生成するシステムを開発したので、報告する。走行車線の特定のためには近年急速に普及が進んでいる車載カメラで撮影した車両前方の画像を利用し、プローブ情報の少なさを補うためには渋滞の伝播モデルに基づいた推定を取り入れている。
1.1 MB
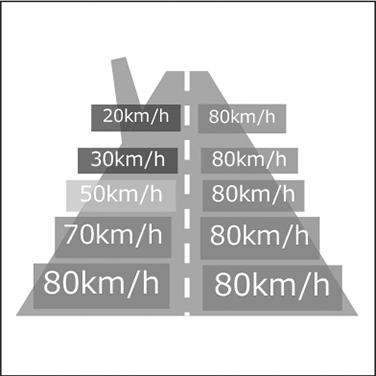
1.1 MB
近年、制御システムにて生産プロセスの効率化・自動化を図る目的で情報系システムと通信接続し、データのやりとりを行う運用が増えつつある。その一方でStuxnet※1による発電所への攻撃等が起こり、制御システムのセキュリティ対策が喫緊の課題となり、制御機器の開発においても最初からセキュリティを考慮した設計を求める動きが生まれている。本研究では設計手順の効率化・属人性の排除を目指し、国立研究開発法人産業技術総合研究所と連携して継続研究を行っている。本論文では、複数フェーズからなるセキュリティ設計におけるリスク評価のフェーズに焦点を当て、既存の脆弱性評価システムを応用し、制御機器・システムに最適なリスク評価の定量化手法についての検討結果について、データロガーをキー要素とする制御システムのケーススタディを交えつつ報告する。
1.3 MB
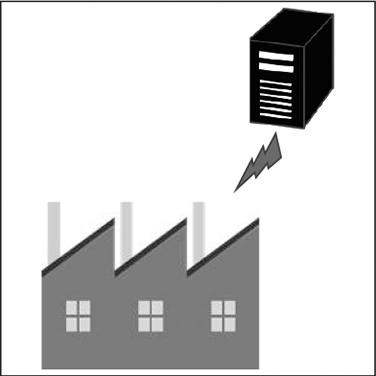
1.3 MB
高速・大容量通信が求められるクラウドサービスの普及に伴い、100Gbit/s用光トランシーバであるCFP4やQSFP28の普及が進んでいる。次世代通信規格として、IEEEにて400GBASE-FR8/LR8の標準規格が定められ、CFP MSAにて400Gbit/sに対応した光トランシーバとしてCFP8が新たに策定されており、市場ニーズが高まっている。当社がこれまで開発してきた4ch集積光受信モジュールの設計をベースとして、今回、8波長の分波機能を1つのパッケージ内に集積した、CFP8に搭載可能な400Gbit/s用8ch集積光受信モジュールを開発した。本稿では、モジュール構造、8波長の分波特性、4値パルス振幅変調(4-level Pulse Amplitude Modulation, PAM4)信号を用いた変調速度26.56Gbaudにおける最小受信感度等の特性を紹介する。
2.3 MB
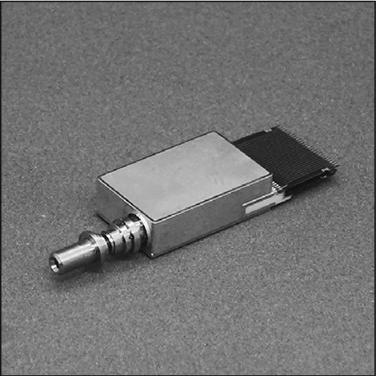
2.3 MB
データ通信は、スマートフォンに代表される無線通信量の増加、クラウドの普及によるデータセンター内での通信量の増加に伴い高速化・大容量化が進んでいる。その中で電気信号と光信号のコンバーターである光トランシーバにも高速化の要望が強い。高速の電気信号を歪みなく伝送させるために、通常、特性インピーダンスなどの評価指標をもとに伝送線路の設計を行っているが、実際の基板上では、いくつかの要因が電気信号を歪ませてしまう。その要因は、それぞれが相関の関係にあるSignal Integrity(SI)・Power Integrity(PI)・Electro-Magnetic Interference(EMI)/ Electro-Magnetic Susceptibility(EMS)によって成り立っている。電磁界解析は、これらの課題解決に重要な役割を果たす。本稿では、その要因について例を挙げて説明した後、電磁界解析を使用し問題点の抽出や解決方法の事例を紹介する。
1.5 MB
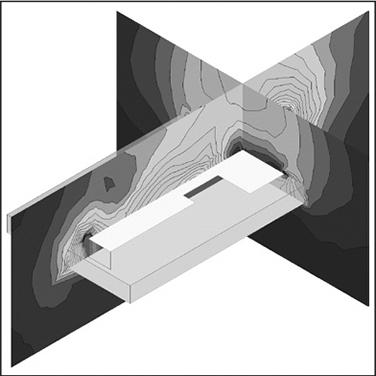
1.5 MB
人工衛星搭載用途や打ち上げロケット制御向けに、L帯※1とS帯※2それぞれにおいて40 Wの広帯域GaN HEMT※3マイクロ波集積回路※4(MIC)を開発している。40 W GaN HEMT MICは前段に10 W出力、後段に40 W出力のGaN HEMTを同一パッケージ内に実装することで実現され、L帯においては1.0 – 1.7 GHzの帯域で出力45 W以上、利得30 dB以上、電力付加効率45%の特性を有し、 S帯においては2.0 – 2.7 GHzの帯域で出力47 W以上、利得30 dB以上、電力付加効率50%の特性を有している。我々はこのGaN HEMT技術に対し衛星搭載用認定試験を行い、衛星用途として要求される全ての品質と信頼性を満足していることを確認済みである。GaN HEMTを用いた固体素子増幅器(SSPA)の実現により、今後衛星の小型化や軽量化に大きく貢献することが期待される。
1 MB

1 MB
再生可能エネルギーや電気自動車など電力供給と利用の多様化が進み、電力変換に用いられるパワー半導体の役割がより重要となってきている。現在広く普及しているパワー半導体の材料はシリコン(Si)であるが、高効率化が実現できるシリコンカーバイド(SiC)の実用化が進んできている。最近では100 Aを超える電流容量の大きいモジュールも市販されてきており、電力損失低減へ用途拡大が期待されている。併せてSiC基板の口径も拡大し6インチの実用化が進展し、その材料面への高品質化も求められてきている。ウエハ上に作製される半導体素子の均一性や歩留りを左右するのがSiCエピタキシャル成長層である。当社は独自のシミュレーション技術を活用し成長技術開発を進めてきており、既にエピタキシャル基板の量産を開始している。本稿ではエピタキシャル成長層における濃度と膜厚の高い均一性を実現し、同時にデバイス性能に悪影響を与える結晶欠陥の大幅な低減を実現したことを報告する。
1.7 MB

1.7 MB
第4次産業革命と呼ばれるIT技術を活用した技術革新により製造現場では大きな変革を迎えている。特に多数のセンサやデバイスをネットワークに接続して大量のデータを収集・分析する“IoT”技術の活用により生産能力の向上や効率化が期待されている。近年、自動車業界における共通プラットフォーム化、モジュール化の流れの中で、自動車部品メーカは超大量生産による原価低減要求への対応、メガ・リコールを含めた品質リスク管理が求められている。 そこで、メガ・プラットフォーム時代に適合した焼結部品の生産方式、品質管理として、当社グループのものづくりコンセプト“SEIPS”を中核に“IoT”技術を駆使し、①検査自動化による自工程保証、②2Dコードを用いた製品1個単位での品質保証、③成形-焼結-サイジング-機械加工までを連結した“1個流し・同期生産”によるリードタイム大幅短縮、及び中間在庫ゼロ化、④It技術を駆使した生産管理・監視システムをコンセプトとする革新的焼結部品生産ラインを構築した。
2.3 MB

2.3 MB
タイトバインディング法とは、原子軌道のエネルギーとその間の相互作用の強さ等を入力データとして物性を求める電子状態計算法である。我々は、赤外センサ開発に向け、ハイブリッド準粒子自己無撞着GW(hybrid QSGW)法に基づいた電子状態計算をInAs/GaSb超格子に対して行い、信頼性の高いバンド構造を得ていた。しかしながら、その膨大な計算量がデバイススケールの超格子への応用を阻んでいた。本研究ではこのような対象へ適用できる電子状態計算法としてタイトバインディング法を選び、これに必要な入力データをhybrid QSGW法から求めた。そしてInAs/GaSb超格子のバンドギャップを求め、フォトルミネッセンス測定やhybrid QSGW法、経験的擬ポテンシャル法による計算と符合する結果を得たのでここに報告する。
1.1 MB
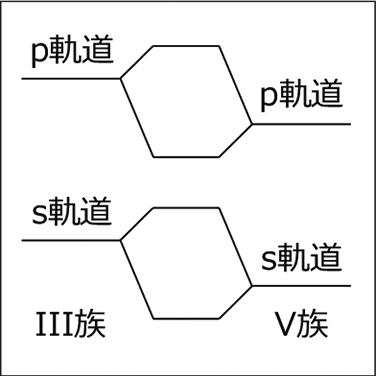
1.1 MB
住宅用蓄電システムは再生可能エネルギーや燃料電池と組み合わせてエネルギー自給率を高め、系統停電時には独立電源システムとして機能できるものとして注目されている。住宅用蓄電システムを普及するための最大の課題は導入コストの低減で、コストに占める蓄電池の割合は大きい。発電電力を全て充電できる大容量蓄電池は雨天・曇天では一部の容量しか使わず稼働率が低くなって経済的効果は低下する。上記課題を解決するには、蓄電容量を必要最低限にし、小型・軽量化によって流通と設置のコストの低減を図り、高稼働率を維持して費用対効果を高めるのが得策である。また、蓄電池に充電した電力を有効利用するとともに、蓄電池の実効容量を高めるためには、変換効率の高い電力変換器も欠かせない。当社では住宅用蓄電システム「POWER DEPOIII」を開発した。
0.8 MB

0.8 MB
住友電工システムソリューションが開発販売するスマートフォン向けのナビゲーションソフトウェア開発キットAgentNaviは、渋滞規制情報を加味し、目的地まで経路案内する機能を提供する。ナビゲーションソフトウェアが適切に案内を行うためには、現在走行中の道路を知る必要があり、通常はGPSセンサーを用いて取得した緯度経度より同定する。しかし、都心部など、GPSが受信しにくい環境下では、情報の誤差が大きい傾向がある。例えば図1で、破線で示した走行経路に対し、GPS情報が示す座標を菱形で示しているが、対向車線や建物上などを指しているため、GPS情報だけでは走行中の道路が判別できない。そのため、AgentNaviはスマートフォンのGPSを含めた各種センサー情報をもとに走行中の道路を推定し、位置情報を補正する位置検出(以下マップマッチング)機能を有している。本稿では、AgentNaviのマップマッチング機能について、自動車に備えつけられた一般的な車載器(以下、カーナビ)との違いを交えて説明する。
0.6 MB

0.6 MB
路側設置レーダー用に76GHz帯トランシーバーであるRFモジュールを開発した。本研究では、小型化・低コスト化に有利な、当社独自の技術である3-Dimensional Wafer Level Chip Size Package(3-D WLCSP)を用い、76GHz帯のチップセット(送信用周波数変換器、受信用周波数変換器、高出力増幅器)を開発した。開発したチップセットをPCB※1に搭載することで、20×34.5mm2の小型RFモジュールを作製し、電波法(送信電力、不要波電力等)に適合し、レーダーシステムから要求されるRF特性(雑音指数、ポート間アイソレーション等)を実現した。
4 MB
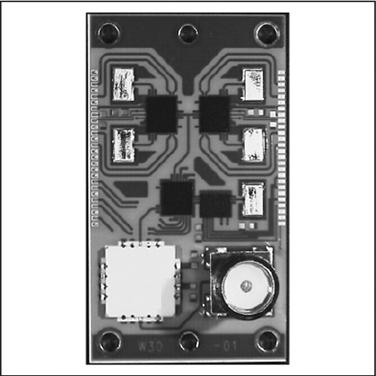
4 MB
現在、広く使われているHgCdTeを材料とした量子型赤外センサに比べ、理論的な性能向上が期待できかつ環境負荷の小さいType-Ⅱ超格子を用いた赤外センサが注目されている。センサ開発に関する報告が多数なされているが、ハイパースペクトルイメージングに必要とされる14 µmより長波長域に関する報告は少ない。今回、我々は受光層材料にInAs/GaInSb超格子を適用し、波長15µmまで感度を有する32万画素(VGAフォーマット※1)の赤外イメージセンサを開発した。バイアス電圧-20 mV、温度77 Kにおける暗電流密度は3.7×10-3 A/cm2を得た。温度分解能(NEdT)は0.29 K(F/1.4レンズ、積分時間200 µs、バイアス0 mV、温度95 K)であり、イメージセンサとして人物画像取得に成功した。
1.8 MB
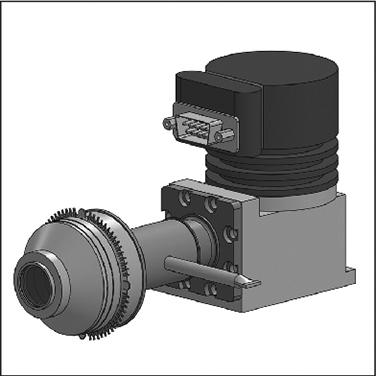
1.8 MB
本稿では、間欠12心光ファイバテープ心線(以下、間欠12心テープ心線)を実装したデータセンタ向超多心スロット型光ファイバケーブルの設計および施工上のメリットについて報告する。間欠12心テープは柔軟性と一括接続性を両立するため、ファイバ2心毎に長手方向間欠的にスリットが入った構造を採用しており、スリット部と非スリット部の比率およびピッチを最適化することにより、両特性を満たすテープ心線を開発した。ケーブル構造は曲げ方向性がなく、布設作業性に優れるスロット型構造を採用し、今回新たに中心のテンションメンバに無誘導性の繊維強化プラスチック(以下、FRP)を適用し、雷害対策不要のノンメタリック型のケーブル構造を実現した。間欠テープ技術とスロット構造を組み合わせることで、従来ケーブルと比較して、同一外径で2倍の心数、最大3456心の光ファイバを収納することに成功した。
3.2 MB

3.2 MB
インターネットの普及に伴う世界のデータトラフィックは爆発的に増加している。インターネットサービスの根幹を支えるデータセンタでは架間や装置間の配線の高密度化と配線作業の効率化が求められている。こうした要求に応えるため、我々は2つの新製品①MPOカセット(PrecisionFlex)と②極性変換LCコネクタ(FlexULC)を開発した。本稿では、これらの新製品と、フィールドにおける使いやすさを大幅に向上させたMPOコネクタ(SumiMPO)付ラウンドコード/トランクケーブル製品とを合わせた、融着不要のプラグ・アンド・プレイ方式による光配線ソリューションを提案する。
1.8 MB

1.8 MB
PON(Passive Optical Network)方式による光アクセス網 は、局舎に設置されるOLT(Optical Line Terminal)と加入者宅あるいは複数の加入者宅を接続するDP(Distribution Point)に設置されるONU(Optical Network Unit)で構成されると定義されてきた。本論文では、距離、ポートあたりの加入者数、幹線ファイバ数、統合OSS(Operations Support System)、機器設置スペースのコストや電力消費の節減、機器の冷却といったMSO(Multi-System Cable Operators)のアクセス網に対する根本的な要求に応えるべく当社が提唱する北米MSOの次世代アクセス網アーキテクチャを紹介する。
1.2 MB

1.2 MB
近年、GaN HEMTは、優れた物性より携帯電話基地局などの高出力、高周波通信機に広く使われている。本報告では、当社が世界に先駆けて市場投入したGaN HEMTについてその特徴と主要特性について述べる。また、携帯電話基地局用途においては、広く使われている出力電力400WのDoherty増幅器を、その基地局間通信においては広帯域特性を有するGaN HEMTのデバイス構造、特性を示す。衛星通信用途においては、地球局用および衛星搭載用の高信頼性GaN HEMT、更に気象観測レーダー等に使われる高出力GaN HEMTについても示す。当社の開発したGaN HEMTが今後の無線通信の小型化、軽量化、低消費電力化に大きく貢献することを期待する。
1.3 MB
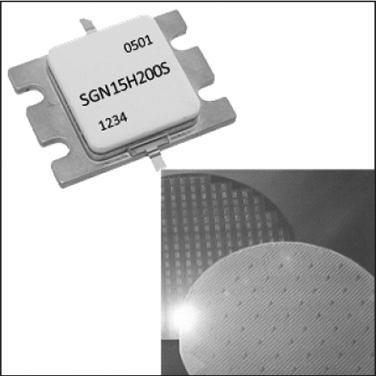
1.3 MB
インターネット環境の更なる向上に対する社会要請に応えるため、光部品市場のニーズは現在主流である100G製品から、早くも200G/400G製品へと移行しつつある。当社はその高速化に加え、20 km超の中長距離伝送に対するニーズにも応えるべく、内製APDを搭載した4ch APD集積受信デバイスを開発した。これまで開発してきた4ch集積受信デバイスの設計をベースとし、当社独自設計の高感度APDチップと光挿入損失の小さい空間結合型の光分波器を内蔵した、伝送速度200 Gbit/sにおいて優れた性能を有する4ch APD集積受信デバイスを実現した。本稿ではデバイス構造や、1シンボルあたり2ビットの情報を伝送することが可能な4値パルス振幅変調(4-level Pulse Amplitude Modulation, PAM4)信号を用いた53 Gbit/sでの受信感度等の諸特性について紹介する。
2.1 MB

2.1 MB
熱収縮チューブの内層にホットメルト接着剤を配した二層チューブは、熱収縮加工時の熱で接着剤が溶融し被覆体の凹凸に追随して高い絶縁・防水保護性を発現し、エレクトロニクス・航空機等の分野で使用されている。近年、自動車分野ではエンジン周りの電装機器の増大によりハーネスの接続部位が高温環境下に晒されるため耐熱性の高い(125℃)二層チューブのニーズが高まっている。従来の二層チューブは、125℃の使用環境下では位置ずれが生じ防水保護性を確保できない課題があった。使用環境下で熱収縮層(外層)が軟化し径方向に内部応力を発生することが位置ずれ原因と特定し、ポリマーブレンドで融点を最適化した位置ずれの生じない外層用ポリエチレン系材料を開発した。また、内層には極性の異なる外層と被覆体(PVC電線)の双方に接着するポリアミド系のポリマーアロイ接着剤を開発し、自動車ハーネス用の新規二層チューブに適用した。
3.1 MB

3.1 MB
電力利用の多様化が進み、電力変換に使われるパワー半導体の高効率化は省エネ社会により重要なものになってきている。パワー半導体は、現在はシリコン(Si)が広く普及しているが、より高効率なシリコンカーバイド(SiC)が実用化されつつある。金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)は主要なパワー半導体のひとつであり、我々はその中でも高効率化に有利なゲートを溝型にしたトレンチMOSFETの開発を進めてきた。トレンチを高効率なV溝型にし、電界が集中しやすいトレンチ底部に電界集中緩和層を導入することで、この課題を克服し、低損失と高耐圧を両立した。さらに、構造最適化を進めるとともに、帰還容量(Crss)を低減する構造を実現し、スイッチング損失を70%削減した高速スイッチングが可能なV溝型SiCトレンチMOSFETを実現した。
1.4 MB
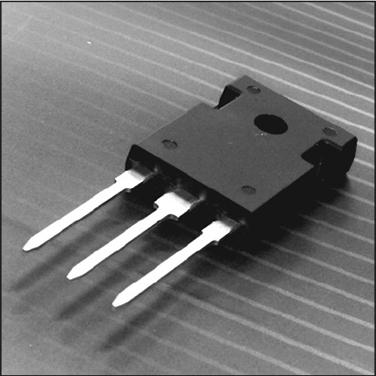
1.4 MB
熱電材料を用いた発電技術は、排熱から直接電力に変換することが可能であり、持続可能なエネルギー源となり得るため、低炭素社会に向けたエネルギー技術として期待されている。しかし、熱電変換効率に直結する熱電性能指数ZTの目標値が自動車廃熱発電で4以上であるのに対し、実際の材料では50年近く2以下しか得られておらず、目標の実現は非常に困難であると見られている。この大きなギャップを、材料の電子構造の変調、すなわちナノ構造の精密制御により打破すべく、研究開発を行っている。本研究では、ナノ構造の作製のために出発母材として必要と考えているアモルファス半導体バルク材料の開発を行った結果を報告する。
1.3 MB
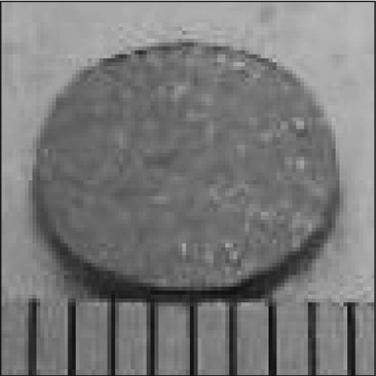
1.3 MB
高温超電導線材(high-temperature superconductors、以後HTSと略す)同士の超電導接続技術は、HTSコイルの永久電流モードでの運転におけるキーとなる技術である。今回、永久電流モードでの運転を可能とする薄膜高温超電導線材の超電導接続技術を開発したので紹介する。本手法の特徴は、高温超電導体であるREBa2Cu3O7-x(以後、REBCOと略す)の微結晶状態の前駆体を用いて接続する点にある。超電導の微結晶である中間体を成長させて形成することからiGS接続(Intermediate Grown Superconducting接続)と名付けた。接続処理後の接続界面の断面をTEM(Transmission Electron Microscope)で観察したところ、接続対象とするREBCO層上の前駆体が配向結晶化することで、線材のREBCO層と原子レベルの理想的な状態で接続されていることを確認した。本接続では、液体窒素中自己磁場下で実用的な値である70A以上の接続Ic(超電導臨界電流※1)が再現良く得られ、また、HTSコイルから引き出された線材端部を本接続技術で接続する
2.7 MB

2.7 MB
ハイブリッド車や電気自動車などの電動車両の普及や家電・エレクトロニクスの省エネ化により電磁部品の需要が高まっている。中でも最大の市場であるモータでは、現在は磁心に電磁鋼板を用いたラジアルギャップモータが主流であるが、近年車載用途をはじめ小型(薄型)・高出力化のニーズが増大しており、これらを両立可能なアキシャルギャップモータに注目が集まっている。しかし、重要な構成部品のひとつである磁心の三次元造形が困難なため、市場での広がりは極めて限定的であった。圧粉磁心は絶縁被覆された軟磁性粉末を加圧成形により造形した材料であり、磁気的等方性と高い形状自由度が特長である。当社では圧粉磁心をアキシャルギャップモータに適用することで性能と生産性に優れる薄型モータを実現し、ラジアルギャップモータ対比で高トルク化・高効率化を実証した。
4.3 MB
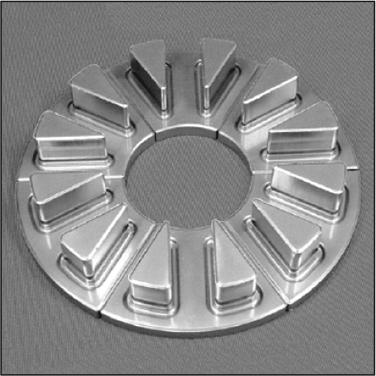
4.3 MB
近年、地球環境への負荷低減、資源の効率的な活用を目的とした様々な取組みがなされており、自動車等に用いられる鋼部品の切削加工においても、被削材の鉛レス化(難削化)や、切削加工条件のドライ加工化および高能率加工化が急速に進んでいる。このような過酷な切削環境下において安定して使用できる信頼性の高い工具が求められている。そのような鋼加工市場でのニーズに応えるため、鋼旋削加工用コーティング材種「AC8015P」「AC8025P」「AC8035P」を開発した。「AC8015P」は高速・連続加工における高能率加工を実現し、「AC8025P」は汎用加工における安定・長寿命を達成する。また「AC8035P」は断続加工における突発欠損を大幅に抑制し高い安定性を実現する。これら3材種により鋼の幅広い加工において、加工コストの低減を可能とした。
5 MB
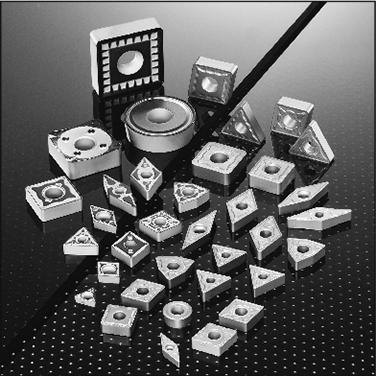
5 MB
高品質なトマト大苗を育成する装置を開発した。大苗とは、収穫までの栽培期間を短縮するため、圃場に定植して栽培を開始する前にできるだけ生育を進めた苗である。閉鎖空間中、人工光下で大苗を育成することにより、病虫害リスクの少ない無農薬の育苗が可能となるが、トマト苗では、人工光下で育成すると生理障害が発生しやすく、十分な期間の育成はできなかった。本装置では、光波長の最適化など育成環境の改善により、生理障害の発生を抑制するとともに均一な大苗を育成することに成功した。本稿では、本装置の特長である生理障害抑制の抑制技術と苗の均一性に重要な気流制御技術について紹介する。(なお本研究は千葉大学との共同研究の中で実施されたものである)
1.8 MB
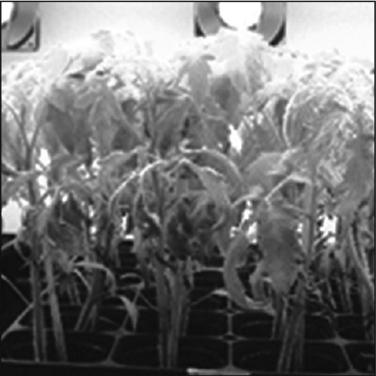
1.8 MB
携帯電話基地局や衛星通信に向けた高効率・高周波動作GaN-HEMT※1では性能の長期信頼性保証が特に重要であり、製品寿命を予測するにはデバイス動作下でゲート電極直下の長さ0.2 µm程のチャネル層の温度(Tch)を測定する必要がある。これまでは赤外顕微鏡による測定を行っていたが空間分解能が4 µmであり温度分布が平均化され正しく測定できなかった。そこで空間分解能が0.8 µmのラマン分光を活用したTch測定法を開発した。測定精度の把握と向上のための試料構造最適化とデータ補正法を検討し、測定精度が5℃の測定技術を確立した。既存製品の製品寿命を試算したところ、同じTchで比較すると予測値が1桁長くなることを確認した。
3 MB
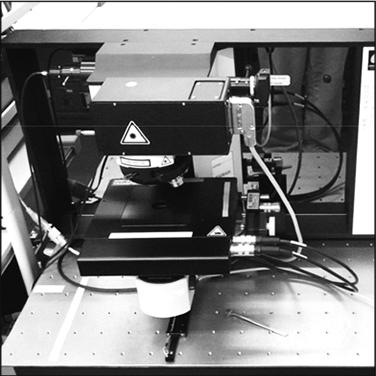
3 MB
強力なX線である放射光を用いることで、材料やデバイス中の構成元素の化学結合状態や原子レベルでの構造、プロセス中の反応解析など、高度な分析を実施することができる。これらを日常的に利用して、開発の加速、製品の信頼性向上などを図るため、佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターに、当社が利用できる放射光ビームラインを建設した。本ビームラインは「住友電工ビームライン」と称し、軟X線用と硬X線用の2本より構成されており、X線吸収分光、光電子分光、X線回折、小角散乱の測定が可能な構成となっている。2015年2月に設置工事に着工し、2016年11月より実際の解析に供している。
1.6 MB

1.6 MB
近年、道路の防災性の向上や良好な景観の形成を背景に無電柱化の検討が為されている。光ケーブルを地中に埋設するには通常、地下管路にケーブルを通線する方式が取られているが、設備費用や敷設作業など非常にコストがかかっている。また外装付ケーブルではケーブルに不具合があった場合、掘り起こして補修・再布設が必要である。今回開発したダクトケーブルは、図1に示すように直接埋設に耐えうる外被の中に、密着しない状態でケーブルコアを収納しているため、一度に管路とケーブル布設が可能で、直接埋設用外被自体にケーブル保護機能があるためケーブルのみ抜き差しによる張替も容易である。実装する光ケーブルコアは、標準的な丸型の光ケーブルだけでなくドロップケーブルも適用できる。これらを使い分ければ例えば図2のようなFTTH配線が可能になる。
0.6 MB

0.6 MB
増加する通信データ情報量の需要に応えるため、海底通信ケーブルに使用される光ファイバには伝送損失及び非線形性の低減が求められる。純シリカコアファイバ(PSCF)は、光を導波するための添加物がコア中に添加されないため、本質的な低損失性・低非線形性を有する。今回、商用化されている光ファイバの中で最高の伝送性能を有するPSCFであるZ-PLUS Fiber 150(Z+150)を開発した。これは、2013年にリリースしたZ-PLUS Fiber 130 ULL(Z+130)に比べ、ガラス品質及びガラスを被覆する樹脂物性がさらに改善されたPSCFであり、伝送損失が0.154 dB/kmから0.152 dB/kmへ、実効コア断面積(Aeff)が130 µm2から150 µm2へ、それぞれ改善されている。また、約4,000 kmのZ+150の量産試作を行ない、製造安定性についても良好であることを確認した。
1.6 MB

1.6 MB
現行のシングルモード光ファイバ(SMF)伝送技術に基づく長距離伝送システムの伝送容量は、近い将来限界を迎えることが予測される。当社ではこの伝送容量限界を打破する次世代の光ファイバとして、直径125µmのガラスクラッドに4つの純シリカコアを内蔵した結合型マルチコア光ファイバ(MCF)を開発し、従来の記録を大幅に更新する低空間モード分散(SMD)と、既報のMCFの中で最も低い伝送損失を実現した。低SMD特性は受信信号のデジタル信号処理計算負荷の大幅な低減に、低伝送損失特性はコアごとの伝送容量拡大に、標準ファイバと同等のクラッド直径は高い機械的信頼性の実現に、それぞれ寄与する。また、開発したMCFが、同等の伝送損失と実効断面積を持つSMFより優れた伝送特性を持つことも実験で確認されている。本開発成果は、結合型MCFが、超長距離伝送システムにも導入可能なレベルの信頼性と性能を兼ね備えた光ファイバであることを示すものである。
1.2 MB
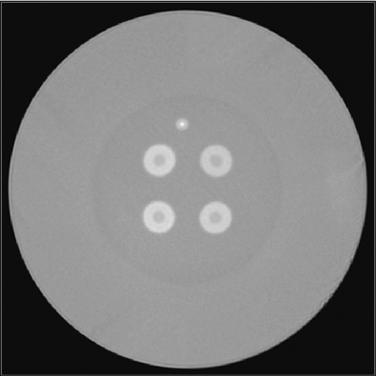
1.2 MB
光通信伝送量の飛躍的な増大に対応すべく、多値変調方式を活用したディジタルコヒーレント光通信技術が注目されており、既に幹線系システムへは広く導入されている。今後、幹線系からメトロ系への展開に向けて光トランシーバの小型化が強く求められている。今回CFP2-ACO光トランシーバに搭載可能なOIF Micro-ICR仕様に準拠した小型光受信器を開発した。導波路型PDと90°ハイブリッドを集積したInP系光集積素子を採用することで、高受光感度かつ12.0×22.7×4.5mmの小型パッケージの光受信器を実現した。光受信器には、VOA及び信号光モニタPDも内蔵し高機能化を図った。128Gbit/s DP-QPSK変調信号および224Gbit/s DP-16QAM変調信号の復調を行い、ディジタルコヒーレント伝送の実証を行った。本稿では、開発した小型光受信器の設計と代表的な特性を紹介する。
1.6 MB
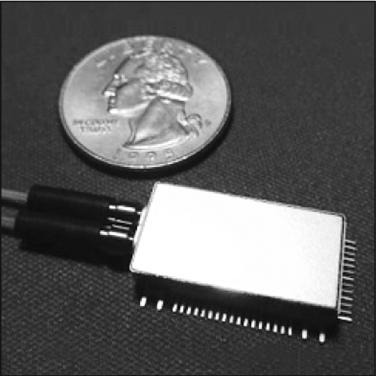
1.6 MB
当社は、光ファイバを用いたFTTHブロードバンドサービスを国内外に普及させるため、PON(Passive Optical Network)方式を採用した機器の開発を行ってきた。ネットワーク上に流れるトラフィックの量は年々増加しており、特に高品質の映像配信サービスに対応するために、ブロードバンドサービスのさらなる高速化が要求されている。そこで当社は、現行方式の1G-EPON※1対比で約10倍の伝送容量を持つ10G-EPON対応の局側装置(OLT: Optical Line Terminal)を製品化した。本書では、既存の1G-EPON用の線路設備や宅内装置を使いつつ、新たに10G-EPON用の宅内装置(ONU: Optical Network Unit)を使用することで、4K/8Kといった高帯域な映像サービスにも対応できる10G-EPONシステムについて記述する。また、10G-EPON OLTを使うことによる設置スペースの縮小や、消費電力の低減など、運用コストの削減などの効果についても記述する。
1.3 MB

1.3 MB
人工衛星への搭載を目的として、L帯※1 200Wの高効率・高出力GaN HEMT※2を開発した。200W GaN HEMTは100W出力をもつGaN HEMT2個を同一パッケージ内に実装することで実現され、1.58GHzのCW動作においてドレイン効率74.6%、電力付加効率71.0%を達成した。この効率性能はL帯200W級GaN HEMTにおいて世界最高水準である。また我々は、このGaN HEMT技術に対し衛星搭載用認定試験を行い、衛星用途として要求される全ての品質と信頼性を満足していることを確認した。GaN HEMTを用いた固体素子増幅器(SSPA)の実現可能性を示し、今後衛星の小型化や軽量化に大きく貢献することを期待する。
1.5 MB

1.5 MB
フラットパネルディスプレイ(FPD)用薄膜トランジスタ(TFT)に用いるための半導体材料として、酸化物半導体が注目されており、すでにIn-Ga-Zn-O(IGZO)が量産されている。酸化物半導体がFPDに用いられる場合、酸化物セラミックス焼結体を原料(スパッタリングターゲット)として薄膜が形成される。当社は、原料である酸化物セラミックス焼結体の販売を目指して、8K-TVを実現できる新規の酸化物半導体材料の開発を行ってきた。その結果、In-W-Zn-O系において、スパッタリングターゲットとして好適な高密度、低電気抵抗の酸化物セラミックス焼結体を合成でき、その焼結体を用いて成膜したTFTは、IGZO比3倍以上の高い電子移動度を実現すると共に、実用特性として重要な信頼性もIGZO並以上を実現できた。
1.6 MB
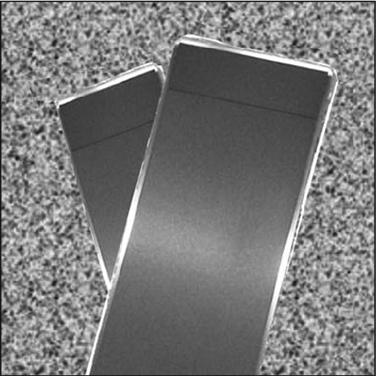
1.6 MB
近年、地球環境への負荷低減、資源の効率的な活用を目的とした様々な取組みがなされており、自動車等に用いられる鋳鉄部品加工の分野でも、軽量化が急速に進んでいる。軽量化に伴い、各構成部品はより薄肉、複雑形状化し、薄肉化した場合にも十分な強度を確保する必要性から、使用される被削材はより高強度・難削化し、工具寿命の低下が課題となる。また、加工現場では、コスト削減要求の高まりや、工作機械の性能向上を背景に、高速・高能率加工への要求が以前にもまして高まっている。このような鋳鉄加工市場での課題を解決するため、鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド新材種「AC4010K」「AC4015K」を開発した。「AC4010K」はねずみ鋳鉄の高速・連続加工を筆頭に高能率加工を実現し、「AC4015K」はダクタイル鋳鉄の加工を中心に汎用加工で安定・長寿命を達成する。これら2材種により鋳鉄の幅広い加工において、加工コストの低減を可能とした。
3 MB

3 MB
近年自動車エンジンへの搭載率が高まっている可変バルブタイミング機構(以下、VVT)は、吸排気バルブの開閉タイミングを可変することにより燃費向上、排ガス低減を実現するシステムである。現在、VVTは部品点数が少なく安価に製造できる油圧式が主流であるが、昨今の環境・低燃費志向の高まりに伴い、構成部品の複雑形状化が進みつつある。中でもロータは、従来単独の部品として存在していたオイルコントロールバルブ機能の一部を備えたものが登場するなど複雑形状化が著しいが、一般に粉末成形法では横穴や内溝形状は造形できないことから、焼結後に機械加工を行う必要があり、加工難易度の上昇に伴う製造コスト増加や品質安定化が課題であった。そこで、高い生産性が期待できる成形体加工技術を適用し、①成形体加工条件の最適化、②成形体加工専用加工ラインの構築、③2Dコードを用いたトレーサビリティ付与システムの開発により、高生産性と高品質を両立するVVT部品生産ラインの構築に成功した。
4.6 MB
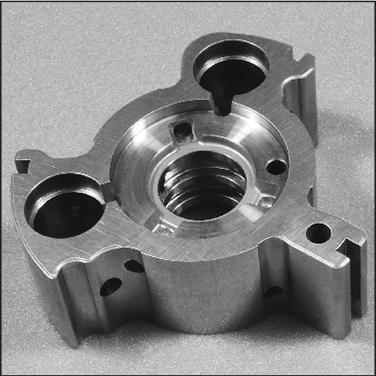
4.6 MB
グラフェンは、次世代の高速・大容量無線通信用途のデバイス材料として注目されている。我々は、グラフェンをデバイス製造に適用すべく、SiC基板から作製したグラフェン品質の面内分布を改善する新製法の開発を進めてきた。この製法は、C面6H-SiC基板上にSiCスパッタ膜を成膜したウエハを高温で加熱し、グラフェンを作製する製法である。本製法で作製したグラフェンをラマン分光法によるマッピングおよび低エネルギー電子顕微鏡観察で評価した結果、75µm×75µmの領域の95%が同一層数の2層グラフェンで占められている事が分かり、非常に優れた層数均一性を実証した。我々は、層数均一性に優れる本製法が従来のグラフェンを作製する方法に比べテラヘルツ帯で動作するトランジスタ作製に適した有力な製法であると考えている。
1.8 MB
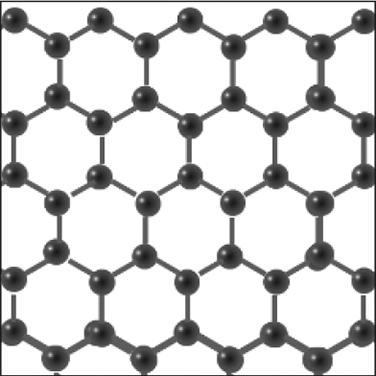
1.8 MB
我々は、中赤外量子カスケードレーザ(QCL)の閾値電流低減に必要な端面高反射化策として、半導体壁/空隙を周期的に配列した分布ブラッグ反射器(DBR)を採用し、これを集積したFP型QCLの開発を行った。その結果、1ペアの3λ/4構造のDBR集積で、劈開端面の2倍以上の66%の端面反射率と11%の閾値電流低減が得られ、DBRがQCL端面の高反射率化に有効であることを実証した。また本DBRを集積した7 µm帯FP型QCLにて、パルスで100 ℃、CWで15 ℃までの発振に成功し、InP系のDBR集積QCLとしては、初めて動作に成功すると共に、センシングに必要なレベルの光出力(数mW~数十mW)が得られた。本DBRは特に、低損失性が必要な前端面の高反射構造としての活用が期待される。
1.6 MB
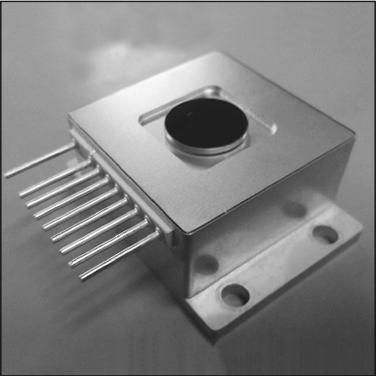
1.6 MB
本研究では、赤外線センサ開発に向けて、第一原理手法のひとつであるハイブリッド準粒子セルフ-コンシステントGW(QSGW)法をタイプ-Ⅱ超格子(InAs)n(GaSb)n(n=1, 2, 3, および 4)に適用し、超格子のエネルギーバンドとして信頼性の高い結果を得ることに初めて成功した。算出されたバンドギャップは層数nの関数として得られ、光ルミネセンス(PL)法による実験値のnに対する傾向をよく再現できていることを確認した。また、バンド端アラインメントの実空間分析により、n=4に対するInAs/GaSbのバンドオフセット(0.5 eV)はX線光電子分光法による実験値と一致した。
1.4 MB
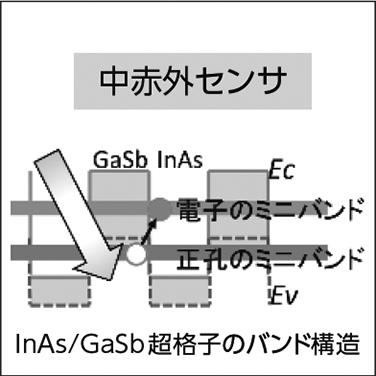
1.4 MB
銅腐食生成物の定量的な状態分析を行う目的で、高アルカリ液(6 M KOH + 1 M LiOH)を電解液としたボルタンメトリー還元法を開発した。引き続き、この手法を用いて銅酸化物(Cu2OとCuO)の成長メカニズムの解析を行った。通常の大気加熱では、Cu2OとCuOが共に生成・成長したが、特定のイオンを含む水溶液に予備浸漬した後に高湿条件で加熱したところ、イオンの種類によって銅酸化物の成長挙動が変化した。予備浸漬液としてLiClやLiBrの水溶液を用いるとCu2Oが選択的に成長した。おそらくLi+イオンがCu2O層中に浸入し、CuOと銅本体の間での均化反応(Cu + CuO → Cu2O)を促進させたために、Cu2Oの成長が継続したと思われる。ただしCu2Oの成長には高湿条件が必要であった。また、KOH水溶液を用いると加熱初期段階からCuOが成長した。銅表面の水膜中のOH–が高濃度化したことが要因と考えられる。
0.8 MB
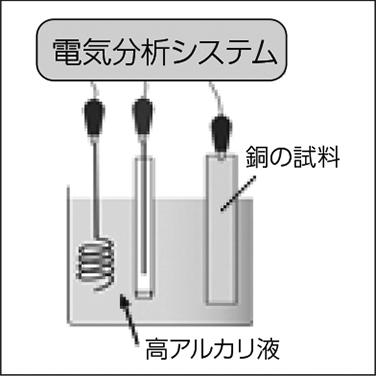
0.8 MB
通信トラフィックの増加を背景に、世界中で光ネットワークの構築が急速に進められている。融着接続を代表とする光ファイバの敷設工事で高精度な接続を行うには、光ファイバへの高品質な前処理が重要になる。特に光ファイバを切断し、端面を鏡面状に仕上げる光ファイバカッタは、接続品質を左右する重要な工具として位置付けられている。当社は、特許技術である切断刃の自動回転機構を搭載したハンディ光ファイバカッタFC-7Rを販売し、光ネットワークの構築に貢献している。今回、その後継機種であるFC-8Rを開発したので報告する。
0.6 MB
新興国を中心にエネルギー需要が急拡大し、地球温暖化など環境問題が顕在化、環境に配慮した安全で安定した電力・エネルギー確保への期待が従来以上に高まっている。こうしたなかで、グローバルに進む発電・送配電網の整備、再生可能エネルギーの導入加速と、その導入に対応した電力系統の信頼度確保など、電力・エネルギーを取り巻く環境はダイナミックに変化しており、また、電力・エネルギーの供給とその品質に対するニーズも多様化してきている。当社グループは、電力インフラ以外に情報通信、自動車、そしてエレクトロニクス等を含む裾野の広い技術・製品群を有しており、新たな電力・エネルギー社会の多様なニーズに対応したソリューションを提供することが可能であり、「環境負荷の低減」、「電力品質の維持向上」、そして「エネルギーセキュリティーの確保」の“3つの価値”実現に向け、製品・技術開発に取り組んでいる。本特集では、当社グループの環境エネルギー事業への取り組みと技術開発の状況を紹介するが、先ずは、同分野を支えてきた電線・ケーブル事業の沿革と技術動向を紹介することから始める。
1.5 MB
1988年に発見されたビスマス系(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3Oy(Bi-2223)超電導体は、線材の高性能化・長尺化の研究が進み、現在では200Aをkmレベルで製造できるまでに開発が進んだ。Bi-2223系超電導線材を使用した実証ケーブル試験やコイル応用したモータ開発等、様々な試験が活発に実施されてきた。しかし、NMRや核融合炉・加速器などの超電導応用機器用途では、より強磁場なマグネットが要求されている。このような背景を踏まえ、Ni合金補強した高強度Bi-2223線材(Type HT-NX)を開発、Ni合金の比抵抗が高いことに起因した線材接続部分での発熱問題も、新しい線材接続方法により解決した。本稿では、Bi-2223線材の高強度化とType HT-NX線材の低抵抗接続方法に関して紹介する。
3.9 MB

3.9 MB
太陽光、風力をはじめとする再生可能エネルギーの有効活用のために大容量蓄電池が重要な役割を果たすことが期待されている。その中でも実システムで実績があるバナジウム系レドックスフロー電池は、応答速度の速さ、容量と出力の設計自由度、安全性の点から注目を集めているが、再生可能エネルギー発電コストの低価格化が進む中で蓄電池コストの低減が最大の課題である。そのため、安価な電解液を用いたレドックスフロー電池の開発が世界中で行われており、当社においても、安価なマンガン材料に着目し、チタン-マンガン系レドックスフロー電池の開発を行っている。本稿では、電解液の開発動向とチタン-マンガン系電解液の電池性能について報告する。
2.7 MB
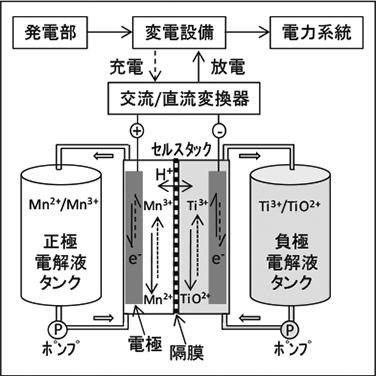
2.7 MB
出力1MW以上のメガソーラー発電所の建設が急速に進んでいるが、大量に導入される太陽光パネルの初期設置不良、長期性能劣化、および外的要因による故障などにより発電量が低下し、売電量の低下を引き起こしている。数千枚~数十万枚で構成される太陽光パネルの故障を検知するため、既に敷設されている電力線を利用しPLC(Power Line Communication)方式を使って、ストリング毎の発電量をリアルタイムに監視するメガソーラー用ストリング監視装置(SSMAP)を開発した。また、ストリング監視装置を導入したメガソーラー発電所において測定した発電量データの解析を行い、発電量の低下を検出した例を紹介する。
2.6 MB

2.6 MB
沿岸海域の水深が深い日本において、浮体式洋上風力発電への関心が高まっている。当該発電方式において、安定した送電を実現する、ダイナミックケーブルシステムを開発し、環境省による浮体式洋上風力発電実証事業へ適用した結果、当社のケーブルは試験期間中問題なく運用された。ケーブルの撤去後の解体調査でも、各部位に顕著な劣化は見られず、当社のダイナミックケーブルシステムが、ハイブリッドスパー型浮体式洋上風力発電においてケーブルに加わる機械的応力に、十分耐え得る性能を有することを確認した。また、ダイナミックケーブルの長期信頼性を担保する為に、海中におけるケーブルの挙動に特化した解析技術の開発に取り組み、所定の海象条件下でケーブルの線形変動を把握可能な解析技術を確立し、浮体式洋上風力発電におけるケーブル布設形態の最適化を可能とした。
3.4 MB

3.4 MB
近年、直流送電線へのXLPEケーブル適用事例が増えている。当社では、長年に亘って直流用XLPEケーブルの開発を行い、これまでの研究開発の過程でその優れた特性が検証されている。2012年には電源開発㈱に納入した直流250kV XLPEケーブルが運転を開始、直流XLPEケーブル線路としては世界最高電圧(当時)であり、かつ極性反転を行う線路への納入は世界初であった。その後、400kV用の評価試験を経て、北海道電力㈱の直流250kV連系線、NEMO Link Limited社の直流400kV連系線を受注、現在は納入に向けた製造等の準備を進めている。当社の直流用XLPEケーブルは、常時導体許容温度が交流用と同じ90℃で、かつ極性反転運用が可能といった特長を有しており、今後ますます増えていくであろう直流送電線のさまざまなニーズに応えることができるものと考える。
1.8 MB

1.8 MB
日本の電力エネルギーを取り巻く環境が大きく変化する中で、日新電機㈱では多様な分散型電源を組み合わせて省エネと電力の安定供給を同時に実現するソリューションを「SPSS(Smart Power Supply Systems:スマート電力供給システム)」として推進している。本稿で紹介するエネルギー管理システム「ENERGYMATE-Factory」はSPSSのコア機能を担い、当社の中核製品である受変電設備に太陽光発電システム、コージェネレーションシステム、蓄電池などの多様な分散型電源を組み合わせて最適に制御することで、エネルギーコスト削減に貢献するソリューションを実現するものである。本稿では「ENERGYMATE-Factory」の概要や特長、および日新電機㈱前橋製作所における実規模検証などについて紹介する。
2.9 MB
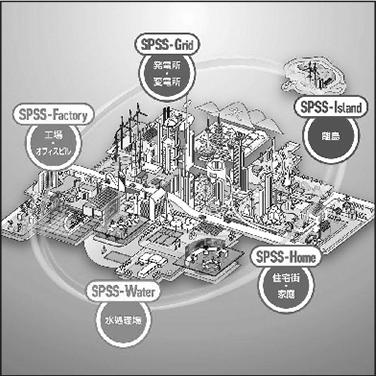
2.9 MB
国内における再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)も導入から3年以上経ち、特に高価であった太陽光発電の調達価格は一段落しつつある。しかしながら、依然世界各地では様々な太陽光発電システムが導入されており、さらなる高機能化、コストダウンが要求されている。当社は国内向けに100~660kW単機容量をSOLARPACKシリーズとしてラインナップし、大規模太陽光システム(メガソーラー)の導入に貢献してきた。今後の顧客ニーズを満たすため、さらなる高効率化、機能改善、保守性の向上をめざしSOLARPACKシリーズの新型機種であるスマートパワコンの開発を行った。
1.6 MB
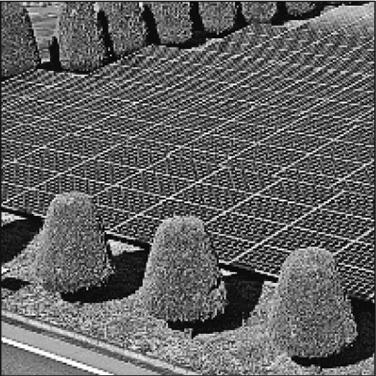
1.6 MB
富山住友電工㈱で量産しているセルメットは、三次元網目状の構造、最大98%まで可能な高い気孔率、高い比表面積といった特徴を有する材料である。これまで、ニッケル、及びニッケルークロム合金のセルメットを製造、販売してきたが、アルミニウムのセルメットが製造できればアルミニウムの特徴である軽量性や高熱伝導性、耐電圧性を活かし、種々の用途への適用が期待される。そこで従来困難とされてきたアルミニウムのめっき技術を開発し、さらに熱処理条件を最適化することでアルミセルメットの開発に成功した。開発したアルミセルメットの諸物性(形状、機械特性、電気特性など)、及びリチウムイオン電池の集電体に適用した際の効果について報告する。
2.3 MB
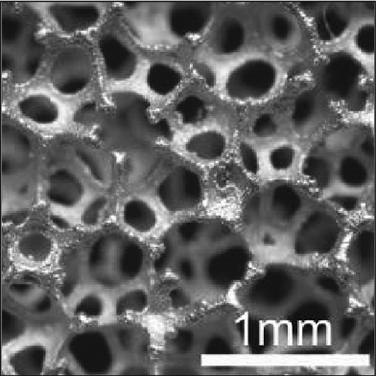
2.3 MB
HEVやEVの高性能化に伴い、パワーケーブルとして用いられる高圧ケーブルの太径化が進み、取り回しの観点からケーブルの柔軟化が強く求められている。ケーブルを構成する導体と絶縁体のそれぞれの柔軟化の方法と柔軟性への寄与度を見積もった。その結果、導体は素線の細径化、絶縁体は低弾性率化が柔軟化に効果的で、特に後者の寄与度が大きいことを明らかにし、低弾性率絶縁材の開発を進めた。ベースポリマーを詳細に検討し、ポリオレフィン系材料を選定した。ポリオレフィンの柔軟性は、結晶領域と非結晶領域の比率で決まるため、この比率をコモノマー比率でコントロールし、高耐熱化・高難燃化の配合処方と架橋を行ってポリマー特性の向上を図り、柔軟性とJASO/ISO規格値を達成する新規の絶縁材を開発した。今後はさらに自動車用の柔軟性ケーブルの拡充を進める。
2.1 MB

2.1 MB
空気ばねは、空気の圧縮性や流動抵抗を応用した柔らかく、減衰性能を有するサスペンションである。空気ばねが鉄道用に採用され60年程経過するが、この技術が現在のように発展を続けてきたのは、新幹線車両に採用され、その高速化に伴う様々な技術課題に適応すべく研究開発が進められてきたことによると言える。高速化に伴う環境影響軽減のため、車両が大幅に軽量化され、台車においてもボルスタが廃止された軽量ボルスタレス台車が採用された。これに伴い、空気ばねの機能も大きく変更になった。また曲線通過速度向上のために、水平方向の非線形特性機構の開発や空気ばねを利用した車体傾斜システムへの適用等、航空機への対抗のために速度向上や乗り心地改善の面で空気ばねが大きく貢献してきた。一部の路線では更なる高速化の検討も進められており、320km/hを超える速度でも安全・快適に走行出来るよう、今後も技術開発が進められる。
1.3 MB

1.3 MB
自動車排出ガスによる環境への影響の懸念から、燃費向上のために自動車の軽量化が図られている。ワイヤーハーネスも軽量化のため、電線の導体を銅からアルミへの変更が進められている。しかし、従来のアルミ電線では導体強度が不足し、0.35mm2や0.5mm2といった細径サイズやエンジン領域での適用ができず、制約が出ている。そこで、我々は、銅と同等以上の強度を有する高強度アルミ合金電線の開発に、業界で初めて成功し、エンジンワイヤーハーネス用0.35mm2電線を皮切りに2015年4月より生産を開始した。開発した電線用の高強度アルミ合金は、目標特性とした引張強さ220MPa、導電率50%IACSを見込んで6000系の時効析出型アルミ合金をベースに、添加成分量を整え、また合金中のMg2Si化合物の析出状態を詳細に調査して、時効条件を選定し、目標を上回る引張強さ250MPaと導電率52%IACSを実現した。
2.9 MB

2.9 MB
近年、E帯無線通信システムは、3G/4G, LTE等モバイルバックホールで急速に増大するデータ伝送や、光通信データを無線で補間するファイバーエクステンションで使用されることが期待されている。E帯通信システムの帯域は71-76GHz, 81-86GHzの各5GHz幅が割り当てられており、10Gbit/s以上の高い伝送レートを可能にしている。このシステムは、高変調方式や遠距離の通信を行うために、0.5W(27dBm)以上の高出力電力が要求されている。ここでは、GaAs PHEMTテクノロジを適用し、安定化設計を組み込んだE帯1W(30dBm)クラス増幅器MMICについて紹介する。
1.9 MB
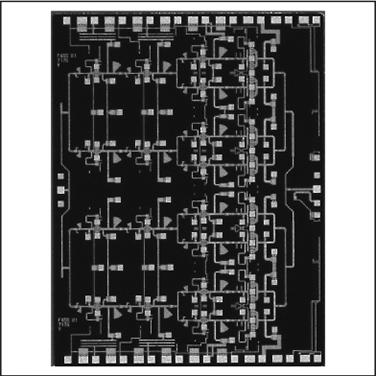
1.9 MB
GaN HEMTを用いたS帯 600 W、X帯 200 Wの高出力・高効率・内部整合型増幅器の製品化について報告する。レーダー用送信機の固体素子化に向けて、GaNデバイスのさらなる高出力化が期待されている。S帯においては主に航空管制レーダー向けに2.7 – 2.9 GHzの帯域で出力600 W以上、パワーゲイン12.8 dB以上、ドレイン電力付加効率59 %を有する完全50Ω整合型のGaN HEMT、およびX帯においては 主に船舶レーダー、気象レーダー向けに8.5 – 9.8 GHzの帯域で出力200 W以上、パワーゲイン9 dB以上、電力付加効率38 %を有する完全50Ω整合型のGaN HEMTをそれぞれ製品化した。これらは、製品化された内部整合型GaN HEMTにおいて世界最高水準の出力電力であり、レーダー送信機の小型化、軽量化、低消費電力化に大きく貢献している。
1 MB
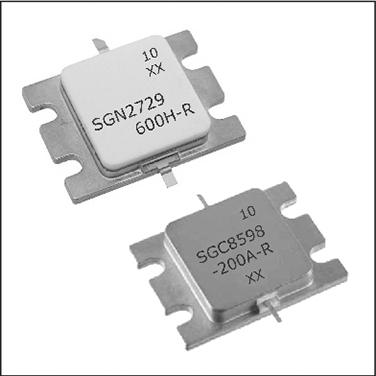
1 MB
熱電材料を用いた発電技術は、排熱から直接電力に変換することが可能であり、持続可能なエネルギー源となり得るため、低炭素社会に向けたエネルギー材料技術として期待されている。しかし、熱電変換効率に直結する熱電性能指数ZTの目標値が自動車廃熱発電で4以上であるのに対し、実際の材料では50年近く約2以下しか得られておらず、目標の実現は非常に困難であると見られている。この大きなギャップを、材料の電子構造の変調、すなわちナノ構造の精密制御により打破すべく、研究開発を行っている。本研究では、高い性能指数を実現するため、必要条件と考えているナノ粒子の粒径および粒間隔の制御を行なうべく、分子線エピタキシー装置による薄膜積層技術により、ナノ構造を制御する観点から研究した結果を報告する。
2.1 MB
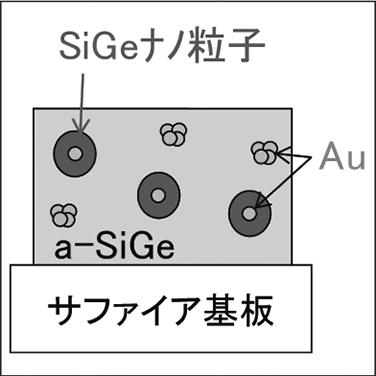
2.1 MB
自動車や電子部品等の様々な分野において銅合金は幅広く適用されている。中でもベリリウム銅合金は、その人体や環境への影響が懸念されており、材料の置換えが要求されている。しかし、ベリリウム銅合金は優れた特性を有しており、代替材による置換えは一部に留まっている。そこで、住友電工スチールワイヤー㈱は鋼芯の表面に銅を厚く被覆した厚銅覆鋼線を開発した。厚銅覆鋼線は鋼線の強度・耐へたり性と銅の導電性を両立させた材料であり、鋼芯の強度調整と銅の被覆率を変更することで容易に特性をデザインすることが可能である。実際に機械特性評価を実施したところ、ベリリウム銅合金と同等以上の特性を発現可能であることが確認された。本報では、厚銅覆鋼線の各機械特性評価結果について述べる。
1.6 MB

1.6 MB
近年、自動車部品加工市場においては省エネ・低燃費化の推進により部品の小型・軽量化が進んでいることから、これらに用いられる材料も強度の向上や多品種化が進んでいる。当社はこれらの自動車用部品に代表される小型部品の精密加工における様々な課題を解決するため、新PVDコーティング技術「Absotech Bronze」を適用した「AC1030U」と微小切削用ブレーカ「FYS型」を開発した。「AC1030U」は高い刃先品位と優れた耐摩耗性を併せ持つ精密加工用材種であり、「FYS型」ブレーカは微小切削領域において優れた切りくず処理性と耐摩耗性を持つ。新材質、新ブレーカにより鋼・ステンレス鋼・耐熱鋼・純鉄といった様々な材料の精密加工に対応し、加工コストの削減を可能とした。
3.4 MB
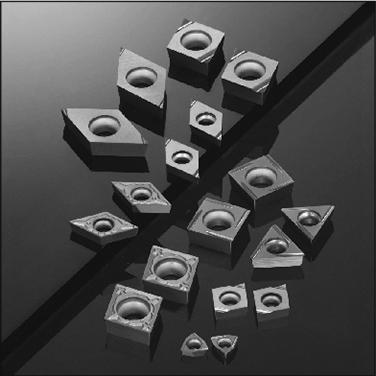
3.4 MB
ニューサンドポニックス(NSP)は、従来の砂栽培装置サンドポニックスに底面給水を組み合わせた新しい栽培装置である。従来の砂栽培は、砂が再利用可能である反面、装置が重くなるという難点があった。NSPは、従来のサンドポニックスの10%以下の砂培地量にすること、また、給液方法を改良することによりメンテナンスの軽減を達成した。現在は排水が無く成長状態に応じた液肥給水による野菜品質の制御を実現しつつある。本稿では、その特長である培地中の根への酸素供給性能をさらに改善することで、トマト収穫の増量に成功したNSP栽培の例を示すとともに、当社が目指す農業のIoT化に向けた、サンドポニックスを用いた農業生産の支援システムの構築の試みについて紹介する。
2.5 MB

2.5 MB
住友理工㈱では、これまで培ってきた高分子の配合技術を活かし、柔軟な静電容量型の圧力センサである『スマートラバー(SR)センサ』を開発してきた。このSRセンサの技術を応用し、心臓マッサージ(胸骨圧迫)の訓練評価システム『しんのすけくん』を開発した。『しんのすけくん』は、胸骨圧迫の訓練時の、圧迫深さ、テンポ(リズム)、リコイルに加えて圧迫位置も評価できることが特長のリアルタイムオートフィードバック機器である。さらに、SRセンサを用いていることにより、マットレスの上など柔らかい下地でも圧迫深さを評価できることも特長である。『しんのすけくん』が普及することにより、心肺蘇生を行える人材の裾野の拡大に貢献し、救命率の向上につながることを期待している。
1.1 MB

1.1 MB
近年のCO2排出量増加による地球温暖化の問題に対応するため、自動車業界ではハイブリッド自動車などの電動車両の開発が活発になっている。ハイブリッド自動車は内燃機関に加え、主にバッテリ、インバータ、モータからなる電気駆動系を備え、その時々の走行状態に適した駆動系を選択して、燃費を大きく向上させている。ダイレクトコネクタは、インバータのモータ直上搭載に適した、機器一体型コネクタで、インバータと駆動用、発電用の2基のモータとをケーブルレスでの接続が可能です。当社グループの住友電装(株)は、新たに柔軟導体を採用することで、インバータとモータの接続をコネクタ嵌合とし、自動車製造ラインでの組み付け作業性を向上させた、ダイレクトコネクタを開発した。本製品は16年2月に発売された本田技研工業(株)のオデッセイ ハイブリッドに採用された。
0.7 MB
1990年代初頭から整備されてきた光ビーコンシステムにおいて、通信量の拡大と、信号情報活用運転支援システムが可能な高度化光ビーコンへの移行が徐々に進んでいる。この背景には、近年自動車の低燃費化や安全性向上に関する技術開発の活発化が後押ししている。このシステムは、赤外線通信経由での路線信号情報を入手することで、ドライバへの安全走行とエコを促すサービスを提供する。当社グループの住友電装(株)、住友電工システムソリューション(株)、(株)オートネットワーク技術研究所の3社は、上記システムに搭載される車載用高度化光ビーコンを開発した。本製品は本田技研工業(株)のアコードに採用された。
0.6 MB
半導体技術の進歩によってマイクロプロセッサは1971年の登場以来、40年で100万倍の高度化を遂げ、コンピュータのダウンサイジングと普及とともにネットワーク化が進んだ。パーソナルコンピュータの普及期には、光通信技術を利用した高速大規模LANと多様な方式に対応したLAN間中継装置によって、導入期から大規模化に向かう企業のコンピュータ通信の発展を支えた。2000年代には、ディジタル伝送技術とパケット通信技術を組み合わせたADSLとPON製品によって公衆アクセス網の改革を支え、我が国のインターネット普及に貢献した。コンピュータ通信が今後ますますグローバルに、生活や企業活動の隅々に浸透していく中、新たな役割を担っていく。
1.2 MB

1.2 MB
タングステンは超硬工具の主成分として用いられている。鉱山は中国に偏在しており、その供給が不安定であるため、安定的に超硬ビジネスを行うためには中国依存度を下げるのが望ましい。このような観点から、住友電工グループでは使用済みの超硬工具からのタングステン回収に注力しており、効率的・低環境負荷なリサイクル技術を産学共同研究により開発・実用化した。実用化にあたり様々な問題に直面したが、これを克服し事業として成立するプロセスを確立することができた。本稿では、主に環境対策と不純物の混入抑止について述べる。これまでは高品位の原料を扱ってきたが、今後はこれまで廃棄されてきた低品位原料も活用するための技術開発に注力し、レアメタルのリサイクル率向上に貢献していく。
1.8 MB
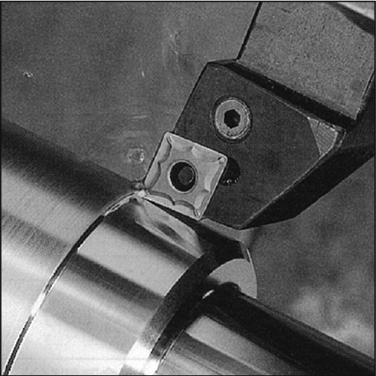
1.8 MB
自動車の電子制御化が進むにつれ車載制御ユニット(ECU:Electric Control Unit)が増加し、複数のネットワークを接続して車載LAN(Local Area Network)を構成することが必要となっている。これまでは2系統のネットワークを接続する2チャンネルゲートウェイECUを使って多段のネットワークを形成してきたため、車両の通信設計が複雑になっていた。今回、車載LANプロトコルの一つであるCAN(Controller Area Network)通信のインタフェースを6チャンネル持ち、各チャンネル間の通信データを中継できるセントラルゲートウェイECUを開発した。これにより、車載LANをシステム別に分けシステム間の独立性を高めることができるため、多くのECUを接続する場合も通信設計をシンプルにできる。セントラルゲートウェイECUは車載LANの核となるECUであるため、住友電気工業㈱がワイヤハーネス、J/B(Junction Box)と合わせて車載インフラ全体のシステム提案を行っていくうえで重要な製品となる。
2.3 MB
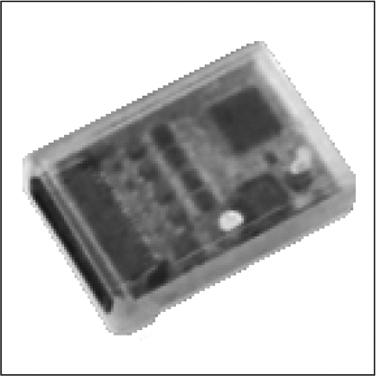
2.3 MB
本稿では、間欠接着型12心光ファイバテープ(以下、間欠12心テープ)を実装した超多心、高密度スロット型光ケーブルについて報告する。今回開発した間欠12心テープは柔軟性と一括融着接続性を両立すべく、ファイバ2心毎に長手方向間欠的にスリットが入った構造を採用しており、接着部と非接着部の比率およびピッチを最適化することにより、両特性を満たす12心テープを開発した。さらに今回は曲げ方向性がなく、布設作業性に優れるスロット型構造を採用し、間欠テープ技術とスロット型構造を組み合わせることで、従来ケーブルと比較して、同一外径で2倍の心数を詰め込むことに成功した。今回は間欠テープの設計、一括融着特性、1728心光ケーブルおよび商用レベルで世界最高心数となる3456心光ケーブル設計および特徴についても報告する。
2.8 MB

2.8 MB
光ファイバ内で発生する非線形現象は、広帯域光発生、ファイバレーザ、光増幅、光信号処理、センサ、計測、分光など非常に多くの分野での応用が検討されており、シリカベース高非線形光ファイバ(HNLF)は、標準的なシングルモードファイバ(SMF)に比べて非線形性が10倍以上大きいことに加え、伝送損失やSMFとの接続損失が低いこと、高次分散を含めた波長分散特性の高精度制御が可能という利点を有しており、これらの用途に適した有望な媒体として期待されている。本稿では、各用途に合わせて当社が開発した各種シリカベースHNLFを紹介する。特に、HNLFの重要な特性である波長分散特性に関して、ゼロ分散波長がファイバ長さ方向に極めて安定なHNLF、4次分散を制御したHNLFについて述べる。また、波長分散の高精度測定技術についても述べる。加えて、HNLFを用いた最新の応用技術として、光周波数コムへの適用例を紹介する。
1.5 MB
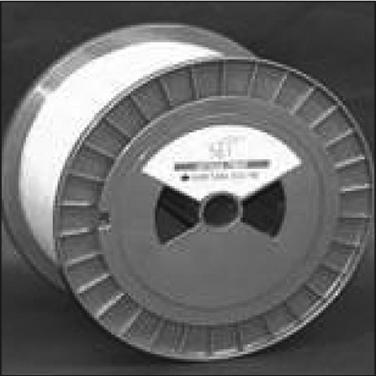
1.5 MB
スーパーコンピューターの計算並列化やデータセンターの処理データ量の増大に伴う短距離インターコネクトでの通信データ量増大に対応するため、大容量のデータを高密度に伝送する光インターコネクト技術の研究開発が盛んに行われている。今回当社は、光インターコネクトに適したマルチコア光ファイバ(MCF)を開発した。本MCFは、標準的な外径125µmのガラスクラッドの中に、1310nm付近の波長帯において汎用シングルモードファイバと同等の光学特性を有するコアを8つ内蔵し、同時にコア間クロストークの抑圧を実現している。標準的なクラッド径の採用により、汎用光ファイバと同等の機械的信頼性を実現可能であり、また、汎用光ファイバ向けのケーブル化技術などの様々な関連技術を活用可能である。本MCFを用いて試作した高密度MCFケーブルは実使用模擬環境下においても良好な光学特性を実現した。
1.3 MB
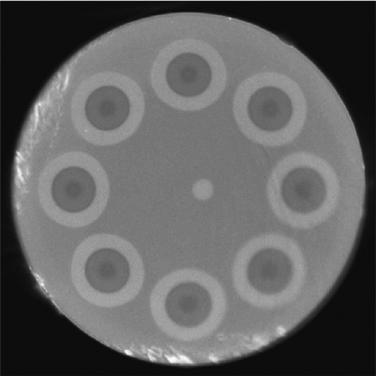
1.3 MB
インターネットの高速化に対応するためのブロードバンドアクセス技術としてとして、当社は光ファイバを用いたPON(Passive Optical Network)方式を採用した光アクセス機器の開発を行ってきた。本報告では、さらなるネットワークサービスの高度化と多様化に対応するため、新たなコンセプトで開発を行った10G-EPONシステムFSU7100について報告する。FSU7100は、従来の1GEPONの10倍の速度に対応できる10G-EPONに対応し、高速化されたPON回線に相応する高速大容量スイッチを備えた光アクセスプラットフォームである。共通フレームワークsOFIA(Sumitomo Electric optical fiber access system integration architecture)、回線カード、集線カードのそれぞれの特長について報告すると共に、ソフトウエア機能として、CATV事業者が既存の装置からPON方式に移行する際のコストを低減するDPoE(DOCSIS Provisioning of EPON)についても述べる。
1.4 MB

1.4 MB
量子カスケードレーザ(QCL)を光源としたガスセンシングは、従来困難であった、高感度、リアルタイムな計測が可能で、かつポータブル性を兼ね備えた手法として期待されている。ポータブルなセンシング装置実現のために、当社はこれまでに波長7 µm帯の QCLの低消費電力化に関する研究を行ってきた。この低消費電力な分布帰還構造(Distributed Feedback、以下DFBと略す) QCLのセンシング性能の評価のために、これを光源として中赤外領域でのガスの吸収スペクトルを測定し、ガスセンシングを行った。測定には多重反射型ガスセルを用い、DFB-QCLの印加電流を掃引することで波長掃引を行った。初めに大気をサンプルとした測定では、大気中の水とメタンの吸収を観測でき、シミュレーションともよく一致した。次に既知の濃度のメタンをサンプルとし、装置の感度を評価した結果、DFB-QCLの消費電力は3 W以下の低消費電力でありながらメタンに対して17 ppbの高感度なセンシングを達成した。
1.6 MB
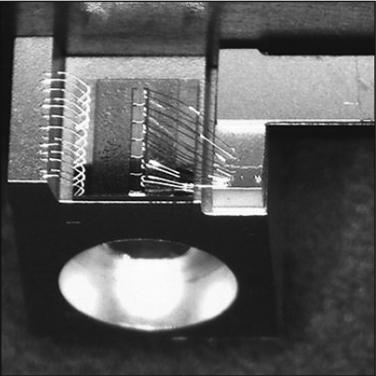
1.6 MB
データトラフィックの爆発的な増大に対応するために、400 Gbit/sを超える超高速光通信システムの開発が進められている。光通信においてレーザや光変調器を駆動するドライバICには高速、かつ高耐圧特性を有するInP-DHBTが適している。一般的に、高速化に対応するためにはInP-DHBTには大電流密度での動作が要求される。しかしながら、そのような過酷な動作条件はInP-DHBTの自己発熱による特性劣化を早め、寿命が短くなるという問題がある。そこで今回、放熱性の高いSiC基板上にInP-DHBTを作製することでデバイス温度の上昇を抑制する試みを行った。SiC基板上へのInP-DHBT作製には常温かつ低加圧で金属接合が可能な原子拡散接合を用いた。試作したデバイスにおいて、SiC基板の高放熱性により40%以上の大幅な熱抵抗低減効果を確認した。
1.9 MB
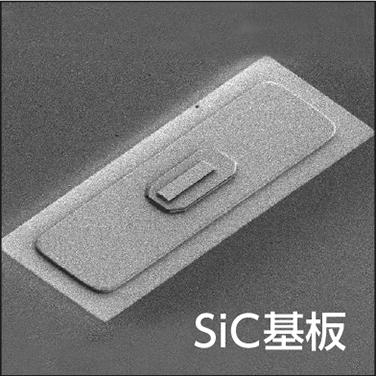
1.9 MB
当社はフッ素樹脂の中で最も耐薬品性に優れるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の延伸加工による多孔質化技術を世界に先駆けて開発し、ポアフロンの商品名でフィルター製品をはじめとする多くのPTFE多孔質膜製品を供給している。それらの中で、耐薬品性が必要とされる、酸やアルカリなどの化学薬品のろ過にはPTFE多孔質膜フィルターが必要不可欠である。特に半導体や液晶パネルなどの電子部品の製造工程で用いられる化学薬品には、電子部品の加工プロセスの微細化に伴って、より高い清浄度が求められるようになってきており、従来よりも微小孔を有するPTFE多孔質膜の要求が高まっている。当社では、従来の延伸加工に代わる新規のPTFE多孔質化技術によりナノサイズの微小孔を有するPTFE多孔質膜を開発したので報告する。
3.6 MB
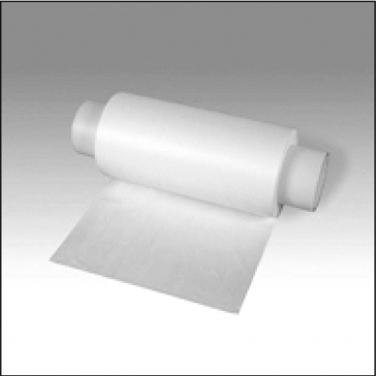
3.6 MB
ワイドギャップ半導体であるシリコンカーバイド(SiC)はシリコン(Si)に比べて絶縁破壊電界、電子飽和速度、熱伝導率が大きい、という優れた特性を持つことから、次世代のパワーデバイス材料として期待されている。従来のSiを材料とした場合、スイッチング損失の小さい金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)では、鉄道車両や電力設備などのインフラ用途で需要の高い3,300 V耐圧を実現するのが困難なため、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)やPN接合型ダイオード(PND)が広く用いられている。我々は、SiCを用いた3,300 V耐圧のMOSFET、ショットキーバリアダイオード(SBD)及びこれらを搭載したモジュールを作製した。 SiCパワーモジュールでは、高速スイッチングのため、モジュール内部インダクタンスで発生する過大電圧が懸念される。内部インダクタンスを等価回路で表すことはその解析に有効である。筆者らはモジュール全体を表現する新たな等価回路を開発したのでここに報告する。
1 MB

1 MB
固体酸化物燃料電池(SOFC)の集電体には高い耐酸化性とガスの拡散性が求められている。我々が開発しているニッケル-スズ(Ni-Sn)セルメットは耐酸化性に優れ、かつガス拡散性が良好な3次元構造を有している。そこで今回NiやNi-SnセルメットのSOFC用集電体への適用可能性を検討するため、長時間の耐酸化性、高温での電気抵抗率、集電体へ適用し試作したSOFCの発電特性、を評価した。その結果、空気極集電体については、今後ニーズが増すと推測される600℃以下の中温域で動作するSOFCへの適用が可能と考えられた。中でもSnを10wt%含有したNi-Snセルメットは600℃、3000時間後の酸化重量増加量は0.14 mg/cm2、電気抵抗率は0.017 Ωcm2と良好な特性を有し、試作したSOFCでも比較品のPtメッシュと同等な出力を確認できた。また燃料極集電体への応用は、圧縮挙動、試作SOFCでの評価により、特に800℃の高温域でNiセルメット、Ni-Snセルメットは好適であると思われる。
2.6 MB
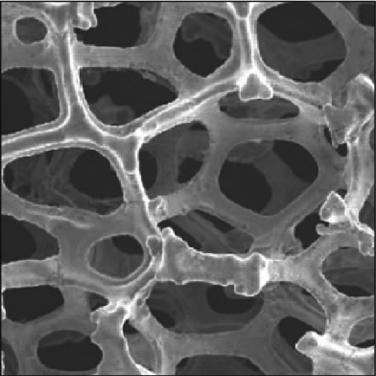
2.6 MB
近年、自動車の安全安心制御や家電の省エネ化などのニーズの高まりに対して、モータの高効率化や磁気センサの高感度化といった要求が強くなっている。モータやセンサの性能を大きく左右する永久磁石材料は、磁石性能そのものの改良に加えて、部品点数の削減や磁気回路設計の自由度向上などに寄与する部品の複雑形状化、エンジン周りへの対応や長寿命化に寄与する耐熱・耐環境性の改善による改良が重要視されている。既に、形状の複雑化に有効な磁石として、磁石粉末(Nd(ネオジム)-Fe-B)を樹脂で固化し、複雑形状をネットシェイプ成形できる希土類ボンド磁石があるが、樹脂の耐熱・耐環境性に課題があり必ずしも要求に対し十分ではない。当社では、磁石粉末自身に塑性変形性を付与することによって、樹脂を用いず、且つ、複雑形状のネットシェイプ成形が可能な新たな磁石製造工法を確立し、優れた耐熱性を示すバルクNd-Fe-B磁石を開発した。
3.4 MB

3.4 MB
波長3-5 µmの中赤外帯では、有害ガス検出や地球観測衛星向けとして高感度で応答速度の速いセンサが期待されており、近年そのセンサ材料として理論的に優れた性能を有するInAs/GaSb超格子が注目されている。InAs/GaSb超格子は分子線エピタキシー法(MBE)による開発例はあるが、生産性に優れる有機金属気相成長法(OMVPE法)による報告は少ない。今回我々は、OMVPE法による高品質な100周期InAs/GaSb超格子の成長に成功した。これを用いたセンサを作製したところ、整流特性が得られるとともに暗電流密度として印加電圧-50 mV、素子温度77 Kにおいて2×10-4 A/cm2を得た。また、波長3~5 µmにて感度が得られ、波長3.5 µmにおいて量子効率15%, 20 Kを観測した。これらの結果より、今回我々が成長したInAs/GaSb超格子は高性能な中赤外帯検出器の実現につながるものと期待できる。
1.5 MB
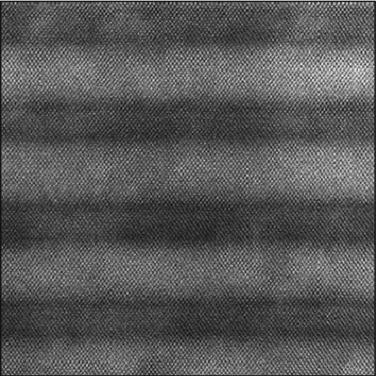
1.5 MB
半導体エレクトロニクス、情報通信技術など多岐に亘る工業分野において、デバイスや材料の構造微細化が急激に進展している。これに伴い、特性制御のための添加元素に着目した、ナノスケールの二次元分布の可視化技術開発が強く求められている。我々は、電子線マイクロアナリシス(EPMA)において、分析試料を薄片化すると試料内の電子線拡散が抑制でき、分析時の空間分解能が向上することを明らかにしてきた。例えばインジウムガリウムリン(InGaP)の分析では、約100 nmまでの薄片化により分解能を180 nmから40 nmまで向上できる。しかし、試料を薄片化すると分析体積が減少するため、検出感度の低下が避けられない。今回、試料の薄片化に加え厚さを制御することによって、必要な感度を確保した上で十分な分解能を有する分析手法を確立した。
2 MB

2 MB
近年のCO2排出量増加による地球温暖化の問題に対応するため、自動車業界ではハイブリッド自動車などの電動車両の開発が活発になっている。ハイブリッド自動車は内燃機関に加え、主にバッテリ、インバータ、モータからなる電気駆動系を備え、その時々の走行状態に適した駆動系を選択して、燃費を大きく向上させている。パワーケーブルは、インバータと駆動用、発電用の2基の3相交流モータとを接続するケーブルである。モータを駆動する大電流に対応した断面積の大きい太物電線を、それぞれのモータに3本、合わせて6本用いており、両端にインバータ、モータに接続するコネクタを有している。車両の軽量化やシステムの小型化のため、常に小型、軽量化が求められてい る。当社グループの住友電装(株)、(株)オートネットワーク技術研究所は、新たに6相一括モールド技術、銅布シールドを採用したパワーケーブルを開発した。本製品は、15年12月に発売されたトヨタ自動車(株)のプリウスに採用された。
0.6 MB
近年のCO2排出量増加による地球温暖化の問題に対応するため、自動車業界ではハイブリッド自動車などの電動車両の開発が活発になっている。ハイブリッド自動車は内燃機関に加え、主にバッテリ、インバータ、モータからなる電気駆動系を備え、その時々の走行状態に適した駆動系を選択して、燃費を大きく向上させている。床下パイプハーネスは、バッテリとインバータの間で大電流をやりとりするケーブルであり、飛び石などからの保護機能、電磁ノイズを遮断するシールド機能を備えたアルミパイプに電線を通し、端末にはインバータに接続するコネクタを有している。当社グループの住友電装(株)、(株)オートネットワーク技術研究所は、新たにPNコネクタ*1、アルミ電線を用いた床下パイプハーネスを開発した。本製品は、15年12月に発売されたトヨタ自動車(株)のプリウスに採用された。
1 MB
省エネ法の下、エネルギー使用の合理化等の促進のため、蛍光灯に代わりLED照明灯の普及が進んでいる。今回、LEDの特徴である長寿命、低消費電力を最大限に活かし、過酷な環境下で耐久性を求められる、とう道(通信ケーブル布設用トンネル)用に最適なLED照明灯の販売を本格的に開始した。
0.9 MB
近年、機械加工現場においては、一層の納期短縮、加工コストの低減、更には省人化(自動化、無人化)が求められるようになっている。それに伴い、切削工具に対しては高能率化や長寿命化に加えて、切削加工時に突発的なトラブルを起こさない工具寿命の安定化に対する要望が従来にも増して強くなっている。そこで当社ではこのような要望に対し、寿命の安定性、信頼性を著しく向上させた新CVDコーティング技術「Absotech Platinum」を適用した「AC8025P」を開発し、販売を開始した。
1.2 MB
1920年代、当社大阪製作所の電線工場では、高速な伸線設備導入により、生産性の大幅な向上が期待されていた。しかし、伸線工程に於ける銅の加工点であるダイス※1の材料は鋼であった。このため耐摩耗性が低く、設備の高速化に対応できず、急速な摩耗によってダイスが短寿命化するという新たな問題に直面した。頻繁に設備を止めてダイスを交換しなければならず、折角高速化した設備の稼働率を狙い通りに向上させることができなかったのである。一方、電球メーカーであるドイツのオスラム社にて、タングステンカーバイト(WC)を硬質相とし、コバルト(Co)をバインダーとした複合材料である超硬合金が1923年に発明された。WC粉末にCo粉末を一定割合で混ぜてプレス成形し、高温で焼結する粉末冶金製品の誕生である。1927年には同じくドイツの鉄鋼メーカーであるクルップ社が、WIDIAのブランドで超硬合金を発売し、粉末冶金製品が上市されることとなった。
1.2 MB

1.2 MB
近年、世界的な環境意識の高まりから、自動車分野ではハイブリッド車に代表されるように省燃費車が広く普及し始め、エネルギ分野では、太陽光や風力等を活用した発電機の普及が推し進められている。これらの機器には、電動機構や電源装置が必須であり、それらに用いられる中核部品のひとつに、鉄心と銅巻線からなる電磁変換コイルがある。その磁心材料として、一般的には電磁鋼板やフェライト等が知られているが、各種機器の小型化や高効率化、高出力化を実現するために、当社では交流磁気特性と形状自由度に優れた圧粉磁心を開発し、ハイブリッド車のリアクトル用途等で実用化してきた。圧粉磁心は、絶縁被覆された磁性粒子をプレス成形して作製する材料であり、優れた磁気特性を得る観点から、磁性粉末の組成制御や高純度化、絶縁膜材料とその被覆方法、ならびに潤滑剤やバインダ等の添加剤を、用途に応じて開発することが重要な要素である。これらの技術を活用して当社が開発した純鉄系および合金系(Fe-Si-Al)磁心は、優れた磁気特性を示し、モータやチョークコイル用途に適している。
3.2 MB
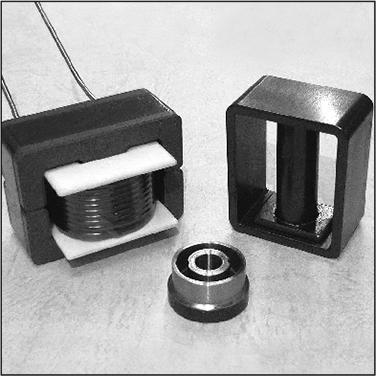
3.2 MB
1928年に当社ではじめて線引きダイス用として製品化された超硬合金はその後、切削工具用材質として大きく進化を遂げてきた。鋼切削に適合するようにチタン炭化物を添加する技術に始まり、コーティング母材として高靱性を発揮させるためのエース層超硬母材技術、ユーザーニーズである高能率加工に応えるZr添加超硬母材技術へと進化している。またジェットエンジン材料の開発から生まれたチタン系硬質相を主成分とするサーメット工具は被削材である鋼との反応性が低く、美しい仕上げ面が得られることから、切削工具の材質の 1つとして独自の進化をしてきた。そもそも靱性に課題のあったサーメットは、窒素添加技術により合金強度を飛躍的に向上させ、またその後開発された表面硬化技術により耐摩耗性と靱性の両立を図ることで切削性能の向上を果たしてきた。本報ではイゲタロイ®における超硬合金、サーメットの進化の歴史について述べる。
2.3 MB
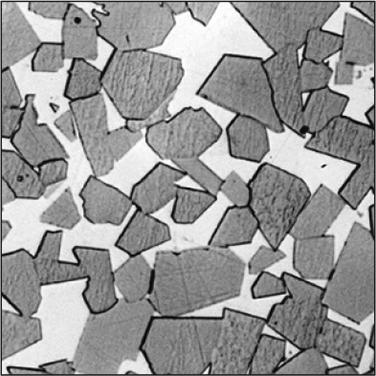
2.3 MB
我々は、非常に硬くて強靭な革新的超硬質材料:ナノ多結晶ダイヤモンドとナノ多結晶cBN(cubic Boron Nitride)を開発した。超高圧高温下での直接変換焼結法と呼ばれる独自の新製法により創製した、従来の焼結体や単結晶とは全く異なる形態の新材料である。非常に微細な粒子が、バインダー(結合材)や介在物なしに極めて強固に直接接合しているため、非常に高い硬度と強度を同時に合わせ持ち、優れた耐熱性や高精度性も備える画期的な硬質材料である。ナノ多結晶ダイヤモンドは非鉄金属や硬質セラミックス、超硬合金の加工、ナノ多結晶cBNは鉄系金属材料の加工用の精密切削工具材料あるいは耐摩工具材料として非常に高いポテンシャルを有す。これらは、各産業分野における昨今の強い市場要請である加工の高速化、高能率化、高精度化に十分応えうる究極の硬質材料であり、今後大きな活躍が期待される。
2.3 MB

2.3 MB
焼結製の内接歯車オイルポンプロータは、自動車用オイルポンプの基幹部品としてエンジン潤滑用や自動変速機の油圧発生用、ハイブリッド車の変速機潤滑用途など幅広く利用されている。1980年代当時、自動車の燃費向上対策としてオイルポンプの小型・軽量化のニーズの高まりから、当社独自設計歯形を有するパラコイド®ロータを開発・実用化して以降、燃費規制や排気ガス規制を背景に、高まるオイルポンプの損失低減要求に対応すべく、メガフロイド®ロータ、ジオクロイド®ロータといった新歯形を有するオイルポンプロータを開発・実用化してきた。今回、高効率と静粛性を兼ね備えた最新の開発歯形であるパラコイド®EXロータに至るまでの開発事例・動向を紹介する。
4.5 MB

4.5 MB
粉末冶金法は粉末を金型で圧縮して成形体を作製し、それを焼結することで鋳鉄と同等の強度を得ることが可能であり、形状の自由度は高く、完成品、もしくは完成品に近い形状(ニアネット形状)を得ることができる製法である。このようにニアネット形状で製品を作製することで、鋳鉄からの削り出し品と比較して安価に製造できることが可能で、鋳造切削品のVA※1としてその市場を拡大してきた。 しかしながら粉末冶金法では二次元での形状自由度は高いが、高さ方向(Z方向)の形状は金型からの抜出の制約があり、形状が限定されてきた。我々は粉末冶金法での金型成形での造形技術に接合という技術を加えることで、金型成形の二次元での形状自由度の利点を生かしつつ三次元的にも形状の自由度を持たすことに成功した。本稿では現在量産している接合製品の特徴を示すと共に接合の保証方法についても詳しく紹介する。
1.8 MB
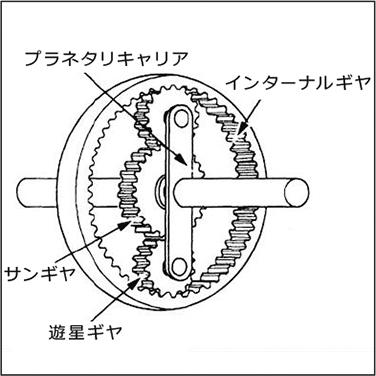
1.8 MB
ダイヤモンド切削工具は、その優れた切れ味・耐摩耗性を生かし非鉄金属加工の様々な用途で使用されている。その中でも単結晶ダイヤモンドを用いる超精密ダイヤモンド切削工具は光ディスクのピックアップレンズやスマートフォンカメラレンズなどの樹脂レンズ金型、液晶パネルの光学プリズム金型、レーザ反射鏡など光学部品の超精密加工に用いられている。一方、超精密加工技術としては1nmで制御が可能な5軸の超精密加工機が現れ、これらに対応するため超精密ダイヤモンド切削工具も高精度化、微細化が求められている。本稿では合成ダイヤモンド単結晶 スミクリスタル®を用いた超精密ダイヤモンド切削工具 UPC®の特徴を通じて開発の経緯などを紹介すると供に、UPC®を用い超精密加工されている住友電工ハードメタル㈱の光学部品についても紹介する。
2.9 MB
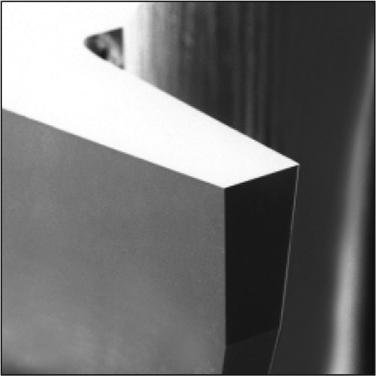
2.9 MB
弊社は1970年代後半からダイヤモンド焼結体やCBN焼結体をベースとした切削工具を開発し、世界中に提供してきた。1977年には、焼入鋼切削用CBN焼結体、スミボロン®BN200が開発された。焼入鋼切削は世界初の技術であり、この後、用途を拡大して世界中に拡がっていった。1980年代には欠損が問題となる断続切削用の材質、BN250、BN300が開発され、その適用領域を拡大した。1990年代は転削工具への展開が加速し、鋳鉄の超高速加工用フライス工具や、焼入鋼の転削加工を実現するエンドミルが開発された。さらに、2000年代にはPVD法でセラミックス膜を被覆したコーテッドCBN工具が開発され、工具の耐摩耗性や面粗度の安定性が飛躍的に向上し、高精度加工の領域が拡大した。このように、CBN焼結体は今後も材質や工具形状、新加工法の開発が進展し、適用領域を拡大していくことが期待されている。本稿ではこれら工具の開発の歴史について述べる。
1.5 MB
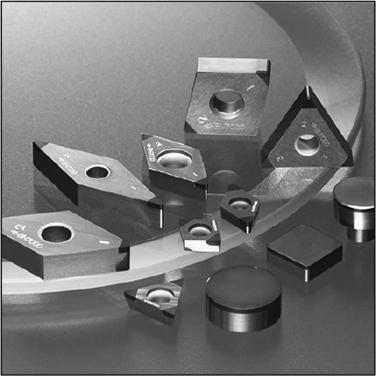
1.5 MB
住友電工スチールワイヤー㈱は、既存技術である1860MPa級PCストランドに比べ強度が1.2倍の15.7mm高強度ストランド(2230MPa級)を開発し、コンクリート構造物への普及に努めてきた。今般その技術を応用し、太径PCストランドとしてその定着システムにも適用を図り、大容量シングルストランド工法の開発に成功した。この高強度ストランドはエポキシ樹脂やポリエチレン樹脂の防食被覆加工を施すことで一般的に高強度化により懸念される遅れ破壊を防ぐだけでなく、その高い耐食性により近年のコンクリート橋に求められる高耐久化に寄与する製品である。本稿では「29.0mmプレグラウト高強度ストランドシステム」および「17.8mmECF高強度ストランドシステム」の特徴と性能について述べる。
3.4 MB
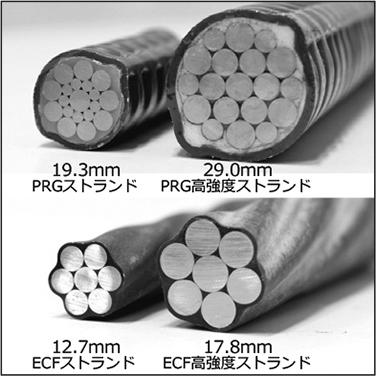
3.4 MB
高アルカリ液(6 M KOH + 1 M LiOH)を電解液とした電気化学的なボルタンメトリー還元法による銅腐食生成物の定量的な状態分析法を開発した。0.1 M KClなどを電解液とした従来法がよく用いられてきたが、二つの大きな課題があった。計測時の銅酸化物の還元順番が不明確な点、及びCu2OとCuOの分離が悪い点である。2001年に、開発法に関する最初の論文を投稿し、電解液として高アルカリ液を用いることで両酸化物を完全に分離できることを発表した。また計測過程ではCuO→Cu2Oといった熱力学的な理論に則した順番で還元することを明らかにした。引き続き、この開発法をCu2S、Cu(OH)2、緑青の評価に応用展開し、銅の大気腐食のメカニズム解明のために有用なツールであることを示した。
0.7 MB
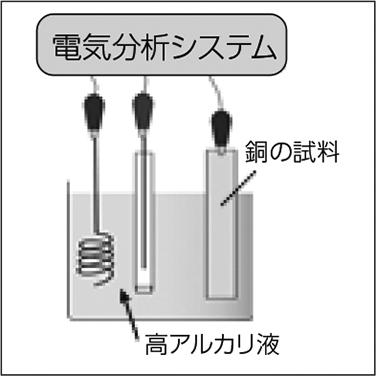
0.7 MB
フレキシブルフラットケーブル(Flexible Flat Cable:以下、FFC)※1とマザーボードなどの回路基板との接続にはコネクタが用いられているが、近年の電子機器の小型化に伴って、コネクタを使用せずケーブルと基板を直接接続する‘コネクタレス接続’のニーズが高まっている。コネクタレス接続として用いられる異方性導電膜※2は、保管管理や圧着操作が難しく、より簡便な接続部材が求められている。そこで当社では独自の導電性ペースト※3と微細印刷技術をベースとして、薄型で簡易接続可能なコネクタレス接続構造を新規に開発し、FFCと回路基板の高い接続信頼性を実現したので報告する。
2.9 MB
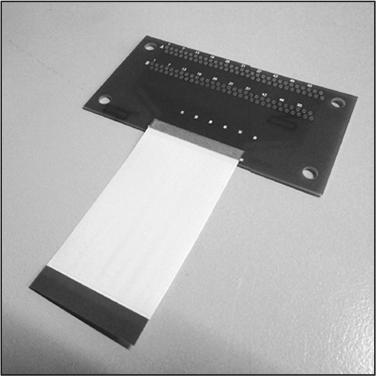
2.9 MB
広い温度範囲で動作する今までにない超小型RGBレーザモジュールを開発した。RGB各レーザチップ、フォトダイオードチップ、サーミスタ、光学部品等が熱電クーラー上に搭載され、それらが全てハーメチックシールされている。11×13×5.7mmの金属パッケージに収まり、そのパッケージから安定した高品質なコリメート光が出射される。半導体レーザ(特に赤色レーザ)の高温における出力低下が厳しいことにより今までRGBレーザモジュールの+85℃における動作は困難であったが、チップ実装により低熱容量化を行うことで熱電クーラーを使用したモジュール温度の制御が可能となり、-40~+85℃の広い温度範囲におけるモジュールの動作を実現した。温度制御は早い応答速度(4秒以下)を実現している。
2.4 MB
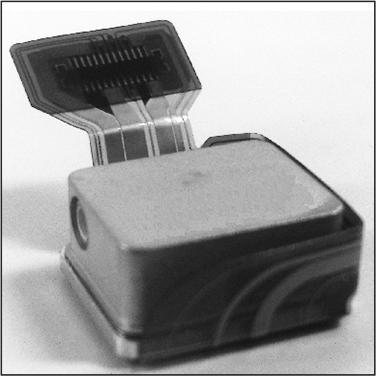
2.4 MB
集光型太陽光発電(CPV)は結晶シリコン太陽光発電(Si-PV)と比較して、単位面積あたり及び公称出力あたり大きな発電量が期待できる。これらを比較するために、CPVの展開が期待される高日射地域(モロッコ)で実証試験を行いCPVは固定Si-PVと比較して直達日射強度(DNI)が7.9kWh/m2/dayの時に単位面積あたり約2.5倍、公称出力あたり約1.3倍の発電量を得られることを明らかにした。また今回、モジュールのガラス表面への砂の堆積をさけるため、夜間ガラス面を下に向ける構造の架台を新たに開発し、砂塵の影響のある地域で砂による発電電力量低下を大幅に低減できることを明らかにした。
1.5 MB

1.5 MB
近年、プリント基板の穴開け加工に使用されるPCBドリルの小径化、長尺化が進んでいる。電子部品の小型化、高集積化により加工穴が小さくなり、また、能率向上のため加工時の基板重ね枚数が増加傾向にあるためである。これにより、穴開け加工中にドリルがたわみやすくなり、穴位置精度は低下し、折れやすくなる。そこで、それら特性低下を克服する画期的な超硬合金素材の開発が求められていた。我々は、従来製品を徹底的に調査し、改善方法を模索したところ、超硬合金の組織均質化が有効であることを突き止めた。原料選定の見直しと製造条件の最適化を行った結果、課題であった穴位置精度と耐折損性能が向上した高信頼性PCBドリル用超硬合金素材「ZF20A」の開発に成功した。
2.4 MB
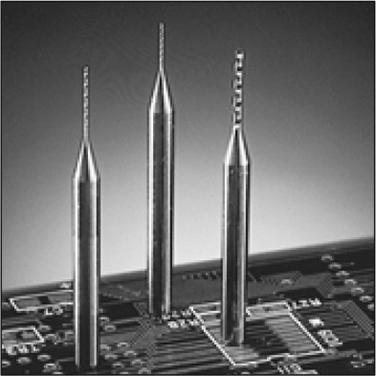
2.4 MB
ナノスケールの細孔構造を持つ素材は、化学原料やイオンの吸着などに特異な特性を持つ。ここでは、炭化物を塩素雰囲気で処理して得られるナノ構造炭素を評価した結果を示す。原料としてSiC、TiC、Al4C3を用い、1000℃以上の温度領域にて塩素雰囲気ガス処理を行うことで、ナノ多孔質構造を生成した。TiC、Al4C3由来炭素は、グラファイト構造が形成し処理温度上昇に従いサブナノ細孔の減少と結晶成長が観測された。それに対し、SiC由来炭素は、グラファイト層構造をとらず、1400℃の高温処理でもサブナノ空孔を安定的に保持できることが確認された。本手法は原料と雰囲気処理温度の調整により様々な特性の多孔質炭素材を形成することが出来、ガス吸着や電力貯蔵など様々な用途に適用することが可能である。
3.6 MB
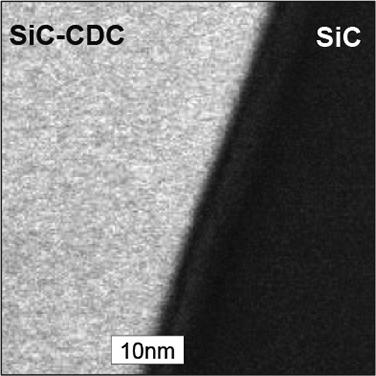
3.6 MB
近年、自動車の電子化の進展は著しく、コネクタの増加や多極化が進行している。そのため、コネクタの信頼性の確保が重要な課題となっている。高信頼の車載コネクタの開発に当たっては、実際の走行車両に搭載されたコネクタの劣化状態を知ることが重要である。そこで、本研究では実走行車両(10万キロ走行、15万キロ走行)のコネクタを回収し、端子劣化状態とその要因について調査した。その結果、端子劣化は走行距離に応じて進行しているものの、信頼性が問題となる水準には達していないことを確認した。また、回収端子の表面観察の結果から、主な劣化要因は摺動摩耗によるものと推定された。そこで、台上試験である微摺動摩耗試験との比較により、10万キロ走行に相当する微摺動試験での摺動回数の推定を行った。結果、その回数は予想よりも非常に小さく、コネクタの信頼性を十分維持できるものであった。
2.1 MB

2.1 MB
現在、光コネクタは、押圧力を付与することで光ファイバの端面同士を互いに押し付け、光ファイバ端のコア間を隙間なく面接触させる「フィジカルコンタクト」接続方式が主流である。しかし近年の多心化で押圧力の増加が大きな問題となっている。さらに、コア直径が約10ミクロンのシングルモード光ファイバ(SMF)の場合、ダストに敏感であるため端面の念入りな清掃を必要とする。当社は、レンズを用いた接続方式でこの問題を解決する技術開発に取り組んだ。レンズ方式はレンズと光ファイバ間の高精度な組立精度を要するため、従来SMFには適用困難であったが、高精度な部品成形によりSMFのコネクション技術を開発し良好な光学特性を実現した。
1.3 MB
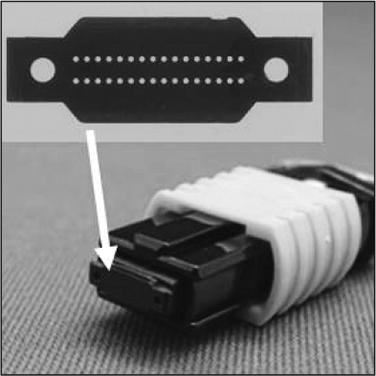
1.3 MB
Eバンド(71~86GHz)は周波数を広帯域に利用できるため、自動車レーダ(76GHz帯、79GHz帯)や携帯・モバイル通信を支える大容量バックホール用周波数帯として注目されている。これらEバンド無線機器の性能やコストは、機器を構成するデバイスはもとより、デバイスの実装形態に大きく依存する。SEDI/SEIではマイクロ波およびミリ波帯デバイスの実装を簡易化、量産化するため、3-D GaAs MMIC技術を発展させたWafer-Level Chip Size Package(WLCSP)技術を開発した。ここではこの3-D WLCSP技術を用いたミリ波帯低雑音増幅器(LNA:Low Noise Amplifier)について、従来のワイヤ実装を用いたLNAと比較しながら紹介する。
1.4 MB

1.4 MB
窒化ガリウム(GaN)は高耐圧かつ高速性に優れ、高電子移動度トランジスタ(HEMT)の材料として適している。幹線通信網のバックホールとして、広帯域・大容量の無線通信が可能なミリ波Eバンド(70~80GHz)の活用が期待されており、この用途に対応したGaN HEMTの実現を目指した。マイクロ波(~16GHz)を中心とした既存製品と比べて要求周波数が著しく高いため、周波数特性の大幅な改善が必要であった。そこで、高い相互コンダクタンスが得られるよう電子供給層の材料にInAlNを選択すると共に、周波数特性改善の要となる低容量ゲート技術の開発に着手した。ゲート容量(Cgs)を低減するために、ゲート長を100nmまで微細化して、ゲート電極をY型としたゲート技術を開発した。本技術開発により、既存製品を凌駕する0.58pF/mmの低いCgsを得て、電流利得遮断周波数は110GHzまで改善し、Eバンドをカバーする優れた周波数特性を有するGaN HEMTを実現した。
1.8 MB

1.8 MB
GaN HEMTを用いたX帯高出力・広帯域内部整合型増幅器について報告する。X帯レーダー用増幅器の固体素子化に向けて、GaN HEMT増幅器の高出力化が期待されている。我々は14.4 mmのゲート幅を有するGaN HEMTを2つ用い、入力および出力側にそれぞれ2段のインピーダンス変換器を備えた内部整合型増幅器を開発した。今回開発した増幅器は、ドレイン電圧65 Vのパルス駆動で、8.5-10.0 GHzにおいて出力電力310 W、パワーゲイン10.0 dBを得た。また、9.0 GHzにおいて出力電力333 W、パワーゲイン10.2 dBを得た。この結果はこれまでにX帯で報告されているGaN HEMT増幅器において最高の出力電力である。
1.6 MB

1.6 MB
近年、電子制御方式の機器が増加し、電流容量も増加傾向にあることから、それらの制御用スイッチにも大電流化のニーズが高まっている。これまで大電流スイッチには水銀リードスイッチが使用されてきたが、環境負荷物質である水銀の全廃にともない、水銀を用いないリードスイッチへ変更されている。しかしながらリードスイッチには、通電によるリード線の発熱が大きくなると、リード線の磁気特性が失われ、スイッチとしての機能を果たさなくなるという問題があり、大電流化が制限されてきた。当社は、リード線用の従来合金線と同様の優れた特性を有しつつ、通電による発熱を抑制し、温度が上昇しても磁気特性を失わない(高キュリー温度)コバルト-ニッケル-鉄合金線を開発した。本合金線を用いたリードスイッチは、大電流化が可能であり、自動車LED向けの制御用リードスイッチ等への適用が期待できる。本レビューでは、開発した合金線の優れた特性を紹介する。
1.2 MB
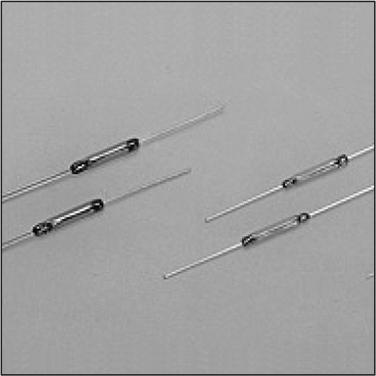
1.2 MB
ワイドギャップ半導体であるシリコンカーバイド(SiC)はシリコン(Si)に比べて絶縁破壊電界、電子飽和速度、熱伝導率が大きい、という優れた特性を持つことから、次世代のパワーデバイス材料として期待されている。従来のSiを材料とした場合、スイッチング損失の小さい金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)では、鉄道車両や電力設備などのインフラ用途で需要の高い3.3 kV耐圧を実現するのが困難なため、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)やPN接合型ダイオード(PND)が広く用いられている。我々は、SiCを用いた3.3 kV 耐圧のMOSFET、ショットキーバリアダイオード(SBD)及びこれらを搭載したモジュールを作製し、従来のSi IGBTを用いたモジュールと比較し、スイッチング損失を3分の1に低減することができた。
2.1 MB

2.1 MB
近年、分散電源の普及と 2016年度の電力自由化などのエネルギー政策に伴い、EMS(Energy Management System)が普及し、さらに、地域全体の電力需給調整とも連携が進んできている。当社は、工場向けEMS(sEMSA®)を開発し、2014年度の横浜製作所とN社製作所での実証を経て、2015年度製品化を準備中である。当社が開発したsEMSA®は、数理計画法を用いた最適な運用計画と、実時間をベースとする動的再配分制御の技術を特徴とする。さらに、デマンドレスポンス信号を全自動で最適な運用計画に取り込み、最適性を維持しつつ受電電力の引き下げが可能である。本稿では、sEMSA®の概要、および横浜製作所とN社製作所の実証結果について報告する。
4.4 MB

4.4 MB
近年自動車メーカーではCO2排出量削減に向けた車体軽量化及び、衝突安全性の向上のため、引張強度980MPa以上の超高張力鋼板の適用を拡大している。しかし、超高張力鋼板は鋼板中に炭素が多く含まれるため、現行の抵抗スポット溶接では十分な接合強度を得にくいという問題がある。一方、摩擦攪拌接合は、接合用ツールを用いて摩擦熱により被接合材同士を軟化、塑性流動させる固相接合技術であり、炭素量の多い超高張力鋼板でも高い接合強度が期待できる。摩擦攪拌接合はアルミ接合では既に実用化しているが、鋼接合ではツール寿命が短いため実用化していない。我々は、耐欠損性、耐塑性変形性、耐熱亀裂性を兼ね備えた超硬合金母材、硬度、耐酸化性に優れたPVDコーティング、高い接合強度を維持できるツール形状をそれぞれ開発、またツール摩耗を抑制するための接合条件を見出し、超高張力鋼板接合用ツールの長寿命化(~7000打点)に成功した。
1.6 MB
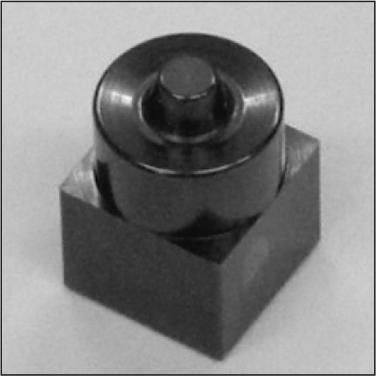
1.6 MB
切断、溶接、穴あけ等の様々な用途で活用されているレーザ加工機では、加工特性の改善や加工対象物からの反射光の除去のために、λ/4波長板(リターダ)が用いられる。従来は反射型のリターダ(円偏光ミラー)が用いられてきたが、レーザ光の伝送系設計を行う上で、入射光の偏光方位や入射角に制約があった。ZnSe製のプリズム型基板の採用と光学薄膜設計の適正化で、前述の制約のない透過型波長板を開発した。製作したZnSe製波長板の光学特性として、波長9.6µm光に対する透過率及び位相差は、それぞれ 98.0%、87.6°であり、400Wの連続発振型CO2レーザに利用できることを確認した。開発した波長板は、放射性元素であるTh(トリウム)や、RoHS規制対象元素であるCd(カドニウム)を含まないため、様々な分野での活用が期待できる。
1.6 MB

1.6 MB
近年のIT関連の半導体、精密電子部品製造において、金型に用いられる超硬材料の精密加工には、電極線から材料へアーク放電を起こし、瞬間的な高熱によって材料を局所的に溶融・除去するワイヤ放電加工が適している。加工メーカーが抱える高い顧客要求に伴い、放電加工電極線にも、高速加工、高精度、高品位といった面での要求が高まっている。住友電工スチールワイヤー㈱は、鋼芯の表面に新合金γ相黄銅を被覆した放電加工電極線「スミスパークガンマ」を開発した。新合金の優れた放電特性とそれに適した加工条件設定によって、高速加工、高精度の両立を実現した。また、当社のコア技術である高炭素鋼線の伸線加工技術を活用し、芯材である鋼の高強度化に成功した。これにより、電極線の断線を抑制しつつ、更に、加工中の張力を大きくし、線の振動を抑えることで精密加工が可能となった。本報では、スミスパークガンマの特長と性能について述べる。
2.4 MB

2.4 MB
現在印刷市場は、大変重要な転換期を迎えている。市場全体予測として年率3%前後の規模で縮小が見込まれる中、印刷関連メーカーによる新市場拡大に向けた取り組みが行われている。その中で重要視されているのは、環境対応である。従来の印刷工程では大量の有機溶剤を使用していたことから、一般社団法人日本印刷産業連合会にて2001年に各印刷法に合わせたグリーン基準の制定が始まり、VOC排出抑制に業界を挙げて取り組んでいる。こういった中、住友理工は、無溶剤インキでの印刷に適したフレキソ印刷用の凸版として、2009年から環境に優しい水現像フレキソ版を欧米で販売展開してきた。その後、高画質印刷向けに改良を加え、水現像フレキソ版「AquaGreen®」として昨年、廃液レスシステムと共に国内販売を開始した。本商品は、現在主流の溶剤製版に対し水現像製版であるため、全印刷工程でのVOC抑制が可能である。
1.6 MB
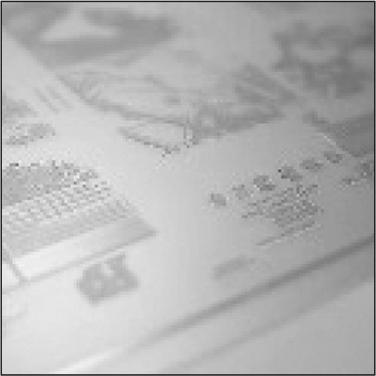
1.6 MB
次世代のクリーン電源として期待される中温型の固体酸化物形燃料電池(IT-SOFC)の開発では、高出力を実現するための高活性燃料極触媒の探索が重要課題となっている。触媒材料としてNi, Co, Feなどの遷移金属の合金が有望視されていたが、最適組成は未解明であった。また、実際のSOFCでは燃料極触媒を固体電解質に担持させる必要があり、その触媒活性への影響を解析することも課題であった。本研究では、放射光分析の1つであるX線吸収微細構造(XAFS)法を応用し、上記2つの課題の解決に取り組んだ。特に、触媒活性と高い相関を持つ「(触媒自身の)還元速度」に着目し、これをその場XAFS測定で評価した。まずSOFCに組み込む前の触媒単体を試料に用い、XAFS測定モードとして最も簡便な透過法により、組成が異なる合金触媒を網羅的に評価した。その結果、Ni系とCo系では単体金属の方が合金よりも触媒活性が高く、一方、Fe系は単体よりもNiまたはCoと合金化する方が高活性となることが明らかとなった。次に、電解質に担持させたNiなどの単体試料も同様にその場測定で評価した。その結果、電解質担持により、NiとCoでは
2.7 MB
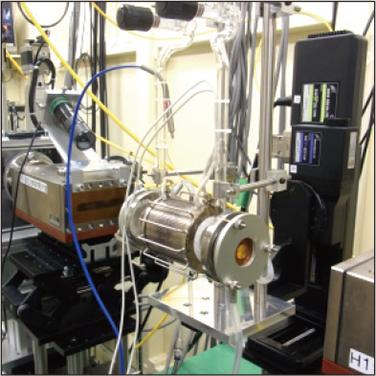
2.7 MB
近年、エレクトロニクス機器の軽薄短小化、高機能化は益々進展し、フレキシブルプリント回路基板(Flexible printed circuit: 以下、FPC)にも更なる薄型、ファインピッチ化が要求されている。FPC薄型化、ファインピッチ化のキーとなる層間接続技術について、従来のスルーホールめっき法に対して、当社独自のナノ導電ペーストを用いたペーストビア法を開発した。スルーホールめっき法で不可避の銅厚みの増加なく層間接続部を形成できるペーストビア法により、薄型化、ファインピッチ化が可能となり、既に量産適用を開始している。本稿ではこの新しい層間接続技術「ペーストビア接続技術」について報告する。
2.4 MB
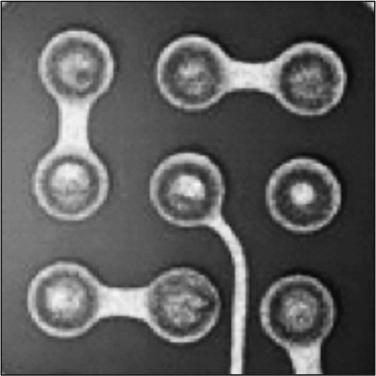
2.4 MB
"ワイヤレス給電モジュールは、制御基板とアンテナで構成されている。従来、アンテナには巻線コイルが使われており、柔軟性がなく、小型化する機器内部での設計では制約となる。そこで、当社独自の立体配線技術の導入により、業界で初めて、巻線コイルをフレキシブルプリント基板(以下、FPC)に置き換えた給電モジュールを開発した。これにより、柔軟性が向上、さらに小型化・薄型化を実現しているのである。また今回開発した製品により、電子機器の高性能な設計やデザインが可能になったほか、防水やコードレス化など機能性の向上にも貢献する。 本製品の使用分野は、防水防塵対応が求められるウェアラブル端末、コードレス化へのニーズが高いヘルスケア機器、産業機器など、ますます小型、軽量化が求められる分野を想定している。"
1.3 MB
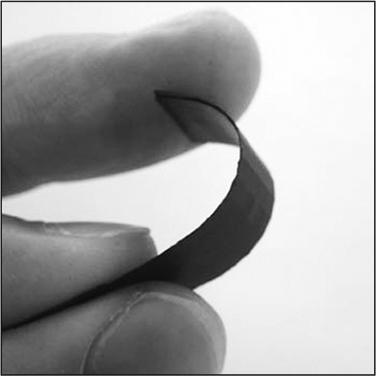
1.3 MB
近年、環境への配慮、快適化などからハイブリッド自動車の普及や、自動車の高機能化により、搭載される電装機器の増加が急速に進んでいる。このような自動車では静粛性も求められており、車両の隅々まで吸音材が搭載され、特にハイブリッド車や高級車には高性能吸音材の採用事例が増えてきている。一方、電装機器の増加に伴い、自動車工場での管理部品点数は増加しており、部品点数削減としてモジュール化による機能統合が図られている。我々は自動車組立工場での管理部品点数削減、作業工程の削減を実現させるため、ワイヤーハーネスと吸音材とのモジュール化技術を開発し、大手自動車メーカーでの採用を実現した。
1.6 MB
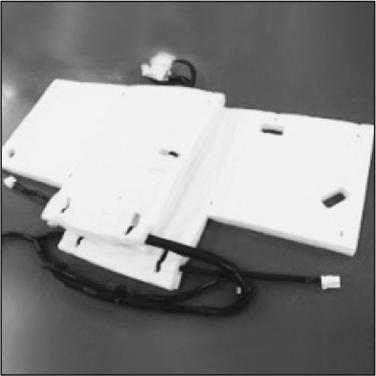
1.6 MB
今回、当社初の製品群となる、ハイブリッド車向け電池配線モジュールを開発・量産化した。またこれが、本田技研工業㈱のアコード/フィット ハイブリッド最新モデルに採用され、搭載された。電池配線モジュールはハイブリッド車の動力源となる高圧バッテリーのセル間を直列に接続する機能を持つと同時に、それらの電圧を検知するための端子/ハーネスを内蔵した部品である。ハイブリッド車以外の環境対応車(PHEV, EVなど)でも、概ね、同様の部品が必要とされている。基本的な要求性能は、安全な電気的接続と周囲の導電部材との絶縁であるが、当社開発品は、さらに顧客での作業性および汎用性を向上させたものとなっている。その特長について紹介する。
1.8 MB
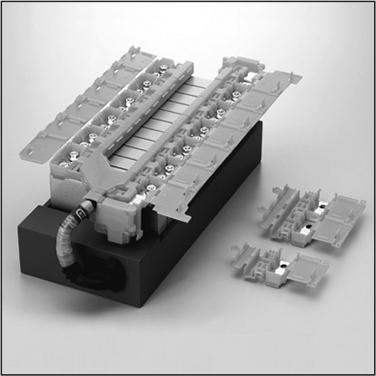
1.8 MB
指数関数的に増加するインターネットトラフィックを支えるため、デジタルコヒーレント通信技術を活用した大容量伝送システムが実用化されている。このような伝送システムでの課題は、光信号対雑音比(OSNR)の改善である。このため、伝送用光ファイバには伝送損失の低減ならびに実効断面積(Aeff)の拡大が要求されている。本報告では、波長1550 nmにおける伝送損失が0.149 dB/kmと、従来の世界記録を11年ぶりに更新する純シリカコアファイバ(PSCF)の試作結果について述べる。さらに、累積25,000 kmでの平均の伝送損失が0.154 dB/kmという極低損失を有するZ-PLUS Fiber® ULL(Aeff=112 μm2)およびZ-PLUS Fiber® 130 ULL(Aeff=130 μm2)の開発に成功したので、その結果を紹介する。これらの光ファイバ性能指数は、今まで報告されてきた光ファイバのなかで最良値を有しており、長距離・大容量のデジタルコヒーレントシステムに最適な光ファイバであると考えている。
1.4 MB

1.4 MB
世界各国で光アクセス網の構築が急速に進む中、融着接続機のユーザ層は先進国から新興国に拡大しており、あらゆる環境下で容易に取り扱える作業性、保守性に優れた融着接続機が求められている。このような多様化するニーズに応えるために開発した新型コア直視型融着接続機TYPE-71C+は、従来対比で体積43%の小型化、重量34%の軽量化を実現すると同時に、耐環境特性の向上に成功した。融着接続と加熱補強の合計時間は従来対比で55%短縮の20秒を達成し、作業時間の大幅短縮を実現した。また業界で初めて融着接続機に無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で融着接続機を管理する「SumiCloud™」システムを開発した。
2.1 MB

2.1 MB
光通信伝送量の飛躍的な増大に対応すべく、多値変調方式を活用したデジタルコヒーレント光伝送技術が注目され、既に幹線系への導入が開始されている。今後のメトロ系への展開に向けては、光通信システム機器への高密度実装のために各光部品の小型化が望まれている。我々は、InP系材料を用いた多値変調素子の開発、リニアドライバICの開発を行った。更に、多値変調素子、4個のリニアドライバIC、偏波多重光学部品を内蔵した多値変調器サイズを34.0×16.5×6.0mm3にまで小型化し、224Gbit/s DP-16QAM変調動作に向けてLiNbO3系変調器と同等の特性を実証した。
1.9 MB
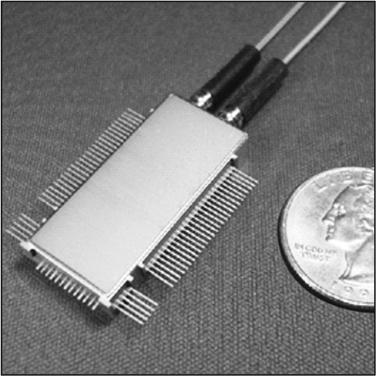
1.9 MB
高速・大容量通信の普及にともない、業界標準規格に基づいた小型な、40Gbit/s用光トランシーバであるQSFP+や、100Gbit/s用光トランシーバであるCFP4に搭載可能な、小型光受信モジュールの開発が求められている。当社は2012年にモジュール内に光分波器を集積し、QSFP+に搭載可能な小型40GBASE-LR4用光受信モジュールを開発した。今回、製品ラインナップを充実させるべく、基本設計を共通展開することで従来と同形状な、QSFP+に搭載可能な40GBASE-ER4用光受信モジュール、及びCFP4に搭載可能な100GBASE-LR4用光受信モジュールを開発した。これらの光受信モジュールは、要求仕様に対して、目標を満たす良好な分波特性、最少受信感度が得られていることを確認した。本稿では、今回開発した小型光受信モジュールの設計と代表特性を紹介する。
2.1 MB
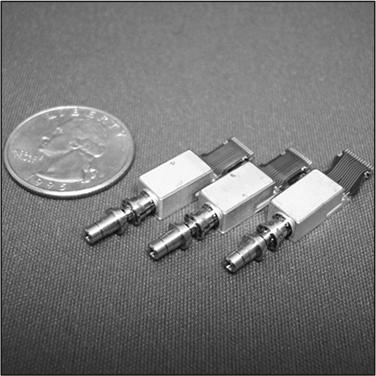
2.1 MB
伝送速度高速化の要求に応える100Gbit/s光トランシーバ向けに、2種類の25Gbit/s光送信モジュールを開発した。1つは電界吸収型変調器集積レーザを駆動するための社内製ドライバICを内蔵したもので、もう一つはドライバICを内蔵していないものである。これら両方の製品を揃えることで、ユーザは光トランシーバの構成に合った光送信モジュールを選択することができる。これらの光送信モジュールは、フレキシブル基板を持ったLCレセプタクル型送信用小型光デバイス(TOSA)であり、良好な変調特性、低消費電力、長期信頼性を示している。本稿では25Gbit/s光送信モジュールの構造や特性などについて示す。
1.4 MB

1.4 MB
我々はワイドバンドギャップ半導体である炭化珪素(SiC)を用いて、従来の平面型構造に対して1/3以下の低損失化を可能とする、V溝形状のトレンチ構造を有した金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)の開発を進めている。トレンチMOSFETは、従来開発されている平面型のDouble Implanted MOSFET(DiMOSFET)特有の電流狭窄抵抗がなく、低損失化に有利であるため、SiC MOSFET構造の主流となりつつある。反面、トレンチ底部の電界集中によりゲート絶縁膜が破壊されやすい問題がある。我々は、埋込みp型領域を用いた電界集中緩和層を導入することにより、トレンチ底部のゲート絶縁膜破壊を抑制し、さらにトレンチ側壁として高移動度の{0-33-8}面をV溝型に形成することでSiCの材料物性限界に近い低オン抵抗と高耐圧が得られている。本開発では、V溝型SiCトレンチMOSFETを作製し、基本特性の評価を行うと共に、スイッチング損失とゲート絶縁膜信頼性を評価することにより実用性の検証を行った。
1.6 MB
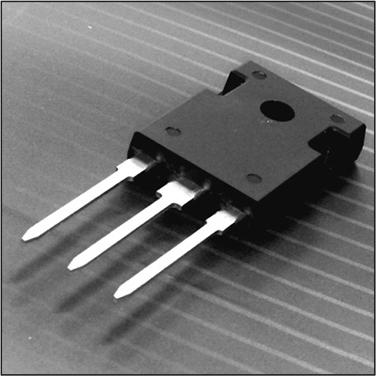
1.6 MB
"我々はワイドバンドギャップ半導体である炭化珪素(SiC)を用いて、従来の平面型構造に対して1/3以下の低損失化を可能とする、V 溝形状のトレンチ構造を有した金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)の開発を進めている。トレンチMOSFETは、従来 開発されている平面型のDouble Implanted MOSFET(DiMOSFET)特有の電流狭窄抵抗がなく、低損失化に有利であるため、SiCMOSFET構造の主流となりつつある。反面、トレンチ底部の電界集中によりゲート絶縁膜が破壊されやすい問題がある。我々は、埋込みp型領域を用いた電界集中緩和層を導入することにより、トレンチ底部のゲート絶縁膜破壊を抑制し、さらにトレンチ側壁として高移動度の{0-33-8}面をV溝型に形成することでSiCの材料物性限界に近い低オン抵抗と高耐圧が得られている。本開発では、V溝型SiCトレンチMOSFETを作製し、基本特性の評価を行うと共に、スイッチング損失とゲート絶縁膜信頼性を評価することにより実用性の検証を行った。
1.9 MB
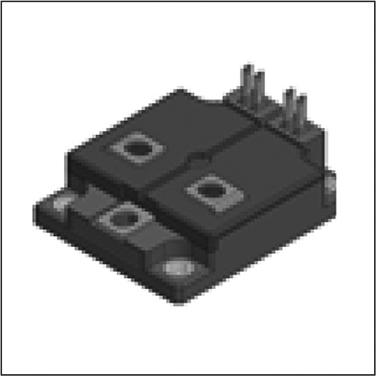
1.9 MB
近年自動車産業では新興国へのライン移管が加速し、ラインの無人化や少人数でラインを運用する場合が増加しているため、切削工具に対して『寿命安定化と長寿命化』の強い要求がある。今回この要求に応えるため、焼入鋼加工用コーテッドスミボロン® BNC2010とBNC2020を開発した。BNC2010は耐境界摩耗性を改善しており、面粗度規格の厳しい高精度加工においても長寿命化を達成できる。BNC2020は耐欠損性とコーティングの耐剥離性を改善しており、焼入鋼の連続から中断続までの様々な加工で寿命安定化と長寿命化を実現する。本報ではBNC2010とBNC2020の特長と性能について述べる。
3.1 MB
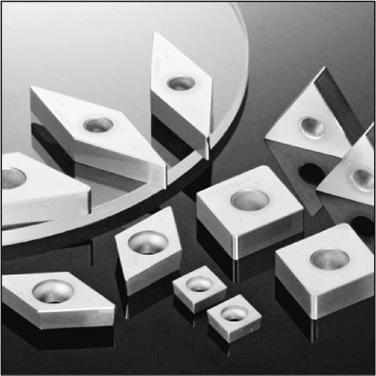
3.1 MB
近年、環境への負荷が低く、かつリサイクル性に優れた材料であるステンレス鋼の需要量が増加している。しかし、ステンレス鋼は高能率・安定加工が困難なことから「難削材」の一つに分類される。当社はステンレス鋼加工における様々な課題を解決するため、新CVD コーティング技術「Absotech Platinum®」を適用した「AC6030M」、新PVDコーティング技術「Absotech Bronze®」を適用した「AC6040M」と粗加工用ブレーカ「EM型」を開発した。「AC6030M」は高い耐摩耗性と耐チッピング性を有する一般加工用材種で、「AC6040M」は優れた耐欠損性を有する断続加工用材種である。新しい材種と新ブレーカにより、幅広いステンレス鋼加工ユーザーの要求を満たすことができ、加工コスト削減を可能とした。
3 MB
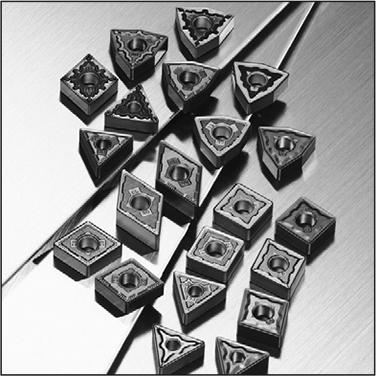
3 MB
"近年の世界的な環境への関心の高まりにより、環境負荷の小さいHEV(Hybrid Electric Vehicle)、PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)等の需要が高まっている。本製品はHEV やPHEV に搭載される自動車モータ駆動システムの昇圧コンバータに搭載されるリアクトル用圧粉コアである。リアクトル用圧粉コアは、従来の電磁鋼板コアに対して高周波特性に優れ、また等方的な磁気特性を活かした3次元磁気回路設計を行えることにより、リアクトルの小型・軽量化に期待されている。本開発では、鉄基軟磁性粉末として磁束密度が高く小型化に有利で経済性にも優れた純鉄粉を選定し、粉末粒径の最適化、圧粉磁心材料の特性を最大限発揮する製品形状の検討、またレーザー加工による表面改質方法の開発を行うことで、これまで電磁鋼板が用いられていた車載用リアクトルコアの圧粉コア化に成功すると共に、従来リアクトルに比べて同一性能で約10%の小型・軽量化を達成した。
2 MB

2 MB
サンドポニックスは、土からの脱却と温室の導入という現在の太陽光利用型植物工場に通じる理念に基づき、世界に先駆け1970年代に開発された当社独自の作物栽培システムである。サンドポニックスは当初より生産物の優れた食味において競合する他の栽培システムに対し優位性を保ってきたが、最近になりシステムが改良され、簡易な給水管理と設備費用の低減、さらなる食味向上が可能となった。最も市場性のある野菜であるトマトをモデル作物としてサンドポニックスで栽培したところ、ボリュームがありかつおいしいと評される適度な甘みをもつ従来にないトマトの生産に成功した。サンドポニックスは国内外の高品質作物需要に応えうる作物栽培システムとして期待される。
1.9 MB
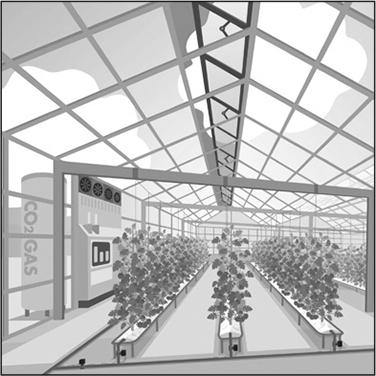
1.9 MB
地球温暖化防止のため日米欧中での自動車燃費規制は2025年まで強化の一途をたどる。 燃費規制・基準に適応するためには従来のエンジン効率向上、空気抵抗の低減、軽量化等の技術では限界があり、自動車会社は各種の低燃費化技術の中から費用対効果で採用システムを模索中である。日米欧の先進国ではHEVが普及、日本の販売比率は約40%であるが、自動車販売を牽引する新興国では高価なHEVは普及困難であり、更に2018年より米カリフォルニア州の無公害車規制(ZEV規制)の対応車からHEVが外れる等の理由によりアイドルストップ(ISS)+回生、トルクアシストの採用が増加する。
0.4 MB

0.4 MB
最近、急速に普及しているHEVにおいて、その良好な燃費性能を生み出すハイブリッドシステムは、メイン機器である高圧バッテリやインバータ、モータを高圧ハーネスで接続して構成されている。それら高圧ハーネスのうち車両床下にレイアウトされている床下ハーネスには、走行中の飛び石等による外傷からの保護機能と電磁ノイズを周囲に与えないシールド機能が求められ、従来ハーネスでは樹脂プロテクタによる保護と編組線による電磁シールドを行っている。2005年には本田技研工業㈱のHEV向けに、保護とシールドの一体化を狙ってアルミパイプを使った高圧アルミパイプハーネスを開発した。今回、その特長について紹介する。
1.6 MB
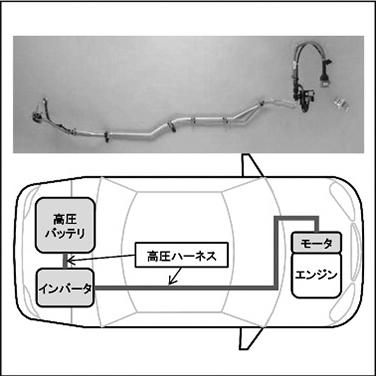
1.6 MB
CO2排出規制等で着目される電気自動車やハイブリッド車は、通常の12V系回路とは別に高電圧・大電流回路が必要であり、当社ではこれらに対応したワイヤーハーネス(以下、高圧ハーネス)を開発・製造している。高電圧・大電流回路では通常の12V系回路との電磁両立性(EMC: Electro-Magnetic Compatibility)のため、電磁シールド(以下、シールド)技術は高圧ハーネス開発の上で重要課題となっている。本稿では、シールド特性の測定手法として欧州で主流となっている伝達インピーダンス法による測定系構築について紹介する。また、欧州の測定手法による評価においてもアルミパイプハーネスはシールド特性に優れることを明らかにしたので、その内容についても報告する。
2.6 MB

2.6 MB
近年、環境への配慮、省エネ志向、原油高騰化などからハイブリッド自動車、電気自動車など自動車の電動化が急速に進んでいる。このような電動化した自動車をさらに普及させていくためには、電動化するためのシステムの小型・軽量化が必要である。一方、ガソリン車並みの走行性能、加速性能を実現するため、システムの高電圧化も必要である。そこで、バッテリ電圧を昇圧するためのコンバータ(昇圧コンバータ)の採用事例が増えている。当社では昇圧コンバータの基幹部品の1つであるリアクトルに新しい磁性材料および新しい放熱構造を適用し、従来と比較して同等性能で10%の小型・軽量化を達成した。
3.5 MB
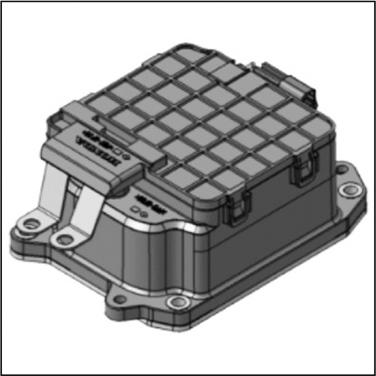
3.5 MB
近年の自動車分野において、静粛性の高いEV/HEVへのシフトが進む中、モータやインバータ等のカーエレクトロニクス製品に対しても静音化ニーズが高まっている。ポリウレタンフォームは軽量で柔軟な吸音・遮音材料として自動車、建材など幅広い分野で用いられるが、多孔質構造に由来した高い断熱性を有するため、モータ等のジュール熱を伴う発熱部品に対しては熱的な弊害があり、防音材としての適用は困難であった。それに対し本件では、マトリックス内に充填した熱伝導粒子を磁場により配向・構造化し、ポリウレタンフォームの熱伝導率を高める技術を開発した。さらに当社独自の高耐熱ポリウレタン材料、およびモールド成型による形状自由度との組み合わせにより、熱対策と騒音対策を両立できる制遮音製品を実現した。
2.3 MB

2.3 MB
SEDI/SEIで開発した3次元Wafer-Level Chip Size Package(WLCSP)技術を基盤とするミリ波GaAsデバイス技術を紹介する。この“3-D WLCSP”は10GHzからミリ波に到るまで対応可能なフリップチップ実装構造のプラットフォームであり、現在使用するトランジスタは0.1µmゲート長・AlGaAs/GaAs PHEMTである。自動車レーダ(76GHz帯、79GHz帯)市場は2016年には数百万ユニットに達すると予測されている。80GHz帯(Eバンド)高速無線通信は急拡大する携帯・モバイル通信を支える大容量バックホールとして実用化の機運が高まってきた。これらの応用分野に対する当社の3-D WLCSP MMICについて記述する。併せて、市場における技術動向を踏まえて3-D WLCSP技術の優位性について述べる。
5.5 MB
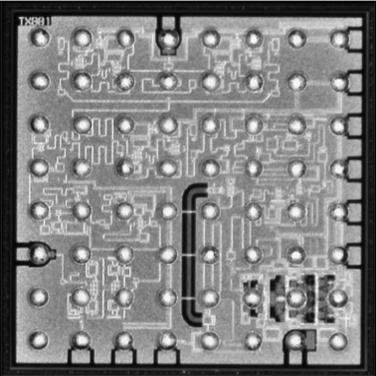
5.5 MB
100Gbit/sを超える大容量伝送システムとして、デジタルコヒーレント通信の導入が進められており、小型コヒーレントトランシーバの実現には、搭載されるレシーバ等の光部品の小型化が必須である。我々は、InP系モノリシック集積要素技術を用いて、レシーバを構成する90˚ハイブリッドとフォトダイオードを集積した90˚ハイブリッド集積型受光素子を開発し、コヒーレント受信に要求される光電特性、および既存の通信用受光素子と遜色ない信頼性を達成した。さらには、この集積型受光素子を搭載した小型レシーバを開発し、高感度特性と良好な128 Gbit/sのDP-QPSK復調特性を確認した。これらの結果から、本開発の新しい集積型受光素子がコヒーレントレシーバの小型化に貢献するとともに、今後の光通信市場の活性化、発展に寄与するキーデバイスとなることを期待する。
3.9 MB
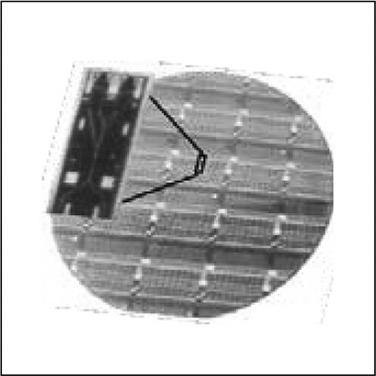
3.9 MB
国内のFTTH加入者は2300万人を超え今後も堅調に増加していく見込みである。経済的なFTTH配線網を構築する為には、光ケーブルには布設作業性の向上が求められる。このような背景から、今回我々は間欠接着型光ファイバテープを用いてケーブル布設、接続性を向上させた細径軽量24心ケーブルを新規に開発した。間欠接着型光ファイバテープの適用とドロップケーブルをベースに矩形構造を適用することにより、従来の非スロット型架空ケーブルと比較し、ケーブル断面積70%の細径化、重量55%の軽量化を実現すると同時に、ケーブル中間部で容易に光ファイバを取り出すことができる、ケーブル同士をコネクタ接続できる等の接続作業性を向上したケーブルを製品化した。
1.9 MB
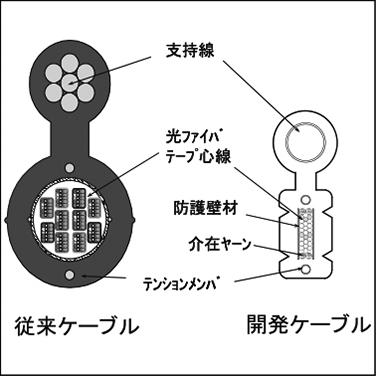
1.9 MB
1990年代初頭から整備されてきた光ビーコンが、整備開始から約20年の歳月が経過し、更新時期を迎えている。既設光ビーコンの更新にあたり、通信容量を拡大した高度化光ビーコンを開発した。拡大した通信容量を利用し、信号制御の高度化や詳細な交通情報の提供を実現するための車両の通行軌跡情報を収集できる。また、高度化光ビーコンは、信号灯色の変更スケジュールから生成した路線信号情報をもとにドライバにエコ運転を促す信号情報活用支援システム(SIDS)にも利用できる。本稿では高度化光ビーコンの概要、開発するにあたって求められる要件、そのための課題および解決に向けて取り組んだ内容について報告する。
1.9 MB
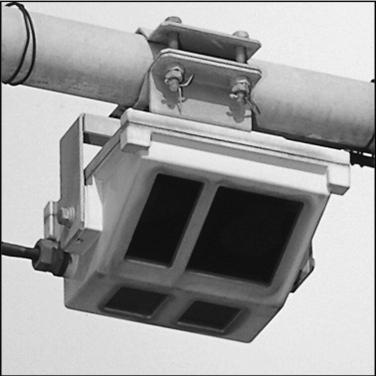
1.9 MB
OFケーブルは高度経済成長期に全国的に普及し重要な電力インフラとして送電網を支えてきた。従来、OFケーブルの劣化は非常に緩やかであると考えられてきたが、近年、経年OFケーブル線路における絶縁破壊事例が確認されている。劣化の実態調査として、経年OFケーブルを撤去し解体調査を行った結果、絶縁紙の炭化現象などOFケーブルの部分放電劣化(局所的な絶縁破壊現象による劣化)を示唆する事象が確認された。また、OFケーブルの電気的弱点である油層部と部分放電の特性を、モデル試料を用いた実験により評価した結果、部分放電が連続発生するためには3つの条件(大きな油層・AC重畳インパルスの侵入・絶縁油ガス吸収特性の低下)が必要であり、また、ガス吸収特性の低下について、部分放電により絶縁油が分解され発生したガスが油層部に局所的に蓄積し、飽和溶解量付近まで高濃度化することが原因とわかった。
3.1 MB

3.1 MB
当社は処理時に薬剤を使用しない環境に優しいシステムである、濾過-紫外線方式によるバラスト水処理装置「ECOMARINE® UV」を開発した。独自開発の高性能濾過フィルタを採用することにより、高い生物除去性能と、紫外線方式としては世界トップレベルの低消費電力運用の両立を可能とした。要素技術開発、プロトタイプでの実証試験を経て、処理能力が200 m3/hのバラスト水処理装置実機を開発し、郵船クルーズ㈱の客船「飛鳥Ⅱ」に船載した。2014年1月に全ての性能試験が完了し、2014年6月に国土交通省より型式承認を取得した。本稿では開発の背景、装置の特長および各種試験の状況について報告する。
2.5 MB

2.5 MB
自動車用変速機で代表的なマニュアルトランスミッション(MT)やデュアルクラッチトランスミッション(DCT)へ採用される焼結部品の多くにシンクロハブがある。このシンクロハブは各変速ギヤへの切替えに対してシンクロの役割を担うと共にエンジンやモーターからの伝達トルクに耐え得る高強度と周辺部品との摺動に対する耐摩耗性が要求される。従来、高強度や耐摩耗性は浸炭焼入れや高周波焼入れによってその要求特性を満足している一方で寸法精度の悪化やプロセスコストの増大などの課題がある。今回、焼結プロセス内で同時に焼きを入れるシンターハードニング技術に対応したローラーハース型高温焼結炉を新しく導入し、最適化した材料組成と焼結条件の工夫により寸法精度の向上と焼入れの省プロセスを実現させたシンクロハブを開発した。
2.9 MB

2.9 MB
近赤外光を用いて対象物の組成分布を画像化する当社技術Compovision®と、光の干渉を用いて対象物内部の断層構造を画像化する光断層撮像(Optical Coherence Tomography, OCT)を融合し、血管の組成と構造の断層分布を画像化する、組成判別機能付き血管内光断層撮像装置(Compovision®-OCT, CV-OCT)を新たに開発した。CV-OCTの特徴は、冠動脈プラークに含まれる脂質の特徴的な吸収ピークが現れる波長1.7µm帯の近赤外光を用いてプラークのスペクトルを測定・解析することで脂質を検出する点である。臨床における血管内診断に必要な性能を実現するため、スーパールミネッセントダイオード光源と分光ラインカメラを用いて、断層画像の1ライン当たり47kHzの速度で撮影し、100dB以上の感度で微弱な反射光を検出する。我々はプラーク血管モデルを用いて脂質分布撮像の実証を行い、90%以上の判定率が得られることを示し、プラーク診断に十分な判定性能であることを確認した。本稿では、CV-OCTシステムの特徴、構成、画像処理、基本性能、およびプラーク血管モデルでの性能検証
3.3 MB

3.3 MB
カーボンナノチューブ(CNT)の成長における触媒として必要な金属ナノ粒子や、グラフェン膜形成のテンプレートとして必要な基板を用いずに、CNT及び多層グラフェンシートを成長させることのできる原理的に新しい製法を開発した。本製法では、高純度鉄シートを酸化処理した後、アセチレンガス中で浸炭熱処理しながら破断すると、その破断面間の拡大に合わせてブリッジした状態でCNTや多層グラフェンシート等のカーボンナノファイバー(BG-CNF)を空間に引き出すように成長させることができる。酸化鉄を還元・浸炭熱処理していくと、鉄基材内部から炭素が大量に内部析出してくる現象が見出され、その段階で基材を破断すると、生じた破断部の微細構造に合わせてBG-CNFが成長することがわかった。本報告では、得られた新しい製法のプロセスを紹介すると共に、その実用化へ向けた可能性と課題について述べる。
3.4 MB
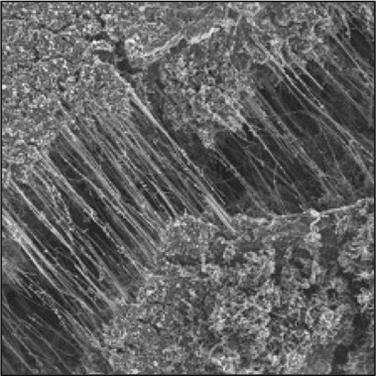
3.4 MB
波長1.0~2.5 µm帯の近赤外領域に感度を有する受光素子は医療分野、食品分野での非破壊検査への応用が期待されている。受光素子の低暗電流化とカットオフ波長の2.5 µm帯までの長波長化の両立が可能な、InGaAs/GaAsSbタイプⅡ量子井戸構造の作製に成功した。量産性に優れた有機金属気相成長(OMVPE)法を用いて、InP窓層を有する受光素子を作製することで、従来の分子線エピタキシー(MBE)法と比較して1桁以上低い暗電流を実現した。受光素子の高感度化に向けて、エピ成長条件の最適化を行い、高い結晶品質を維持したまま量子井戸受光層の更なる多周期化が可能となった。この結果、近赤外領域における外部量子効率は最大48%とMBE法により作製された受光素子よりも高い値を実現した。これまでにない、低暗電流、高感度の受光素子を実現したことで、検査装置の更なる高性能化を可能とし、従来の検査装置よりも詳細な組成や濃度の分析が可能となる。
1.7 MB
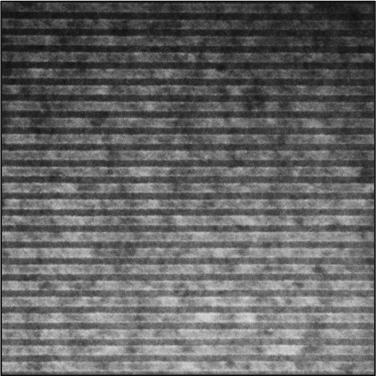
1.7 MB
高速かつ高感度なガスセンシングを行うための中赤外用小型光源として量子カスケードレーザ(QCL)が注目されている。QCLは、発光層の超格子列の厚みや材料組成を変えることで、中赤外全域に亘って発振させることが可能であり、高速性にも優れている。QCLの実用化のためには、1 Wを切る低消費電力化が望ましいが、QCLはその発振原理上、電圧を低減させることは難しいため、低消費電力化のためには、閾値電流の低減が必須となる。そこで今回、我々は埋め込みヘテロ(BH)構造と端面高反射コーティングの組み合わせによる素子サイズの低減、及び独自の垂直遷移型活性層構造の採用によって、閾値電流を大幅に低減し、27℃、CW駆動で閾値消費電力0.52 Wの低消費電力型QCLを作製することに成功した。
1.3 MB
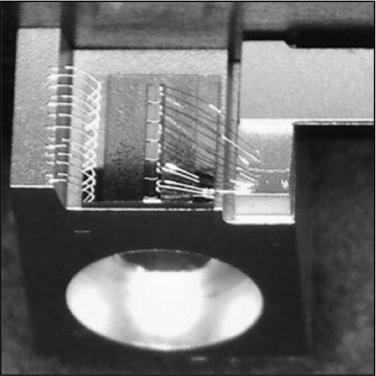
1.3 MB
近年、材料組織やデバイス構造の微細化に伴い、高空間分解能・高検出感度での元素分析の重要性が増している。微小部の微量元素分析法として、これまで主に電界放射型電子線マイクロアナリシス(FE-EPMA)や走査透過型電子顕微鏡付属のエネルギー分散型X線分光法が用いられてきたが、前者は空間分解能、後者は検出感度が不十分な点がある。今回著者らは、FE-EPMA用の分析試料を約100 nmに薄片加工することにより、空間分解能を向上させることに成功した。具体的には、インジウムガリウムリン中のインジウム分析について、感度3800 ppmを維持しながら、分解能を従来の180 nmから45 nmに向上させることに成功した。本法は、微細化の進む材料・デバイスの研究開発に広く展開できるものと期待される。
2.2 MB
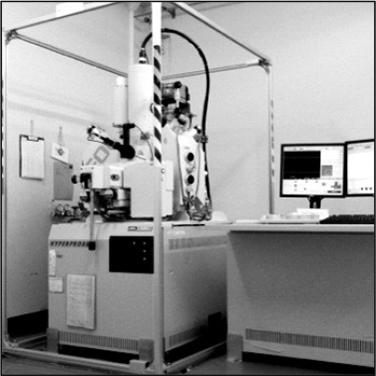
2.2 MB
わが国では、1960年代後半からの、信号制御機をはじめとした交通管制システムの導入や、1990年代からのETCの普及などにより、渋滞の緩和に成果を上げてきた。今日の新興国では、過去の我が国に見られたような急速な経済成長に伴い、渋滞や交通事故の問題が深刻化し、ITSへの期待は切実となっている。一方、欧米や日本では、インフラと車両、あるいは車両同士を無線通信などで繋ぐ技術により、さらなる渋滞緩和や交通事故の削減に向けた取り組みが行われている。このような無線通信技術は、新興国においても安価で高度な信号制御システムに活用することが期待されている。さらに日本においては、高度化光ビーコンが実用化され、新たなITSの幕開けを迎えつつある。住友電工は、広範囲に渡る実績と新技術の開発により、グローバルなITSへのニーズへの高まりに応える。
5.7 MB
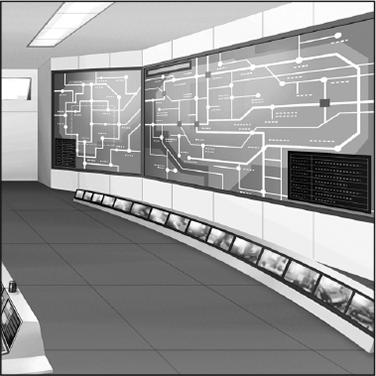
5.7 MB
私達は、安全な交通社会の実現を目指し、ドライバーに安全運転支援情報を提供することで事故の削減を図るDSSS(Driving Safety Support Systems)の開発を実施してきた。これまでは、光ビーコンを活用したDSSSの実用化に注力し、2011年7月より運用開始された。現在は、光ビーコンでは対応できない動的情報の提供に対応可能な、電波を利用したDSSSの実用化に注力している。本稿では、電波を活用したDSSSが必要とする通信エリアやセンサー検出エリア等のシステム定義の検討状況や、それを踏まえた検証実験システムの構築、その検証実験結果について報告する。
13.2 MB
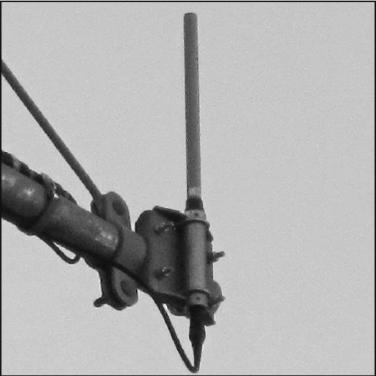
13.2 MB
安全運転支援システムに使用される通信メディア「700MHz帯高度道路交通システム」では、インフラ設備(路側に設置される無線基地局、以下路側機)と車両に搭載された車載機が通信する路車間通信と車載機相互間で通信を行う車車間通信の両方を時分割制御によって共用する通信方式が採用されている。この方式によると路側機は周囲の車載機に自身の送信期間情報(送信時刻や期間等)を通知し、それを基に車載機は自身の送信タイミングを決める。効率的で安定した時分割制御を行うため、路側機は送信タイミングを正確に合わせ、近隣の路側機との送信タイミングの時刻誤差を少なくする技術(基地局間同期技術)が重要である。本稿では、路側機の同期精度が悪化した場合の通信への影響、原因について調査し、それらへの対策をシミュレーション及びフィールド試験により有効性を確認したので報告する。
12.9 MB
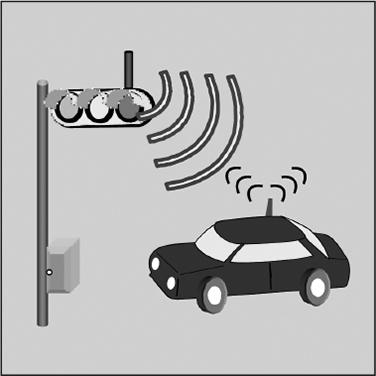
12.9 MB
世界的な燃料規制の強化が進む中で、電気自動車(以下EVと記載)の需要は爆発的に増加すると予測される。しかしながらEVはガソリン車と比較して航続距離が短いという課題を抱えており、バッテリ性能向上以外でも様々な方法で課題解決を図ろうとしている。例えばEVに対して、車両が消費する正確な電力量を推定するエンジンや、走行中の電力消費量や途中の充電ステーションでの充電を考慮した走行経路を提供するためのEV経路探索プラットフォーム等が望まれている。本論文では、分散処理基盤上で動作する消費電力量推定エンジン、具体的には道路リンク固有の特性を考慮したモデル式を使い、消費電力量を推定するエンジンを開発したので報告する。またEVに対して種々の機能を提供することでEVの普及を推進し、温室効果ガス排出を削減することで持続可能な社会の実現に貢献できる「EV経路探索プラットフォーム」を開発したので合わせて報告する。
13.1 MB
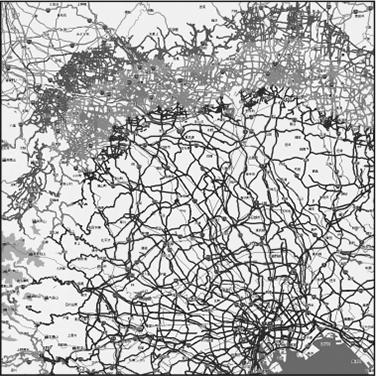
13.1 MB
車両側に特別なデバイスを装着することなく車両の特定が可能なナンバープレート認識システム(LPR)は旅行時間計測など交通管制のための重要な情報収集手段である。急速なモータリゼーションの進展が進むタイでは慢性的な道路渋滞が深刻な問題となっており、LPRの導入は一つの解決策になりうるが、独自のタイ文字の使用など技術的なハードルが高い。本論文で提案するのは、HOGベースのBag of Featuresに基づくプレート検出方式とHOG特徴に基づく文字認識方式であり、これらの問題解決にきわめて有効である。タイで収集した画像による実験の結果、ナンバープレートの検出率は94.6%、検出できたナンバープレートに対する認識正解率は92.0%であった。これらの結果により提案手法はタイ国のナンバープレートの検出・認識に有効であることが示されたが、交通管制への適用のためにはさらなる性能向上が必要である。
13.5 MB

13.5 MB
従来、安全、快適な交通流の実現を目指して交通信号制御(以降、信号制御)が行われてきた。近年、これらに加えて地球温暖化防止を目的としたCO2排出量削減も新たな課題となっている。これらを実現する交通状況に応じた信号制御には、多くの感知器が必要で、高額な設置コストが課題となっている。この問題の解決を検討するに当たり、我々は走行車両がGPS等により自ら収集した走行軌跡情報であるプローブ情報に注目した。プローブ情報を活用して渋滞長のような連続的な空間交通情報(空間データ)を取得し信号制御を行うシステムを開発し、一般社団法人UTMS協会※1におけるシミュレーション実験により信号制御効果の検証実験を行い、感知器削減の可能性を示した。
6.6 MB

6.6 MB
GaN HEMTの歪み特性の改善は、ポイントtoポイントシステムといったマイクロ波帯通信用デバイス市場への浸透を深める上で重要な技術課題である。この論文は、無線通信用GaN HEMTの歪み特性改善に向け、非線形要素を取り込んだ大信号モデルを構築し、このモデルを活用したGaN HEMTの歪み特性改善の検討をまとめたものである。構築した大信号モデルを用いた解析により、10 dB以上のバックオフ領域の歪み特性はドレイン電流立ち上がり領域の相互コンダクタンス(gm)プロファイルが大きく影響することを解明した。これを踏まえて薄いn型層を挿入したバッファ層(ini層)を有するGaN HEMTを試作し、8 dB以上ものバックオフ領域の歪み特性を実現した。
8.6 MB
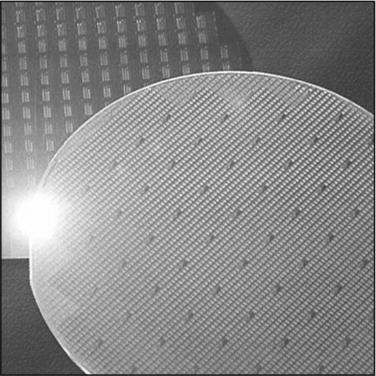
8.6 MB
中赤外センサの受光材料として注目を集めているtype-II InAs/GaSb超格子は、結晶成長には通常GaSb基板が使用される。しかし、GaSb基板は赤外領域での透過率が低く、2次元センサアレイのような基板裏面から受光するセンサの作製にはGaSb基板の除去という困難な工程が必要になる。そこで我々は、透過率が高くGaSbとの格子不整合が比較的小さいInP基板に着目した。InP基板上にGaSbバッファ層を厚く成長した後、InAs/GaSb超格子を成長することで、格子不整合に起因する貫通転位が低減し、結晶学的および光学的特性の優れた超格子が得られることを見出した。さらに、InP基板上InAs/GaSb超格子を用いて初めてカットオフ波長約6.5 µmのセンサを作製した。
17 MB
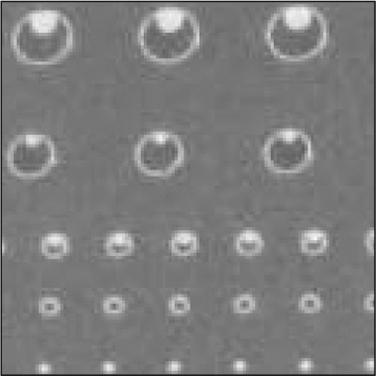
17 MB
高温超電導線材を用いた電力ケーブルやモータ等の電力・産業機器は、コンパクトな形状で大容量送電や大出力・高トルクを可能にし、既存の電力ケーブルや産業機器に比べて損失を低減することが可能であることから、省エネルギー、地球温暖化対策に貢献することが期待されている。当社は、2008年4月から2013年2月にかけて実施された国家プロジェクトに参画し、イットリウム系薄膜超電導線材※1を用いた66 kV/5 kA級の三心一括構造を有する超電導電力ケーブルの開発を行った。まず、短尺ケーブルの試作により超電導電力ケーブルに必要な線材特性を決定し、要求性能を満たす線材を開発した。その後、線材を総長6 km作製し、既設の150 mm管路に収納可能な世界最大の送電密度を有する三心一括型超電導電力ケーブルシステムを構築した。冷却効率を考慮した上で送電損失が従来の電力ケーブルの1/3以下の低損失であることを検証し、長期課通電試験によりその実用性を確認した。
11.5 MB

11.5 MB
"近年、製造業界において加工コスト低減を目的とした高速・高能率加工が急速に広がっている。そのため、鋼を初めとした鉄系材料との親和性が低く高品位な加工面が得られることから主に仕上げ加工に用いられるサーメット工具に対しても、さらなる長寿命化と安定加工への要求が高まっている。 今回、旋削加工用の高耐摩耗性サーメット材種であるT1000Aを開発した。T1000Aは組成を最適化することで、耐摩耗性・耐欠損性を両立させ、焼結条件を工夫し組織を制御することで加工面品位を向上させた。また、鋼の切削に加え鋳鉄、焼結合金の切削にも対応させた。本稿では、開発したT1000Aの特徴と切削性能を報告する。
13.9 MB

13.9 MB
近年、希少金属材料の使用量増加や価格高騰の影響により、タングステン使用量の少ないサーメット工具が脚光を浴びている。中でも粗加工から仕上げ加工までを通して様々な用途で利用されるコーテッドサーメットには、長寿命かつ加工初期から安定して良好な仕上げ面品位を実現することが要求される。当社ではこれらのニーズを実現するため、当社独自のPVDプロセスを用いたBrilliant Coat®を開発し、それを採用したT1500Zを製品化した。Brilliant Coat®は、鋼に対する摺動性と低い反応性を兼ね備えた特殊な被膜であり、従来材種に比べて30%低い切削抵抗を達成した。T1500Zは、従来のコーテッドサーメットより幅広い用途に適応することができ、顧客での加工コスト削減を可能とした。
19.7 MB
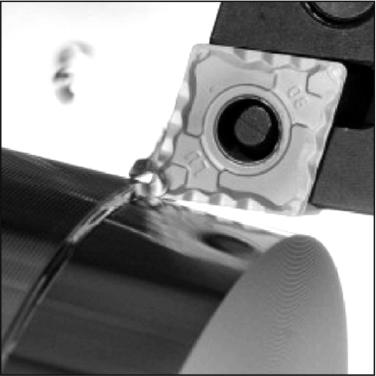
19.7 MB
医療介護の現場で課題となっている床ずれ(褥瘡)防止や、利用者のQOL(Quality of Life)向上、自立支援、体位交換頻度の低減、看護・介護者の負担低減などを目的として、柔軟なSR(スマートラバー®)体圧測定センサーシート(東海ゴム工業㈱製)と、首振り2段エアセルの制御による新規なマットレスを開発している。従来のエアマットレスの構造、機能にとらわれず、医療介護現場が求めるマットレスの開発に医療専門職と共同で取り組んだ。SRセンサー技術により体圧分布センサシートを内蔵し、多数のエアセルが独自に駆動することで、マットレス面が臥床者の体型に合わせて変形する。また、体圧分散性と寝心地の良さ、離床のし易さの両立も図った。
13.6 MB

13.6 MB
距離別時間差課金という従前の電話主体の通信キャリアのビジネスモデルが崩壊し、月額定額料金のインターネットプロトコル(IP)が拡大してきた。デジタルプロセッサ・メモリの能力の急進と、光ファイバケーブルによる通信回線帯域の拡大、モバイル通信技術の進展による携帯端末の長足の進歩により、通信キャリアのビジネスモデルは、ビット当たり単価の急落をクラウドサービスとコンテンツ・アプリケーションによる収益でまかなうサービスプロバイダモデルへと大きく変化すると共に、システムベンダ・部品デバイスベンダのグローバルなビジネスモデルに大きな課題を突きつけ、以下に述べるように技術開発・製品戦略に大きな変化をもたらしている。
0.4 MB
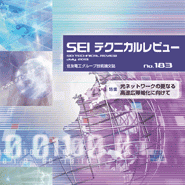
0.4 MB
Optical Thunderbolt Cable─by Yasuhiro Maeda, Michiko Harumoto, Takayuki Shimazu, Yuya Homma, Mitsuaki Tamura and Yoshiki Chigusa─Thunderbolt, an innovative high-speed input/output (I/O) technology developed by Intel Corporation and Apple Inc., enables 10 Gb/s transmission between a computer and peripheral devices. Based on Intel’s technical specifications, Sumitomo Electric Industries, Ltd. developed a Thunderbolt active optical cable (AOC) by drawing on its optical fiber and module technology.
0.6 MB
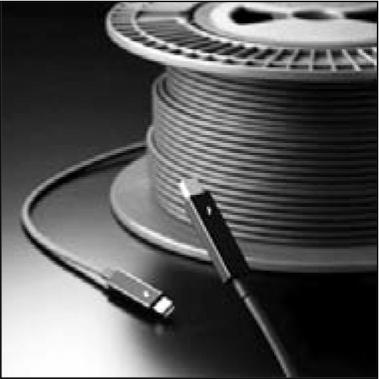
0.6 MB
Multi-Core Fiber for High-Capacity Long-Haul Spatially-Multiplexed Transmission─by Tetsuya Hayashi, Toshiki Taru, Takuji Nagashima, Osamu Shimakawa, Takashi Sasaki and Eisuke Sasaoka─Data traffic is exponentially growing due to the emergence of various network services. Although the transmission capacity of optical fibers has been dramatically increased thanks to advanced communication technologies such as wavelength-division multiplexing and multi-level modulation, the transmission capacity is
1.3 MB
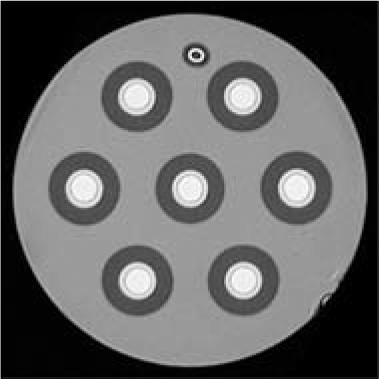
1.3 MB
Multi-Core Fiber Fan-Out Devices─by Osamu Shimakawa, Hajime Arao, Manabu Shiozaki, Tomomi Sano and Akira Inoue─The space division multiplexing (SDM) system using multi-core fiber (MCF) is one of the promising solutions to overcome the capacity limitation of conventional fiber. To achieve practical use of MCF, a fan-out device that allows each core of MCF to be connected into individual single-core fiber is indispensable. We have developed a pluggable fiber bundle type fan-in/out device for MCF
0.6 MB
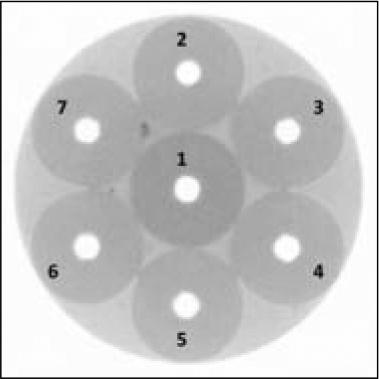
0.6 MB
Ultra-High-Density Optical Fiber Cable with Rollable 4-Fiber Ribbon─by Fumiaki Sato, Heiji Sato, Keigo Yamamoto, Takao Hirama, Masakazu Takami and Hiroshi Miyano─This paper describes a new design of an ultra-high-density optical fiber cable with a rollable 4-fiber ribbon. The new cable has a sheath configuration similar to that of the conventional non-slotted optical cable and contains a rollable ribbon consisting of fiber adhesive parts and single-fiber parts alternately arranged in the
0.4 MB
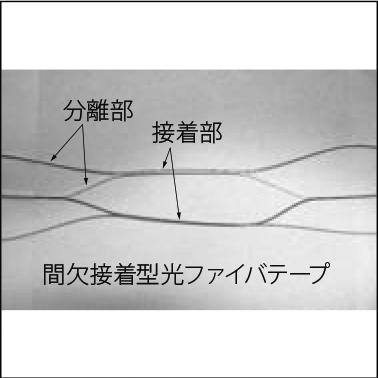
0.4 MB
FTTH System for Cable-TV Operator─by Tadayoshi Senou, Eisuke Izumi, Takashi Yano, Mitsutoshi Imada, Hiroshi Muranaka and Naoto Komazaki─Amid fierce competition with major communication carriers, many cable-TV operators in Japan are undergoing the replacement of the existing hybrid fiber-coaxial (HFC) systems. The Fiber-to-the-Home (FTTH) system is considered to be one of the most efficient solutions for the replacement and many operators are planning to install the system. Since its foundation,
0.7 MB

0.7 MB
Improvement in Maintenance and Operation of 10G-EPON System─by Hideyuki Hirai, Shingo Shiba, Shinichi Kouyama, Yoshiyuki Shimada, Junichi Michimata and Hiroshi Murata─FTTH (Fiber To The Home) is the mainstream broadband service in Japan, and the number of its subscribers has been increasing. Many of these subscribers are using telephone, terrestrial digital television, and video-on-demand services provided by IP networks. Therefore, FTTH systems are required to have high stability and redundancy
0.4 MB

0.4 MB
Tunable Laser Controller IC for Coherent Optical Communication Systems─by Tomoko Ikagawa, Keiji Tanaka, Eiichi Banno, Toshimitsu Kaneko and Katsumi Uesaka─The authors have successfully developed a tunable laser controller IC for digital coherent optical communication systems. The developed IC is composed of both analog and digital circuits fabricated by CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) process, which contributes to the reduction of chip size and power dissipation. The IC, used in
0.6 MB
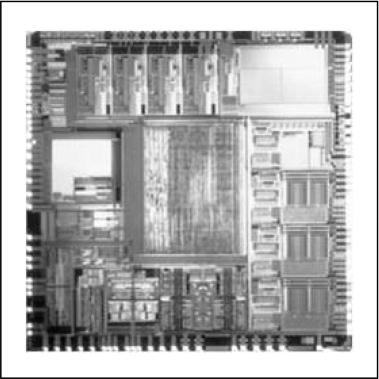
0.6 MB
Narrow Spectral Line-width Full-band Wavelength Tunable Laser for Digital Coherent Communication Systems─by Tsutomu Ishikawa, Hirokazu Tanaka, Masao Shibata, Mikio Tajima, Yoshiki Oka and Toshimitsu Kaneko─Full-band wavelength tunable lasers have been required to have high optical output power and narrow spectral line width for digital coherent communication systems. Sumitomo Electric Industries, Ltd. produces ITLAs (Integrable Tunable Laser Assemblies) using CSG-DR-LDs (Chirped-Sampled-Grating
0.5 MB

0.5 MB
100 Gbit/s Small Coherent Receiver Using InP-Based Mixer─by Yoshihiro Tateiwa, Masaru Takechi, Hideki Yagi, Yoshihiro Yoneda, Kazuhiro Yamaji and Yasushi Fujimura─For next generation coherent optical transmission systems, compact transceivers like CFP (100G Form-factor Pluggable) or CFP2 form factor have been highly anticipated. The authors have successfully developed a compact coherent receiver for such applications. The InP-based MMI (Multi-Mode Interferometer)-mixer chip with an integrated PD
1.4 MB
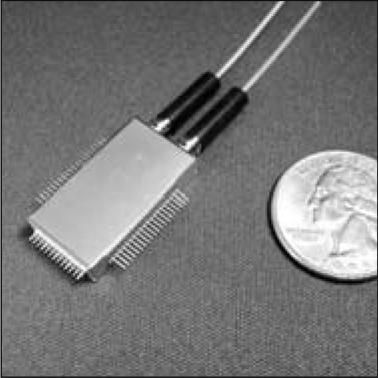
1.4 MB
40 Gbit/s Small-Form Low-Power Optical Transceiver for Data Center Networks─by Hideaki Kamisugi, Kuniyuki Ishii, Tetsu Murayama, Hiromi Tanaka, Hiromi Kurashima, Hiroto Ishibashi and Eiji Tsumura─The authors have successfully developed an optical transceiver that complies with the Quad Small Form-Factor Pluggable Plus (QSFP+) standard. The optical interface conforms to the 40GBASE-LR4 for 40 gigabit Ethernet over up to 10 km single mode fibers using 1.3 µm-range coarse wavelength division
0.5 MB
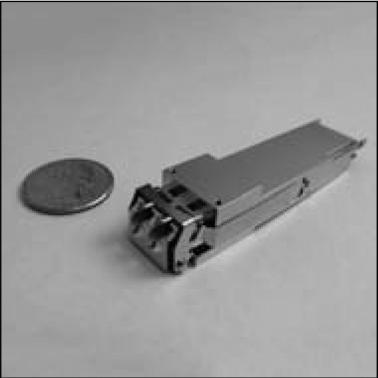
0.5 MB
850 nm Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser and Photodiode for Ultra-High Speed Data Communications over Multimode Fiber─by Chuan Xie, Jiaxi Kan, Shenghong Huang, Li Wang, Neinyi Li, Chan Chih Chen and Shigeru Inano─With the advent of cloud computing, the proliferation of smart phones and tablets, and the omnipresence of social networking, the bandwidth need for data communication continues its phenomenal growth. The maximum data transmission speed is expected to double to the rate of 25
0.7 MB
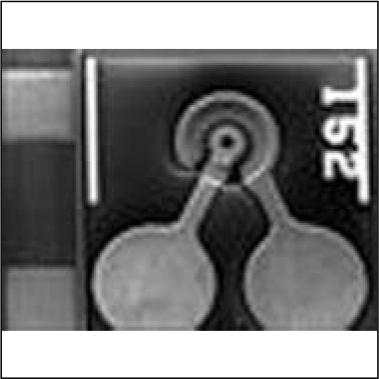
0.7 MB
Highly-Functional Prestressing Steels that Support Infrastructure─by Masato Yamada─Prestressing steels have been widely applied for infrastructure. For the last twenty years, Sumitomo Electric Industries, Ltd. and Sumitomo (SEI) Steel Wire Corp. have been intensively working on the development of highly-functional prestressing steels such as epoxy coated and filled strands and pre-grouted tendons. This paper describes the features of these two products, as well as our 2,230 MPa grade ultra-high-
0.8 MB

0.8 MB
6056 Aluminum Alloy Wire for Automotive Fasteners─by Isao Iwayama, Tetsuya Kuwabara, Yoshihiro Nakai, Yoshiyuki Takaki, Shin-ichi Kitamura and Hidetoshi Saito─The need for high-strength aluminum fasteners is growing quickly with the aim of reducing the weight of automobiles. Sumitomo Electric Toyama Co., Ltd. has developed 6056 aluminum alloy wire suitable for these fasteners. Owing to its homogeneous microstructures, the wire achieved a high tensile strength of 420 MPa and yield strength of 375
0.5 MB
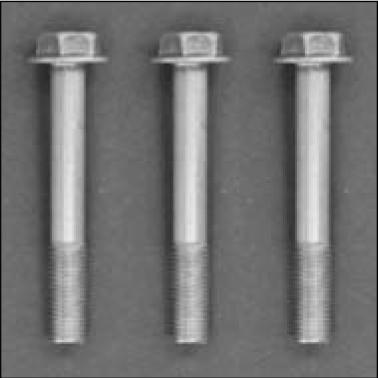
0.5 MB
Test Automation Support Tool for Automotive Software─by Tomomi Kataoka, Ikuko Saka, Ken Furuto and Tatsuji Matsumoto─In recent years, automotive components have become more sophisticated and the electronic control unit (ECU) has employed more complex large-scale software. As the product scale becomes larger, an increasing number of tests are required to assure product quality. Even in the case that auto-testing tools are used, test patterns need to be input manually. This process requires
0.5 MB
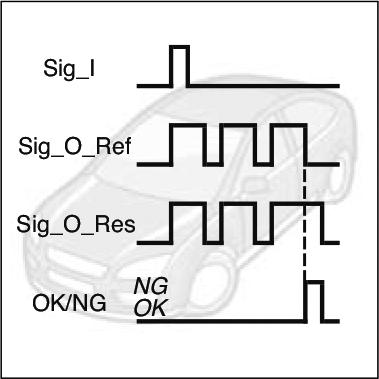
0.5 MB
11.1 Gbit/s Pluggable Small Form Factor Optical Transceiver Module─by Yoji Shimada, Shingo Inoue, Shimako Anzai, Hiroshi Kawamura, Shogo Amari and Kenji Otobe─We have developed an SFP+ (Enhanced Small Form Factor Pluggable) optical transceiver module for 11.1 Gbit/s DWDM (dense wavelength division multiplexing) application, which can cover up to 100 km reach over standard single-mode fiber. We have also successfully reduced its total power consumption to less than 1.5 W by utilizing a newly
0.7 MB

0.7 MB
Triple-Band Polarization Diversity Antenna with Loop Elements─by Toyohisa Takano, Shinji Nakaue, Suguru Yamagishi, Hiromi Matsuno and Masayuki Nakano─Antennas for mobile communication base stations need to support a wide range of frequency bands including 800 MHz, 1.5 GHz, and 2.0 GHz, respond to polarization diversity, and be reduced in size for easier installation. We have developed a triple-band polarization diversity antenna using loop elements, which successfully reduces the antenna size by
0.5 MB
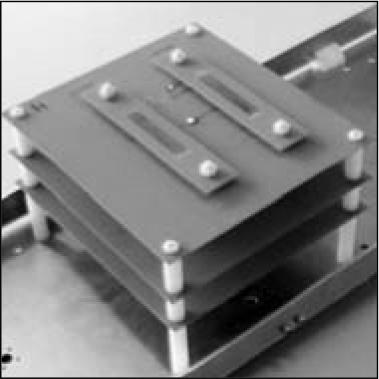
0.5 MB
Application of Simulation Technology to the Development of High-Speed Electronics─by Tetsuro Kinoshita, Yumiko Sawai, Yoshiaki Uematsu, Akinori Okayama and Takashi Inui─As the signal processing speed of electronic devices increases, transmission capability over 10 Gbps has been required for printed wiring boards (PWBs). As electronic equipment has reduced in size and advanced in processing speed, the heat density of such equipment has increased. Since high accuracy is required for the integrity
1 MB
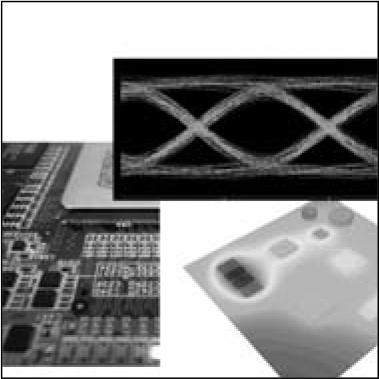
1 MB
High-Power and High-Efficiency True Green Laser Diodes─by Shimpei Takagi, Masaki Ueno, Koji Katayama, Takatoshi Ikegami, Takao Nakamura and Katsunori Yanashima─The authors demonstrated InGaN green laser diodes (LDs) that were grown on semipolar {2021} GaN substrate and achieved output power of over 100 mW in the spectral region beyond 530 nm. In the range of 525-532 nm, these LDs realized wall plug efficiencies as high as 7.0-8.9%, which exceed those reported for c-plane LDs. Moreover, the InGaN
0.4 MB
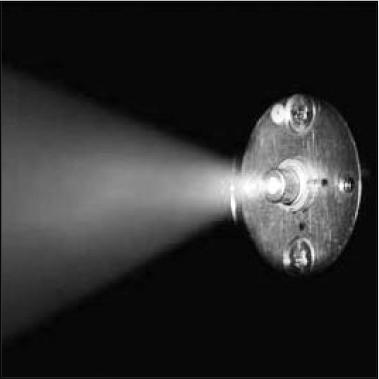
0.4 MB
Optical Characteristics of InGaN Quantum Wells for Green Laser Diodes on Semi-Polar {2021} GaN Substrates─by Takashi Kyono, Yohei Enya, Koji Nishizuka, Masaki Ueno, Takao Nakamura and Yoichi Kawakami─Optical characteristics of InGaN quantum wells (QWs) for green laser diodes on semi-polar {2021} GaN substrates were assessed using time-resolved photoluminescence (TRPL) and scanning near-field optical microscopy (SNOM). The InGaN QWs exhibited a remarkably shorter PL lifetime of 3.1 ns compared
0.6 MB
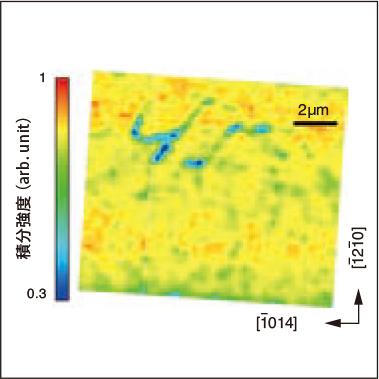
0.6 MB
Low On-Resistance and High Breakdown Voltage GaN SBD on Low Dislocation Density GaN Substrates─by Kazuhide Sumiyoshi, Masaya Okada, Masaki Ueno, Makoto Kiyama and Takao Nakamura─Vertical GaN Schottky Barrier Diodes (SBDs) were fabricated on freestanding GaN substrates with low dislocation density. A high quality n-GaN drift layer with an electron mobility of 930 cm2/Vs was obtained under the growth conditions optimized by reducing the intensity of yellow luminescence using conventional
0.4 MB
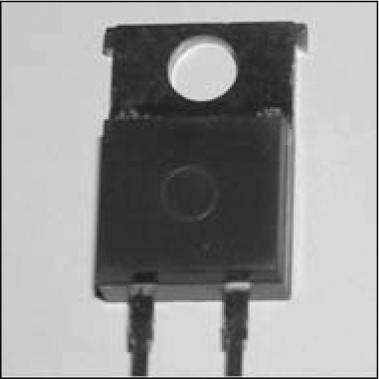
0.4 MB
"SiC High Blocking Voltage Transistor─by Ren Kimura, Kousuke Uchida, Toru Hiyoshi, Mitsuhiko Sakai, Keiji Wada and Yasuki Mikamura─Recently, with the growing global interest on energy saving, power device efficiency is increasingly important. Most power devices are fabricated utilizing silicon (Si) and their performances have approached to the limit that can be obtained with Si. Silicon Carbide (SiC) is the best candidate materials for innovative power devices that can replace Si devices.
0.5 MB
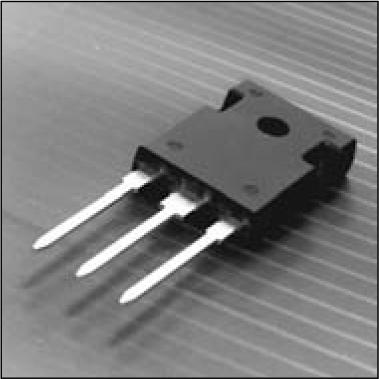
0.5 MB
SiC MOSFET with High Channel Mobility─by Toru Hiyoshi, Takeyoshi Masuda, Keiji Wada, Shin Harada, Takashi Tsuno and Yasuo Namikawa─SiC (silicon carbide) MOS (metal oxide semiconductor) devices are promising candidates for high-power, high-speed, and high-temperature switches owing to their superior properties such as wide bandgap, high breakdown electric field, high saturation velocity, and high thermal conductivity. However, excellent device characteristics expected from these physical
0.5 MB
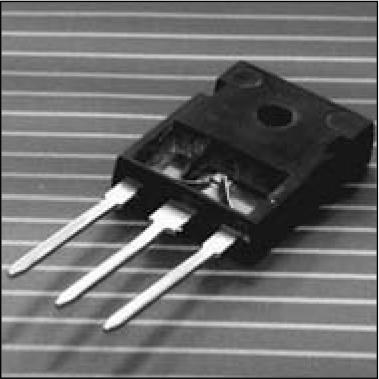
0.5 MB
High-Speed Switching Power Supply Using SiC RESURF JFETs─by Satoshi Hatsukawa, Takashi Tsuno, Kazuhiro Fujikawa, Nobuo Shiga, Tuya Wuren, Kazuyuki Wada and Takashi Ohira─We have developed a silicon carbide (SiC) junction field effect transistor (JFET) with a reduced surface field (RESURF) structure. This JFET is 2 mm × 2 mm in size and has ideal characteristics for high speed switching: a normal saturation current of about 250 A/cm2 at a gate voltage of 2 V, a specific on-resistance of about 13
0.8 MB
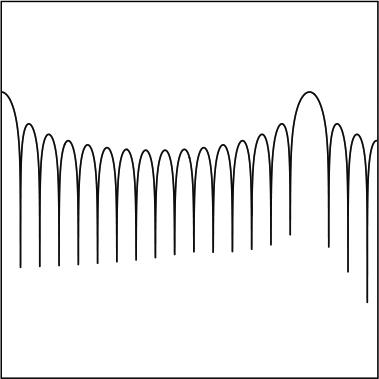
0.8 MB
High-Power All-Solid Secondary Battery with High Heat Resistance─by Takashi Uemura, Kazuhiro Goto, Mitsuyasu Ogawa and Keizo Harada─We have developed an all-solid lithium-ion secondary battery consisting of a sulfide-based thin film electrolyte and pellet-type electrodes. The safety of lithium-ion batteries is significantly increased by replacing the electrolyte solutions with flame-retardant solid electrolytes. This battery has high performance characterized by a high discharge rate and
0.6 MB

0.6 MB
"Non-destructive Analysis Method for Metal-Glass Interface by Synchrotron Radiation─by Junji Iihara and Koji Yamaguchi─We have developed a new technique to analyze an interface between metal and glass nondestructively. In specimen fabrication, we employed a precise thinning technique instead of the conventional exfoliating, so that the interface maintains its original state. In diffraction measurements, we combined a highly brilliant X-ray from synchrotron radiation and 2-dimensional detector.
0.5 MB
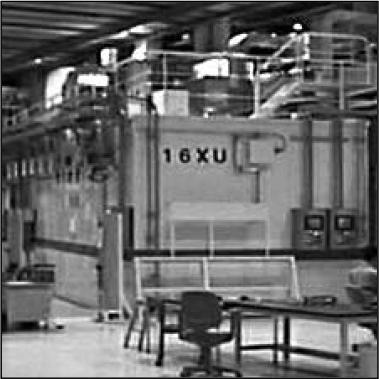
0.5 MB
Dopant Mapping in Semiconductors Using Scanning Electron Microscopy─by Daisuke Tsurumi and Kotaro Hamada─This paper investigates the decrease in dopant contrast of semiconductors due to scanning electron microscope (SEM) observation that causes contamination on the semiconductor surface. We have discovered that second electron (SE) high-pass energy filtering can dramatically reduce the influence of the contamination and, thus, dopant contrast remains stable during the observation. We have also
0.5 MB
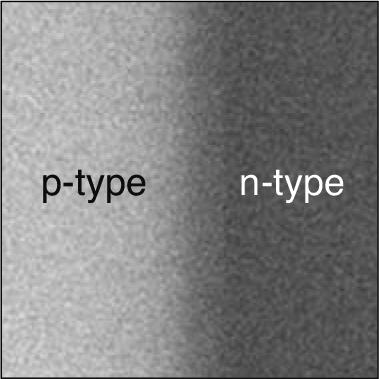
0.5 MB
Sumitomo Electric Industries, Ltd. has recently developed two types of smart-grid demonstration systems. One is the micro smart-grid demonstration system operating at Osaka Works from June 2011. This system consists of four types of renewable power generators and a storage battery with DC-connection to balance fluctuations in natural power generation and power consumption, thereby ensuring stable and efficient power supply to the facilities and equipment of the Works without any commercial power
0.6 MB
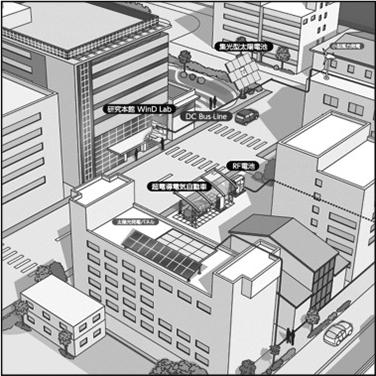
0.6 MB
Renewable energies, such as solar and wind power, are increasingly being introduced as alternative energy sources on a global scale toward a low-carbon society. For the next generation power network, which uses a large number of these distributed power generation sources, energy storage technologies will be indispensable. Among these technologies, battery energy storage technology is considered to be most viable. Sumitomo Electric Industries, Ltd. has developed a redox flow battery system
5.3 MB

5.3 MB
"Sumitomo Electric’s concentrator photovoltaic (CPV) system was developed under the design concepts of light weight, small size, good heat dissipation and use as a display. At its Yokohama Works, a megawatt-class generation and storage system was deployed for demonstration and has been in operation since July 2012. The performance of the CPV modules in this system was evaluated. The module recorded a conversion efficiency of approximately 30% both in sunlight and using a solar simulator.
0.5 MB

0.5 MB
In Japan, an increasing number of megawatt-class solar power systems have been established for industrial use since the introduction of the Feed-in Tariff system, a policy that requires electric power companies to purchase electric power generated by solar power systems at a relatively high price. In line with this, we have added new functions to our 100 kW and 250 kW solar inverters with the aim of preventing voltage fluctuations that are caused by the increased number of solar power systems.
0.6 MB
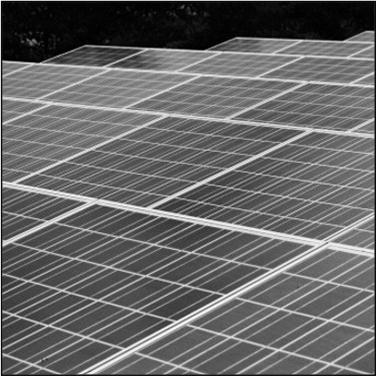
0.6 MB
A molten salt electrolyte battery (MSB) is a sodium secondary battery that uses molten salt as its electrolyte and features high energy density and safety. Our molten salt has a melting point of 61˚C and needs to be heated to 90˚C for battery usage. As the battery has a high energy density (290 Wh/L) and requires no cooling space, small and lightweight battery systems become possible. Although lithium ion batteries (LIBs) and sodium sulfur (NAS) batteries are currently drawing attention for
1 MB

1 MB
The authors have developed a novel porous metal “Aluminum-Celmet™” that is suitable for the cathode current collector of lithium ion batteries and other rechargeable batteries operated by high voltage. Aluminum-Celmet™ features a high porosity up to 98%, large relative surface area, unique threedimensional structure, and high corrosion resistance. In a demonstration test, the lithium ion battery using Aluminum-Celmet™ for its cathode current collector showed improved battery capacity,
0.4 MB
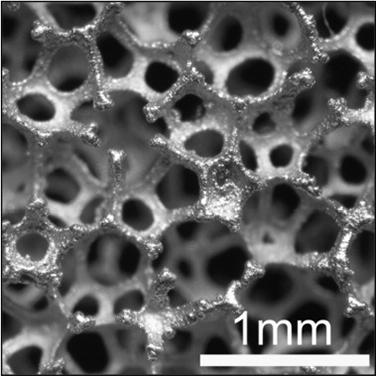
0.4 MB
Japan’s first in-grid demonstration of a high-temperature superconducting (HTS) cable system has been started to evaluate its performance, safety and reliability. We developed the cable using the DI-BSCCO® HTS wire, and repeated design changes and element testing to meet required specifications. The performance of the cable was confirmed in the preliminary test using a 30-m HTS cable system and it was then successfully installed in Tokyo Electric Power Corporation’s Asahi Substation with
0.9 MB

0.9 MB
We have developed a DC-XLPE (cross-linked polyethylene) insulating material that has excellent properties for DC voltage applications. Our high-voltage DC-XLPE cable and factory joints using this material showed positive results in a long-term test partly consisting of a polarity reversal test at a rated voltage of up to 500 kV. In addition, this cable passed 250 kV pre-qualification tests and type tests, which also include polarity reversal tests, in accordance with the test conditions
0.7 MB

0.7 MB
Optical fiber networks have expanded rapidly and more than 200 million km of optical fiber was sold in 2011. The optical fiber has now become a key technology to an information-oriented society. The conventional single mode fiber widely used in the world has not changed much in its refractive index profile, however, the coating materials and coating structures have developed due to changes in cable structures and installation environments. Coating materials play an important role in minimizing
0.9 MB
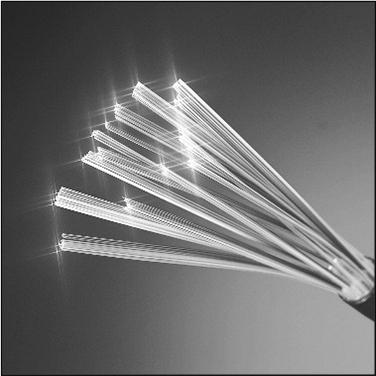
0.9 MB
As the electrification of automobiles progresses, hybrid electric vehicles have been in widespread use and the development of commercial electric vehicles has started. However, the heavy weight of these large vehicles leads to relatively short driving distances. To overcome this problem, the authors have been working on the development of high-efficiency motors using DI-BSCCO® hightemperature superconducting (HTS) wire. They have recently developed an HTS motor and conducted a demonstration
0.5 MB
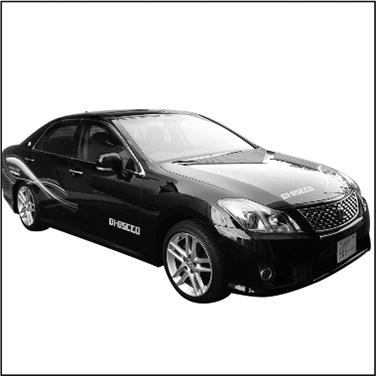
0.5 MB
"To keep up with the exponential growth of demand for broadband Internet traffic, large capacity transmission systems with digital coherent technologies have started operation recently. The major challenge in such systems is to improve optical signal-to-noise ratio (OSNR). Although there would be several techniques to improve the OSNR, the use of low-loss and low-nonlinearity fibers would be one of the most straightforward and effective solutions. In this paper, we present newly-developed
0.5 MB

0.5 MB
In the 3rd generation mobile communication systems such as W-CDMA, data traffic by cellular phones and other wireless tools has been steadily increasing. The data traffic is expected to further increase due to the wide spread use of smartphones and the introduction of WiMAX and LTE services that offer high-speed, high-capacity data transmission. A GaN (gallium nitride) HEMT (high electron mobility transistor) is suitable for the high-speed, highpower application owing to its excellent material
0.5 MB
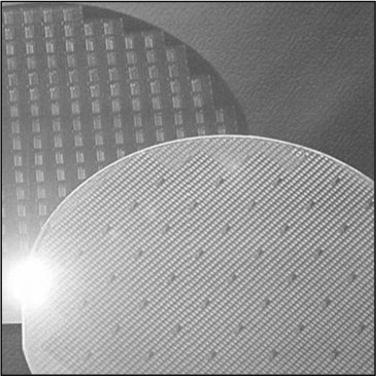
0.5 MB
The authors have successfully developed a small receiver module with an integrated optical demultiplexer. The module is compliant with the 40GBASE-LR4 specification and sufficiently small (7 mm) to be mounted in a QSFP+ (Quad Small Formfactor Pluggable) next generation 40GE optical transceiver. The optical demultiplexer uses thin film band pass filters to divide a multiplexed optical signal into 4 demultiplexed optical signals, thereby realizing low optical insertion loss and low temperature
0.6 MB
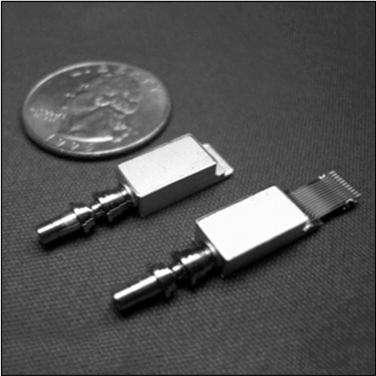
0.6 MB
We have developed a transmitter chipset using a new tripler, up-converter, and power amplifier. Monolithic Microwave Integrated Circuits (MMICs) of these devices are designed using our Wafer Level Chip Size Package (WLCSP) technology, and reflow-soldered on a 10 mm x 14 mm printed circuit board (PCB). The WLCSP technology enables the development of highly integrated package-free flip-chip MMICs suitable for surface mounting, and is therefore expected to reduce the production cost significantly.
0.5 MB
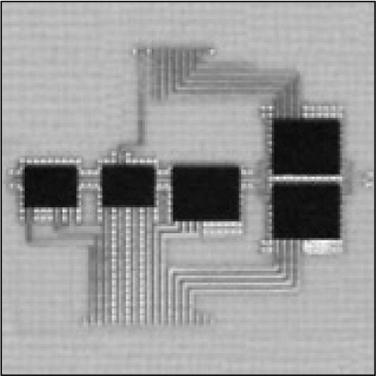
0.5 MB
In wireless communication, there has been an increasing demand for high-speed and high-quality data transmission, particularly since the advent of smartphones. To meet these requirements, multipleinput and multiple-output (MIMO) systems and array antenna systems have been developed. Wireless systems are also increasingly being integrated for improved communication performance, while transmitters are required to remain compact. To this end, we have developed a 1-bit digital radio frequency (DRF)
0.8 MB

0.8 MB
Information communication technology has been widely used for crime prevention and protection of the elderly. Currently, there is an increasing demand for video surveillance systems that can detect and report a stranger or suspicious behavior. Therefore, we have developed a video surveillance device that detects and tracks persons from the video sequence by using filtering logics and reports the result to the user through a network. This paper outlines the video surveillance device and its
0.5 MB

0.5 MB
We have developed the Compovision® imaging system with a near-infrared (NIR) spectrographic camera. This camera incorporates a sensitive sensor that can detect the distinctive absorption spectra reflected or absorbed by organic substances in the wide wavelength band of 1,000-2,350 nm. The camera can process hyper-spectral data of 320 x 256 pixels at the frame rate of 1-320 fps, and thus enables precise real-time imaging. The Compovision® imaging system is expected to be used for the
0.6 MB

0.6 MB
A twodimensional near infrared image sensor with the cut-off wavelength of 2.4 μm has been successfully developed by using InGaAs/GaAsSb type-II quantum well structures as its absorption layer. The 250-pair InGaAs (5 nm) / GaAsSb (5 nm) quantum well structures lattice-matched to InP substrates were grown by metal organic vapor phase epitaxy. The p-n junctions were formed in the absorption layer of each pixel by the selective diffusion of zinc. The sensor chip with 320 × 256 pixels at 30 μm
0.4 MB
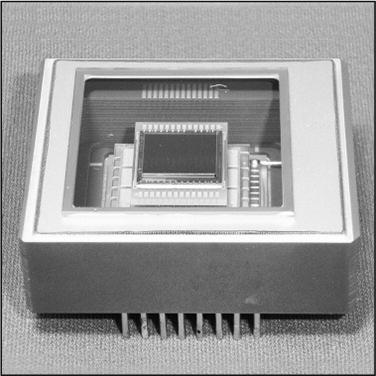
0.4 MB
鉄族金属、非鉄金属の切削に用いられる工具のうち、約90%は超硬合金もしくはコーティド超硬合金が用いられている。超硬合金(WC-Co)はタングステンカーバイド(WC)を硬質相とし、コバルト(Co)をバインダとした複合材料であり、1923年にドイツで発明され、1927年に「ウィディア」と名付けられて独クルップ社から発売された。当社も1928年に線引きダイスの試作に成功、1931年には切削用バイトとして商品化し、2011年に「イゲタロイ®」誕生80周年を迎えることができた。鋼切削用工具として古くは1900年代初頭に高速度鋼(ハイス)工具が登場したが、超硬合金はハイスよりも高速加工が可能であり、更に1970年代後半にはアルミナやTi化合物を被覆したコーティド超硬が開発され、より高速で切削が可能となり、80年間の歴史を経ても今なお切削工具材料の中で主流の座を占めている。その他、ジェットエンジン材料の開発から生まれたサーメット(TiCN-Ni)工具は鋼材料に対する低い親和性 を活かして仕上げ切削に用いられ、アルミナ酸化物(Al2O3)、窒化珪素(Si3N4)などを主体にしたセラミック工具もその耐
205 KB
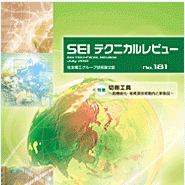
205 KB
Various efforts have been undertaken to lessen the environmental burden. In the automotive industry, for example, cast iron parts and other components have been made lighter mainly to reduce exhaust gas emissions and improve fuel efficiency. For the weight reduction, these components have increasingly thin walls and complex designs, and thus, high-strength, difficult-to-cut materials are used. Meanwhile, there is also a strong demand for high-speed and high-efficiency machining to reduce lead
0.6 MB

0.6 MB
“SUMIBORON” PCBN (polycrystalline cubic boron nitride) tools are widely used in the cutting of hard-to-cut ferrous materials, such as hardened steel, cast iron and powder metal, and contribute to productivity growth and cost reduction for metalworking. In the recent growing automotive industry, the machining of cast iron and powder metal parts has been increasingly required. Conversely, however, the machinability of these parts has been degraded because of their high functionality.
0.5 MB

0.5 MB
The authors have succeeded in the production of single-phase (binderless) nano-polycrystalline diamond (NPD) by the direct conversion sintering of graphite at ultra-high pressure and temperature. NPD, consisting of diamond grains of several tens of nanometers, features fine texture, extreme hardness, and high strength without showing cleavage features and anisotropy of mechanical properties. These salient characteristics indicate that NPD has outstanding potential as industrial material
0.5 MB

0.5 MB
General-purpose face milling cutters are widely used in metal machining. These tools are required to reduce machining cost and offer a wide range of applications. Furthermore, they need to ensure excellent surface finishing for highly functional parts. To address these challenges, Sumitomo Electric Hardmetal Corporation has developed a new milling cutter “SEC-Dual Mill DGC” series for general-purpose face milling. This series employs negative inserts which can be used on both sides to enable
324 KB

324 KB
Grooving is widely applied in machining automotive parts and other industrial components. Compared with general cutting, however, grooving is subject to problems such as difficulty in chip evacuation, which can result in defective groove surfaces, and tool vibration due to the high load operation with the entire cutting edge width. To improve processing efficiency and accuracy while minimizing the cost of grooving tools, Sumitomo Electric Hardmetal Corporation has developed new grooving tools
0.6 MB

0.6 MB
In recent years, mold manufacturers have been prompted to provide low-cost, high-precision products and shorten the delivery time in response to the miniaturization of products and price competition in the global market. Due to this trend, mold manufacturers desire to shift their manufacturing method of hardened steel from electric discharge processing with copper electrodes to direct cutting. Sumitomo Electric Hardmetal Corporation has newly released the cubic boron nitride (CBN) BNBR endmills
0.6 MB
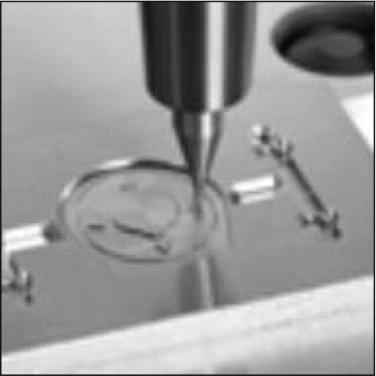
0.6 MB
Tungsten is a base material of cemented carbide tools widely used in automotive, electronic equipment, construction and other industrial fields. Since tungsten is a rare metal produced in a limited number of countries, it is subject to supply risks. We have addressed this problem by recycling and reducing the use of tungsten. While the hydrometallurgy process that we developed for recycling can recover tungsten oxide with nearly the same quality as ore refining from any kind of scrapped cemented
1 MB
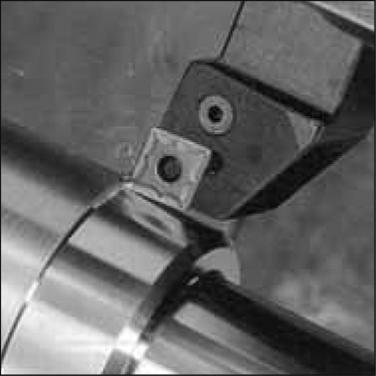
1 MB
Gallium nitride (GaN) and other nitride compound semiconductors show high potential as optical and electronic devices. Sumitomo Electric Industries, Ltd. has been researching this potential, and in the early 2000s succeeded in developing the world’s first 2-inch GaN single crystal substrates with high quality and low dislocation density, which were essential features for violet lasers, by using vapor phase growth technique. Moreover, we have worked on the development of optical and electronic
0.6 MB
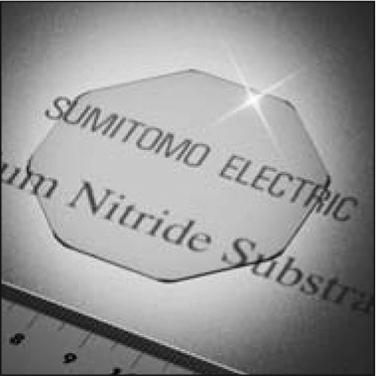
0.6 MB
Radiation chemistry is commonly used in manufacturing industrial products such as heat resistant electrical wires used in the electrical appliances, rubber material used in automotive tires, heat shrinkable tubes and films, foamed material, and battery separators. In radiation chemistry, electron beams are more widely used than gamma rays because of the good handling and operating characteristics, particularly for safety reasons. NHV Corporation has been concentrating its efforts on the
0.5 MB
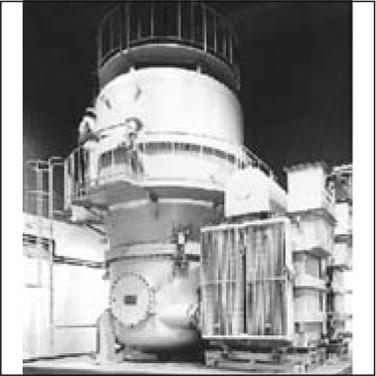
0.5 MB
Sumitomo Electric Industries, Ltd. has developed magnetic powder core materials for power inductors used in eco-friendly vehicles. Pure iron based powder cores with an operating frequency range from 10kHz to 30kHz have been used for boost converter reactors in hybrid-electric vehicles (HEVs), while low-loss Fe-Si-Al alloy powder cores with an operation range of several hundred kHz have shown the potential to replace ferrite cores for buck converter choke coils. Our low-loss alloy powder cores
0.7 MB
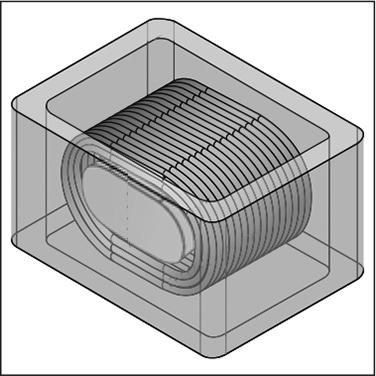
0.7 MB
Sumitomo Wiring Systems, Ltd. designs and develops rubber grommets used for the protection and sealing of automotive wiring harnesses. These grommets are required to have good sealing properties, reduce the insertion force, and increase the removing force. To evaluate the insertion and removing forces, we use computer-aided engineering (CAE), in which the calculation results conform to the experimental results by reflecting the frictional force and material properties. We can also evaluate the
0.6 MB
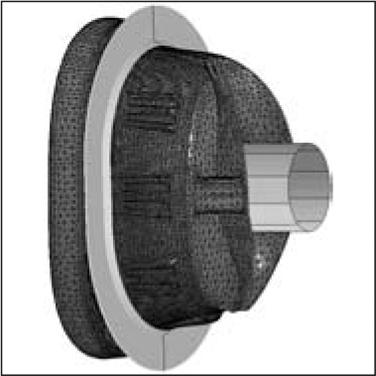
0.6 MB
As the optical access network expands, there is an increasing demand for optical fiber cables that improve Fiber-to-the-Home (FTTH) network installation and maintenance efficiency. To meet this demand, bend insensitive fibers (BIFs) have been developed. Among BIFs, hole-assisted fiber (HAF) shows excellent bending loss characteristics by the strong light confinement effect of air-holes surrounding the center core. Recently, single-mode HAF (SM-HAF) has been demonstrated to show low bending loss
307 KB
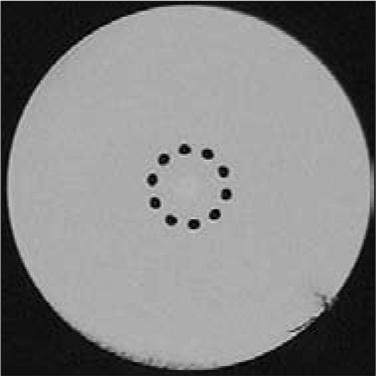
307 KB
As of September 2011, the number of FTTH subscribers in Japan has reached 21 million and is forecast to increase at a consistent pace. To construct FTTH networks more economically, a distribution system using underground conduits has been proposed. In this system, distribution cables are installed in underground conduits and drop cables are routed to each subscriber’s home upon request for FTTH service at the midpoint of distribution cable. Here we have developed 40-fiber and 100-fiber cables
0.4 MB

0.4 MB
As the amount of Internet traffic increases every year, expectation is growing for 10 Gigabit Ethernet passive optical network (10G-EPON) technology that enables high-speed data transmission. For a smooth replacement of the currently-used GE-PON, 10G-EPON needs to support a maximum channel insertion loss of 29 dB and to coexist with GE-PON in the same optical network. In addition, reduction in capital and operating expenditures is required. To meet these demands, optical transceivers can be a
0.4 MB

0.4 MB
The authors have successfully developed optical transceiver modules operating at 43 Gbit/s and 112 Gbit/s. They are compliant with the ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector) standard and the CFP MSA (Centum gigabit Form factor Pluggable Multi-Source Agreement) specification and they showed excellent performance with lower power consumption by leveraging in-house optical devices, ICs, and optical subassemblies. This paper describes the outline of
0.4 MB
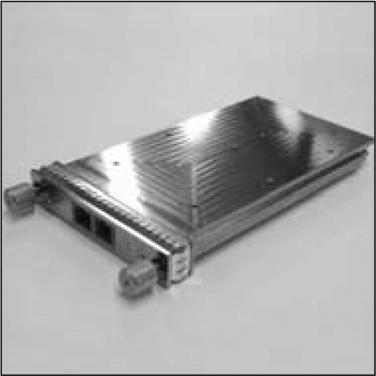
0.4 MB
Existing license plate detection methods have a good success rate in detecting one or a few fixed formats, however, they may fail in some cases such as motorcycles in Japan and foreign vehicles traveling across national borders. The authors have developed a novel method to detect different types of license plates. This method employs Histogram of Oriented Gradients (HOG)-based bag-of-features, which enables the detector to identify characters’ common curves on different types of plates.
325 KB

325 KB
In Japan, automatic license plate recognition systems have been used for more than ten years for measuring the time required for a vehicle to travel between different points and for applications which need detailed plate information. Due to their efficacy, these systems are now being utilized throughout the country. To better respond to the requirements in these applications, we have developed an automatic license plate recognition device that features a high recognition rate, low failure rate,
0.4 MB

0.4 MB
Flexible printed circuit (FPC) boards need to have fine pitch patterns for lighter, thinner and smaller electronic equipment, and connection technology for metal layers (other than copper) is required for FPC diversification. Conductive paste via connection technology offers advantages for manufacturing fine pitch FPC boards and can be applied to non-copper metal layers. The authors have developed highly reliable via connecting technology using conductive paste containing silver nano particles.
0.4 MB
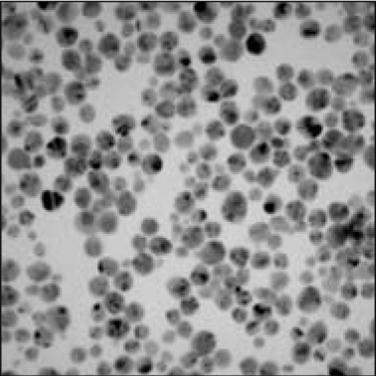
0.4 MB
This paper proposes use of polycrystalline spinel for the temperature compensation of radio frequency (RF) surface acoustic wave (SAW) devices. It shows that spinel can be bonded with LiTaO3 (LT) and LiNbO3 (LN) wafers using the adhesive and direct bonding techniques. Series of RF SAW resonators were fabricated on the LT (LN)/spinel structure, and their performance, including the temperature coefficient of frequency (TCF), was measured. For comparison, SAW resonators employing Si and sapphire
290 KB
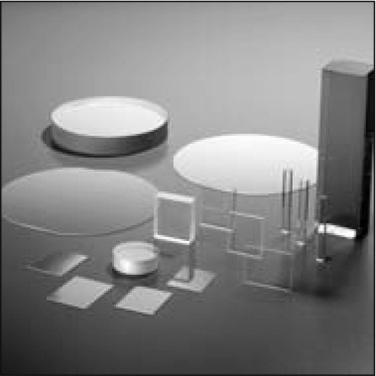
290 KB
Thunderbolt is an innovative high-speed input/output (I/O) technology developed by Intel Corporation. It enables 10Gbp/s transmission between a computer and peripheral devices. Based on Intel's technical specifications, Sumitomo Electric developed a Thunderbolt electrical cable by combining its advanced cable technology with the high-speed transmission technology. The Thunderbolt cable utilizes differential data transmission technology using pairs of coaxial cables that boast excellent signal in
2.6 MB

2.6 MB
With a record-low birthrate and rapidly-growing elderly population, Japan faces a severe demographic challenge compounded by a chronic lack of nursing-care staff. High-function welfare apparatuses are attracting attention as effective tools to reduce the burden of caregivers and to compensate for the lack of nursing-care staff. Related research and development have been widely conducted, and as a result, the necessity of flexible tactile sensors as human-machine interfaces is increasing.
0.6 MB

0.6 MB
A DC micro grid system has been proposed as a power network that enables the introduction of a large amount of solar energy using distributed photovoltaic generation units. To test the feasibility of the system, we have developed a demonstration facility consisting of silicon photovoltaic (Si-PV) units, copper indium gallium (di)selenide photovoltaic (CIGS-PV) units, concentrating photovoltaic (CPV) units, an aerogenerator, and redox flow battery. The redox flow battery,
0.5 MB
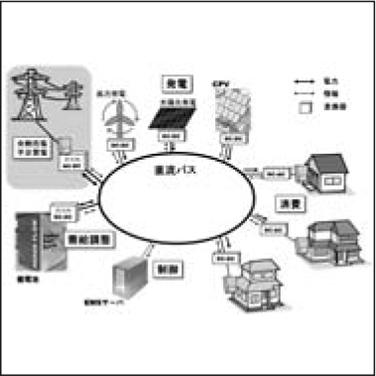
0.5 MB
The authors have developed a novel porous metal with high corrosion resistance. Porous materials are used in fuel cells as the current collector and gas diffusion layer of the electrode. Typical porous materials include carbon sheet, molded carbon and porous metals such as stainless used steel (SUS) and nickel chrome (Ni-Cr) alloys. Among these materials, porous metals are preferable because of their high gas diffusion performance. Because of the highly oxidizing atmosphere in fuel cells,
329 KB
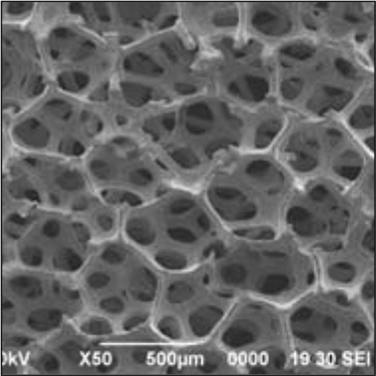
329 KB
High-carbon steel wires, such as piano, hard-drawn, or oil-tempered wire, are used for automotive and electronic parts. Despite their outstanding advantages in strength, ductility, and fatigue resistance, these wires are susceptible to fracture due to the brittle as-quenched martensite structure formed by welding. To overcome this problem, we have developed a high-strength steel wire that consists of a bainitic matrix phase to enhance weldability, by adding carbide former elements to low-carbon
0.4 MB

0.4 MB
This year celebrates the centennial anniversary of the discovery of superconductivity by Prof. Heike Kamerlingh Onnes in 1911. High-temperature superconductivity (HTS) was also discovered 25 years ago, and its actual implementation has just started. The International Electrotechnical Commission (IEC) has promoted the standardization of superconductivity since the foundation of Technical Committee 90 in 1989. This paper describes the present status of international efforts to standardize
307 KB

307 KB
A new voltammetric method using a strongly alkaline electrolyte (6 M KOH + 1 M LiOH) as the supporting electrolyte was applied to the simultaneous determination of copper oxides and sulfides. It was found that the reduction peak of Cu2S was well separated from those of copper oxides and appeared at a slightly higher potential than that of Cu2O. On the other hand, Cu2O was reduced prior to the reduction of Cu2S in 0.1 M KCl, which has frequently been used as an electrolyte for conventional method
0.5 MB
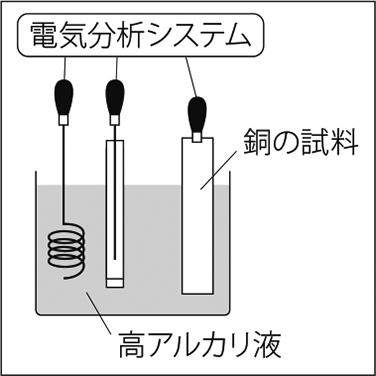
0.5 MB
Single-phase (binderless) ultra-hard nano-polycrystalline diamond (NPD) has been successfully synthesized by direct conversion sintering from graphite under ultra-high pressure and high temperature. The hardness of NPD is considerably high, far surpassing that of single-crystal diamonds even at high temperature. In addition, NPD shows outstanding strength, possessing no cleavage features and no anisotropy of mechanical properties. The NPD consists of very fine grains of several tens nanometers
0.7 MB

0.7 MB
Semiconductor quantum devices, composed of semiconductor quantum wells and superlattices, are widely used in our daily lives as key devices for opto-electronic equipment. The quantum well structure consists of alternating ultra-thin semiconductor films, in which electrons and holes are confined. This structure gives rise to discrete energy levels and minibands in their potential wells, and thus induces new properties of materials. With these properties applied to devices, tremendous improvement
0.8 MB
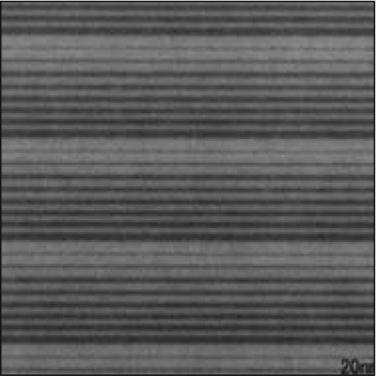
0.8 MB
To reduce traffic accidents and serious injuries at intersections, the development of cooperative driving support systems and related sensors has been promoted. Along with this movement, the authors have developed a “hybrid image sensor” that consists of visible-ray cameras and far-infrared-ray (FIR) cameras to compensate each other. The images taken by these cameras are processed simultaneously, thereby covering various conditions including nighttime, shadows, and high temperature.
0.5 MB

0.5 MB
Internal gear pump rotors are powder metallurgy parts widely used in oil pumps of automobile engines, automatic transmissions (ATs), and continuously variable transmissions (CVTs). In the recent development of energy-efficient environmental-friendly automobiles, oil pump rotors are required to reduce their size while maintaining sufficient discharge volume. To meet the requirements, we have developed a highly efficient oil pump rotor with a new tooth profile “Geocloid.”
1.9 MB

1.9 MB
GE-PON (Gigabit Ethernet-Passive Optical Network) systems have been widely used for broadband access services. As the next generation technology of GE-PON, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3 Working Group standardized 10G-EPON in 2009 to define physical layer and data link layer specifications, and IEEE P1904.1 (SIEPON: Service Interoperability in Ethernet Passive Optical Networks) Working Group has currently been working on the standardization of upper layer protocol
0.4 MB
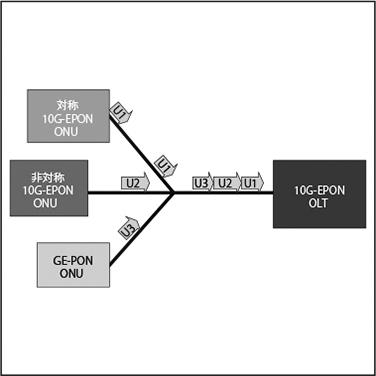
0.4 MB
Facing the rapid increase in data traffic, mobile operators have become interested in small cellular base stations, such as picocells and femtocells, to improve network capacity. Picocells and femtocells, however, may cause inter-cell interference when operated in the same channel with macrocells. To overcome this problem, we have studied an interference suppression method using an array antenna system for the 3rd Generation Partnership Project(3GPP)Long Term Evolution(LTE)uplink based on
1.7 MB

1.7 MB
We have developed a new heat-resistant optical fiber coated with UV (ultraviolet) curable silicone resins. Its diameter (250 µm) is thinner than that of the conventional heat-resistant optical fiber coated with thermosetting silicone resins and a poly (tetrafluoroethylene-co-perfluoropropylvinylether) (PFA) outer sheath. While showing excellent heat-resistance at 200˚C, it has microbending resistance and dynamic fatigue property superior to those of the conventional heat-resistant optical fiber.
0.8 MB
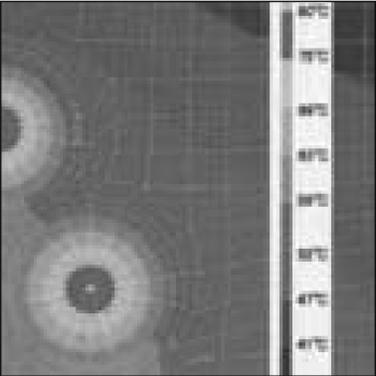
0.8 MB
The authors have developed new EA (electro-absorption modulator) driver ICs for both 25 Gbit/s and 40 Gbit/s transmission. These ICs achieve low power dissipation and high bit-rate operation by adopting the InP D-HBT (double-heterojunction bipolar transistor) process and optimizing the circuit configurations for each bit rate. In addition, the authors have successfully reduced the size of optical transmitter modules by building the EA driver ICs with the DFB (distributed feedback laser) chips in
0.5 MB
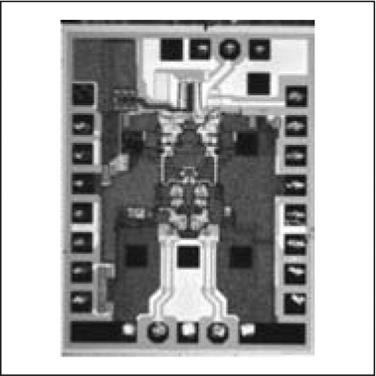
0.5 MB
High-power broadband devices are increasingly required for microwave wireless communication systems such as terrestrial and satellite communication over 6 GHz (e.g., C-band). Formerly, GaAs devices have been used in these systems, however, the properties of GaAs are not sufficient to meet the high-power broadband requirements. To address this challenge, we have focused on the superior physical properties of GaN. Based on our established GaN high electron mobility transistor (HEMT) technology for
0.4 MB
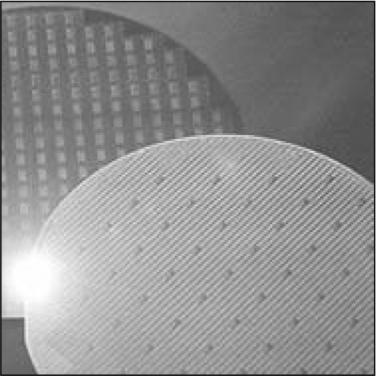
0.4 MB
This paper describes the newly developed 8-fiber bunched indoor cable that enables fast and easy installation to MDUs (Multiple Dwelling Units). The cable is composed of eight indoor cable elements, each of which has a thin and light-colored jacket. The cable is installed on the outside wall of an apartment house, and each element can be extracted at a subscriber’s residence. The thin elements are beneficial for easy installation and the light-colored jacket can improve the externally appearance
291 KB
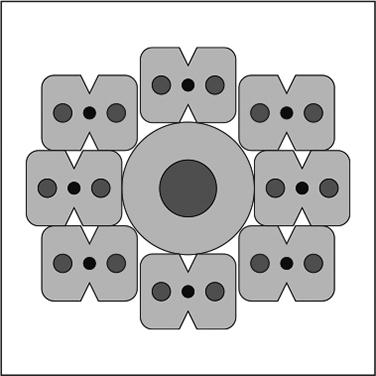
291 KB
As electronic equipment has reduced in size and advanced in processing speed, the heat density of such equipment has increased, and therefore, thermal design has become more important to release the heat effectively. Since the early 1990s, SimDesign Techno-center, a business unit of Sumitomo Electric System Solutions Co., Ltd., has applied simulation technology to its thermal design development. Due to the rapid advancement of electric equipment, conventional thermal designs using fans, vents,
0.6 MB
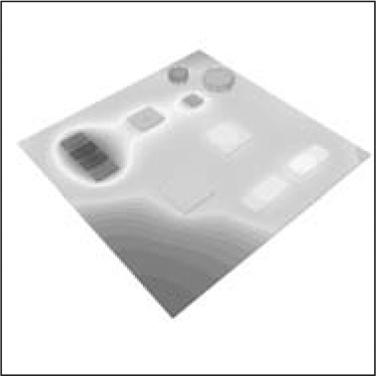
0.6 MB
With the current increase in information traffic, even higher speed and density transmission is required for access network equipment. To meet this demand, optical transceivers capable of operating in high-temperature environments and saving energy are indispensable. Thus far, development has been focused on 10-Gbit/s semiconductor lasers that cover a wide temperature range. Since the standardization of 100 Gigabit Ethernet in June 2010, directly modulated 25-Gbit/s lasers have been developed to
2.3 MB

2.3 MB
High electron mobility transistors (HEMTs) with AlGaN channel layers are promising for the next-generation high-power and high-frequency electron devices. These are expected to show higher breakdown voltage and better high-temperature characteristics than GaN-channel HEMTs since AlGaN has a higher breakdown field and larger bandgap energy than GaN. However, epitaxial growth of the structure is difficult because of the large lattice mismatch between GaN and AlGaN.
0.6 MB
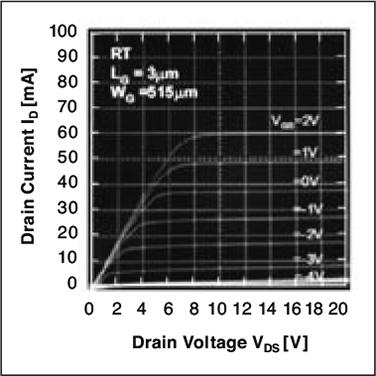
0.6 MB
Soft magnetic powder cores are used for electromagnetic conversion coils which are essential for automotive, home appliance, and electronics industries. These cores, manufactured by compacting pure iron powder covered with an insulation film, are distinguished by their high electromagnetic conversion efficiency. However, the electromagnetic conversion efficiency drastically decreases when they are subjected to the conventional finishing process. This is directly attributable to the conductive
0.6 MB

0.6 MB
All-solid-state batteries do not use a flammable organic liquid electrolyte which has a risk of boiling, freezing, or burning, and are therefore expected to operate in a wide temperature range. This paper reports on the development of a solid-state thin film lithium battery using a high conductive sulfide solid electrolyte and its charge-discharge characteristics at high and low temperatures. The high ionic conductivity of the sulfide solid electrolyte can reduce internal resistance,
0.6 MB
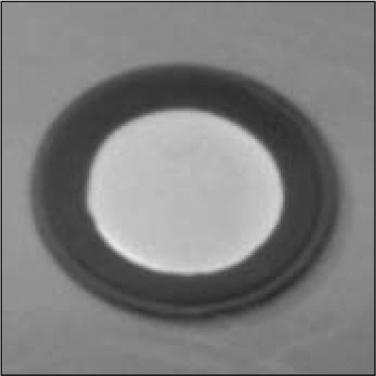
0.6 MB
The authors have developed new ammonia gas removal device using fuel cell technology. In this device, YSZ (yttria stabilized zirconia) is used for the solid electrolyte, LSM (lanthanum strontium manganate) for the cathode, and Ni/YSZ porous cermet for the anode; and ammonia gas flows through them. The porous Ni (Celmet®) is applied to the current collector, which also functions as the gas diffusion layer of the anode. Chained Ni powder made by the titanium-redox method is used for the anode
4.4 MB

4.4 MB
Tokai Rubber Industries, Ltd. (TRI) has developed window films for solar shading and heat insulating applications by combining its advanced technologies of optical multi-layered membrane design, precision coating, and elongated spattering as well as accumulated knowledge of materials. An optical function membrane is a multi-layered membrane that consists of thin Ag alloy membranes and thin dielectric membranes with a high refractive index. TRI has significantly reduced the manufacturing cost of
1.2 MB
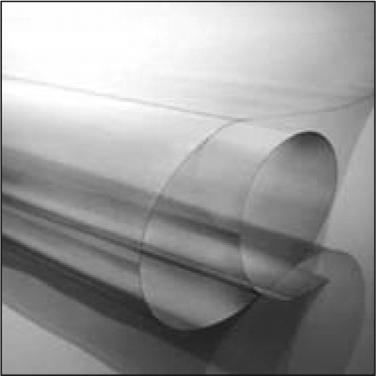
1.2 MB
Many countries and regions all over the world have turned into information societies, where significant volume of data is transmitted ubiquitously. Communication infrastructure that supports these information societies is largely depending on optical and wireless communication technologies. Optical transmission technology in particular is playing an important role in various applications including public communication systems, local area networks, FTTx networks, computer peripheral devices and
0.4 MB
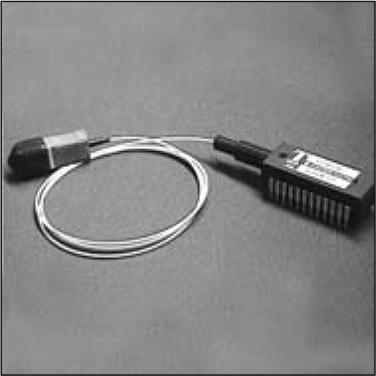
0.4 MB
Renewable energies, such as solar and wind power, are increasingly being introduced as alternative energy sources on a global scale toward a low-carbon society. For the next-generation power network, which uses a large number of these distributed power generation sources, energy storage technologies will be indispensable. Among the energy storage technologies, battery energy storage technology is considered to be most viable. In particular, a redox flow battery, which is suitable for large
0.8 MB
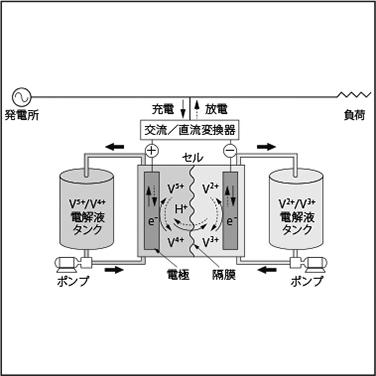
0.8 MB
This paper describes technologies related to passive optical components, such as fused fiber couplers, optical filters, splitters and fiber gratings. These components have been actively deployed in FTTH (Fiber to the Home) networks. A splitter connects transmission equipment at a central office to many users, leading to economical PDS (Passive Double Star) networks. A splitter with a directional coupler circuit or an optical filter enables multiplexing of video signals.
1 MB

1 MB
Nissin Ion Equipment Co.,Ltd. has been mainly engaged in the manufacturing and sales business of medium current ion implanters for manufacturing semiconductor devices since its establishment. The EXCEED® series has been widely acknowledged by device manufacturers for its quality in the basic machine concepts and for its continued supplies of the leading-edge models that meet ever-changing customer requirements. This paper reviews improvements in the system performance and key technology
0.7 MB

0.7 MB
In PC steel bar production, Sumitomo Electric Industries, Ltd. uses direct heat treatment technique utilizing sensible heat from hot rolled steel bars. To produce high tensile strength PC steel bars with pearlite microstructure, mist cooling is conducted using a mixture of water and air as a coolant after hot rolling. This technique enables us to control the temperature where pearlite transformation starts and the resulting heat generation. This paper introduces the direct heat treatment
0.5 MB
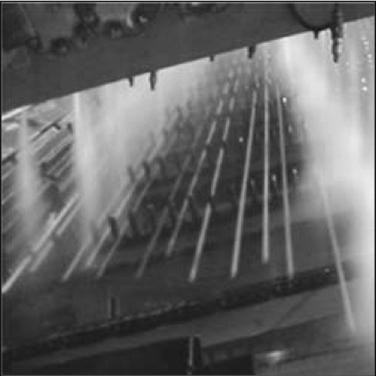
0.5 MB
As a global warming countermeasure, reduction of carbon dioxide and improvement of fuel efficiency have become increasingly important. Recently, automotive manufacturers have been developing not only hybrid electric vehicles (HEV), but plug-in hybrid electric vehicles (PHEV) and electric vehicles (EV), which are more effective on carbon dioxide reduction. The vehicles, such as PHEV and EV, have an AC/DC converter which supplies electric power from a commercial power system to an onboard
0.4 MB

0.4 MB
In order to reduce the amount of CO2 exhaust, we are required to develop light weight wiring harnesses. Aluminum wiring harness is one of the solutions for weight reduction of automobiles. However, we have to consider some negative points of Aluminum wire such as lower conductivity, lower strength, oxide layers on a wire surface and galvanic corrosion. To solve these problems, we have developed a special Al alloy conductor, terminal with unique serrations and anti-corrosion technology.
0.6 MB
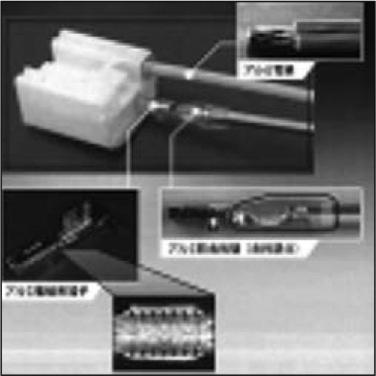
0.6 MB
In this technical paper, the authors propose an analyzing method of the root causes for software problems. To prevent the recurrence of the same problems, it is necessary to logically identify the root causes and take appropriate measures. Therefore, the authors applied “the 5 whys analysis,” a technique that has been used mainly in the manufacturing process, to the trouble shooting of software. First, the authors visualized the procedures of software design by arranging documents illustrating
0.4 MB
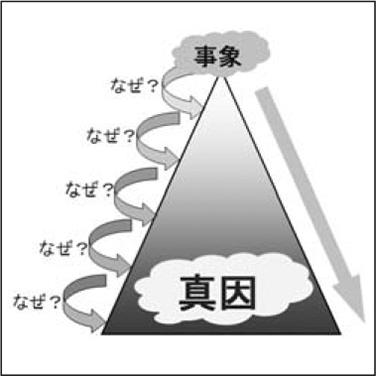
0.4 MB
The Japanese government has planned to operate a new radio communication system for improving vehicle safety. In this system, on-car units send packets including information of their location and speed to each other according to CSMA (Carrier Sense Multiple Access) procedures. However, when radio wave is blocked by buildings and some units cannot detect others, two or more units can send their packets simultaneously. This can cause a packet collision called “hidden terminal problem,”
0.5 MB
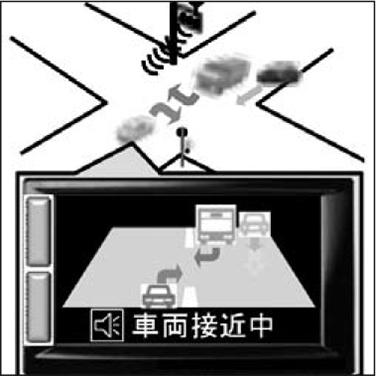
0.5 MB
Due to the spread of mobile devices and the evolution of mobile broadband networks, a larger number of mobile device users watch video contents on their own devices. The authors have developed a USB-connected transcoder to convert high-quality contents into suitable formats and qualities for mobile devices. This development allows existing recorders and broadcast receivers to make MP4 files and to send streaming video data to video devices via IP networks.
0.4 MB
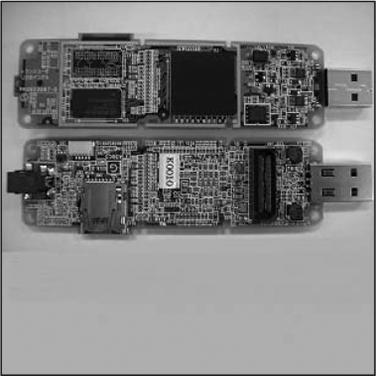
0.4 MB
The fiber optic data transmission system plays an important role in broadband communication. According to the market trend, data traffic is significantly increasing and larger throughput of communication systems is required. Many opto-electronic conversion devices (so called optical transceivers) are used in the system. Because of that, the electro-magnetic noise radiation becomes a serious consideration. Although the noise level is proportional to the number of transceivers,
0.5 MB
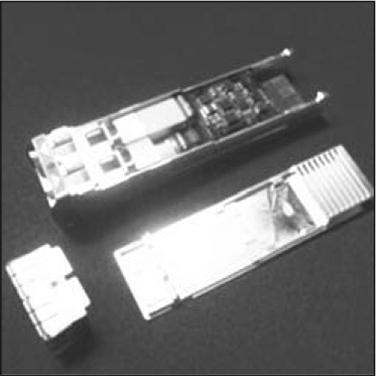
0.5 MB
A novel image processing vehicle detector has been developed and released to the market. We have resolved defects seen in conventional detectors, most of which are caused by weather changes or lack of resolution. To overcome these problems, we have adopted two approaches: the improvement of algorithms for vehicle detection, and the use of a high resolution camera. These improvements have enabled the product to provide stable performance all day throughout the year and also to detect vehicles
0.4 MB

0.4 MB
A multi-core flexible flat cable has been used for electric wiring of electronic appliances. Along with the increase of electronic equipment installation in automobiles, the application of the flexible flat cable for automotive use has been increasing due to the advantage of its flat shape for high-density and compact wiring space. Sumitomo Electric Industries, Ltd. has continuously developed and manufactured various kinds of new flexible flat cable products for electronic appliances.
291 KB
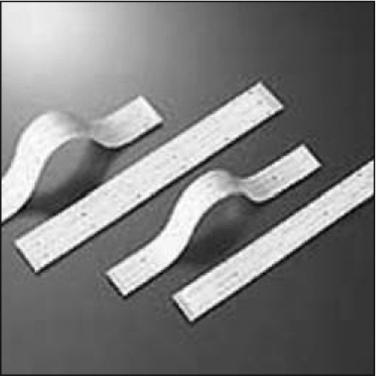
291 KB
Anisotropic conductive film (ACF) is a film adhesive with conductive particles dispersed in thermosetting resin, and is mainly used for circuit board connection in the field of liquid crystal displays (LCDs), mobile phones, TVs, etc. High performance LCDs strongly requires ACF that is applicable to the connection of circuit boards with narrow pitch electrodes. We have developed a new concept ACF for the connection of circuit boards using our nickel nano straight-chain-like particles.
321 KB
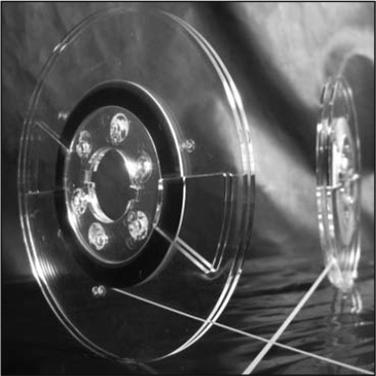
321 KB
To improve the luminous efficiency of white light-emitting diodes (LEDs) for general lighting, the InGaN-based-LEDs with thick quantum wells (QWs) were examined on our unique freestanding gallium nitride (GaN) substrates with low dislocation density. With LEDs on sapphire substrates, which are currently commonly-used, the crystalline quality of QWs was deteriorated and the luminous efficiency was degraded with the increase in the total thicknesses of InGaN QWs.
0.4 MB
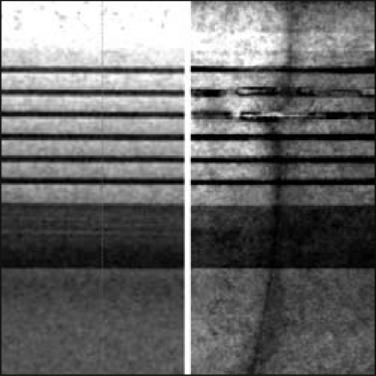
0.4 MB
R&D efforts have been made for various applications of high temperature superconducting (HTS) conductors such as power cables, high field magnets and transformers. In Japan, a national project to develop materials and power applications using coated conductors was started in 2008. Since then, we have been fabricating pulsed laser deposition (PLD)-GdBCO tapes for the development of a 5 kA, 66 kV class 3-in-One HTS model cable system as a part of this project. In order to construct the HTS
0.9 MB
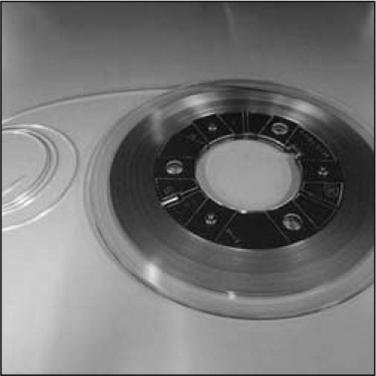
0.9 MB
Hard materials for cutting tools include cemented carbides (WC-Co) and cermets (TiCN-Co/Ni). Tungsten, the main component (about 80 vol%) of cemented carbides, is subject to supply risks. On the other hand, titanium, the main component (about 70 vol%) of cermets, is at a much lower risk than tungsten. This work evaluates a composite structure of cemented carbide and cermet to reduce tungsten usage while maintaining the performance of the cutting tool.
0.4 MB

0.4 MB
Machines used at construction and industrial sites are required to cut large and complex shaped parts and shave off large cast surface areas. However, this can lead to major problems such as time consumption and short tool life. To overcome these problems, Sumitomo Electric Hardmetal Corporation has developed a new milling cutter “DNX series” for cast iron and cast steel milling. This series enables a large depth of cut at a high feed rate, thereby enhancing milling efficiency. Moreover,
326 KB

326 KB
Cast iron is widely used in various products for daily applications and industrial machine components. In the automotive industry, growing global awareness on environmental issues has required the improvement of fuel efficiency. Accordingly, the ratio of the automotive parts made of ductile cast iron is increasing for weight saving. However, while superior in tensile strength, ductile cast iron parts are inferior in machinability to those of gray cast iron.
0.7 MB
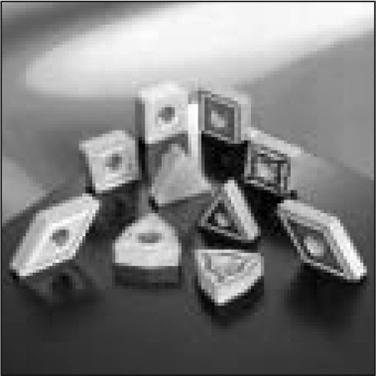
0.7 MB
Sumitomo Electric Industries, Ltd., and Sumitomo Electric Networks Inc., leading companies in the broadband network equipment market in Japan, have jointly developed an energy management system targeting homes and small offices by applying information and communication technologies which have been accumulated in the Sumitomo Electric Group. This energy management system is comprised of a smart power strip and a power distribution board, both of which can measure electric power consumption and
0.5 MB

0.5 MB
In the construction industry, industrial waste is becoming a big problem of construction pollution. Above all, construction sludge has a bad recycling rate, and the surplus muddy water which is a side product of underground power transmission line construction was usually treated as industrial waste. For environmental protection and expense reduction, Sumitomo Densetsu Co., Ltd. has developed a pipe filling material using the surplus muddy water. The author reports on the development process and
0.4 MB

0.4 MB
This paper looks back on the history of the development of measurement technology that has contributed to the improvement of quality assurance levels of Sumitomo Electric Industries, Ltd. for 50 years. It also includes technical explanations of the measurement and inspection equipment that the company has recently developed as well as crack detection technology on which the company has particularly focused its efforts. Finally, this paper describes the future of image processing technology and
0.5 MB
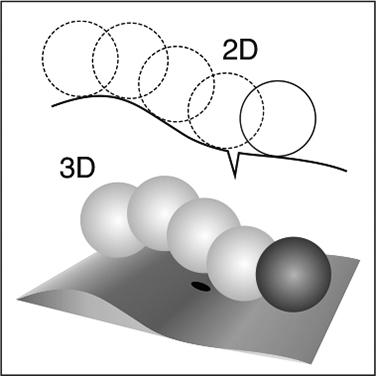
0.5 MB
Many different compound semiconductors can be formed by changing the combination of constituent elements. Properties of alloy semiconductors, mixture of multiple compound semiconductors, can be changed in a continuous fashion by changing the mixing ratio. Very thin alloy semiconductor multilayers, which show interesting properties, can be formed by sophisticated epitaxial growth method such as MOVPE (metalorganic vapour phase epitaxy) or MBE (molecular beam epitaxy). Based on these matters,
0.5 MB
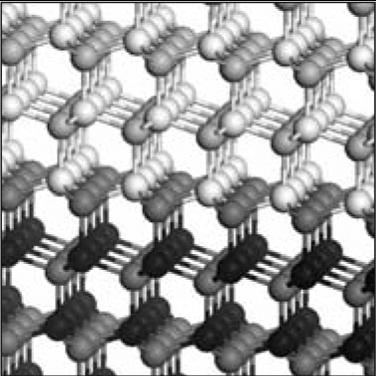
0.5 MB
The electromagnetic field analysis is an indispensable method for designing and developing electric machines. Although the development of electromagnetic field analysis software has simplified the process of analyzing electromagnetic fields, it is still important to understand the electromagnetic theory to construct analytical models and evaluate results. Nevertheless, it is difficult for the beginners to acquire knowledge of this field. In this paper, the author summarizes the basics of
0.4 MB
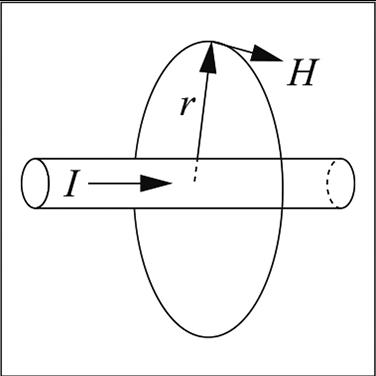
0.4 MB
ZnSe based white LED can be fabricated by homoepitaxial growth on ZnSe conductive substrate. This LED emits white light by mixing the blue−green emission from the ZnCdSe active layer and the deep level yellow emission from the ZnSe substrate excited by the active layer emission. Large conductive ZnSe substrates with high quality are required for this device application. The vapor growth techniques, such as PVT (physical vapor transport) method and CVT (chemical vapor transport) method, were
0.5 MB
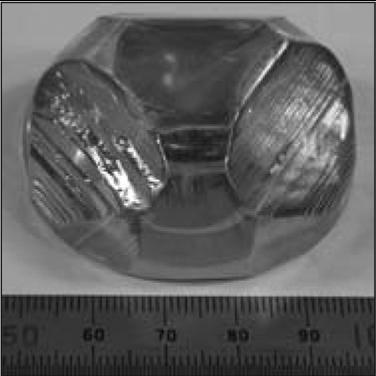
0.5 MB
The history of multilayered, three-dimensional monolithic microwave integrated circuit (3-D MMIC) technology is described here. Significant researches were carried out in the second half of 1990’s, however, there were many twists and turns before and after the era. Since 2008, an aggressive and realistic development of 3-D MMIC Wafer Level Chip Size Package (WLCSP); for extremely low cost and surface-mount compatible MMIC products, has been performed to provide a one-stop solution for
0.6 MB
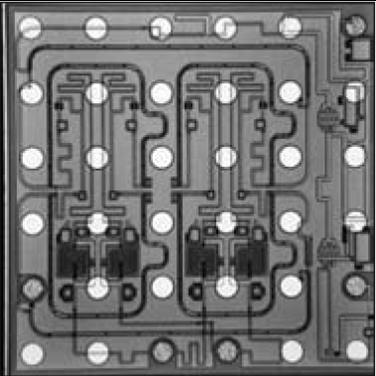
0.6 MB
Printed circuit boards (PCB), widely used in electronic devices, have been increasingly improving in performance, cost effectiveness and miniaturization. This trend seems to continue for a while, and accordingly, further sophisticated microdrills are also required for precise drilling of PCB. We, at Sumitomo Electric Hardmetal Corp., have produced cemented carbide materials to be used for microdrills for many years, and commenced mass-production of special materials for composite-type
0.4 MB
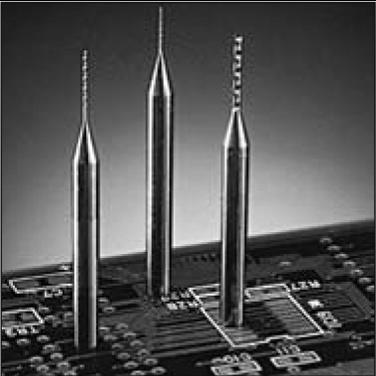
0.4 MB
SEI Technical Training Center (TTC), which provides a variety of in-house training programs, has developed a learning course for junior high school students. In this course, they can experience the joy of monozukuri through a “crafting spinning top” competition, a team game of crafting long-spinning tops by using the quality control method. TTC believes that such experience will allow students to become interested in science and manufacturing afterwards, and that cooperation between industry and
0.4 MB

0.4 MB
Recently, global warming has become a serious social problem. Growing concerns over this issue have prompted us to develop environmental-friendly automobiles such as hybrid electric vehicles (HEVs), plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs), electric vehicles (EVs) and fuel cell vehicles (FCVs). For these eco-friendly vehicles to be widely used, their driving performance and power of acceleration must be equivalent to those of gasoline-fueled vehicles. To meet these requirements, boost converter
0.4 MB
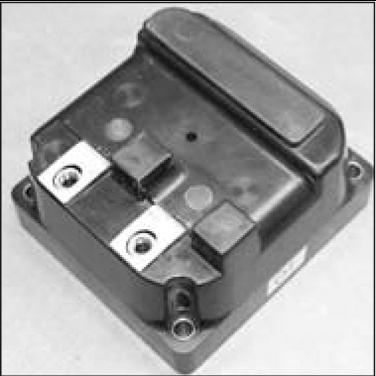
0.4 MB
Recently, there has been a growing trend toward a low carbon society. In the field of energy, development of clean power generation systems, such as solar and wind generators, have been promoted. Electric vehicles are also replacing petrol vehicles in the automotive industry, and energy-saving electrical appliances are expected more than ever. Due to this trend, small and powerful power-supply devices with better conversion efficiency are increasingly demanded, and accordingly,
0.5 MB
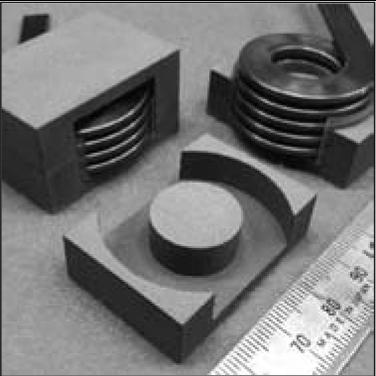
0.5 MB
A multi-agent system which can forecast traffic conditions based on probe car data with data mining method has been developed. This system consists of estimation and learning agents assigned to road links. Estimation agents renew normalized congestion level for each road link, while learning agents renew weight values for estimation. The weight values are calculated by multivariate analysis. Estimation and learning agents provide calculated results alternately to improve the accuracy of forecast
0.5 MB

0.5 MB
This paper describes the cost effective 77 GHz transmitter and receiver MMIC (monolithic microwave integrated circuit) that uses a three-dimensional MMIC technology optimized for flip-chip implementation. The MMIC structure incorporates inverse TFMS lines so that a ground metal can be applied to cover the whole chip surface except for interconnect pads. Four metal layers, including the ground metal, are formed between and the top surface of polyimide layers each of which is SiN coated for
0.3 MB
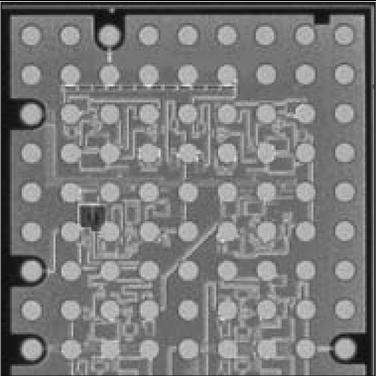
0.3 MB
The authors have successfully developed new TOSAs (Transmitter Optical Sub-Assembly) which are operational for a wide operating temperature range from -40 to 90 degree C and high speed of 10 Gbit/s or more. The device introduced multi-layer ceramic packages with a precisely controlled characteristic impedance and wide frequency characteristics up to 23 GHz. In addition, an optical system using front facet monitoring technique has achieved stable tracking error characteristics within ±0.2 dB.
0.4 MB
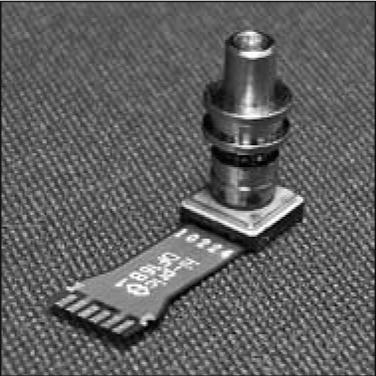
0.4 MB
This paper describes the newly developed SZ-slotted core optical fiber cable that provides fast and easy mid-span access. The cable uses new wrapping tape that can be peeled easily and safely without using any cutting tool, thus reducing the time required for mid-span access operation. The result of the mid-span access test confirms that the newly developed cable enables safe and easy mid-span access operation and 40% operation time reduction. These advantages are beneficial to
0.4 MB
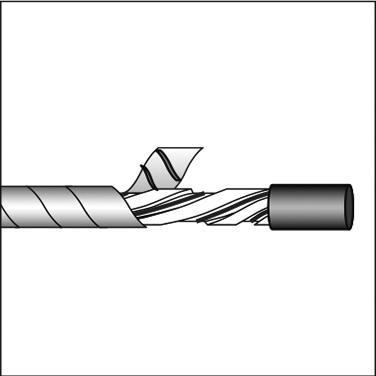
0.4 MB
As the signal processing speed of electronic devices increases, transmission capability over 10 Gbps has been required for printed wiring boards (PWB). In designing these PWB capable of Giga-speed signal transmission, traditional MHz-based signal integrity simulation results used do not always ensure signal integrity. In 2008, SimDesign Techno-center, a business unite of Sumitomo Electric System Solution Co., Ltd., developed a new method to overcome this problem by combining 3-D
0.4 MB
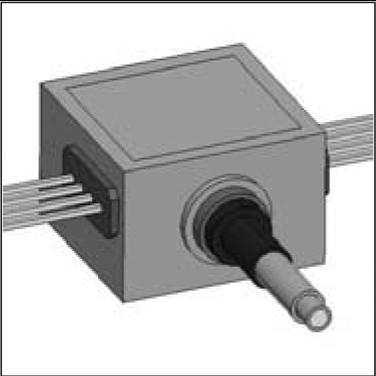
0.4 MB
We have developed super high brightness infrared light emitting diodes (LEDs). The LEDs at the wavelength of 870 nm reached record-breaking output power of 9.8 mW, which was more than 1.3 times higher than the evaluated value of the conventional 850 nm LEDs. These super high brightness infrared LEDs can be fabricated without using time and cost consuming wafer bonding technologies, such as metal bonding and glue bonding. They are also free from reliability issues possibly arising from
294 KB
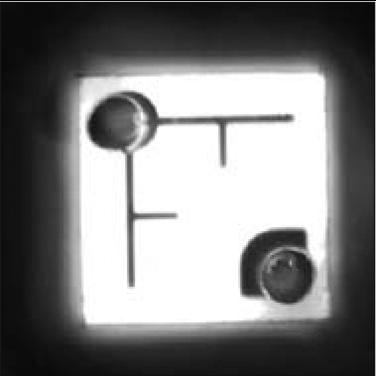
294 KB
To meet the growing market demand for energy-saving business machines, Canon Inc. developed on-demand power-effective laser beam printers (LBPs) using their new toner-fixing method. Since 1993, Sumitomo Electric has manufactured fixing-film sleeves, indispensable components for the LBPs. Recently, the authors have developed an advanced fixing-film sleeve applicable to high-speed printing systems. This sleeve is made of composite materials consisting of highly thermal conductive carbon nanofiber
0.3 MB

0.3 MB
A novel vertical heterojunction field-effect transistors (VHFETs) with re-grown AlGaN/GaN two-dimensional electron gas channels on low dislocation density free-standing GaN substrates have been developed. The VHFETs exhibit a specific on-resistance of 7.6 mΩcm2 at a threshold voltage of -1.1 V and a breakdown voltage of 672 V. The breakdown voltage and the figure of merit are the highest among those of the GaN-based vertical transistors ever reported. It was also demonstrated that the threshold
330 KB
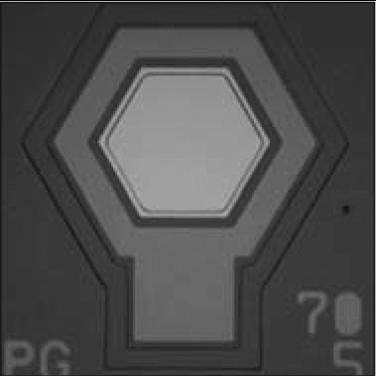
330 KB
SiC reduced surface field (RESURF) type junction field effect transistors (JFETs) are currently under development for high-speed switching power devices. The use of both wide band gap properties of Sic semiconductors and RESURF structure allowed the switching power devices to exhibit superior characteristics to those of Si metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETs) with similar current and blocking voltage ratings. In addition, microfabrication technology shortened channel
336 KB
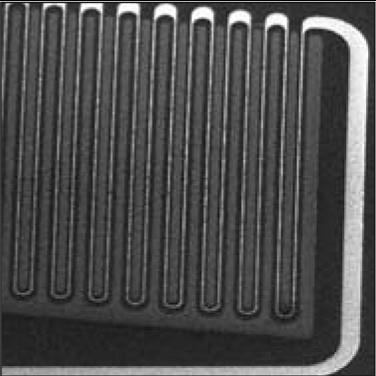
336 KB
We specialize in manufacturing and installation of large DC current conductors and related electrical equipment. This time, we have developed a movable contact switch which enables automatic switching of large current conductors in graphite product manufacturing. This user-friendly switch simplifies heat expansion absorption processes compared with water cooled cable, and thus, shortens the time required for switching operation and reduces equipment costs.
0.4 MB
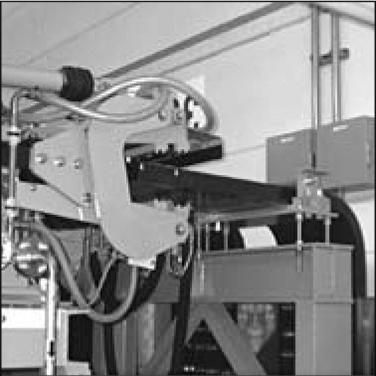
0.4 MB
Sumitomo Electric Hardmetal Corporation has newly developed a coated carbide grade “ACE COAT AC810P.” AC810P is a grade used for especially high speed steel turning, featuring more than 1.5 times higher wear resistance than that of our conventional model “AC700G.” AC810P has successfully achieved such property by applying the originally developed chemical vapor deposition (CVD) coating technology, “Super FF Coat.” This original coat consists of a titanium film with a fine, smooth surface and
0.5 MB

0.5 MB
With the expanding use of PCBN (polycrystalline cubic boron nitride) cutting tools in hard turning applications, there is an emerging demand for cutting tools of further advanced PCBN which can be used universally for various machining such as precision turning of small parts, in which cutting speed is limited under 80m/min, and die steel or high-speed steel cutting. In order to meet these requirements, SUMIBORON® BN1000/BN2000 has been developed. With high-purity ceramics binder,
0.5 MB

0.5 MB
Sumitomo Electric Hardmetal Corporation has developed a new cermet “T1500A” for steel turning. In turning operations, improvement of work efficiency by introducing high-feed or high-speed processing is increasingly important. Meanwhile, in the precision processing of electrical and electronic machine parts, improvement in machining accuracy and surface quality is desired. Under such circumstances, T1500A has been developed to satisfy these requirements. T1500A features high hardness
0.4 MB
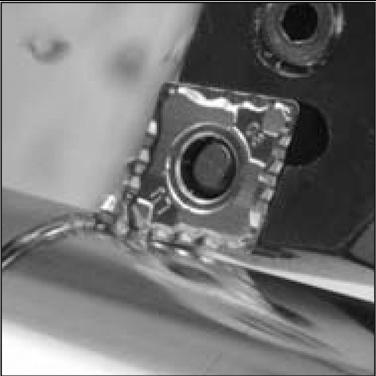
0.4 MB
In order to meet requirements in next generation micro-processing, the authors have developed a 1.06 µm pulsed fiber laser employing a simple master oscillator power amplifier (MOPA) configuration. This laser features broad pulse width flexibility (100ps to 20 ns), excellent beam quality (M2≦1.3), and a wide range of pulse repetition frequencies (50 kHz to 1 MHz). With these attributes of the laser, the optimum laser width for processing both amorphous silicon (a-Si) and copper indium
0.7 MB

0.7 MB
The Jacobi-Davidson method consists of two major parts: the Davidson part, where an eigenproblem is projected on a small subspace, and the correction equation part, where orthogonalization is operated. However, the orthogonalization can be a bottleneck when many eigensolutions are sought at once. In this study, electronic structure calculations are tested with the aim of reducing orthogonalization costs without sacrificing computational efficiency. As a result, the correction equation without
338 KB
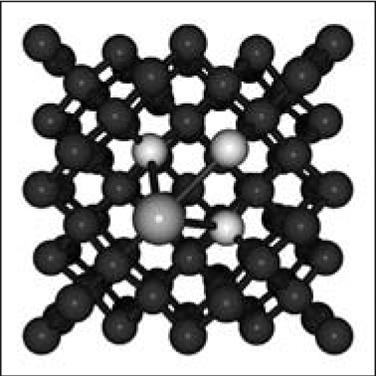
338 KB
In 2011, we will celebrate the centennial anniversary of the discovery of superconductivity. The past, present and future perspective based on 24 years’ activity of high temperature superconductivity will be summarized. The superconductivity is deeply related with our social infrastructure and everyday life, and it is important to pursue sustained R&D activity.
1 MB

1 MB
This paper describes the three electrochemical analyses that we have developed. First, voltammetry using strongly alkaline electrolyte (6 M KOH + 1 M LiOH) is explained, in which the reduction peaks of copper oxides (Cu2O and CuO) and copper sulfides (Cu2S, etc.) appear separately. This method enables the selective determination of Cu2O and CuO in the form of nm - µm of layers on copper surfaces, which is not always successful with conventional electrolytes such as 0.1 M KCl.
0.4 MB
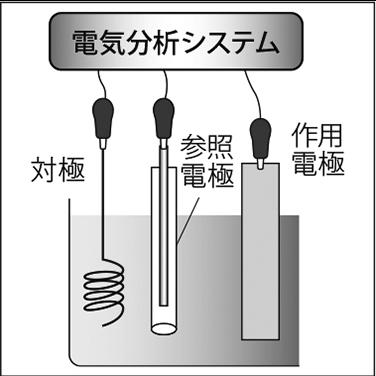
0.4 MB
The nickel foam CELMET® has such characters as the over 98 % porosity, the large relative surface area and easily processing, and is widely used for the cathode current collector of Ni-MH batteries, mainly applied for hybrid electric vehicles. CELMET® is produced by the following methods: conductive treatment of urethane, nickel electroplating, and burning away of urethane under reducing atmosphere. From the increasing awareness of environmental issues in recent years, the low emission process
1.2 MB
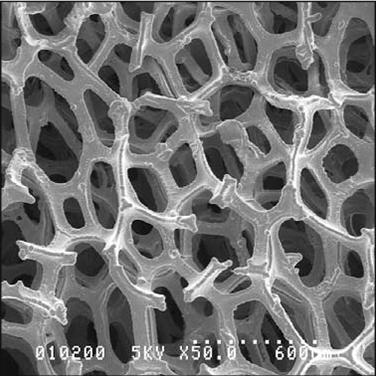
1.2 MB
For more compact and advanced electronic devices (such as cellular phones and notebook computers), size and weight reduction of printed wiring boards (PWBs) is increasingly required. These PWBs are processed by a laser drilling machine which can create small holes at high speed. In this process, a laser beam must be focused on a target position on the PWB. Here the f-theta lens plays a pivotal role. The f-theta lens used for PWB processing need to be capable of focusing the laser beam upon fine
1.2 MB

1.2 MB
In today’s automotive industry, FlexRay and other next generation protocols for automotive network communications are gaining attention. However, these protocols are unlikely to replace existing applications in the immediate future due to the cost and reliability problems caused by the replacement. In this paper we propose Scalable CAN, a new automotive network protocol based on the existing CAN (controller area network). Having a new ACK (acknowledgement) information field,
0.5 MB
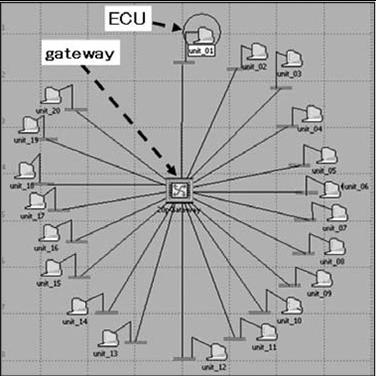
0.5 MB
For virtual connector designing, it is important to predict contact resistance at a mating point. This study investigated the relationship between contact load and contact resistance in terms of contact shape, plating material and plating thickness. Tin or silver plated copper alloy was used in this study. The contact resistance between an embossment pattern and a flat plate was measured by the four-probe method, while the indentation contact area was examined using an optical microscope.
0.9 MB
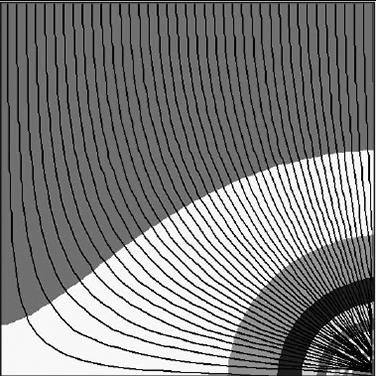
0.9 MB
As the demand for radio data communication increases, WiMAX services have expanded throughout the world. With limited radio frequency resources, efficient use of the radio frequency will become more important as the service expands. For this reason, the multi-antenna technology is expected to be a solution to improve transmission efficiency.
0.4 MB

0.4 MB
Driving Safety Support Systems (DSSS) provide the drivers with visual information on the surrounding traffic environment to alert the drivers of possible driving-related dangers, preventing traffic accidents. The image processing sensors installed on the road for the systems need a high reliability in tracking vehicles regardless of the environmental conditions. The authors have developed a tracking algorithm with high accuracy and stability even in adverse lighting or weather conditions.
0.7 MB
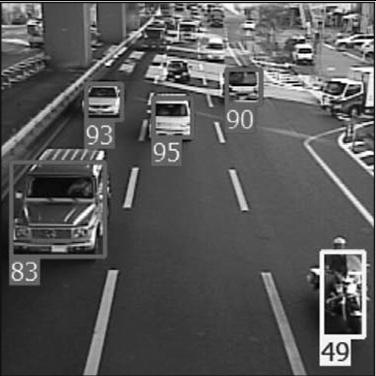
0.7 MB
The authors have developed a new system that uses estimation and learning agents to interpolate traffic information. To evaluate the interpolation accuracy of the new system, coefficient of determination (CD) and mean square error (MSE) were used. The interpolation accuracy was improved by the alternate use of estimation and learning agents, and the iterative use of the same probe data. The standard deviation of the normalized velocity error was improved to 0.1353, and that of the velocity
0.6 MB

0.6 MB
In 2002 Sumitomo Electric launched its leading edge low bending loss optical fiber “PureAccess®” that has an allowable bending radius of 15mm. Since then the company has contributed to the construction of FTTx networks through its info-communications technology and products including cables, termination boxes and connectors. As the FTTx networks expand throughout the world, there is an ever increasing demand for optical fiber that facilitates overall space savings and decreases deployment
0.4 MB

0.4 MB
The authors have succeeded in employing nanoimprint lithography (NIL) to form diffraction gratings of distributed feedback laser diodes (DFB LDs) that are increasingly used in optical communication. Uniform gratings and phase-shifted gratings with a period of 232 nm were formed by reversal NIL in combination with the use of a step-and-repeat imprint tool. Line edge roughness kept sufficiently low with the fabricated gratings. DFB LDs fabricated by NIL have indicated characteristics comparable
0.6 MB
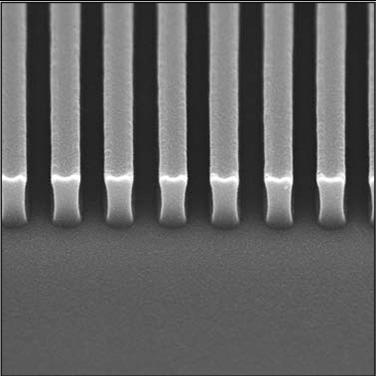
0.6 MB
The demand for high speed Internet services is ever increasing. As of April 2010, there are 30 million Internet subscribers using the FTTH (Fiber to the Home) service in Japan alone. Meanwhile, the Japanese government has launched the digital terrestrial broadcasting service in view of the effective use of frequency range and improvement in image quality. The transition from analog to digital broadcasting will be completed by 2011 For this change, specialized broadcasting fixtures are required
0.6 MB

0.6 MB
The authors have successfully developed new TOSA (transmitter optical sub-assembly) and ROSA (receiver optical sub-assembly) with a wide operating temperature range of -5 to 90 deg. C. These devices meet the requirements of an XFP (10 Gigabit Small Form Factor Pluggable) module for DWDM (dense wavelength division multiplexing) networks. TOSA has low power dissipation by using a newly designed EML (electro-absorption modulator integrated laser diode) chip, a good stability of wavelength and
0.8 MB

0.8 MB
The sublimation growth of aluminum nitride (AlN) single crystals was investigated. The crystals were prepared in two methods: By slicing along the m-plane from c-plane-grown thick crystals, and by heteroepitaxial growth on m-plane silicon carbide (SiC) substrates. The defects of the crystals were observed by a high-resolution transmission electron microscope. Dislocation density in AlN/SiC (0001) decreased significantly at about 1.5 µm above the interface, while stacking faults initiated
0.6 MB
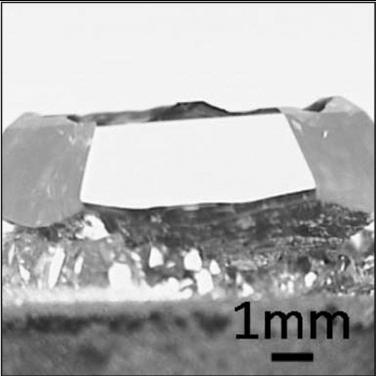
0.6 MB
The epitaxial structures of aluminum gallium nitride (AlGaN) channel high electron mobility transistors (HEMTs) were grown on sapphire and aluminum nitride (AlN) substrates. Reduction in the full width at half maximum of X-ray rocking curve for (1012) peak of the AlGaN channel layer, owing to the reduction of threading dislocation densities, resulted in a sharp decrease in the sheet resistance of 2-dimensional electron gas (2DEG). For AlGaN channel HEMTs, it was found that improvement
327 KB
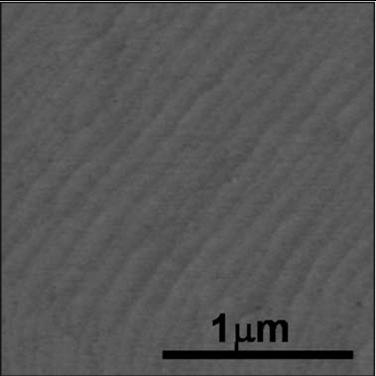
327 KB
High power and high efficiency devices are increasingly required for the 3rd generation and other future cellular base station transmitter systems (BTSs). Gallium nitride (GaN) is ideal for these applications, because of its wide band gap and high saturated electron velocity. We have focused on the GaN high electron mobility transistor (HEMT) on silicon carbide (SiC) substrates and released the world’s first commercial BTS device. We have also studied efficiency enhancement techniques,
0.4 MB
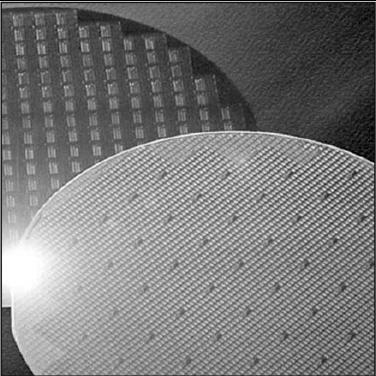
0.4 MB
Aluminum Conductor Invar alloy Reinforced (ACIR) can double the capacity of overhead power transmission line by simply changing the electrical conductor without the installation of a new power transmission line or the reinforcement of a steel tower. Recent years have seen a worldwide increase in the demand for electric conductors which have a large transmission capacity to meet rapidly growing electricity consumption.
341 KB
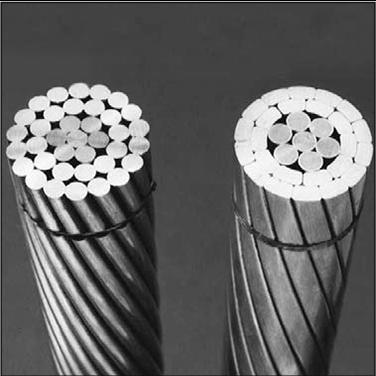
341 KB
Nano-polycrystalline diamond (NPD) obtained using direct conversion sintering process from graphite under high pressure and high temperature has a very fine texture composed of small diamond grains of several tens of nanometers without any binder materials or secondary phases. For this reason the NPD has significantly high hardness, no cleavage feature and high thermal resistance. Because of its superior features, the NPD is considered to be highly useful for cutting tools. Here,
0.5 MB
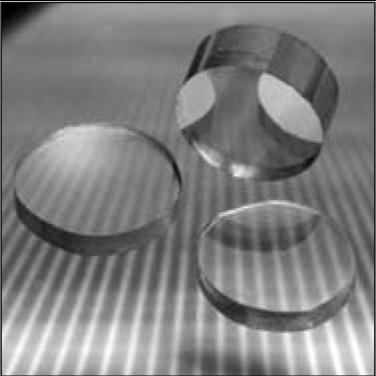
0.5 MB
Previously Sumitomo Electric Hardmetal Corp. developed an ultra low absorption lens for high power CO2 lasers without using thorium fluoride (ThF4). That is because ThF4 is a radioactive substance that requires special care in handling and storage. Our ThF4 free ultra low absorption lens shows long duration and high performance in metal sheet processing. Meanwhile, there was also a need for ThF4 free lens that has a moderate absorption level similar to that of existing ThF4 lens so as to save
0.5 MB
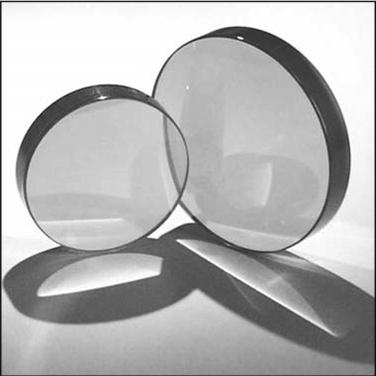
0.5 MB
Laser scribing is a commonly used process for manufacturing thin film solar cells. The quality and efficiency of the scribing process can be improved by the use of rectangular flat-top beams. The rectangular flat-top beams are easily formed by rectangular core optical fiber. Thus the rectangular core optical fiber gives scribing systems great flexibility. In this study, the authors developed a rectangular core optical fiber, and examined its characteristics. The results demonstrated that
348 KB

348 KB
We have developed a PIN photodiode with a type-II quantum well structure, which can operate in a short wavelength region up to 2.5µm. This photodiode will make uncooled operation possible. The absorption layer consisting of 250 pair-InGaAs(5nm)/ GaAsSb(5nm) quantum well structures was grown on InP substrates by solid source molecular beam epitaxy (MBE). The p-n junctions were formed in the absorption layer by the selective diffusion of zinc. Dark current density was 0.92mA/cm2,
300 KB
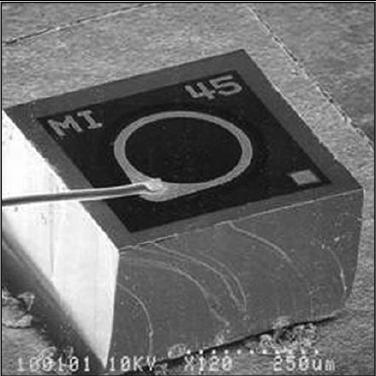
300 KB
In a power cable accessory, insulators need to prevent dielectric breakdown over a long period of time. For this purpose, electric fields generated in the accessory must be controlled so that its maximum electric field can remain small. Since the power cable accessory is composed of multiple insulators with complicated structures, the calculation of an electric field distribution requires numerical simulations using either the finite element method or other mathematical techniques.
0.6 MB
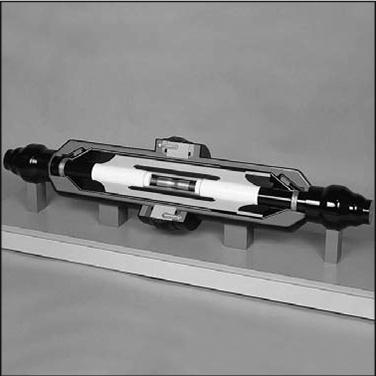
0.6 MB
The vacuum is classified into three categories depending on the state of gas: viscous, intermediate, and molecular flows. The viscous flow evacuation is generally regarded as a basic technique, with which pressure decreases along with the exponential curve of time. However, this is not always the case when the conductance of the pipe is considered. To begin with, the author theoretically solved the evacuation equation in the viscous flow.
1 MB
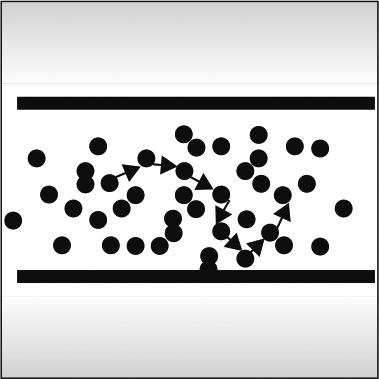
1 MB
As the transition to information society has been accelerated in industrialized countries and other nations around the world, a so-called ubiquitous society has become a reality. To support such information-oriented society, optical communication technologies will play the key role in building the communication infrastructure. Optical communications are enabled by a fiber optic communication sub-system, which consists of optical data links (used as optical transmitters/receivers) and
0.7 MB
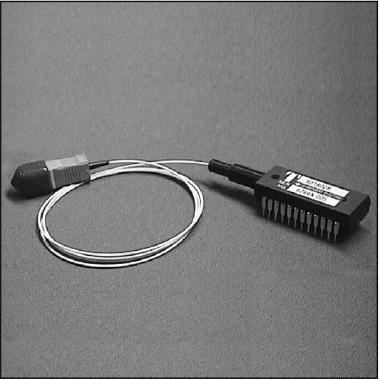
0.7 MB
"The polymer alloy technology is a polymer blend technology in which immiscible polymers are melt blended together to create a new material with the characteristics of each polymer. Sumitomo Electric utilizes the polymer alloy technology to develop covering materials for wires and cables and adhesives for heat-shrinkable tubings. In this report, an application of the polymer alloy technology to engineering plastics is discussed. The author focused on the micelles of a compatibilizer
0.7 MB
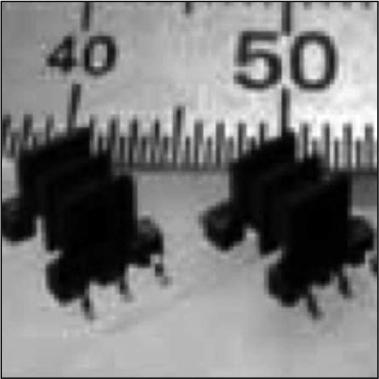
0.7 MB
"Analytical characterization techniques using a transmission electron microscope (TEM) or a focused ion beam (FIB) system have contributed to the development of semiconductor devices. In particular, at Sumitomo Electric these techniques have been applied to the analysis of metal-InP interfaces and the investigation of ohmic contact formation mechanisms, with the aim of developing Pd based ohmic contacts for p-type InP with a shallow reaction layer and low contact resistance.
0.9 MB
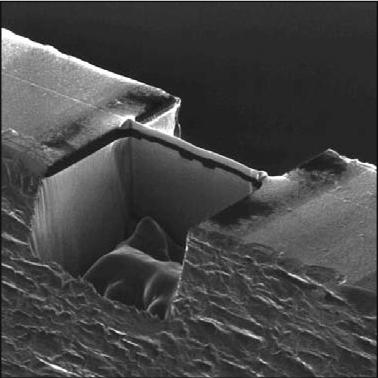
0.9 MB
Power capacitors in Japan have made remarkable progress since the OF (oil-feeding) tank type power capacitor was born in 1931. The progress has been achieved by innovation in mineral oil impregnated paper dielectrics, mixed paperfilm and all-film dielectrics impregnated with aromatic hydrocarbon oils. Improvement in capacitor elements and equipment structures as well as advancement in production techniques are other factors to have accelerated such progress.
1.2 MB
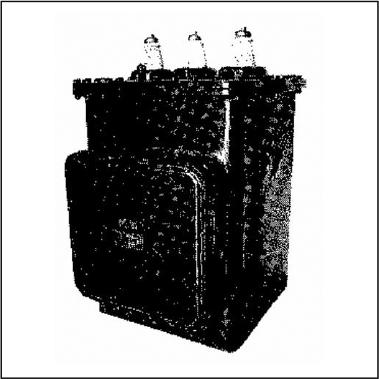
1.2 MB
The features of superconductivity, such as zero electrical resistance and a high current density, enable excellent power efficiency and high magnetic fields which normal conductivity would never generate. Thus superconductors have the potential to be used in high-performance electrical equipment. The authors, at Sumitomo Electric, developed the world’s first electric car powered by a superconducting motor.
0.5 MB
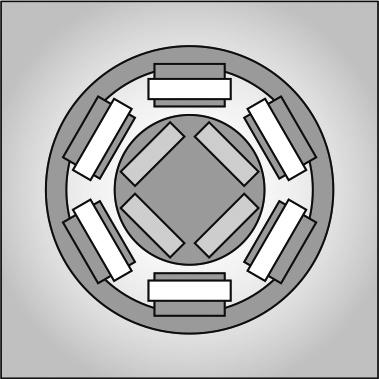
0.5 MB
The demand for wireless communications is rapidly growing all over the world, and wireless data traffic is predicted to increase by 10 times in 2015, compared to 2008. To respond to this strong demand, many operators are planning to upgrade their mobile systems from the 2nd generation to the 3rd generation or newer. Such upgrade, however, involves a big problem for operators increased power consumption by communication equipments for faster and wider broad band services.
0.7 MB

0.7 MB
The demand for wireless communications is rapidly growing all over the world, and wireless data traffic is predicted to increase by 10 times in 2015, compared to 2008. To respond to this strong demand, many operators are planning to upgrade their mobile systems from the 2nd generation to the 3rd generation or newer. Such upgrade, however, involves a big problem for operators increased power consumption by communication equipments for faster and wider broad band services.
0.5 MB
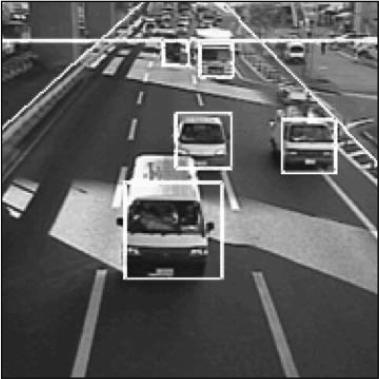
0.5 MB
The authors have successfully developed an XFP (10Gbit/s small form factor pluggable) transceiver module, which satisfies all of the requirements by XFP multi source agreement (MSA) at -5 to 85°C. The power dissipation of the newly developed XFP is around 3.0W and 20% lower than the conventional XFP. Furthermore, this module can reach up to 80km (1600ps/nm) at 11.1Gbit/s. We believe that this module will contribute to reduction in the size and cost of transmission equipment.
0.5 MB

0.5 MB
This paper describes a new optical distribution system using “Free-Branch Cable,” with which each fiber can be individually accessed at any point along the span of optical cord bundles. We propose the application of the Free-Branch Cables that can be deployed on the floor or outside wall of Multi-Dwelling Unit (MDU) buildings. In addition, with this system, fibers can reach every unit where FTTH service is required.
0.4 MB
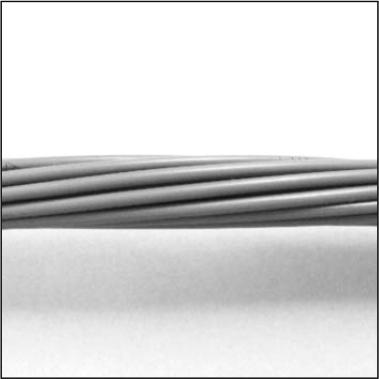
0.4 MB
In recent years, as the processing speed of electric equipment is increasing, routing over Gbps high-speed traces on printed circuit boards (PCB) is gaining the importance. To design such over-Gbps signal transmission lines, consideration needs to be given to not only conventional signal integrity techniques; e.g. impedance matching and wave form improvement, but also to radio-frequency effects; e.g. dielectric losses, parasitic parameters of via holes, and noises on power lines.
0.9 MB
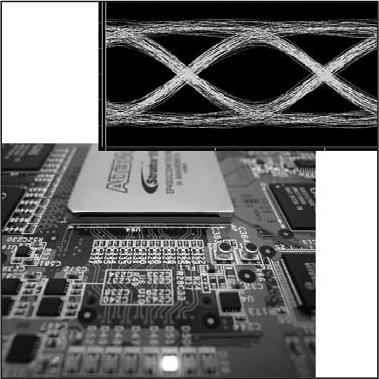
0.9 MB
We have developed the world highest optical output power infrared LED at 940 nm. By newly developed an epitaxial layer structure and a p-type electrode, the optical output power was increased to 5.3 mw at 20 mA DC current, which was about 2.5 times higher than that of a conventional 940 nm LED’s. Forward voltage was 1.35 V. The FWHM (full width of half maximum) of spectrum wavelength of the device was 25 nm and less than half of that of the conventional one.
335 KB
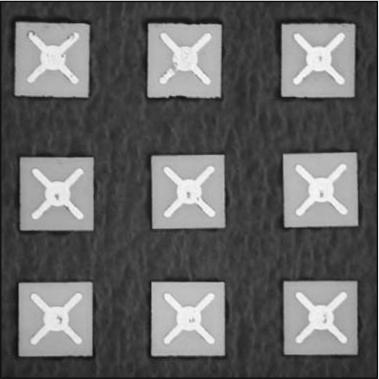
335 KB
A new molten salt system, N-ethyl-N-methylpyrrolidinium chloride (EMPyrCl)-ZnCl2, was investigated for the electrodeposition of molybdenum at intermediate temperature. A phase diagram was constructed for the EMPyrCl-ZnCl2 system, which shows the lowest melting point of 45°C at an equimolar composition. A thermal gravimetry indicated that thermal decomposition starts from 230°C for the equimolar melt. The viscosity and conductivity of the equimolar melt were 75 cP and 22 mS cm, respectively,
0.6 MB
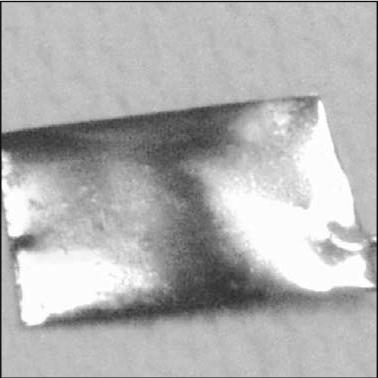
0.6 MB
InGaN based green laser diodes (LDs) with a wavelength of 531 nm were demonstrated on semi-polar {202(_)1} GaN substrates under pulsed operation. The advantages of {202(_)1} planes for green lasing have been revealed by investigating the optical properties of spontaneous emission from LD structures. The amounts of the blueshift on {202(_)1} planes were dramatically reduced from those on conventional cplanes, indicating that piezoelectric fields within InGaN active regions are well diminished
0.5 MB
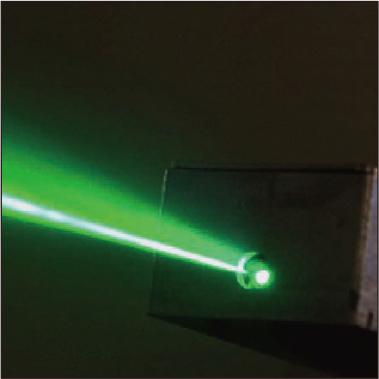
0.5 MB
True green InGaN-based laser diodes (LDs) on novel semi-polar {202(_)1} free-standing GaN substrates, lasing under pulse operation at wavelengths long as 531nm, were successfully demonstrated for the first time. Room temperature continuous-wave operation at 520nm was also achieved by improving the epitaxial layers and applying a ridge-waveguide structure. The threshold current and voltage were 95 mA (7.9 A/cm2) and 9.4 V, respectively. This paper reports the lasing properties of these true green
284 KB
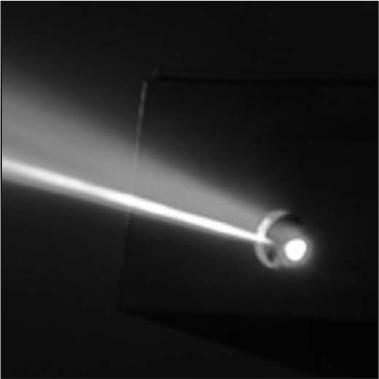
284 KB
AlGaInP laser diodes are used in various digital equipment, such as MO/CD/DVD optical pickup units, laser printers and barcode scanners. Recently, the lasers have been expected to expand their application to the next-generation hard disk drives (HDD) for a thermally-assisted magnetic recording system and mobile devices. In response to such expansion of the market, high-power, short-cavity lasers have turned out to be essential. The authors have undertaken the development of higher-output and
0.4 MB
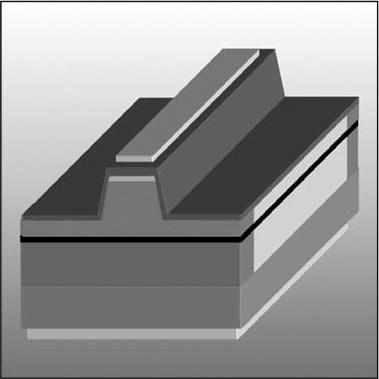
0.4 MB
The high-temperature superconducting (HTS) cable demonstration project has taken place since 2007, aiming to verify the reliability and operation stability of a 66-kV, 200-MVA HTS cable in the actual power grid. An HTS cable, termination and joint have been finalized for this demonstration project, and installed into Sumitomo Electric’s facility as a 30-meter HTS cable system before the actual demonstration in Tokyo Electric Power Company’s Asahi Substation in Yokohama.
0.8 MB

0.8 MB
For power distribution in high-rise buildings, either one of the two wiring systems has been commonly used in order to connect trunk line: branch cable system or bus duct system. However, these systems do not always work well with the predominating built-up construction method, in which floors are built up one by one and interior work is also conducted at a time. As a solution to this problem, Toyokuni Electric Cable developed a split type module branch cable and launched it in 2003.
0.4 MB
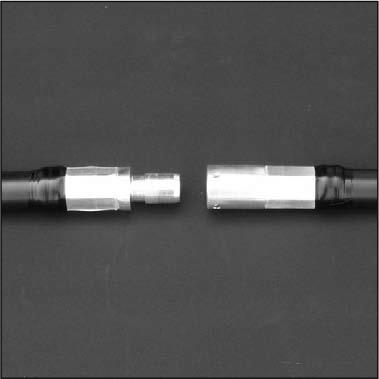
0.4 MB
“SUMIBORON®” PCBN tools are widely used in the cutting of hard-to-cut ferrous materials, such as hardened steel, cast iron and powder metal, and contribute to productivity growth and cost reduction for metalworking. In recent automotive industry, powder metal consumption is increasing. The powder metal materials have more flexibility in design and can be sintered into complex shapes. However, the machinability of powder metal parts is not so good.
0.5 MB

0.5 MB
In this study, we have set up an ocular motor neural system model to control a stereo active camera device. As a result, we have obtained the following human-eye-like characteristics: smooth pursuit (tracking movement), saccade (fast movement to chase a target) and binocular movement (such as conjugate and vergence movement). Drawing upon such characteristics of eye movement and its excellent accuracy, we have also conducted a field evaluation to detect pedestrians using our trial machine.
0.8 MB
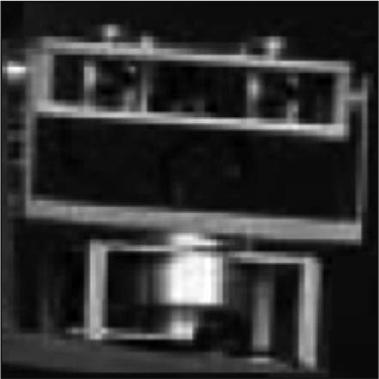
0.8 MB
Prevention of traffic accidents between human and vehicles on road has become one of the major issues today and the development of advanced in-vehicle safety systems is highly expected. A sensing system installed into a vehicle can be a solution to the issue, playing a complementary role for the elderly with poor detection capabilities, especially in aging society. Although visible light imaging and thermal infrared ray (TIR) sensing have been put into practical use in some fields,
0.7 MB

0.7 MB
The electromagnetic field analysis, one of the numerical analysis, is now an indispensable method for designing and developing electromagnetic application products. Such advanced analysis techniques including finite element methods, and faster, higher-capacity analytical hardware such as personal computers enable even the most complex electromagnetic phenomena to be investigated. Depending on the frequency of an object, an analysis is carried out differently; products with high frequency must
0.9 MB
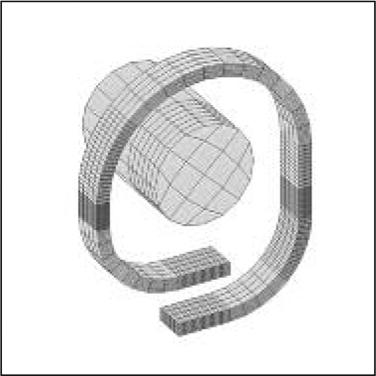
0.9 MB
To commercialize violet lasers, the mass production of high quality gallium nitride (GaN) single crystal substrates is the key. Sumitomo Electric had successfully developed a process to obtain GaN substrates by means of vapor phase epitaxy. In this process, a thick GaN crystal layer is grown epitaxially on a foreign GaAs substrate, and later, the GaAs is removed. However, a large number of crystal defects (dislocations) generated on the interface between GaN and GaAs had remained a problem.
0.8 MB
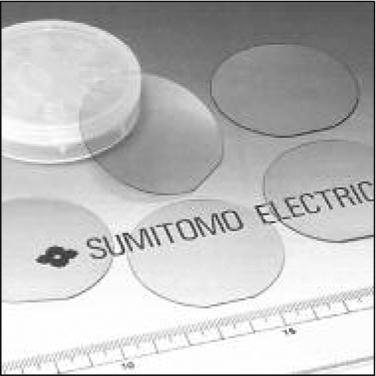
0.8 MB
The performance of semiconductor lasers has been dramatically improved by applying quantum well structure including strained layer superlattice and innovation of crystal growth techniques such as organometallic vapor-phase epitaxy. The semiconductor laser used for optical communication came to be indispensable for our life as an optical component connecting not only long-distance, large-capacity optical transmission trunk lines but also access networks.
0.8 MB
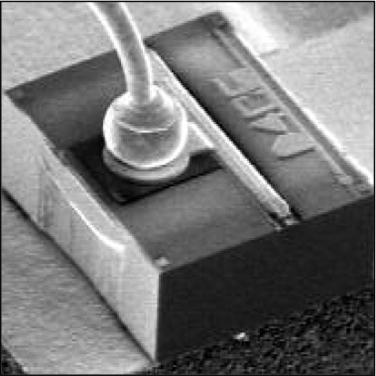
0.8 MB
To realize “defect-free products,” every product should be numbered and its individual record should be kept for the traceability. On that basis, we must concert all efforts to achieve Six Sigma aiming at the improvement of product properties through the modification of each product. At the same time, currently undergoing “visualization” in production sites should be promoted to “vocalization,” encouraging verbal communication to enhance mutual understanding and information sharing for
0.9 MB
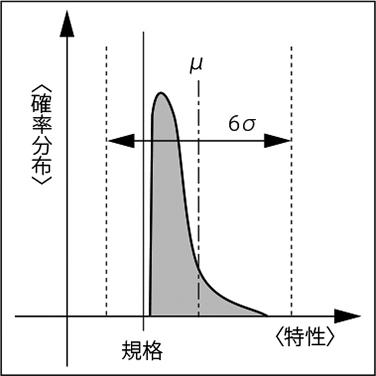
0.9 MB
Recently, global warming has become a serious social problem. As an environmental measure, the automotive industry has been putting their efforts into the development of environmentally-friendly automobiles such as the hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), electric vehicle (EV) and fuel cell vehicle (FCV). To be popularized, these eco-friendly vehicles should have high energy efficiency, as well as powerful acceleration equivalent to gasoline-fueled vehicl
0.7 MB

0.7 MB
In repetitive switching load operations, newly developed power relays for automotive use were tested. The relays are mounted on printed circuit boards and reduced in the case volume by 50 percent compared to low-profile ISO plug-in microrelays. The operating voltage and relay temperature was set to 14 V and 120 deg. C, respectively. The tests of normally open contact type relays were conducted with lamp loads (11 A) and horn loads (8 A), while those of transfer (changeover) contact type relays
1.3 MB
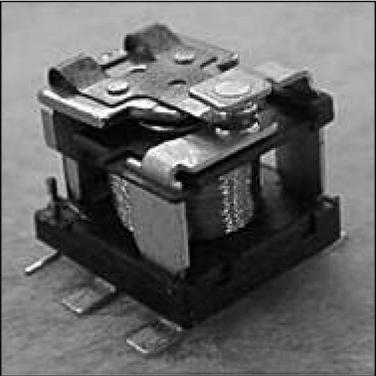
1.3 MB
Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) has established standard specifications of automotive software including layered software architecture and development methodology. We have made a prototype of our body ECU software in accordance with AUTOSAR standard specification to compare properties, such as ROM and RAM sizes and execution speed, with software produced by our current platform. In this report, model-based development methods are also evaluated along with AUTOSAR standard
0.5 MB

0.5 MB
As sensing technology and robot performance advance, robots’ application field has expanded; especially on assembly lines, robots are replacing manual operations. The wire harness, one of Sumitomo Electric Industries’ core products, involves complicated processes such as the insertion of terminals into connector cavities and the placement of harness on assembly boards, requiring manual assembly. To determine the application possibility of robots for the wire harness assembly, we have focused on
0.7 MB

0.7 MB
Gigabit Ethernet-passive optical networks (GE-PONs), which were ratified by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.3 committee in 2004, have been widely used for FTTH service in Asia, particularly in Japan. However, five years have passed since the inauguration of its commercial deployments and Internet service providers are not satisfied with the GE-PONs any more for their providing latest broadband applications such as high-definition video distribution.
0.6 MB

0.6 MB
To realize Cooperative Driving Safety Support Systems (DSSS) aiming at the reduction of traffic fatalities and serious injuries, an image processing sensor needs to be installed on the road. With such a sensor, automobiles, motorbikes and pedestrians in driver’s blind corners are spotted and the obtained traffic data is provided to the driver. Due to the purpose, the sensor should be able to detect the position and travel speed of objects with a higher precision than that of traffic counters,
0.7 MB

0.7 MB
For Small Form-factor Pluggable plus (SFP+), the authors have successfully developed a chipset, which is composed of a transceiver IC equipped with a vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL) driver and a shunt driver IC. This paper describes the concept of low-power-consumption designs and the details of circuit designs. This combination of the shunt-laser driver and the VCSEL driver with an asymmetric pre-emphasis circuit has enabled to reduce the total power dissipation of SFP+ module
0.7 MB
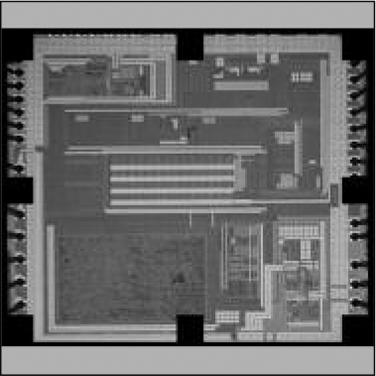
0.7 MB
Aiming at high-speed direct modulation over 10 Gbit/s, the authors have developed a 1.3 µm wavelength AlGaInAs/InP distributed feedback (DFB) laser with a ridge-waveguide structure of 1.0 µm in the ridge width by utilizing a benzocyclobutene (BCB) planarization process. The laser recorded a wide electrical bandwidth of more than 20 GHz, promising the reduction of parasitic capacitance due to the effects of BCB buried structure. At the measurement temperature of 25 degrees Celsius,
0.5 MB
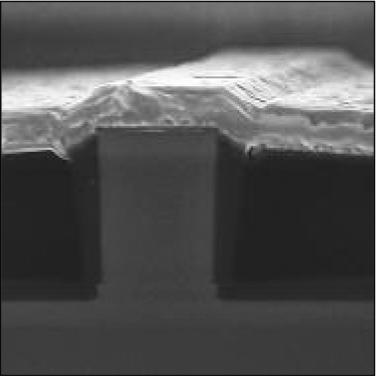
0.5 MB
The number of Fiber-to-the-Home (FTTH) service subscribers has already reached 13 million and is forecast to increase at a consistent pace. Still, Very high-bit-rate Digital Subscriber Line (VDSL) service using copper twisted telephone cable is prevailing for multi-dwelling units (MDUs). As the volume of communication increases, however, high-speed transmission media is firmly required. To meet such demand, FTTH service can be an excellent alternative to VDSL in MDUs.
0.5 MB
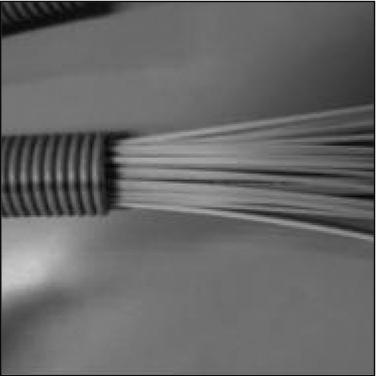
0.5 MB
As Fiber-to-the-Home (FTTH) service is rapidly increasing its popularity throughout the world, construction work to lead optical drop cable into houses needs to be streamlined. In such construction, field assembly connectors are widely used due to the applicability to cable wiring and compact bodies which are easily stored in optical fiber housings such as optical network units (ONUs). Thus field assembly connectors are attracting worldwide attention not only from the FTTH market but also from
0.6 MB

0.6 MB
Sumitomo Electric Industries have studies annealing ambient effects on the optical properties of a GaInNAs/GaAs single quantum well by utilizing photoluminescence (PL) spectroscopy and photoreflectance (PR) spectroscopy to investigate carrier localization and intrinsic band-edge transitions, respectively. By the systematic analysis of PL and PR spectra, the authors have revealed that the annealing conditions in the GaInNAs epitaxial growth greatly effected improvements in the optical properties.
0.5 MB
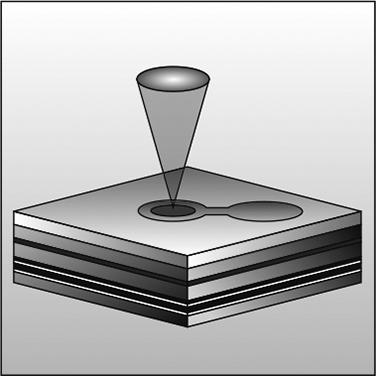
0.5 MB
De jure standards published by internationally acknowledged organizations such as the International Electrotechnical Commission (IEC) and the International Organization for Standardization (ISO) are known as “consensus-based” standards. Currently, such international standards are becoming more important in conducting global business, and are especially effective for expanding market in the early phases of product development and for reducing costs in business enhancement activities.
0.5 MB
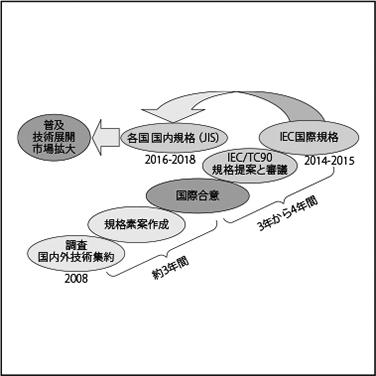
0.5 MB
The 21st century is “the era of energy, resource and environment.” In the near future, an increasing population and advanced civilization will urge us to rely on solar-derived new energy sources. More specifically, hydrogen (H2) energy generated by photovoltaic power will assume an important role and start powering the blessings of modern civilization, vehicles. The H2 energy will be delivered in liquid form by a tanker to H2 stations, where the liquid hydrogen (LiH2) will be supplied to every
2 MB

2 MB
Recently, demand for far-infrared ray (FIR) cameras, which visualize objects without any light source, has been increasing for security purposes and other applications such as night-vision devices installed in vehicles. To meet the demand, the development of affordable lenses is desired and Zinc sulfide (ZnS) can be one of the solutions. We have currently realized a low-cost ZnS lens by a newly developed precise mold-forming process utilizing a powder metallurgical technology,
0.7 MB
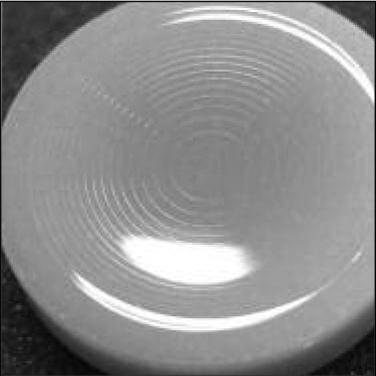
0.7 MB
An increase in silicon (Si) additive amount to hard-drawn steel wire has successfully improved material characteristics such as tensile strength, fatigue limit and heat resistance. Enriched Si has also realized thinner spring wire and application for engine valve springs. We have already reported on heat-resistance mechanism in the wire, which was improved by Si solid solution strengthening and strain relaxation resulting from high-temperature annealing. This report describes a minute
0.7 MB
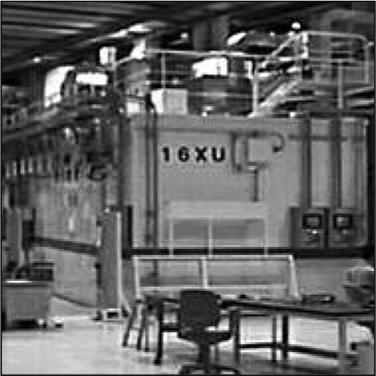
0.7 MB
In order to improve the performance of electronic equipment and reduce its size and weight, UV laser drill machines are highly required, with which small holes within ø50 µm in diameter can be provided during printed wiring boards (PWBs) processing. To meet such demand, Sumitomo Electric Hardmetal Corp. has developed an f-theta lens for UV lasers with the diffraction-limited performance over an entire scan field of 50 mm × 50 mm. Test results by transmission wavefront measurement have confirmed
0.7 MB

0.7 MB
Laser technology is now indispensable for today’s industry, introduced to various fields such as steel, automobiles and electronics. Above all, laser drilling is widely used for drilling minute holes in circuit boards, which enables the size and weight reduction and functional advancement of electronic devices. The result of laser processing greatly relies on the quality of the laser and optics, especially a f-theta lens, which is a multi-element lens having diffraction limited performance over
0.5 MB

0.5 MB
Sumitomo Electric Hardmetal Corporation has newly developed a coated carbide grade “ACE COATTM AC820P” and “AC830P.” AC820P is a general grade used for a wide range of steel turning from highly-efficient continuous machining to interrupted rough machining. On the other hand AC830P, is used exclusively for heavy machining and interrupted machining. Both AC820P and AC830P are doubled in the tool life and improved in the reliability compared with conventional grades.
1.6 MB

1.6 MB
Analysis Technology Research Center has been contributing to designing reliable and sophisticated products and optimizing manufacturing processes using Computer-Aided Engineering (CAE) technology throughout Sumitomo Electric’s five major business segments: “Automotive,” “Information & Communications,” “Electronics,” “Electric Wire & Cable, Energy,” and “Industrial Materials;” and in new business segments. Thus, CAE analysis technology has become increasingly important as the key to competitive
0.7 MB

0.7 MB
Cemented carbide is a composite material of ceramics and metal, and the major structures are WC-Co and WC-TiC-Co. The advantages cemented carbide has over other materials are high degrees of hardness and wear resistance. Cemented carbide is already put into practical use in various applications, such as cutting tools, wear-resistant tools, corrosion-resistant tools and decorations, and this trend is spreading widely. Today, the annual production of cemented carbide in Japan has exceeded 6,000 t
0.9 MB
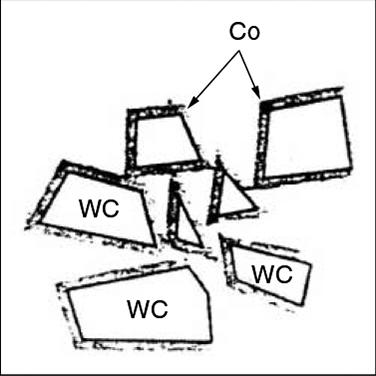
0.9 MB
In recent years, to reduce the risk of airbag-related injuries, “smart” airbag systems that get activated depending on occupant position and crash condition are increasingly being developed. The use of various occupant detection methods such as weight/pressure sensors, ultrasonic sensors or image sensors is being proposed, but it is difficult to accurately sense the size and position of an occupant. FIR cameras, which offer thermographic images, are useful for detection of human presence.
0.9 MB

0.9 MB
For quality assurance during software development, preventing and removing code errors is important. While strict quality control is conducted during production of industrial products, not enough statistical quality control is carried out in software development. Because of this lack of statistical control of quality in software development, it is extremely difficult to assure that all errors have been removed. Sumitomo Electric has defined measurement parameters such as those that
0.6 MB
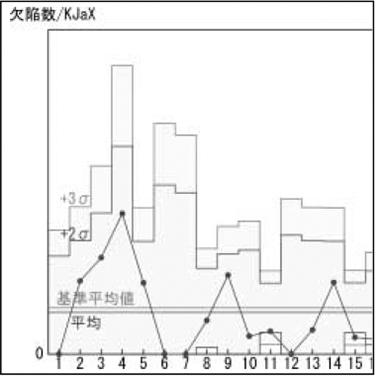
0.6 MB
Enterprise 2.0 refers to the recent trend of applying the web technologies widely deployed in Internet services (such as Google and Yahoo!) to enterprise intranet systems so as to improve system designs based on user experience. One such web development technology that is especially attractive for application in enterprise system interface designs is Ajax. Unfortunately, utilizing the Ajax technology to enterprise systems is challenging,
1.3 MB
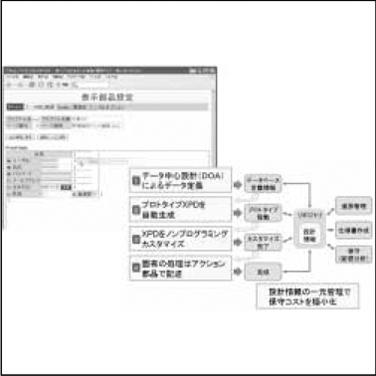
1.3 MB
Mobile Worldwide Interoperability for Microwave Access (Mobile WiMAX) is a next-generation wireless communication technology that enables higher data throughput and better mobility compared to wireless local area network (WLAN). Mobile WiMAX supports a 1-cell reuse pattern for improving spectrum efficiency, but this cell allocation suffers from heavy co-channel interference (CCI). Adaptive array antenna can be an efficient solution for canceling interference signals, but it is difficult
0.9 MB
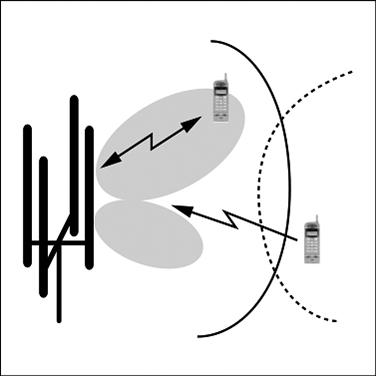
0.9 MB
The authors have developed a reduced-diameter multi-mode fiber that can withstand bending and an MT-type high-density multi-fiber optical connector. To realize easy splicing of optical fibers, the authors have examined the technology for splicing fibers without removing their coatings. This report presents the structure of a mechanical splicer that allows easy fiber splicing using the V-groove positioning method, and its various optical characteristics.
0.5 MB
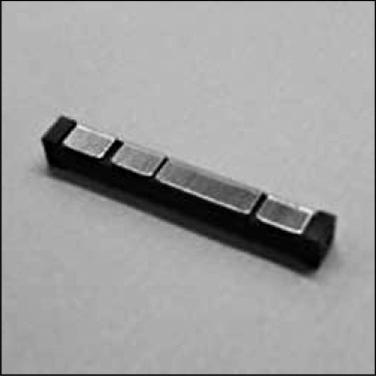
0.5 MB
SFP+ is the latest pluggable 10Gbit/s optical transceiver. Its form factor is compatible with SFP, which is a major lower-speed (below 4Gbit/s) optical transceiver on conventional optical networks. This paper describes the fundamental structure of SFP+ and the design of Sumitomo Electric’s “SPP5101-SR” 850nm SFP+ for 10Gbit/s multimode-fiber application (10GBASE-SR). Sumitomo Electric had developed in the past the 300pin, X2 and XFP as 10Gbit/s optical transceivers.
0.6 MB
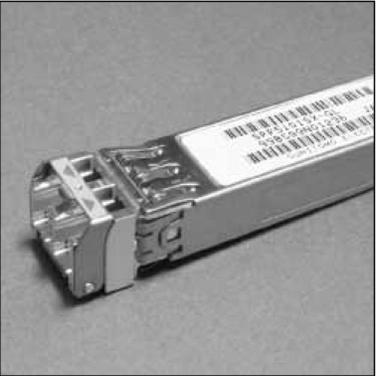
0.6 MB
We proposed for the first time the introduction of a buried tunnel junction structure to a GalnNAs vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL) and demonstrated high power and low resistive operations. By introducing a buried tunnel junction as a current confinement structure, the differential resistance was reduced to 65Ω, which is 40% lower than that of a conventional long-wavelength oxide VCSEL. The maximum output power was 4.2 mW at 25℃ and 2.2 mW at 85℃.
0.5 MB
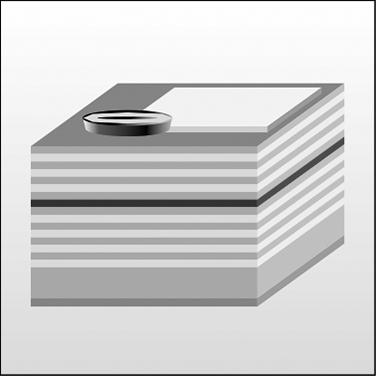
0.5 MB
As the number of FTTH subscribers in Japan rapidly increases, the number of optical fiber cables in access networks is also rising dramatically. There are more than 13 million FTTH subscribers in 2008, and access networks are overcrowded with optical cables. In order to construct economically-efficient optical fiber line networks, downsizing of optical cables has been demanded. Therefore the authors have devised an optimized cable structure and developed a small-diameter,
0.5 MB

0.5 MB
For the purpose of constructing more economical FTTH networks, the authors have developed a new aerial fiber distribution cable named “Free Branch Cable (FBC)” and a pre-connectorized elastic spiral drop cable. In this paper, the authors introduce the configurations of these new cables and propose a new wiring concept with these new cables that can reduce total cost of FTTH deployment.
0.6 MB
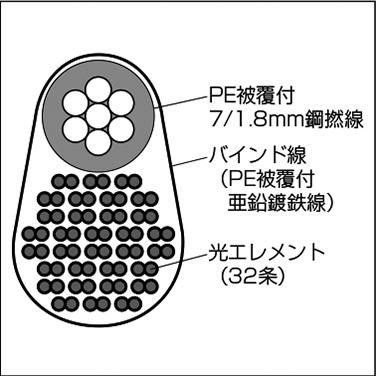
0.6 MB
The transition to terrestrial digital TV broadcasting from analog broadcasting in Japan is scheduled to complete in 2011, and broadcasters are setting up necessary infrastructure across the country. However, investigations show that this shift will cause blind spots (places with poor TV reception) that did not exist during analog broadcasting to arise and affect about 300 thousand households in mountainous regions. A solution to this problem that is gaining widespread attention is the use of
0.7 MB
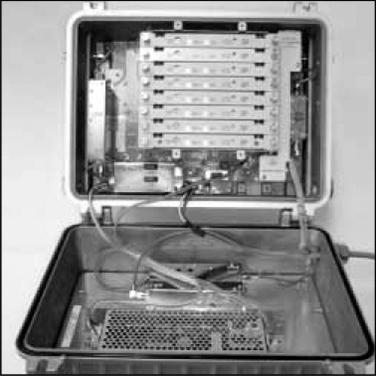
0.7 MB
Gallium nitride (GaN) Schottky barrier diodes (SBDs) with a SiNx field plate (FP) edge termination structure have been designed and fabricated on low-dislocation-density free-standing GaN substrates. The SBDs with FP structure effectively suppressed the increase in leakage current and the breakdown voltage gradually improved along with the increase in FP length, as can be explained by the simulation results. The breakdown voltage (Vb) of the SBD with FP structure was 680 V,
0.5 MB

0.5 MB
Diamond is seen as one of the most promising semiconductor materials to be used for power devices because of its superior physical and electrical properties, such as wide band-gap, high breakdown electric field, high mobility and high thermal conductivity. Through the technology for growing low-defect diamond, the breakdown field of diamond Schottky barrier diode (SBD) has reached 3.1 MV/cm, which was higher than that of SiC SBD. Though the heat of power device is the biggest problem
0.8 MB

0.8 MB
Electrochemical impedance spectroscopy was used to study the mechanism by which copper oxides are reduced in neutral solutions of alkali chloride. For the reductions of CuO and Cu2O, a capacitive loop and also an inductive loop under certain conditions were observed in the complex plane. The electrochemical impedance for CuO reduction was not greatly dependent on the kind of alkali chloride. On the other hand, the electrochemical impedance for Cu2O reduction was considerably affected
0.7 MB

0.7 MB
High-temperature superconducting (HTS) cable, characterized by its high current density and low transmission loss, is a promising compact power cable with large transmission capacity, and has a variety of environmental advantages such as energy saving, resource conservation and EMI-free. Due to these advantages, HTS cable demonstration projects are being promoted around the world. Since the discovery of HTS materials, Sumitomo Electric has been conducting the development of HTS BSCCO wires
4 MB
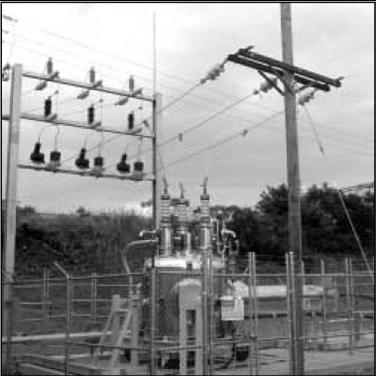
4 MB
Sumitomo Electric had been using textured Ni-alloy substrates in its development of REBa2Cu3Ox (RE123) coated superconducting tapes. Here, RE means Ho and Gd. The Company has successfully fabricated a Ho123 superconducting coated conductor on Ni-alloy tape that is 200m and has an Ic value of 205 A/cm-width. However, Ni-alloy substrates are unsuitable for AC applications because of high magnetic loss of Ni. Moreover, Ni-alloy substrate has low mechanical strength.
0.7 MB
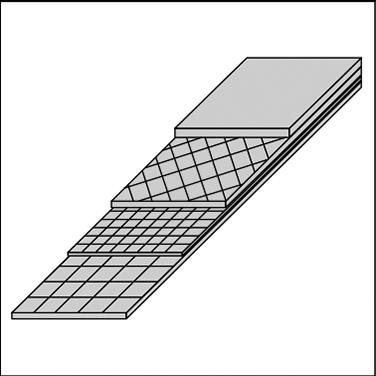
0.7 MB
Self-bonding magnet wire can contribute to solving environmental issues by alternating the varnish impregnation process. But till now, two technical challenges restrict the application of self-bonding wire to refrigeration compressor motor. One is to combine heat resistance property with low-temperature bonding property. Another is to achieve material design that provides strength against the insert process. The authors succeeded in accomplishing these challenges by using a new modified epoxy.
0.7 MB
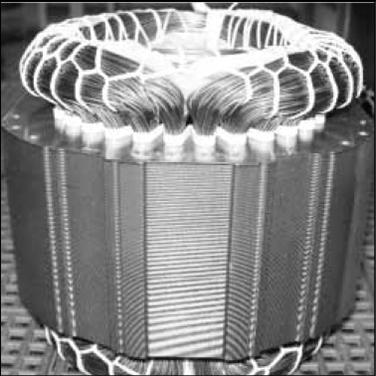
0.7 MB
Multi-stories buildings being built in recent years are becoming larger and more intelligent. As more buildings become extensively equipped with lighting and air conditioning and use of office automation equipment become more common, electricity demand for buildings is increasing every year. In the interest of economy, therefore, 6600V branch cable is used for the main power supply line in a building and the voltage is changed to the proper level by the transformer installed in each floor.
0.6 MB
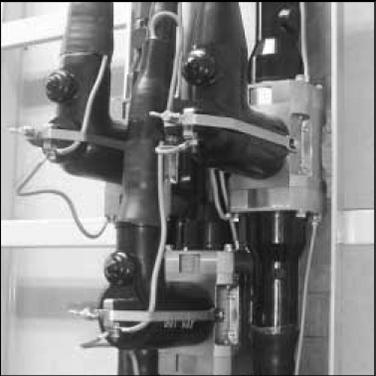
0.6 MB
Silica glasses are well-known as being substantially higher in purity and more transparent than fused-quartz glasses. Therefore, they are widely used not only for optical fibers but also for electronics industry applications like optical lenses for semiconductor exposure apparatus and photomask substrates for optical lithography. The authors have developed and improved the technique for manufacturing high-quality VAD silica glasses that has excellent mass productivity.
0.6 MB
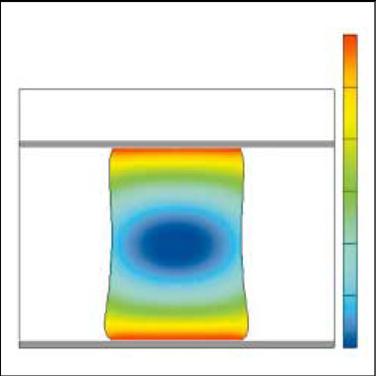
0.6 MB
Recently increasing global awareness on environmental issues has induced demands for high-efficiency machining that improves productivity and cut capital spending. In order to satisfy such demands, SUMIBORON NEW BNC200 has been developed. NEW BNC200 provides longer tool life and higher machining efficiency by over 50% compared to the conventional BNC200 grade by drastically improving breakage resistance while at the same time maintaining high wear resistance.
0.7 MB

0.7 MB
Optical data link modules (ODLs) are one of the basic components used in optical communication systems. In the beginning, ODLs were developed as low-end components applicable for 1 Mb/s transmission rate. With the progress of optical transmission technologies, ODLs evolved to become faster, smaller and multifunctional. Today, the most advanced ODLs have a transmission rate exceeding 10 Gb/s, a dispersion penalty compensation function, and also various control functions
1.8 MB

1.8 MB
Many different compound semiconductors can be formed by changing the combination of constituent elements. Properties of alloy semiconductors composed of a plurality of compound semiconductors can be changed in a continuous fashion by changing composition ratios. Very thin alloy semiconductor multilayers showing interesting properties can be formed by sophisticated epitaxial growth methods such as MOVPE and MBE. Based on these matters, innumerable compound semiconductor devices with a wide
1.2 MB
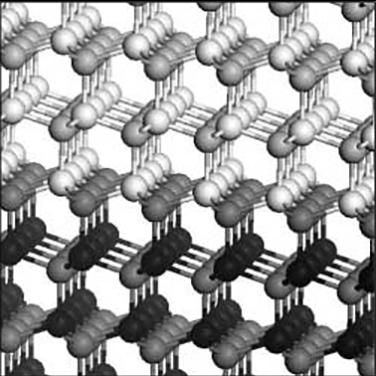
1.2 MB
In electromagnetic equipment, laminated steel sheets and soft magnetic powder core are used as the magnetic core in electromagnetic circuit. Soft magnetic powder core has three advantages over conventional magnetic core, which are three-dimensional formability, three-dimensional flux capability and material recyclability. Due to these advantages, soft magnetic powder core is being expected to be used as a new soft magnetic material in recent studies.
0.7 MB
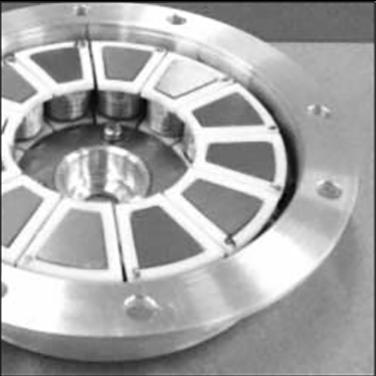
0.7 MB
In recent years, global warming has become a serious environmental issue. Development efforts are currently underway toward achieving practical application of high-temperature superconducting wires. A high-temperature superconductor has zero electrical resistance at the temperature of liquid nitrogen, so it can reduce the power losses in electrical equipment. The authors have developed a prototype electric vehicle equipped with a motor system that uses bismuth superconducting wire to verify
0.7 MB

0.7 MB
In recent years, development of eco-friendly cars is an important theme in the initiatives for environmental protection and energy conservation. The production of various kinds of hybrid electric vehicles is growing rapidly. The biggest obstacle in widespread use of hybrid electric vehicles is price. High voltage harnesses are necessary for connecting between hybrid units (inverter, motor and battery) that must be fitted in a limited vehicle space. In particular,
0.5 MB
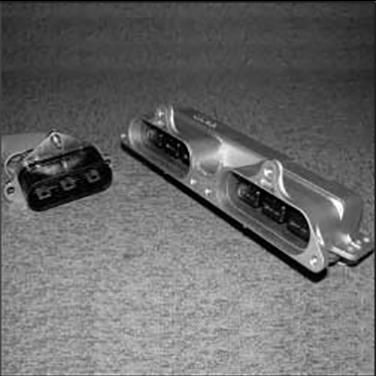
0.5 MB
Structure analysis technology using X-ray measurements and molecular dynamics (MD) simulations has been established for amorphous materials such as optical fiber glass and diamond-like carbon thin films. X-ray scattering measurements using highly brilliant X-ray from synchrotron radiation was found very effective to obtain scattering spectra with a high signal to background ratio, despite the extremely small quantities of specimen. X-ray absorption fine structure (XAFS) was employed to
0.7 MB
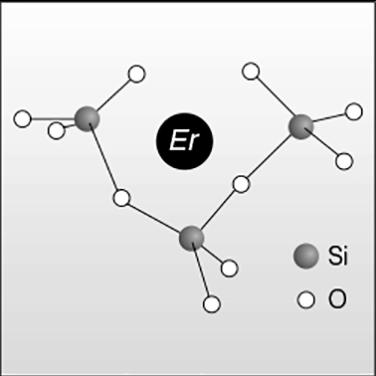
0.7 MB
The authors have found that antimony (Sb) plays an important role in improving the optical properties of GaInNAs/GaAs quantum well in a 1.3 μm region grown by metalorganic vapor phase epitaxy. It has been investigated how the two kinds of trimethylantimony (TMSb) supply sequences affect the photoluminescence (PL) property of GaInNAs. Non-annealed samples grown with pre-flow of TMSb showed good optical properties equivalent to those of annealed samples grown without TMSb.
0.4 MB
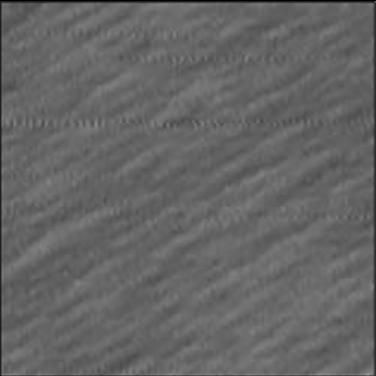
0.4 MB
Optical access services are expanding quickly in Japan and North America. Passive optical network (PON) systems that allow one optical fiber to be shared between two or more users at low service prices have been adopted in optical access services. Sumitomo Electric is one of the manufacturers of Bi-directional transceiver devices used in PON systems. On the other hand, in the case of systems for supporting point-to-point communication schemes such as Ethernet where two optical fibers are
0.6 MB

0.6 MB
Due to the spread of mobile phones and the evolution of broadband networks, the mobile content delivery market is growing. In the case where a single content data is transmitted simultaneously to many user terminals, it is difficult to retransmit all lost data packets because the packet loss pattern varies from one user to another. The FEC technology is an effective means of restoring original data without retransmitting the lost data packets. The authors have developed the FEC
0.8 MB

0.8 MB
As broadband Internet services become more widespread, visual communications especially video conferencing is becoming more popular. With an aim of improving the efficiency of business in industry sectors, the authors have developed visual communication system software named “TVcation” as a solution to more efficient manufacturing. When dealing with information related to manufacturing business, the processing of still images and photographs is particularly important.
1.5 MB

1.5 MB
The demand to manage computers as enterprise information asset has further increased with the recent rise in awareness of corporate compliance and information security. The authors have developed “ManagementCore®/IT Asset Management”, a management system software that provides comprehensive support to various missions, ranging from network management to security management. This product is an amalgam of Sumitomo Electric’s software agent technology cultivated while developing network
1.1 MB

1.1 MB
Recently, solid-state NMR systems are increasingly being utilized for research and development of new materials in both the industrial and academic fields, and this trend is no exception in the National Institute for Materials Science, which has the largest high magnetic field supply system in Japan. During an NMR analysis, a large electric power is supplied to a hybrid magnet system, but the output of a rectifier needs to be modulated to prevent the water-cooled copper magnet from being
0.6 MB
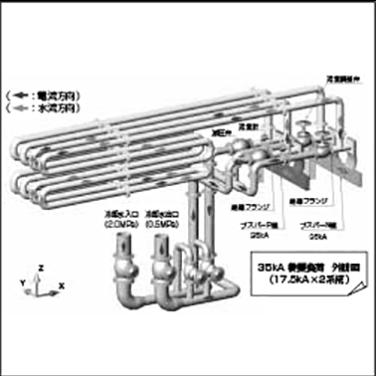
0.6 MB
ICarbon nanotube (CNT) has excellent properties for use in electric wires and cables. It is expected that CNT achieves lighter weight than aluminum and lower electrical resistivity than copper. The authors propose the “Carbon Transmission Method (CTM)” as the novel production method for realizing higher quality and longer length CNT. In CTM, the supply of carbon source gas and the growth of CNT can be independently controlled in different atmospheres through the use of fibrous catalyst.
0.6 MB
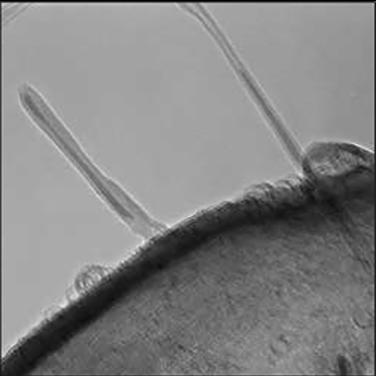
0.6 MB
The market for magnet wire for refrigerant compressor motors is one of the largest magnet wire markets in China. It is important for a magnet wire manufacturer to maintain and expand its share in this market. In general, refrigerant compressor motors are impregnated with varnish at 160 to 180 degrees C. Therefore there are two main user demands. One is to balance high wire lubricity with high impregnating-varnish bond strength, and the other is to balance anti-scratch property with adherence
0.5 MB
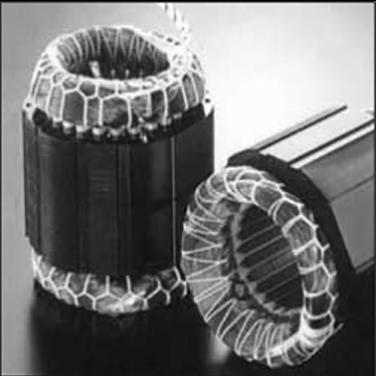
0.5 MB
The application of exotic materials like titanium alloy and heat resistant superalloy is increasing more and more, especially in the aircraft industry. Such exotic materials are difficult to machine because of their good mechanical properties and high temperature during machining. Newly developed AC510U and AC520U are high-toughness carbide grades with “Super ZX Coat®”, an exclusive physical vapor deposition (PVD) coating. Super ZX Coat® is super-multi layered coating consisting of
0.5 MB

0.5 MB
Sumitomo Electric Hardmetal Corporation has developed the new coated carbide grade “AC410K” for cast iron turning application. The “AC410K” coated carbide adopts a newly developed chemical vapor deposition (CVD) coating “SUPER FF COAT” as its coating film. This new CVD coating consists of flat and smooth layers of fine-particle titanium carbonitride (TiCN) and aluminum oxide (alumina), and far surpasses conventional coatings in terms of resistance to wear and peeling and achieves the higher
0.7 MB
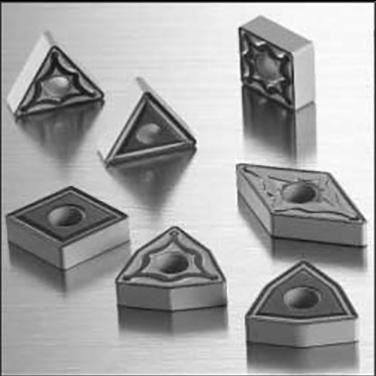
0.7 MB
In recent years, the demand for machining is growing, and cutting tools are used in increasingly severe machining environments. Therefore, evaluating machining environment is important for developing new cutting tools and providing technical support to customers. This paper outlines the following technologies of machining environment evaluation: visualization of chip formation process using a high-speed video camera, measurement of cutting temperature using a high-speed infrared radiation
0.7 MB
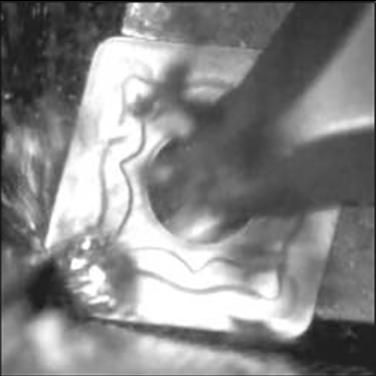
0.7 MB
Rainfall observation using weather radars has a major advantage that it is possible to observe precipitation over a wide area in a short time. However, the precipitation data observed by weather radars often do not correspond to those obtained by ground-based rain gauges. One of the causes of this disagreement is the non-uniformity of rainfall distribution in a radar scattering volume. Another cause is that most types of radar cannot receive radar echo at low altitude,
0.6 MB

0.6 MB
Sumitomo Electric is a comprehensive wiring material manufacturer who was among the first to start developing flexible printed circuit (FPC) in Japan about forty years ago. It was only in the latter half of the 1970s that FPC began to be used in consumer products and the FPC market has been steadily growing year after year since the 1980s. Since the full-scale spread of mobile phones in 2000, the FPC market is expanding rapidly. During this time, Sumitomo Electric has been actively engaged in
1.3 MB
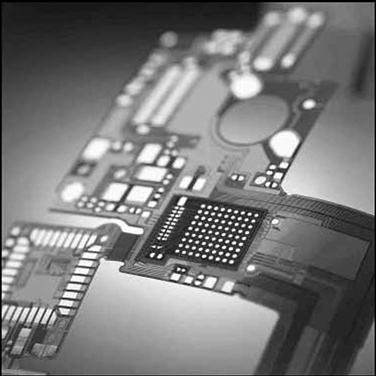
1.3 MB
The world population has overpassed 6.6 billion in August, 2007, and is expected to reach 9 to 10 billion by the middle of this century. The International Energy Agency expects that the world electricity demand will grow by 50% by the year 2030 accordingly. In terms of all primary energies, the growth of demand between 2000 and 2050 is expected to be as high as 200%. Since greenhouse gas emissions increase along with the expansion of energy consumption that will bring about environmental
3 MB

3 MB
To keep vehicle embedded software quality high, products must be verified on every event timing including unexpected timing.Especially important is the timing of power supply switching. In general, in the time region just after power supply is switched on, the possibility of occurrence of software error is higher than in the steady state. This is because the operating conditions at the time of switch-on of a power supply are different from those in the steady state,
0.6 MB
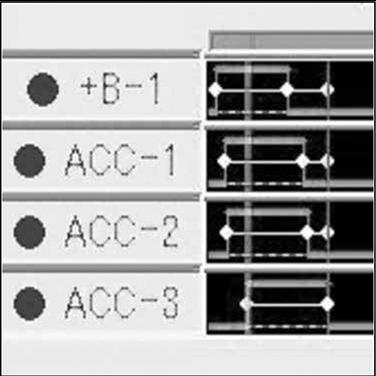
0.6 MB
Powder metallurgy (P/M) internal gear pump rotors are widely used in automobiles, especially for oil pumps. In recent years, because the automotive market demands low fuel consumption and more use of hydraulic power, oil pumps are demanded to have higher volumetric efficiency and smaller sizes. To meet these demands, Sumitomo Electric has developed P/M internal gear pump rotors with a new tooth profile. The theoretical discharge volumes of pumps that use the new internal gear rotors are higher
0.7 MB

0.7 MB
As document digitization and information sharing increase in enterprises, the volume of information within a company’s possesion grows steadily. As a result, there are increasing needs to effectively search across a company’s information assets. Enterprise search is a system for searching through all data owned by a company in a cross-sectoral manner. This paper describes the functions and features of the “QuickSolution” search engine developed as enterprise search software. First,
1.2 MB

1.2 MB
Erbium (Er)-doped optical fiber amplifier (EDFA), which can amplify optical signals without converting them into electric signals, is an optical component essential for creating today’s photonics networks. It is known that the gain characteristic of EDFA is influenced by the Al concentration in Er-doped fiber (EDF), which determines the coordination structure around Er. In this paper, the authors report on the first successful direct analysis of coordination structure of EDF.
1.1 MB
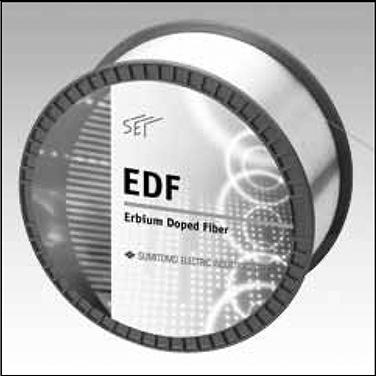
1.1 MB
With the rapid development of today’s digitally-networked information society, information electronic equipment is increasingly required to process large-volume information at high speed. Recently, the optical interconnection technology is getting a lot of attention as a mean to achieve highspeed transmission. The authors have developed a new type of optoelectronic ferrule called the “LFI” (or Lead Frame Inserted) ferrule for application to optical interconnection modules.
348 KB
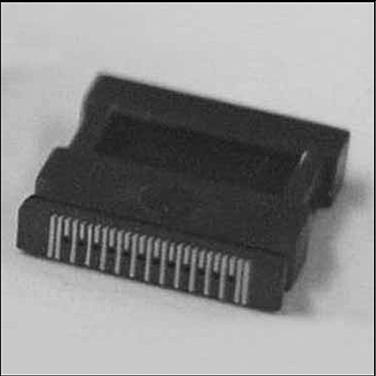
348 KB
The authors have successfully demonstrated a multi-rate optical transceiver in the small formfactor pluggable (SFP) platform for applications from OC-3 up to 4GFC. For the purpose of providing multi-rate operation, the authors have developed the following three technologies: a multi-rate receiver optical subassembly (ROSA) with a gain-selectable transimpedance amplifier (TIA), a dual-loop automatic power controller (APC) based on the peak level hold function, and a front facet monitor
1 MB

1 MB
Sumitomo Electric has developed new X2 transceiver SDX4101LM. This transceiver is compliant to the IEEE802.2aq (10GBASE-LRM) standard which may allow FDDI multimode fiber networks built in the 1980s to achieve 10Gbit/sec. In order to meet the standard, the transceiver employs not only 10Gbit/sec optical devices, but also the electronic dispersion compensation (EDC) technology for compensating degradation due to mode dispersion on MMF.
0.6 MB
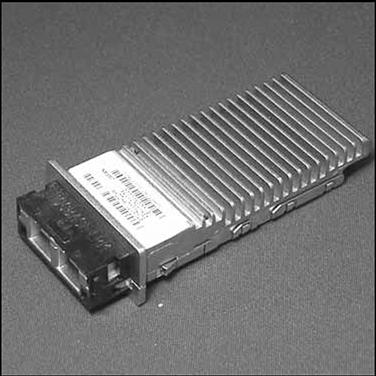
0.6 MB
This paper describes the newly developed SZ-slotted core optical fiber cable that provides fast and easy mid-span access. The cable uses new wrapping tape that can be peeled easily and safely without using any cutting tool, thus reducing the time required for mid-span access operation. The result of the mid-span access test confirms that the newly developed cable enables safe and easy mid-span access operation and 30% operation time reduction. These advantages are beneficial to the cost
0.9 MB
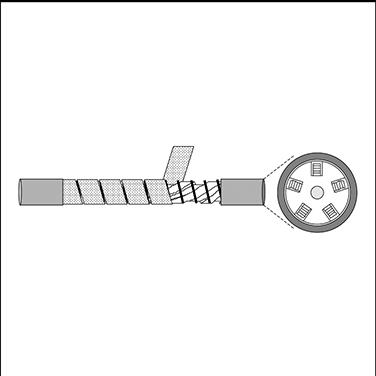
0.9 MB
Anti-lock brake system (ABS) has been installed as a basic system for supporting safety driving of automobile since 2000. SEI has developed the heat adhesive ABS sensor cable that contributes to the reduction of process cost for wheel speed sensor unit production. The heat-adhesion ABS cable adheres to the housing material during the injection molding process to make a waterproof seal between the cable and the sensor. SEI is promoting the use of environmentally friendly halogen free wire and
0.7 MB

0.7 MB
Flame retardance is a very important property of polymer materials, and red phosphorus is often used as a flame retardant. Because red phosphorus contains a high level of elemental phosphorus, fire-retardant property can be obtained even when polymer materials are very lightly doped with red phosphorus. In material development, quality control, and material acceptance inspection of compound resins, it is important to qualitatively and quantitatively analyze red phosphorus contained.
0.5 MB
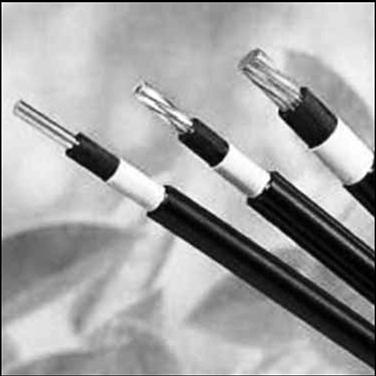
0.5 MB
The authors have developed a high-current electron emitter device using the highly-uniform device fabrication process and phosphorus-doped n-type diamond. Diamond is a highly electron emitting material, and phosphorus-doped n-type diamond has an especially high electron-emission property. The threshold voltage for electron emission from the sharp emitter tip of n-type diamond was lower than that of p-type diamond. Emission properties changed also according to surface conditions.
0.7 MB
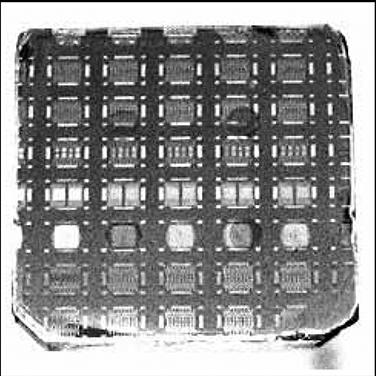
0.7 MB
Recently, with the growing global interest on energy saving, power device efficiency is becoming increasingly important. Almost all power devices are fabricated utilizing silicon (Si) and their performances have approached to the limit that can be obtained from Si. Silicon carbide (SiC) is one of the candidate materials for innovative power devices that can replace Si devices. The authors have developed a reduced surface field (RESURF) type junction field effect transistor (JFET) as the new
2.1 MB
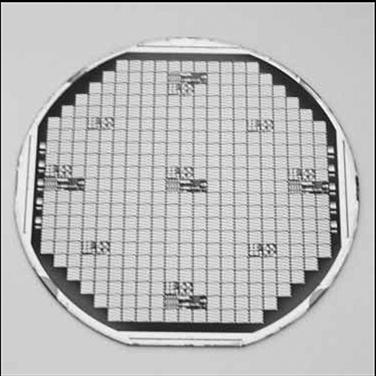
2.1 MB
Sumitomo Electric Fine Polymer has developed a technology for fabricating a brand new elastic material made of electron-beam (EB) irradiated polylactic acid (PLA) in the joint research with the Japan Atomic Energy Agency (JAEA). This new technology enables PLA to be cross-linked by EB irradiation and then swollen in hot plasticizer solution, resulting into a “PLA organogel with plasticizer”. Even though this was performed under a temperature condition of 80 degrees C,
0.8 MB
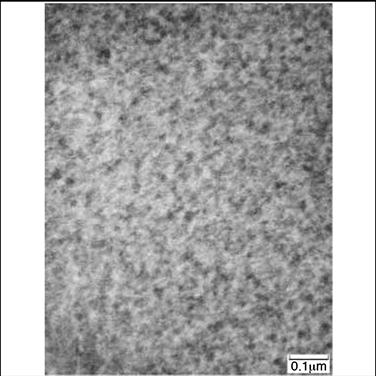
0.8 MB
In 1986, high temperature superconductors (HTS) were discovered, and in 1987 a yttrium-based HTS material (YBaCuO) was discovered followed by a bismuth-based (BiSrCaCuO) HTS material in 1988. Among them, the BiSrCaCuO HTS material was discovered in Japan, and we can improve a critical current property by adopting plastic deformation process with a feature of mass production. Althogh this material has shortcomings of brittleness due to a nature of oxide,
1.9 MB

1.9 MB
Bi-based oxide superconducting wires that operate at temperatures higher than liquid nitrogen temperature are currently being studied to achieve the practical use as electric power transmission wires, electromagnets, and so on. In order to realize larger power transmission and smaller size, the increase of superconducting current is required. To achieve this goal, the authors are optimizing the sintering process for superconductors so that the formation of hetero-phases
0.7 MB

0.7 MB
Performances of Bi2223 high-temperature superconducting wires developed by Sumitomo Electric have been dramatically innovated since the introduction of the CT-OP (controlled over-pressure) sintering process in 2004. The critical current (Ic) of a short-length Bi2223 tape with a cross section of 1 mm2 has reached 218 A, This Ic value is sufficient for use in various equipment that use superconductivity technologies such as high-field magnets, motors and cables.
0.9 MB
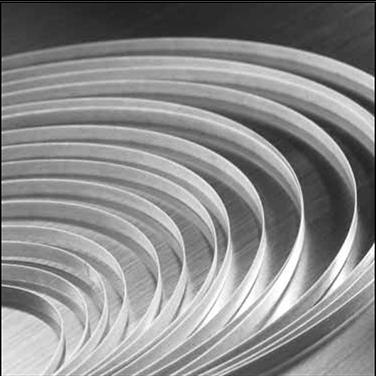
0.9 MB
The authors propose a novel carbon nanotube (CNT) production technique called Carbon Transmission Method (CTM) that uses fibrous catalyst. The supply of carbon source and the growth of CNT can be independently controlled in different atmospheres at each end of a fibrous catalyst. The authors demonstrated that by diffusion of carbon from the one end of a Fe fibrous catalyst in CO gas, the growth of CNT can be observed on the other end of the catalyst in an isolated state in Ar gas.
0.6 MB
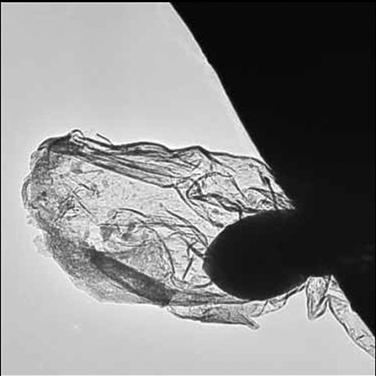
0.6 MB
High-purity nano-polycrystalline diamonds synthesized by direct conversion of graphite under high pressure and high temperature have extremely high hardness, no cleavage and high thermal stability. Because of these features, they have an immeasurable potential for industrial uses in applications such as cutting tools and abrasion resistance materials. In order to clarify the factors contributing to their high hardness, the microstructures and mechanical properties of nano-polycrystalline diamond
1 MB

1 MB
Cubic boron nitride (cBN) shows high levels of hardness and thermal conductivity second only to diamond and has a low affinity to ferrous metals. Cutting by polycrystalline cBN(PCBN) tool “SUMIBORON®”, which is produced by binding cBN particles with a special ceramic binder, has many advantages over conventional grinding process. Recently, the increasing global awareness of environmental issues has induced demands for high-speed and highprecision cutting. In order to satisfy such demands,
0.9 MB

0.9 MB
The newly developed SUMIDIA DA1000 grade, which is applicable for machining of nonferrous alloy parts that are hard to cut, has been developed as a solution to environmental problems in various industries such as automobile and machine manufacturing. DA1000 is made by densely sintering the fine grains of diamond and provides the highest level of wear resistance and toughness as well as excellent surface roughness. The SUMIDIA DA1000 grade realizes higher productivity and excellent surface
0.6 MB
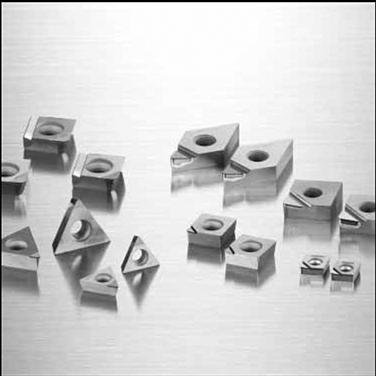
0.6 MB
Inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES) is widely used in various high-sensitive and high-precision elemental analysis such as environmental analysis and material analysis. Although the influence of coexisting elements on ICP-OES is known to be relatively small, in the axially viewed ICP-OES, the measurement error due to ionization interference could be observed depending on the combinations of coexisting elements and analyte elements.
0.6 MB

0.6 MB
Laser has been used widely in surgical treatment of oral tissues that are easy to bleed, because of its ability to incise tissues with hemostasis. Among different kinds of dental lasers, CO2 laser and near-infrared diode laser are especially widely used. CO2 laser beam is highly absorbed by water and therefore is able to efficiently incise soft tissues that contain much water. On the other hand, near-infrared diode laser features compactness and ease of use.
0.7 MB
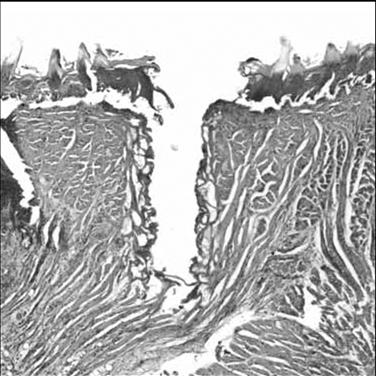
0.7 MB